対談 星新一さんと「理系文学」の世界
新井素子氏 × 鏡 明氏
2014/03/18
昨年日本で初めての「理系文学」の賞として創設された日経「星新一賞」(主催=日本経済新聞社)の受賞作が3月13日発表された。文学界に限らず、日本の社会に大きなインパクトを与えそうな理系文学。同賞の創設や受賞作選考に深く関わった二人が、「理系」の秘めた力と可能性を語り合った。
精緻な論理と広い世代の心をつかむ普遍性が魅力
鏡:僕が学生時代にSF作家クラブに入ったとき、星新一さんと緊張しながらお会いしたのを覚えていますが、新井さんは、SF雑誌『奇想天外』の新人賞で、審査員をしていた星さんに絶賛されたのがきっかけですよね。当時まだ高校2年生でしょう。
新井:結果的には佳作だったんですけど、星さんに作家としてのデビューの場を与えていただいたり、とてもお世話になりました。
鏡:それまで星さんの作品は?
新井:中学生のときに、作品はほぼ読み尽くしていました。特に『ボッコちゃん』や『ようこそ地球さん』に収録されたショートショート作品は、一つ一つが短いから、夏休みの読書感想文の題材にはもってこいで(笑)。あの頃、私もそうなんですけれど、星さんの作品を読んで、これなら自分でも書けると勘違いした人がずいぶんいました。

鏡:中学生にそう思わせるところが、星さんのすごいところだと思いますね。易しく書いてあるけれど、とてつもなく奥が深い。星新一さんといえば、ショートショートという文学形式を確立した作家というイメージが強いけれど、今回、お嬢さんの星マリナさんから星新一賞創設のためにお声掛けいただいたとき、ショートショートの域を超えたもっと大きな、作家・星新一の作品世界を踏まえたものにしたかったんですね。
新井:私も審査員をやらせていただくことになりましたが、星新一賞が掲げる「理系文学」というコンセプトは面白いですね。
鏡:星さんご自身、東大大学院まで行って農芸化学を研究した理系の人ですし、星さんの作品は、ショートショートに限らず、非常に精緻な論理で構成されていますよね。と同時に、われわれ大人だけでなく、小学生でも中学生でも、いつの時代でも楽しめる普遍性がある。
新井:以前、ある出版社の編集者に聞いたのですが、星さんが亡くなられてもう17年もたつのに、いまだに星さん宛てに小・中学生から手紙が来るんですって。「星先生、お元気ですか。僕は今何々しています」って。普通、SF作品って、時代と共にどうしても古く感じられてしまうものだけど、星さんの作品にはそれがない。風俗描写を一切しなかったり、古さを感じさせる要素をあえて排除したところもすごいじゃないですか。
鏡:それも、星さんならではの理系的な論理が働いている気がしますね。
「理系」が力を持たないと世の中のバランスが崩れる
新井:私、星さんのアンソロジーを編集したことがあって、あらためて驚いたのは、書いてあることがそのまま現実になっていることがたくさんある。例えば、「声の網」という作品には明らかにパソコンやネットの話が出てくるんだけど、あれが最初に発表されたのは1970年ごろでしょう。インターネットの「イ」の字もない時代に。しかも、ちゃんと電話回線を使うという話になっている。
鏡:単なる科学的な先見性というより、作家としての圧倒的な想像力、発想力を星さんは持っていた。今回の星新一賞でも私が期待していたのは、その点ですね。小説としての形が整っているかどうかより、どんな面白いアイデアから生まれた作品なのか、それをどのような形で伝えようとしたのか、そこには当然、論理性も関わってきます。
新井:そこが理系文学のまさに面白いところですね。「理系」と「文学」という、考えようによっては矛盾するようなコンセプトを成立させようとしている。興味を持ってくれる人もけっこういると思いますよ。
鏡:これまで日本は文系の方に軸足を置き過ぎていたと思うんですよ。もう少し理系が力を持たないと世の中のバランスが崩れてしまう。文学の世界も決して例外ではないと思います。星新一賞で「理系文学」を掲げたのは、文学的な創造性の上でも、理系が大きな力を持っていることを示したかったからです。新井さんの他に、宇宙飛行士の野口聡一さんやノーベル物理学賞の益川敏英さんといった、およそ文学からは遠い世界の方々にも審査員をお願いしたのは、そうした方々の視点、これまでの文学賞とは異なった視点が必要だと信じていたからです。そして応募作品の中にある理系的な力を見抜いてくださったと思っています。
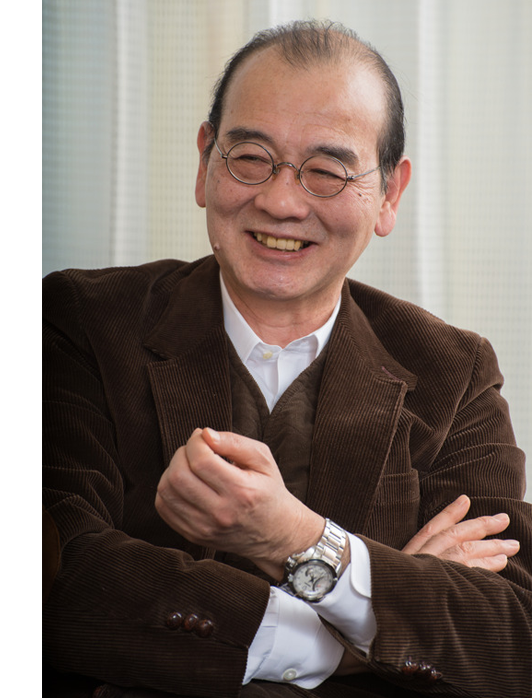
新井:理系文学だから、アイデアとか論理性に重きを置くというのはとてもよく分かります。ただ、星さんは理系的な発想や論理もさることながら、やはり素晴らしい作家であるということですね。その名前を冠した賞である限り、やはり、作品世界に引き込まれる魅力だとか、話の展開の面白さだとか、あるいは文章の読みやすさといった点も決しておろそかにできない。そんな思いで応募作品と向き合いました。
鏡:新井さんにお願いしてよかったです。理系とはいえ、もちろん、文学賞ですから、新井さんには作家としての視点で評価していただきたいと思っていました。理系文学の定義にはまだ議論の余地はあるでしょうが、私たちが目指す大きなゴールの一つは、若い人にもっと理系的な思考や発想の面白さに気付いてほしいということですね。少し大仰な言い方をすれば、理系文学に関心を持ってくれる若者が増えれば、日本の文化もわくわくするほど面白くなるし、社会もより良い方に変わっていく。そんなふうにさえ思っているんです。
応募者がつくる「星新一賞」若い世代の発想に期待
新井:今回の応募総数は3000を超えたと聞きましたが。
鏡:3057作品、私も驚きました。主催する日経新聞のサポートも大きかったと思いますが、私は1000を超えれば万々歳だと踏んでいたので、あらためて星新一という作家の偉大さを思い知らされました。
新井:それはすごい数字ですね。
鏡:少し意外だったのは、一般部門は思いの外、小説作品が多かったことですね。僕はもっと論文っぽいものがあってもいいと考えていて。ほとんど数字だけのものとか、因数分解のような作品があってもいいし、ツイッターで書いたような小説があってもよいと思っていた。その手法の是非はともかく、発想の奇抜性は星新一さんの名前を冠した以上、最も大事にしたいものの一つですから、もっと、びっくりさせてもらってもよかった。
新井:私は、ジュニア部門で印象的な作品が多かった。今後も、受賞作品を小学生や中学生たちが読んで、「これならオレも書けるぜ」とどんどんチャレンジしてくれるとうれしいですね。単に若い作家が数多く出ればよいということではなくて、公の場で人に読んでもらうために書く楽しさを知ってほしいし、理系的な発想で書くことが楽しいと思える子どもたちがもっともっと増えてほしいという意味で。
鏡:おっしゃる通りです。一般部門に応募する方も、来年以降、さまざまな発想でトライしてほしいですね。第1回の今回は、応募者それぞれの理系の捉え方があったと思います。それは、一般の読者の人とはちょっと違う理系だったかもしれません。まして、それが「理系文学」と言われたときには、「いったい何?」と思う人もいると思います。今回の受賞作品が、理系文学の世界そのものかといえば、必ずしもそうとは限りません。むしろ、これから何年も何十年も受賞作が積み重なっていく中で理系文学の確固たるスタイルができていくのだと思います。
新井:いいですね、書く人の力によって理系文学のスタイルや概念が固まっていくというのは。「これは私の考えている理系とは違う。私が思う理系の世界はこれだ!」なんて言う人がどんどん現れてきてほしいですね。
鏡:そういう意味では、星新一賞というのは、決して高みにある賞じゃない。より多くの人が応募してくれることで、理系文学の世界観が出来上がり、星新一賞という文学賞がつくられていく。そして、理系文化がもっと広まっていくことで、世の中を変えていく力にもなる。だって、過去にも優れたSF作品が、現実の科学を強烈に刺激したじゃないですか。
新井:SFってもともと理系文学という側面を持っているし、ミステリーだって伏線や謎解きは理屈っぽいというか、いわば理系的な論理の世界。理系的な思考や論理に、独創的なアイデアや発想が加われば、文学としての面白い作品になるのは当然ですね。
鏡:そして社会にも貢献を果たす。理系文学のこれからにぜひ期待したいと思っています。(おわり)
第1回日経「星新一賞」一般部門では、グランプリに遠藤慎一さん(52)の「『恐怖の谷』から『恍惚(こうこつ)の峰』へ〜その政策的応用」、準グランプリ1作品、優秀賞2作品、ジュニア部門グランプリに松田知歩さん(15)の「おばあちゃん」が選出された。写真は第1回の募集ポスター。




