電通BX/DXウェビナー2021「Disruptive & Sustainableな生活者視点の事業変革」No.2
【電通DXウェビナー】
顧客ファーストなDXのススメ
2021/12/03
社会が大きな変革期を迎える中、企業の在り方そのものや、顕在化していない課題に目を向け、ビッグアイデアとともに非連続な変革を実現可能にするために
必要なことは?
電通グループならではの「BX(ビジネストランスフォーメーション)」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」のアプローチを、各分野のプロフェッショナルや外部ゲストを交えてさまざまな論点から考察した、ウェビナーの様子をリポートします。
「BX」パートを紹介した前回に引き続き、今回は「DX」パートより、4つのプログラムをダイジェスト形式でお伝えします。
顧客体験ファーストで実現するデジタル変革

登壇者は、トヨタ・コニック・アルファ代表取締役の平川昇吾氏。トヨタ自動車の事例をもとに、DXによる顧客体験の改革を実現するためのポイントを紹介しました。モデレーターは電通エグゼクティブDXディレクターの加藤剛輔氏が務めました。
トヨタ・コニック・アルファは、2021年にトヨタ自動車と電通が共同出資で設立した新会社。「データで、ありがとうをつくる仕事。」をミッションに、データを活用した新しいビジネス開発と、販売店におけるDX推進を掲げています。
平川氏はトヨタが新会社を設立した理由について、これまで自動車製造業において“トヨタの強み”とされてきた「現状をスタート地点としたカイゼン文化」や「内製指向」といった文化が、DX推進では足かせとなっていた可能性を挙げます。
「DX推進に必要なバックキャスト型のタスク定義や、推進のノウハウ、スピード感のある改革(=“グリーンフィールド開発”)を行うための独立組織が必要という判断に至ったのです」と平川氏は述べます。
続いて、同社が開発した「オンライン相談」と「スマートカタログ」の紹介がありました。
オンライン相談は、顧客体験の向上と営業活動の効率化を実現するサービス。新型コロナウイルスの流行をきっかけに、自動車販売店でもオンライン接客が浸透しつつあります。しかし、従来のオンライン接客は、「予約確定まで時間がかかる」「質の悪い配信環境」「既存ツールを流用した分かりにくい商材説明」「来店時の引き継ぎ不足」といった課題がありました。
そこで、同社のサービスでは、「即時予約システム」「高い操作性を備えた配信環境パッケージ」「オンライン専用カタログの開発」「メモ機能や写真保存機能などを活用した情報蓄積」を実現。お客さまとの接点づくりや関係性強化、成約率の向上といった効果につながっています。
この取り組みから派生し、実用化に向けて検証を進めているのが、オンライン専用カタログ「スマートカタログ」です。顧客に合わせてカタログをカスタマイズする機能、ワンタップで動画に遷移する機能、複数車種を左右画面で比較する機能などを実装。車の選定から購入までの総合サポートツールを目指しています。また、スマートカタログをはじめ、各種ウェブサイトなどでトラッキングできる顧客の行動データを一元管理して分析することで、1to1のアプローチも推進していく狙いがあります。
平川氏は、今回のプロジェクトで大切にしていることを3つ挙げました。
- サービス(CX)ファースト
お客さまから真に評価されるサービス設計・顧客体験を最初に考え、そのために必要なデータ・システム要件を定義する。 - 失敗を数多く経験し、学びながらサービス品質を向上させる
顧客起点の企画は仮説段階では不確実性が高いため、テストをしながらお客さまのフィードバックをもとにサービスの解像度を上げていく。 - 一度ローンチしたサービスは高速PDCAを回しながら常にアップデートし続ける
一度作って終わりではなく、常にアップデートし続けることで自社サービスの競合優位性を高める。
最後に、加藤氏から「改善しながらグロースさせるのは非常に大切なことだと思う一方で、撤退やピボット(方向転換)のタイミングの見極めも重要で、そのあたりはどのようなプロセスで進めているのでしょうか?」と質問がありました。
「戦略的な合理性はかなり重視しているのですが、短期的な収益性がなくても長期的に販売店のDXに大きく寄与する可能性があるものはまずMVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)のローンチを目指します。ローンチ後に重視しているのがプロダクトマーケットフィットですね。私たちがどんなに良いと思ってもお客さまが使わないものは難しいので、その場合は即時変更または中止することを心がけています」と平川氏は述べました。
構想企画書だけに終わらせない、DX組織立ち上げの成否を握る3つの鍵
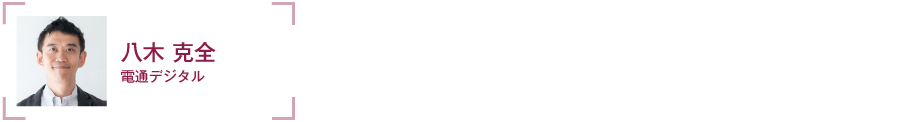
続いては、電通デジタル執行役員デジタルトランスフォーメーション領域担当の八木克全氏のプログラム。テーマは、DXに向き合う企業の悩みと、その克服方法についてです。
冒頭、八木氏は自動車メーカーや保険会社、大手エネルギー企業の執行役員にヒアリングした、DXに関する要望を紹介。「ビジネスモデル変革をスピーディに推進したい」「自社人材を育成して変革を加速させたい」「DX事業がサイロ化しているので、顧客データ基点で統合し、シナジーを生みたい」といったニーズがあり、構想や計画は描けているものの、「実際に組織や人を動かして具現化し、全社的な成果に結びつけることが難しい」という共通の悩みを抱えていることを指摘します。
なぜ、構想の具現化や全社的な成果の実現が難しいのでしょうか?その背景にあるのが、DX組織の構造的な問題です。
DX組織は、単体事業としてのアプリ開発・運用や統合型データマーケティングに関する成果が求められるだけでなく、新規事業開発系部門と協働した新デジタルサービス開発、既存事業系部門へのDX支援なども推進しなければなりません。しかし、八木氏は「これは非常に難易度が高いことです。なぜなら、それぞれの施策に必要なアプローチやテクノロジー、人材が異なるからです」と述べました。
例えば、DX組織単体の事業はKPI達成のために高速PDCAマネジメントが求められ、テクノロジーはマーケティング系のAIやMAツールなど、人材はUXデザイナーやデータサイエンティストが必要です。
一方、新規事業開発系部門との協業ではベンチャーキャピタル的なアプローチ、FinTechなどサービス領域のテクノロジー、ビジネスプロデューサーなどの人材が欠かせません。既存事業系部門のDX支援の場合、コンサル的なアプローチ、BPR(Business Process Re-engineering)系のテクノロジー、必要な人材は変革プロデューサーやコンサルタントなどになります。
「このように、DX組織は成果期間が異なる縦割りの事業体に向き合わなければならない中、それぞれに必要な機能の違いや、特に人材不足について悩んでいらっしゃる企業が多いのが現状です」と八木氏。
では、この課題を克服するためにはどうすれば良いのでしょうか?
八木氏は、戦略/仕組み化/運用の各層に合わせた“3つの鍵”を提示します。
まず戦略に関しては、テスラが「人類を救済する」というミッションを掲げ、自動車産業のみならずエネルギー産業も含めた大きな社会変革に挑戦することでサステナブルな成長を実現していることを例に挙げ、単なる「デジタル/データの活用」ではなく「人びとを幸せにする社会や顧客サービス創造」で変革ビジョンを持つことが一つ目の鍵になります。
続いて仕組み化の部分では、顧客と従業員の双方が“腹落ち”した状態をつくることで、顧客は自社の商品・サービスを使い続け、従業員は自律的に顧客と向き合い続けるようになり、サステナブルな組織を実現できるといいます。
そして運用については、顧客分析と施策開発をどちらか片方ではなく両方同時に推進していけるチームを作ることが鍵になると述べました。
また、今後はグローバルな市場との戦いも見据えて、「豊かな文化産業や、おもてなし精神、カイゼンのプロセスといった、日本ならではの強みを戦略/仕組み化/運用における“3つの鍵”に組み込むことで、戦えるDX組織にしていくことができると考えています」と八木氏は付け加えました。
最後のまとめとして、八木氏は「今日から何をすれば良いか」についての提言を述べました。
「DX組織単体事業では、はじめに人材調達計画を策定しつつ、まずはシンプルに成果を出す。同時に、新規事業開発系部門と協働体制を確立することで、単体事業のサービス強化を実現する。さらに、既存事業系部門とはPoC(実証実験)を進めてこれまでの成果を証明していく。その結果、成果を武器に全社改革の合意形成が得られ、全社改革の旗振りができるようになるのです」(八木氏)
なお、電通デジタルでは、ビジョンと事業開発を一気通貫する共創型未来デザインプログラムや、生活者の社会的不満から自社の存在意義を再定義し、新サービス開発や顧客体験変革を支援するプログラム、変革専門人材を提供してプロジェクトを生きた社内運動に昇華するプログラム、変革人材育成プログラムなどを用意しています。
八木氏は、「皆さまが企業活動を前向きに推進していくご支援ができればと考えております」と締めくくりました。
LINEとLookerで実現するデータドリブン・マーケティング

続いて登壇したのは、電通国際情報サービス(ISID)プロジェクトマネージャー/コンサルタントの丹羽ひかる氏。データドリブン・マーケティング戦略に最適なLINEとLookerの活用方法を紹介しました。
冒頭、丹羽氏はデータドリブン・マーケティング実践の障壁を5つ挙げます。
- 何から手を付ければ良いのか分からない
- 因果関係が不明
- データ不足
- 経営資源やツールが不足
- 組織や人の問題
この中でも、2と3はデータが整理されれば解決できる問題であり、ポイントは1と4の乗り越え方にあると丹羽氏は言います。
まず「1. 何から手を付ければ良いのか分からない」に関しては、「簡単なデータから始めて、クイックウィンをつくることが重要です」と丹羽氏。最初から100%のデータをそろえたり、多額のインフラ投資を行うのではなく、まずは簡単に手に入るデータを用いて成果を出すことから始めることで、データドリブン・マーケティングを進めることができます。
続いて「4. 経営資源やツールが不足」に対しては、「データドリブン・マーケティングのインフラ構築」の重要性を説きます。「時間や費用、ツール、システムがない場合でも、インフラをしっかり設計することがポイントです」と同氏。
この「簡単なデータから始めてクイックウィンをつくる」と、「データドリブン・マーケティングのインフラ構築」の双方を、コミュニケーションアプリ「LINE」と、データプラットフォームの性質を備えたBIツール「Looker」そしてISIDのインテグレーションのノウハウを掛け合わせることで実現できます。
LINEは日本国内の“生活のインフラ”として定着しており、利用者数や利用率が高いだけでなく、LINEでしかリーチできないユーザーも数多く存在します。「リーチ力が高いLINEは、小さく始めて早く成果を出すために有用なサービスです」と丹羽氏。さらに、ユーザーと1to1のコミュニケーションが取れるLINE公式アカウントや、LINE公式アカウントで取得したデータを広告配信に用いる(※1)“クロスターゲティング”が可能なLINE広告を活用することで、より効果的かつ最適なコミュニケーションが実現できるそうです。
Lookerはデータプラットフォームとしての性質を備えたSaaS(※2)型のBIソリューションです。APIや拡張可能な独自の連携機構も備えているので、分析・抽出結果をシームレスに外部連携できるといった特徴があります。
※1=これらのオーディエンスデータはLINEファミリーサービスにおいて、LINEユーザーが登録した性別、年代、エリア情報とそれらのユーザーの行動履歴(スタンプ購入履歴、LINE公式アカウントの友だち登録履歴など)、LINE内コンテンツの閲覧傾向やLINE内の広告接触情報をもとに分類した「みなし属性」および、実購買の発生した購買場所を「購買経験」として個人を特定しない形で参考としているものです(「みなし属性」には携帯キャリア・OSは含まない)。
「みなし属性」とは、ユーザーが「LINE」上で購入・使用したスタンプや興味のあるコンテンツのほか、どのようなLINE公式アカウントと友だちになっているかといった傾向をもとに分析(電話番号、メールアドレス、アドレス帳、トーク内容等の機微情報は含まない)したものです。
※2=SaaS(Software as a Service)
ユーザーが必要な機能を必要な分だけ利用できるソフトウェアサービス。
すなわち、LINE公式アカウントやLINE広告をLookerに連携することで、自社システムとの大掛かりな統合をしなくても、クイックウィンをすぐに実現することができるのです。
アカウント連携を実装し、ファーストパーティデータをひも付いた形でLookerに取り込むことで、LINEのユーザー属性補完が可能となり、より詳細な分析をすることができます。さらに、弊社が独自開発したCustomer Match for LINEを使えば、Lookerの分析結果をLINEのオーディエンスとして活用できます。その結果、よりコンバージョンしやすいオーディエンスへの配信ができるようになります」と丹羽氏。実際にJINSでは、LINEとLookerを組み合わせて高度なターゲティングを繰り返すことでデータドリブン・マーケティングの精度を高め続けています。
「弊社ではLINEとLookerを核としたインテグレーションにより、お客さまのデータドリブン・マーケティングを実現させ、競争優位性の獲得に貢献していきたいと考えています」と丹羽氏は述べました。
電通SHOPPING EXPERIENCEが考える、OMO実現に向けたキーポイント

最後に登壇したのは、電通グループ横断プロジェクト「dentsu SX(SHOPPING EXPERIENCE)」より、電通デジタルDX領域ビジネストランスフォーメーション部門長の安田裕美子氏と、電通ライブ執行役員の石阪太郎氏。コロナ禍で変化する顧客体験とOMO(Online Merges with Offline)の潮流を押さえながら、今後のキーポイントを紹介しました。
冒頭、安田氏は複数のクライアントから「コロナ後、デジタルチャネルや施策を増やしたがイマイチ効果が見えない」「店舗を削減する方向だが、店舗自体の位置付けをどう考えればいいのか」「OMOとよく聞くけど、EC以外に何から手を付けていいのか分からない」といった相談を受けることが増えたと言います。そのような疑問を解決するためのヒントを提示するのが、本プログラムの主旨です。
dentsu SXは世界的サービスデザイン企業frogと協働し、各業界の有識者ヒアリングや国内外の各業界動向分析をもとに「新たな買い物行動に関するマクロトレンド」を発表しています。その中でマクロなトレンドキーワードに挙がったのは、「サステイナブルで身の丈にあった消費スタイル」「息を吸うようにいつでもどこでも検索」「人の集まる場/ゆるいつながりを買い場に」の3つです。
「例えば、近年は企業の社会課題に対する姿勢・思想への共感が購買を大きく左右しますし、店舗で商品を手に取りながら、もう片方の手にあるスマホで競合商品をチェックします。コミュニティ的な人とのつながりを基点にしたECが登場したり、買い物行動は大きく変化し続けています」と安田氏。
さらに、コロナ禍での顧客の購買体験の実態を詳しく調査したところ、下記3つの購買体験タイプが見えてきたそうです。
- デジタル接点に乗り切れない「オンボード困難層」
- リアル、デジタルを機能別に使い分け「オンオフ使い分け層」
- 購買行動はすべてデジタル「オンライン完結層」
安田氏は、「例えば、オンボード困難層であれば、現状のECやデジタル接客にペインを感じているので、オンボードのための“場”の工夫に潜在ニーズがあります」と、各タイプのペイン・ゲインポイントにOMOのヒントがあることを述べました。
続けて、同氏はOMO実践のためのキーポイントを3つ挙げて解説しました。
- チャンネル発想から体験発想へ。「場」をつくれているか?
いくらチャンネルを増やしてもユーザーの周りに点在している状態では顧客体験の向上にはつながらない。リアルのつながりを活用したデジタルへのオンボードなど、“オムニエクスペリエンス”視点の体験設計が必要。 - 従業員のリスキルのためのデジタル支援を、真の支援に。
従業員のコンシェルジュ化を目指すも、高度で複雑なデジタル活用では逆効果。従業員体験に沿ったシステム構築や、顧客から進んで入力する仕組みづくりを。 - 店舗はもはや買うための場ではない。オンライン体験の再定義。
店舗の役割は購買から、新たな体験価値の提供へ。オンラインでつながる顧客の体験をさらに向上させる目的型店舗に可能性アリ。
プログラムの後半では、石阪氏がdentsu SXの取り組みを紹介しました。
同チームは、オンオフの体験を一貫性のある文脈かつ共感できる体験として提供することを目指しています。具体例を見てみましょう。
例えば、既存店舗の役割の再定義や、中長期的な顧客との関係構築には、「次世代型常設店舗ソリューション」が解決策の一つに挙げられます。
「ある自動車ディーラーはロードサイドに大型店舗を出店していましたが、コロナ禍で集客に苦戦。そこでショッピングセンターに小型の店舗を出店しました。花屋やアウトドアメーカーとコラボすることで“販売”色を低減し、店舗スタッフとの会話を誘発する仕掛けを店内にさりげなく設置することで、オンラインでは実現できないエモーショナルな体験を創出しています」(石阪氏)
もう一つ取り上げたのが、流通を介さずリアルな顧客接点にチャレンジしたいというニーズに対する「ポップアップストア型ソリューション」です。
「ある高級コスメブランドは、ECや百貨店ではリーチできないエントリー層を開拓したいと考えていました。そこで若年層をターゲットにした期間限定の体験型店舗を実験的にオープンし、バーチャルストアも展開。SNSやLINEを活用してクッキーレス時代に向けたテストマーケティングも行い、感情認識AIを用いたデータ収集も試しています」と石阪氏。コロナ禍で不動産物件の流動化が加速していることから、今後もさらに使い勝手の良いオンオフのハイブリッド施策として期待ができるそうです。
最後に石阪氏は、「私たちのミッションは、“購買体験をテクノロジー×クリエイティブで、顧客起点にトランスフォームする”こと。世界の企業のマーケティングを支えるオンのノウハウ、多くのオフのコンタクトポイントで実績を積み上げてきた、人の心を動かすオフのノウハウ、これらを結集させて、クライアント企業のプロジェクトを推進いたします」と述べて締めくくりました。




