アド・スタディーズ 対談No.1
日本のパブリックリレーションズを振り返る
―新しい次元に向けた
PR理論の再構築へ―①
2013/12/09
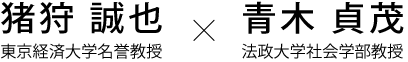

メディア環境の激変やグローバル化が進展するなか、企業にはどのような思想が求められているのだろうか。
今回は、日本における広報を草創期から理論的・実践的に主導され、『日本の広報─満鉄からCSRまで』という記念碑的著作でも知られる猪狩誠也氏をゲストにお迎えし、企業のコミュニケーションやブランド研究を通して企業の文化力を提案されてきた青木貞茂氏と、これまでの歴史を振り返りながら、企業コミュニケーションとしてのパブリックリレーションズの重要性と理論的な再構築に向けた課題と展望を話し合っていただいた。
パブリックリレーションズの原点
青木:日本は今、3.11の東日本大震災によって大きく変わろうとしているようにも見えますが、まず、パブリックリレーションズの歴史的な流れについてお話しいただきたいと思います。
猪狩:明らかに3.11から日本社会は変わったと思いますが、それ以前に、産業資本主義から金融資本主義への転換が、社会や企業活動に非常に大きな変化をもたらしたと考えています。私は歴史を振り返るために『日本の広報・PR100年』という本を書き、その中で、パブリックリレーションズ発祥の地であるアメリカにもちょっと触れましたが、その原点は、アメリカ建国の思想にあると思うのです。ヨーロッパから来た人たちが新しい国、新しい町をつくるにあたって、ジェファーソンやアダムスといった建国に尽くした人だけでなく、見ず知らずだった人びとが対話、議論しながらコミュニティを、そして関係性をつくっていった。
一方、3.11で見えてきたのは電力会社、政治家、官僚等の間には対話がない、またそれぞれの行動には思想・哲学がないことでした。”絆”という言葉が流行りましたが、絆をつくるには多くの言葉は必要ない。しかし、温かいコミュニケーションは必要でしょう。僕はパブリックリレーションズはいわば絆をつくることであり、そこにはそれなりの思想・哲学が必要じゃないかと考えました。

青木:日本ではパブリックリレーションズを広報と訳しましたが、本来の意味とはだいぶ違う理解のされ方をしましたね。
猪狩:敗戦後、アメリカからパブリックリレーションズが日本に入ってきた時には、それは民主主義の一つのツールと考えられていた。日本証券投資協会から1950年代に『パブリックリレーションズ』という月刊誌が出ていましたが、最初のうちは「経営の民主化」が中心テーマでした。ところが、アメリカですでにパブリックリレーションズの意味がかなり変化していたのですね。
近代化には民主化と産業化という2つの側面があります。中世という時代も持たないアメリカではこの2つが同時に達成され、大衆消費社会が非常に早く成立したため、パブリックとの関係性よりも消費者との関係性に重点が移ってしまったわけです。
日本には1950年の朝鮮戦争頃からアメリカの経営技術が入ってきて、すでにアメリカではマーケティング技術に組み込まれていたパブリックリレーションズも日本企業の高度成長のツールとなり、PRと略されて、原点であるパブリックとの関係性から離れてしまったのですね。
もうひとつ「広報」という言葉ですが、戦前、満鉄に「弘報」という部署があり、戦後、官公庁に導入された時部課名に英語はつけられない、「弘」は折からの漢字制限で使えないことから「広報」にしたといわれています。そして1970年代のオイルショックの際、企業の社会的責任を問われた時にメディアの取材窓口として「広報課」をつくった企業が多かったのです。
青木:relationsというのは当然、関係性の問題なのに、翻訳されたときは情報の「報」が当てられています。佐藤卓己先生が「情報」の語源を調べたら、どうも森鷗外がinformationをこう翻訳したようです。いわゆる軍隊の情勢報告を縮めて情報にしたということです。そこには、パブリックリレーションズの根底にある対話や関係というニュアンスがありません。
猪狩:日本広報学会設立のとき、学会の名称についてはかなり議論した覚えがあります。「広報」ではワン・ウェイ・コミュニケーションだし、パブリックリレーションズにすれば、すぐPRに略されてしまう。議論の結果、英文名もコーポレート・コミュニケーション・スタディーズにしましたが、もう少し議論すべきだった。
広報とパブリックリレーションズ
青木:本来なら企業と顧客、企業と社会、企業と共同体との関係をつくるためにはどんなコミュニケーションをするのかということが重要だったのに、企業が独り歩きして顧客や社会は置き去りにされてしまったような気がします。
猪狩:日本はもともと対話とか関係性というものに対して非常に鈍いというか、少なくとも戦前は対話など問題にもされませんでした。そこにアメリカの大衆社会の中で変質したパブリックリレーションズが入り、PRという極めて言いやすい言葉になってしまったわけです。もともとの原点からみれば、まったく違ったものになってしまいました。
青木:パブリックリレーションズにはダイアローグという意味での対話や深い絆づくりというニュアンスがありますが、インフォメーションではどうしてもニュースや報告といった側面が非常に強くなってしまいます。日本企業では広報という組織はどのように捉えられていたのでしょうか。

猪狩:1978年に経団連が経済広報センターをつくりました。70年代前半にオイルショックが起き、いわゆる企業の社会的責任が問われたため、広報が大事だということになったのです。高度経済成長時代にPR部門はできていましたが、それは今流のPRで、社会的責任といった問題を考える組織ではありませんでした。
企業の広報担当者の中では、PRというのはもっぱら宣伝系の言葉であって、社会的な問題を考えたり、それに対処するものとは思われていない。また広報というのは字面からいっても広く知らせるということであると思っているようですが、そこからはリレーションズという感覚はまったく出てこなかったと思います。
青木:学生たちに講義するとPRと広報の違いがわからず、それは広告・宣伝ではないですかとよく訊かれます。特に日本の場合は顕著で、広報に思想とか哲学、あるいは社会性といった裏付けがなくなっているということですね。
猪狩:最近、政治学の分野などでは公共性や熟議の民主主義などと言われるようになってきました。これはパブリックネスということで、関係性を論じようということですが、広報の世界ではそういった根本的な論議は行われていません。
例えば、今回の原発問題でも、いろいろな公聴会をやっていますが、単なる形式的なポーズにしか見えません。行政や地方公共団体は、もっと公共の対話や関係づくりを心がけなければいけないのではないでしょうか。
〔 第2回へつづく 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。



