【続】ろーかる・ぐるぐるNo.169
マネジメントは「見守り役」ではない
2020/02/13
作家井上靖が少年時代を過ごした伊豆半島、天城を舞台に描いた自伝小説が『しろばんば』。『夏草冬濤』『北の海』と続くシリーズを、ぼくは中学時代、むさぼるようにして読みました。お恥ずかしいことに、特に覚えているのは食べ物のシーン。主人公洪作が、少し不良がかった先輩に連れられて食べに行く三島の「ラーメン」は味の描写など一切ないのに、「もう一杯食うか」「うん」というやり取りだけで、その姿が目に浮かぶようでした。金沢で旧制高校柔道部の仲間と囲む「スキ焼」も然り。
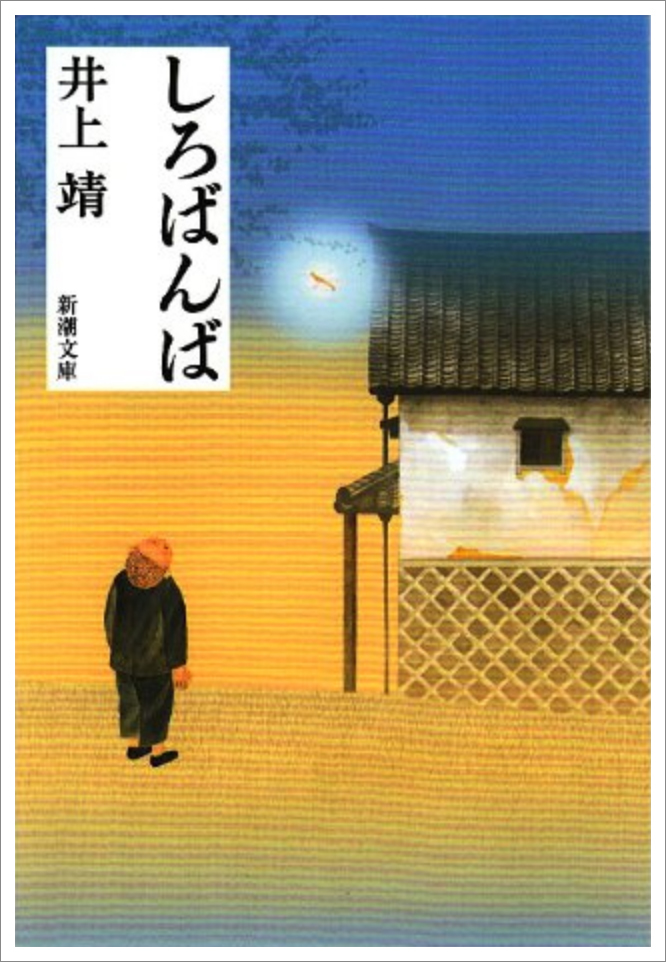
先日、懐かしくて読み返したのですが、そういった食べ物に関する印象は見事に変わらないままでした。ただ、ストーリー全体について言うと、ひたすら洪作に共感していた昔に比べ、その成長を見守り心配する大人連中に気持ちが動くようになっていました。商売で失敗を繰り返し、酒ばかり飲んでいる祖父の、孫を思いやる視線にも初めて気がつきました。すぐれた小説は、読み返せば読み返すほど発見があるものですね。
これはどうも、文学に限ったことではないようです。経営学の名著『知識創造企業』を初めて読んだのは入社して間もない頃。降りかかってくる実務に溺れそうな日々に、アカデミックな匂いが懐かしくて手に取ったのですが、その読み方は完全に学生レベル。イノベーションに関するあらゆる事例に対しても実感はなく、ただ学ぶべき知識として受け止めていました。
それが入社15年目くらいに読み返したときには、いろんな事例が身近に、自分ごとに感じられ、とりわけそれを主体的に動かしていくミドル・マネジメントの悩みに共感し、その成功を生々しく嫉妬しました。
以来、年を重ね、少しずつトップ・マネジメントの目線にシフトしている気がします。「リーダーによって提起される漠然とした企業ビジョン」は、果たしてどのように設定されるべきものなのか?どうすればミドル・マネジメントはいきいきとプロジェクトに取り組むのか?同じ本を読んでいるはずなのに、「知りたいこと」は明らかに変わってきました。
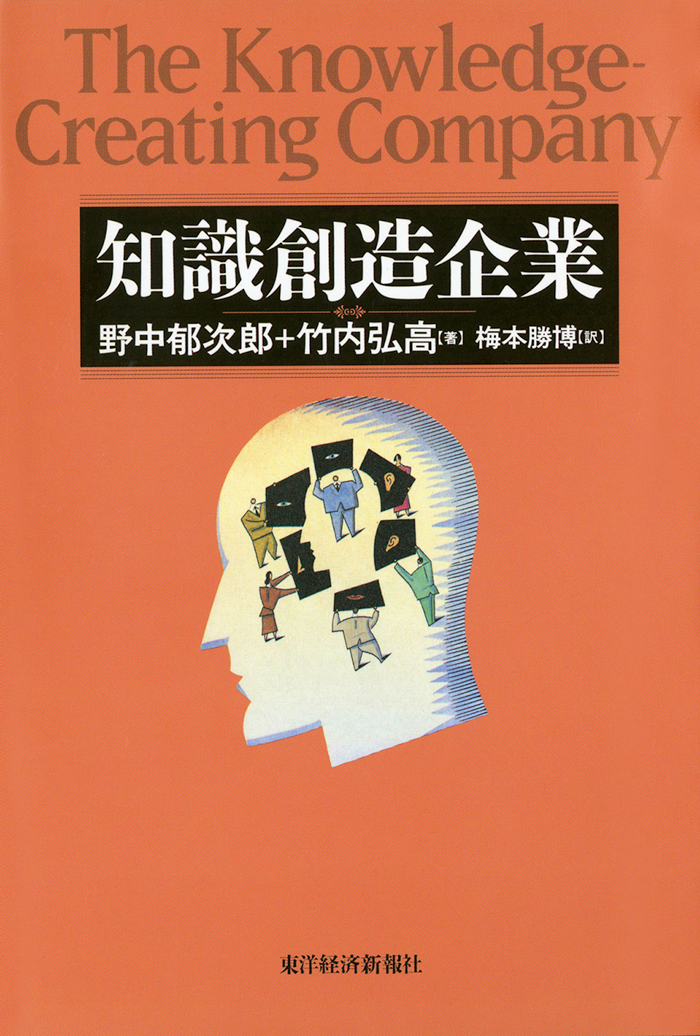
最近、いろいろな企業で「新規事業開発プロジェクト」の現場に立ち会うのですが、しばしばそのリーダーが「ものわかりの良い見守り役」を自任して、「大胆に、自由にやってみてよ」と仰っている姿を目にします。正直、ぼくも生意気な若手社員の頃であれば、「そうそう、任せておいて!」と思ったに違いありませんが、『知識創造企業』をいろいろな目線で読み重ねた今では、実感をもって「それではダメだ」と考えます。
理由はシンプルで、放ったらかしたままでは、その企業・団体に相応しいプロジェクトになる確率が低いから。たとえば家庭用食品を扱う会社で現場が「未来の食材として『昆虫』に取り組みましょう!」と提案したとき、なんと答えるのか?実は「大胆に、自由にやってみてよ」というリーダーに限って「それはないでしょ(笑)!」「うちの会社がやると思う?」なんて言い出します。そして「では、うちの会社らしさって、何ですか?」と尋ねても「………ほらさ、わかるだろ?」という始末。これでは現場が浮かばれません。
マネジメントは現場に対して「壁」になる責任があります。ひとつは、そこに今までの常識を覆す「コンセプト」があるのか?を問い続けること。もうひとつは(きちんと企業ビジョンを言語化したうえで)それが、その企業が取り組むべきことなのか?問い続けること。その「壁」を現場が乗り越えようとする意欲こそが、イノベーションの原動力になるのです。
本棚に眠る昔の本でも、きちんと読み返してみると、きっと多くの発見があります。

ところで伊豆といえば「海の幸」ですが、『しろばんば』に刺激されて天城界隈をうろうろしていたら、名産のワサビだけでなく、シカやイノシシといったジビエも豊かであることに気がつきました。港町下田にドライブする道すがら味わう「山の幸」というのも、なかなか素敵な発見でございました。
どうぞ、召し上がれ!




