アートの価値はどうやって作られるのか
2016/07/13
広告会社の視点から、日本のアートと企業・経済・マーケティングの関係性やこれからについて考えていく連載。第1回ではアートが持つポテンシャルについて、マーケティングを専門領域とする東京理科大・大西浩氏と電通・上原拓真氏が事例を交えて紹介しました。今回は日本のアート界の最前線で活躍するNPO、アーツイニシアティヴトウキョウ(AIT)の塩見有子氏、電通でアートマーケティングに関するプロジェクト「美術回路」を運営する若林宏保氏・上原氏が座談会を行いました。

※第1回「アートはマーケティングできるのか」
誰もが現代アートにアクセスできる場をつくったAIT
上原:今や国内外に強いコネクションを有しているAITは2000年代初頭から活動を始め、日本のアート市場の成熟と共に歩んでいる組織だと思います。まずは、塩見さんとAITがこれまでどのような活動をしてきたか教えてください。
塩見:AITは2001年にキュレーターやアートマネージャーが立ち上げた組織で、翌年にNPO法人化しました。アーティスト集団が団体として活動する例はたくさんありますが、AITのように専門性をもった人でNPOをつくったのは当時としてはまだ珍しいものでした。
また2001年は、第一回目の横浜トリエンナーレが開催された年で、現代アートに対する社会的関心が増しているのを肌で感じていました。作品に反応したオーディエンス(鑑賞者)の皆さんから「もっとアートを知りたい!」という声が上がったり、数百人規模のボランティアが参加してトリエンナーレの日々の運営を支えたりということが起こりました。
上原:直接的にアートに関わりたいという人たちが現れ始めた時期だったわけですね。
塩見:ええ。ですが一方で、アートを職業としないオーディエンス層がアートについて学ぶ場はほとんどなかったんです。アートマネージメントを教える大学はありましたが、マネージする対象であるコンテンツ(作品)について国際的あるいは批評的な視点をもってアートを学び、それを活性化するための場所が国内にほとんどないことに違和感がありました。特に、現代アートは経済・社会・歴史などと関わりが強く、それらをベースとした議論を重ねていく知的なフィールドでもあるので、その議論のための学校をつくろうというのがAIT設立の理由の一つです。
上原:それがAITが主宰している現代アート講座「MAD」(Making Art Different)ですね。

塩見:はい。15、6年続けると、MADの修了生がアート界でキャリアを積み、重要な仕事に携わるようになってきています。
上原:教育だけでなく、AITは「アーティスト・イン・レジデンス」にも携わっていますよね。
塩見:はい。アーティスト・イン・レジデンスというのは、アーティストが異国の地に一定期間に滞在しながら、作品制作やリサーチを通じて国際的な文化交流を行う活動です。1960~70年代頃から欧州を中心に活発になり、日本でも90年代から地方都市に施設が建設されるなどしましたが、東京にはほとんどなかったので、東京に制度化されたアーティスト・イン・レジデンスをつくることもAITを設立した動機の一つです。


若林:現在だと、トーキョーワンダーサイト(TWS)などがレジデンスとしては定着していますね。
塩見:TWSもAITと同じ2001年に活動をスタートしていますね(※レジデンスの開館は2006年)。当時の私たちが持っていた「東京は、経済・文化ともに国際都市のはずなのに、アーティストを受け入れる受け皿がない」という問題意識を共有していたのだと思います。
私たちは資本が少なかったこともあって、向島の小さなアパートを拠点にして2003年からレジデンス事業を始めました。現在は教育事業(MAD)とレジデンス事業を軸にしながら、メルセデスベンツ、マネックス証券、日産など企業が主導する文化プログラムのアドバイスや運営なども手がけるようになりました。
若林:教育やレジデンスといった事業をゼロからスタートするというのは、大変な苦労があったのではないでしょうか?
塩見:そうですね。ただ、ニーズがあるのはわかっていましたし、小さく始めて少しずつ大きくすればいいとも考えていました。AITの最初のパートナー機関は「IASPIS」というスウェーデンの政府系財団だったのですが、他にもフランス・英国・ドイツなど日本に拠点を持つ海外の文化機関からしてみると、日本人アーティストを自国にたくさん受け入れて文化交流しているのに、日本にアーティストを送るときには受け入れ先がない、という不満がありました。
苦労という意味では、レジデンス活動は滞在地のスタジオでの作品制作が中心でしたが、AITにとってスタジオ維持は金銭的に難しい面もありました。そこで東京の特徴を生かした、他と違うレジデンスを作りたいと考えました。東京という、ものすごい勢いで大量の情報や人が動いている特殊な場所だからこそアーティストに提供できるものがあります。例えば新しくて刺激的な情報を得たり、専門的な知見を持つ人と出会ったり、リサーチ&ディベロップメントの機会としてレジデンスをとらえることができます。
上原:日本に海外のアーティストを紹介すると共に、オーディエンス層を育てたり、アート業界の人材を輩出したりと、金銭的な価値だけではない重要なアートサーキットの一部を担っていますね。
塩見:2008年には、レジデンスのアーティストの作品を集めて、ファンドレイジングとチャリティーを目的としたオークションを開催するなど、マーケットをつくることへの意識も持っていたいと思っています。
若林:昨年開催された「日産アートアワード2015」にもAITは関わっていますね。近年、企業がアートを支援する動きが目立っている印象ですが、どのような背景があるのでしょうか?
塩見:実は、企業が芸術文化を支援する活動は、もっと前から始まっています。「企業メセナ協議会」という組織が1990年に設立されていますが、文化支援活動を行う企業をつなぎ、その活性化を目指しています。そうした中で目立っている印象があるのは、特に2000年以降、例えばファッションや音楽がアートと結びつき、メディアにのって世界展開していることです。
ファッションとアートはさまざまな理由から親和性が高いように思います。日産についていえば、デザインとアートという視点もあります。カルロス・ゴーン社長は、日本でのビジネスが成功してきた理由の一つに、「文化的な資源があるから」という考えを持っています。例えばそれが車のデザインにも生かされているなど、日本の文化の創造者に感謝していることから、現代アートのアワード創設に至ったと聞いています。

「日産アートアワード2015」授賞式の様子 撮影:越間有紀子 Photo Courtesy:日産アートアワード

「日産アートアワード2015」グランプリ 毛利悠子《モレモレ:与えられた落水 #1–3》2015 撮影:木奥恵三 Photo Courtesy:日産アートアワード

「日産アートアワード2015」ガイドツアーの様子 撮影:越間有紀子
日本のアートは、世界からどのように評価されているのか
塩見:ところで若林さんは、現代アートがお好きだそうですね。
若林:はい。実は電通には僕以外にも、アーティストを兼業している人がいたり、自分でアートプロジェクトを立ち上げる人もいたり、アート好きが多いんです。
上原:好きが高じて、アートマーケティングについての論文も書いたくらいですよね。
若林:そうなんです。この論文を書いた2010年くらいに、僕は写真家の森山大道さんにハマっていたんですけど、彼は1960年代から活躍しています。それがなぜ今になってこんなに価値が高まっているんだろう、という疑問を持ったのが執筆のきっかけです。アートの価値が高まるプロセスとその現象を俯瞰して論文にしました。
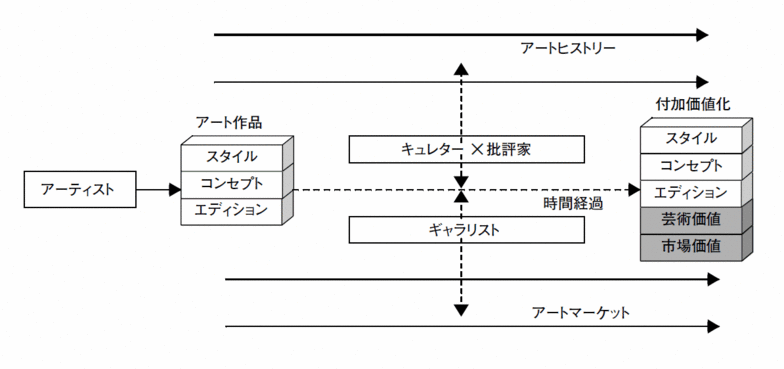
塩見:そうなんですね。具体的にはどういったことなんですか?
若林:1960年代から70年代にかけて雑誌『カメラ毎日』の編集長だった山岸章二さんは、森山さんを含む日本の新進写真家を精力的に取り上げ、1974年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された日本人写真家15人を紹介する「ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー」展の企画に関わるまでになります。
また近年では、ロンドンでは写真家・写真史家のマーティン・パーさんが、当時の日本の写真集の質の高さを再評価しています。このようにメディア、ギャラリー、美術館といったアートに関わるさまざまな立場のプレーヤーが、森山大道というアーティストの価値をその時代ごとに高めていって、脈々と価値が形成されていきました。
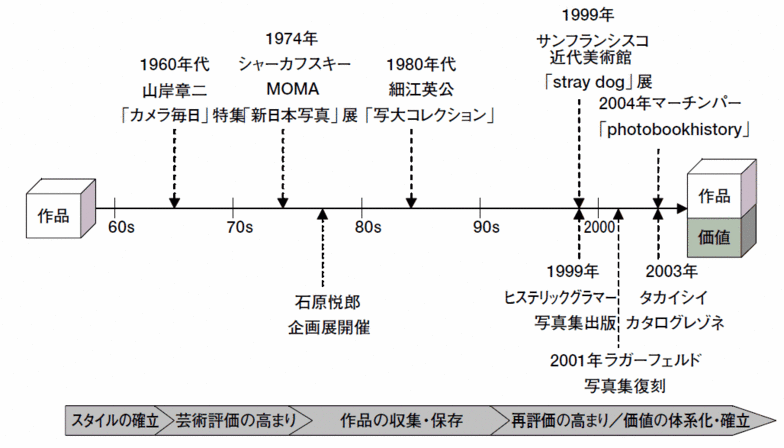
塩見:欧米では、そうやってさまざまなプレーヤーが一緒に価値をつくっていきますね。
若林:日本に置き換えてみると、世界で一番美術館に足を運ぶのは日本人だといわれているように、アートへの関心はとても強いものの、その価値を高めていくことがこれからの課題です。
上原:私たちはこのような生態系を「アートサーキット(美術回路)」と呼んでいるのですが、塩見さんはこの市場形成プロセスをどのように見ていますか?
塩見:日本のアートは若林さんのいう通り、外国のキュレーターにより企画された展覧会によって再評価されるという流れがあるのは事実です。例を挙げると、1994年にアジアの現代アートに詳しいアレクサンダー・モンローさんというキュレーターが、「戦後日本の現代美術」という展覧会を横浜美術館で企画し、その後サンフランシスコの美術館に巡回しました。最近だと、ニューヨークのグッゲンハイム美術館が2013年に「Gutai: Splendid Playground 」展で戦後日本の前衛芸術運動を代表する「具体美術協会」を取り上げたり、MoMAが2012年に「Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde」展で日本の戦後美術やデザインにフォーカスしたりしました。ギャラリーであれば、日本にも支店を持つブラム&ポーが、1960年代末から70年代にかけて精力的に活動した「もの派」を大々的に扱ったのは記憶に新しいですね。ただ、この展覧会は日本人のキュレーターが企画しているので、これまでと違う流れも生まれています。
若林:「具体」や「もの派」は、欧米がきっかけになって作品の価値が高まっていってますね。
アートサーキットをくぐり抜ける本当のアートとは?
若林:最近は、僕が論文を書いた2010年よりもダイナミックにアートサーキットが動いていると思います。
塩見:一方で、あまりにもスピードが加速し、過密化もしてもいます。これは、現代の経済活動とも呼応しているとも思います。森山大道さんの価値形成は長期的なものですが、極端な見方かもしれないですが、一年間のアート界のイベントを追うと、その価値形成の一端を見ることができます。
例えば、アジアでは3月に香港でアートフェアがあり同時にオークションも行われ、コレクターの所蔵作品による展覧会も開催されます。5・6月には、現代アートのオリンピックといわれる「ベネチアビエンナーレ」の後にスイスで開催される世界有数のアートフェア「アートバーゼル」が開催され、ベネチアで紹介された作家の購入可能な作品としてずらりと並んでいます(※参照:第1回「アートはマーケティングできるのか」)。

2015年にベネチア日本代表となった塩田千春がアートバーゼルに新作を出品 Galerie Daniel Templon|Chiharu Shiota @Art Basel
塩見:春と秋には大手オークション会社による現代アートのセールがニューヨークとロンドンで行われ、12月には北半球の冬を避けるようにして真夏のマイアミでまたアートフェアが開催されます。その間、ギャラリーや美術館でも、展覧会やフェアに出ているアーティストによる力の入った個展が企画されます。このように国際展で価値付けされたものが即座に市場に反映されたり、アートフェアの期間中にオークションが行われるなど、価格の正当性を担保したり、評価を高めあう仕組みができているのが現在の状況です。
若林:さらに戦略的になっているんですね。だからこそ、アートの歴史を見直して再評価したり、まさにAITが取り組んでいるようにアートを文化機関の側面から継続的に支えたりすることが大切で、それが本当に歴史に残るべき作家を支援することになるとも思います。
上原:今は本当に、重要な境目に来ているような気がしますね。
若林:そうですね。現代アートの多様な作品形態をマーケット自体が許容するようになってきたという変化も特徴的です。僕はその代表格である田中功起さんの作品がとても好きなのですが、彼の作品をコレクションするのはちょっと勇気がいります。映像やコンセプトを作品として買う、という決心がなかなかできない…(笑)。

田中功起 《everyday statement (cheese toast)》 写真 2010年
ノート:毎日チーズトーストをつくるという行為は、言ってみれば創造性のサンプルだと思う。毎日ぼくらはせっせと何かを創造している、意識するしないに関わらず。
塩見:つまり、私たちの「買う、所有する」という概念も変えていかなければならないということですよね。でも、それがまた面白いところで「やっとアートの本質をつかんだぞ!」と思って手を握りしめても、その手を開いて確かめようとした途端に、分かったはずのことが逃げ出していて、また違う考え方に気付く。アートの移り変わりを鏡として、私たちの意識や価値観も変わるということが繰り返し行われているんですね。
若林:それはマーケティングの世界とは対極的で、本当のアートっていうのは、既存の価値観をくぐり抜けていく存在なのかもしれないですね。
塩見:アートをマーケティングすることの難しさはそこにあります。ある程度のところまでは、マーケティングできるかもしれない。でも、アートの本質を考えるとどこかでずれてくる。いつの時代でも、アーティストは常識をくぐり抜けたり、飛び越えたり、物事をトランスフォームして、違う道を探そうとする人たちなんです。そしてそこには常に、世の中に対する問いと正解のない答えがあるのだと思います。
アートを買うと何が見えるのか?
上原:最後に話を聞きたいのですが、作品を買うということについてはいかがでしょうか?
若林:コレクターの心理として答えると、買った後よりも買う前がとにかく楽しいんです。食べ物や服のような機能を伴わないので、普通に考えるとアート作品を買うのはハードルが高いじゃないですか。でも、だからこそ魅了される。
アーティストについての記事や批評を読んだり、過去の活動をリサーチしたりしているうちに、だんだんとその作家の活動やコンセプトへの理解が深まっていって、その頃にはものすごく欲しくなってしまっている。それでようやく手に入れると…もう後悔しかない残らないんです(笑)。なんで買っちゃったんだろう、という。でも時間が経つと、自分にとってかけがえのないものになっている。
上原:そのプロセスも含めて、作品を体験しているということでしょうか?
若林:まさにそうです。先ほど言ったように参考資料を探したり、影響を受けたアーティストや、哲学的な背景を深堀りしたりしていくうちにものすごくハマってしまう。
また、自分の生き方のヒントやアートリテラシーなど目には見えないだけで自分の中に蓄積されていくものも確実にあるのも事実です。
塩見:作品にコミットすることで、自分自身にコミットしていくということですよね。それは同時にアーティストにコミットすることでもあって、作家と交流を持てることはコレクションの醍醐味の一つでもあると思います。

編集後記
15年以上にわたって日本の現代アートの発展に貢献してきた塩見氏から、アートの価値形成のプロセスについて、多くの示唆をいただきました。特に日本のアートは、近年「具体」や「もの派」が再評価された例のように、欧米の展覧会で取り上げられ、同時に作品が売買されることで価値が付いていきました。そのサイクル(アートサーキット)が「世界的に数年単位にまでどんどん短期化している」と塩見氏が指摘されたことは興味深いと感じました。
アーティストたちは、さまざまな表現形式で「私たちの意識や既存の価値観」を揺さぶる新しいアートを生み出し続ける中で、それらをどうやってマーケティングによって価値を高めて後世に残していくのか。これからの日本の課題はアートの価値化とその継続であると思いました。一方で既存の価値観やマーケティングでは常に捉えられない存在こそが本当のアートなのだという論点も出てきました。アートの価値を定義した途端にそこから抜け出して、新たな価値を探しだすアートとは一体何なのでしょうか。
次回の連載では、奈良美智、村上隆らを世界に輩出してきた「小山登美夫ギャラリー」の小山登美夫氏に、AITの塩見氏が個人と企業とアートの関係性と歴史、そしてアートマーケットの最新情報についてインタビューします。(上原)
お問い合わせ:美術回路 kairo@dentsu.co.jp



