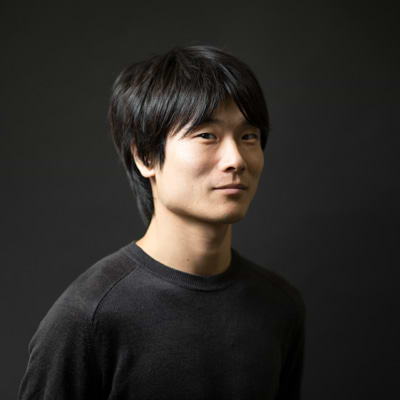株式会社GNUS (ヌース)がDXに取り組む大企業の管理職500名を対象に実施した調査 では、「自社のDXの成果に満足できているか?」「DX推進において何を重視しているか?」などを質問。DXに取り組む企業にとって多くの示唆を得られる結果となりました。インタビュー後編では、調査結果を踏まえ、DX成功の突破口を見つけるためのヒントについて、GNUSの立ち上げ時から参画している栗林祐輔氏に聞きました。
DX成功のカギを握るのは「アジャイルプロセス」による開発 株式会社GNUS 栗林 祐輔氏 Q.調査結果の公表後、どのような反響がありましたか?
栗林: 発表からまだ日が浅いので、あまり多くのご意見は聞けていませんが、「確かにDXではプロダクト開発が大事だよね」とか「ビジョンだけではなく、具体的に何ができるかを考えることが必要ですよね」といった共感の声が寄せられています。また、調査結果をまとめた資料のダウンロード数はじわじわと増えてきており、やはり自社のDXに悩まれている企業さまが多いことを感じています。
Q.今回の調査結果を踏まえると、DX成功のためには何が重要なのでしょうか?
栗林: 特に重要なのは、早い段階で具体的なプロダクトを作り、テスト・改善を繰り返しながら完成度を高めていく、いわゆる「アジャイルプロセス」ではないでしょうか。アジャイルプロセスは事業と開発の距離が近くなければ成功しませんし、お客さまの生の声を聞いて開発に落とし込んでいくことも必要です。そのためGNUSでも、サービス・プロダクトをリリースした後に、各企業さまが自社の力でシステム構築を進めていけるように、内製化支援を行っています。具体的なやり方は、開発チームを中心に継続的にアップデートできる仕組みを構築して、その中にクライアントサイドのプロジェクトマネージャーやエンジニアにも入ってもらうことで、徐々に自走できるようにサポートします。加えて、スキルレベルなどを担保しなければプロジェクトが思うように進まなくなるので、OJTのような形でスキルの移管も並行して行っていきます。
Q.GNUSにはDXに関するさまざまな相談が寄せられていると思いますが、それらを通じて、日本におけるDXの課題はどんなところにあると感じていますか。
栗林: やはり大きいのは、人材不足ですね。DX人材の不足に関しては経済産業省が2021年度「企業と連携するデジタル人材に関する調査」として公開しているのですが、それによると特に足りていない人材はDXプロデューサーやプロダクトマネージャー、ビジネスデザイナーとされています。さらに、今回の当社による調査でも、「DXを推進する上で、現在あなたの企業に不足している人材は?」という質問をしたところ、同様に、多くの企業さまがDXプロデューサー/プロダクトマネージャーが足りないと回答しています。つまり、ハードを構築する以前に、プロジェクトを企画してまとめていく人や、実際にどのようなプロダクトを作るべきかを考える人が足りていないと言えます。
Q.GNUSに相談される企業さまは、あらかじめどういう役割の人材が自社に足りていないかイメージできているのでしょうか。
栗林: DXプロジェクトの企画立案や推進をする人材が足りない、ということにはなかなか気がつかない企業さまも多い印象です。特に初期の頃は、「エンジニアがいればなんとかなりそう」「デザイナーがいれば」という相談を受けることが多く、GNUSとしても「いいエンジニア、デザイナーがいますよ」とご紹介していました。しかし、実際にプロジェクトを進める上で「何を実現したいのか」「どう実行していくべきか」というコンサルティングから始めないと、円滑に進めるのは難しいと感じるようになりました。そのため、今ではただエンジニアやデザイナーを紹介するのではなく、全体を設計できる人をチームに組み込むようにしています。
いいプロダクトを作るためには、基盤となる仕組みの構築が大切 Q.DXに取り組む上で、まずはエンジニアやデザイナーのアサインを希望する企業さまが多いのには、どのような背景があるのでしょうか。
栗林: 何を実現したいか、ということよりも「とにかくアプリを作りたい」といった思いが先行しがちなのではないでしょうか。「アプリを作りましょう」というだけであれば、それほど手間や予算をかけなくても作る方法はありますが、それがビジネスを根本的に変えられるかというとそうではないので、クライアントさまに対しては、事業成長のためにはまず基盤づくりが重要だと説明します。例えば、お客さまのリアルなニーズを知るための仕組みも必要ですし、プロダクトの価値を高めるための社内的な仕組みも必要です。
Q.高級食材でおいしい料理を作ることよりも、毎日食べ続けても飽きない定食のようなメニューを作ることの方が意外に難しい面もありますよね。アイデアに関しても同じで、日常的に使い続けたくなるものを考えることは難しいですね。
栗林: そうなんです。何かプロダクトを開発するときには、目新しい機能を搭載したい、デザインを大胆に変えたい、といったことを考えがちですが、ユーザーの悩みを1つひとつ解決していくことの方が、結果的に大きな成果につながることもあると思います。ストレスを感じずに毎日使い続けられるものを作るためには、ユーザーの声に寄り添い、地道に改善を重ねていくことが重要なのではないでしょうか。
DXに取り組む上で「世の中の注目を集めるような画期的なプロダクトを作りたい!」と意気込んでいる企業も少なくないかもしれません。もちろん、そうした理想を描くことも悪いことではありませんが、果たしてそれが本当にユーザーの役に立つプロダクトになり得るのか、という点についても、考えを巡らせてみる必要があるかもしれません。