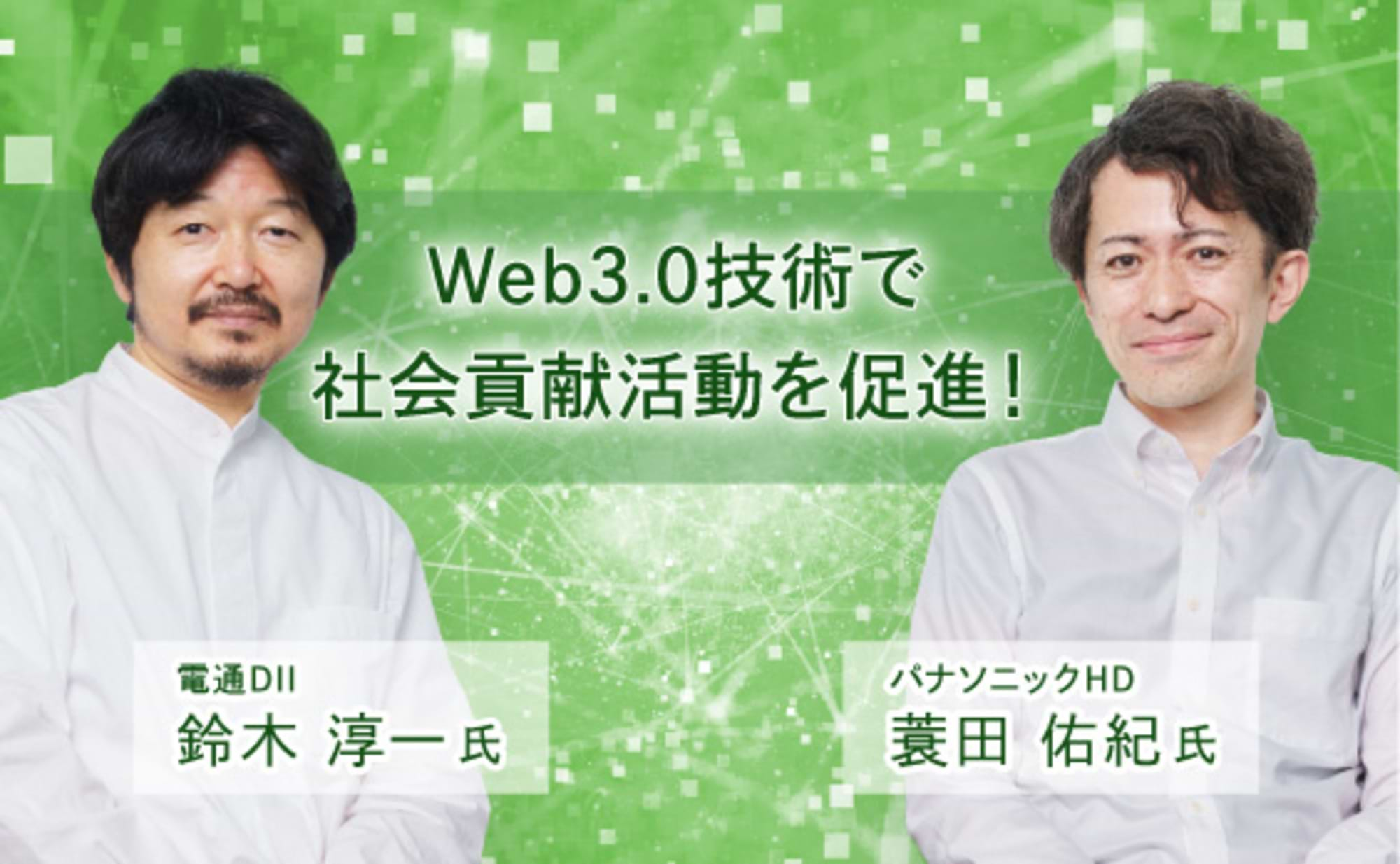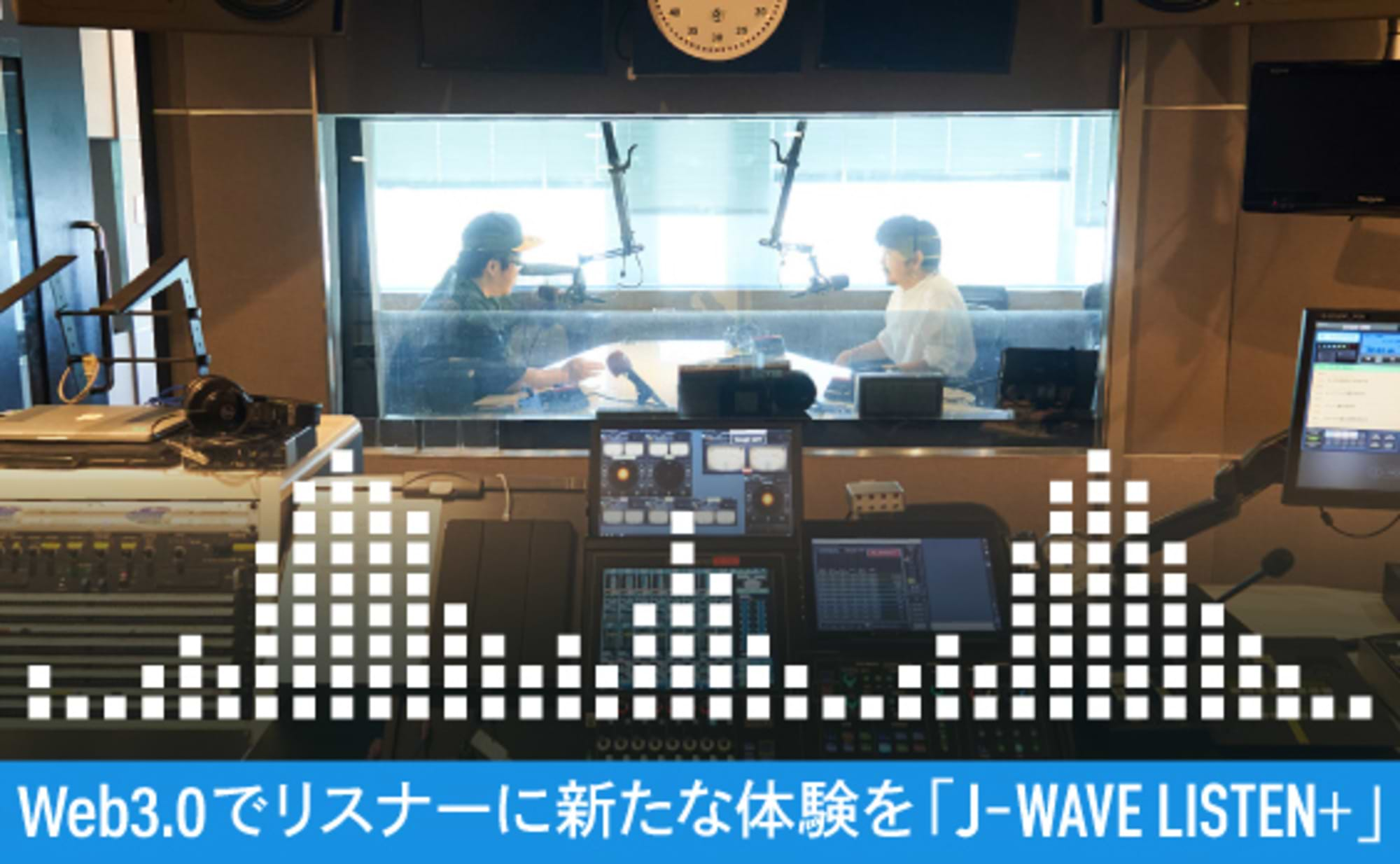ドラマなどのテレビコンテンツ領域において、視聴者によるコンテンツの解説記事やシナリオの予想記事などを、SNS上で発信することがトレンドとなっています。このように、コンテンツの著作権を守ることは重要ですが、そこからのn次創作が新たな可能性やマーケットを生み出していくということも現実として起こっています。そうした流れを受け、株式会社 電通グループ では、ブロックチェーン技術に基づくNFT(非代替性トークン)を用いて、視聴者がクリエーターとしてテレビコンテンツをオフィシャルにn次創作していく「ghost Link 」という取り組みの実証実験を7社共同で行っています。
この「ghost Link」をはじめとして、多くの先端技術プロジェクトに携わる電通グループ 電通イノベーションイニシアティブプロデューサー鈴木淳一氏へのインタビュー。「ghost Link」リリースに至るまでの経緯やプロジェクトの概要を聞いた前編に続き、後編では、さまざまなNFT活用ビジネスの可能性や、これからのWeb3.0社会についての展望を聞きます。
NFTの影響力をデジタル空間から実空間へと拡大 Q: 前編 では「ghost Link」について、今回の実証実験に至るまでの流れなどを聞いてきましたが、今後はどのような展開を想定しているのでしょうか。
鈴木: ここ数年、さまざまな形でNFTとハードウェアウォレット(暗号資産などのデジタル資産をインターネットから隔離した状態で保管するデバイス)による個人のアイデンティティー形成の支援とその活用、つまりNFTというかたちで蓄積された個人のアイデンティティー情報を与信情報と捉えることで、個々の与信状況に基づき行使可能な権利として活用する取り組みを進めています。その1つに、「ghost Link」で作品制作にも参加していただいたメディアアーティストの落合陽一氏が開催するサマースクールでの取り組み があります。
NFT発行&インセンティブ受け取りの流れ Q:子どもたちがドラマコンテンツを基に二次創作をするということでしょうか。
鈴木: 『TOKYOCASE』はホラーコンテンツで、「怨霊マガツヒ」も子どもたちが扱うにはやや難しいキャラクターなので、サマースクールで題材にするのは、落合氏が「ghost Link」のスキームで制作した「怨霊マガツヒ」の二次創作作品です。これがかなりポップなテイストになっているので、こちらを基に三次創作をしてもらいます。今後はスマホなど子どもたちが普段から使っているデバイスで操作できる、動画編集アプリなどを併せて提供し、手軽に楽しく創作を楽しめる仕掛けづくりを行いたいですね。そして、制作した動画コンテンツは、夏休みの自由研究として学校に提出できるように、データ保存できるようになればと思っています。
株式会社 電通グループ 鈴木 淳一氏 Q:NFTアート作品を学校の夏休みの自由研究として提出するというのは、あまり他に例のない話ですね。
鈴木: 「ghost Link」の世界観として、NFTを付与することを「憑依」という言葉で紹介しましたが、憑依することでいろいろな能力が手に入るわけです。現時点ではn次創作する権利だけですが、今後はもっと現実世界に影響を与える能力も想定しています。例えば、憑依された人が近づくことで照明がついたり、周囲に流れるBGMが変わったり。IoT技術と掛け合わせて個人が所持するNFTをセンシング(検出し情報を取得する技術)する環境を作ることで、「NFTとリアル世界との間に何らかのインタラクションが起こる」ことも可能になります。
NFTの利活用で、社会はどのように変わるのか Q:今のお話にあった、NFTを所有していることで、照明がついたりBGMが変わったりという状況は、NFTがこれまでのような仮想空間にとどまらず実空間へ広がっていくという一例として、非常に興味深いですね。鈴木さんが近年取り組まれているNFTを活用した事例について、もう少し具体的に紹介いただけますか。
鈴木: まずは先ほど少し触れた、卒業証明書などの「教育履歴の証明」です。落合氏のサマースクール受講証明NFTは、将来の受験などに備えた課外学習履歴の証明のほかにも、次回のサマースクールに優先的に参加する権利や、その権利を他者に譲渡するという分かりやすいインセンティブとして展開することもできます。つながループ 」という家庭用のコンポストで堆肥を作り市民農園などで活用する取り組みや、地域住民・農園・企業などが一体となって食資源循環社会の実現に取り組むコミュニティー活動を、NFTを用いて活性化させる仕掛けです。
Q:現在、近畿大学でも大規模なNFTの実証実験が行われているそうですね。
鈴木: はい。近畿大学で個人の体験を価値化するWeb3.0の取り組みとして、2023年4月から「アプデミー 」β版の実証実験を開始しています。まずは、4月1日に行われた2023年度の入学式で、新入生を対象に入学式に参加したことを証明するNFTを、学内ポスターや大型スクリーンに投影されたQRコードを読み取ってもらう形で配布しました。今後は、入学証明書のほか大学内でのさまざまな体験や学びの実績をNFTとして配布していく予定です。
Q:今まさにいろいろな取り組みが動いているということですね。では、最後に今後の展望について教えてください。
鈴木: Web3.0の基本は、活動履歴やそれに基づく与信など、個人が所有するあらゆる資産をデジタル化し、主体的に管理・活用するユーザーエコノミーであると言われています。しかし、現時点ではそれを実感するサービスの提供までは辿り着けていません。NFTなどの社会的なマス・アダプションには、NFT単体でなくハードウェアウォレットといったICカード型のデバイスに秘密鍵を格納することでウォレットのセキュリティー耐性を向上させるなど、自己主権の裏返しである自己責任について、低減する手法が求められます。また技術が優れていれば利活用が進むとも限りませんから、さまざまな先端技術を活用するとともに、企業や教育機関、自治体、マスコミなど幅広い分野と共創することで、個人がメリットを感じられるようなインセンティブの開発やシンプルで簡便なサービス動線を生み出していきたいと思っています。
コンテンツのn次創作の可能性を大きく広げた「ghost Link」。さらに、その技術を応用することで、NFTは教育業界や地域活動などにも変革をもたらしはじめています。
NFTを用いて個人の行動履歴をはじめとするあらゆる情報を自分自身で管理・活用することが当たり前になれば、これまでになかったビジネスの創出や、全く新しい社会の仕組みの構築が可能になりそうです。