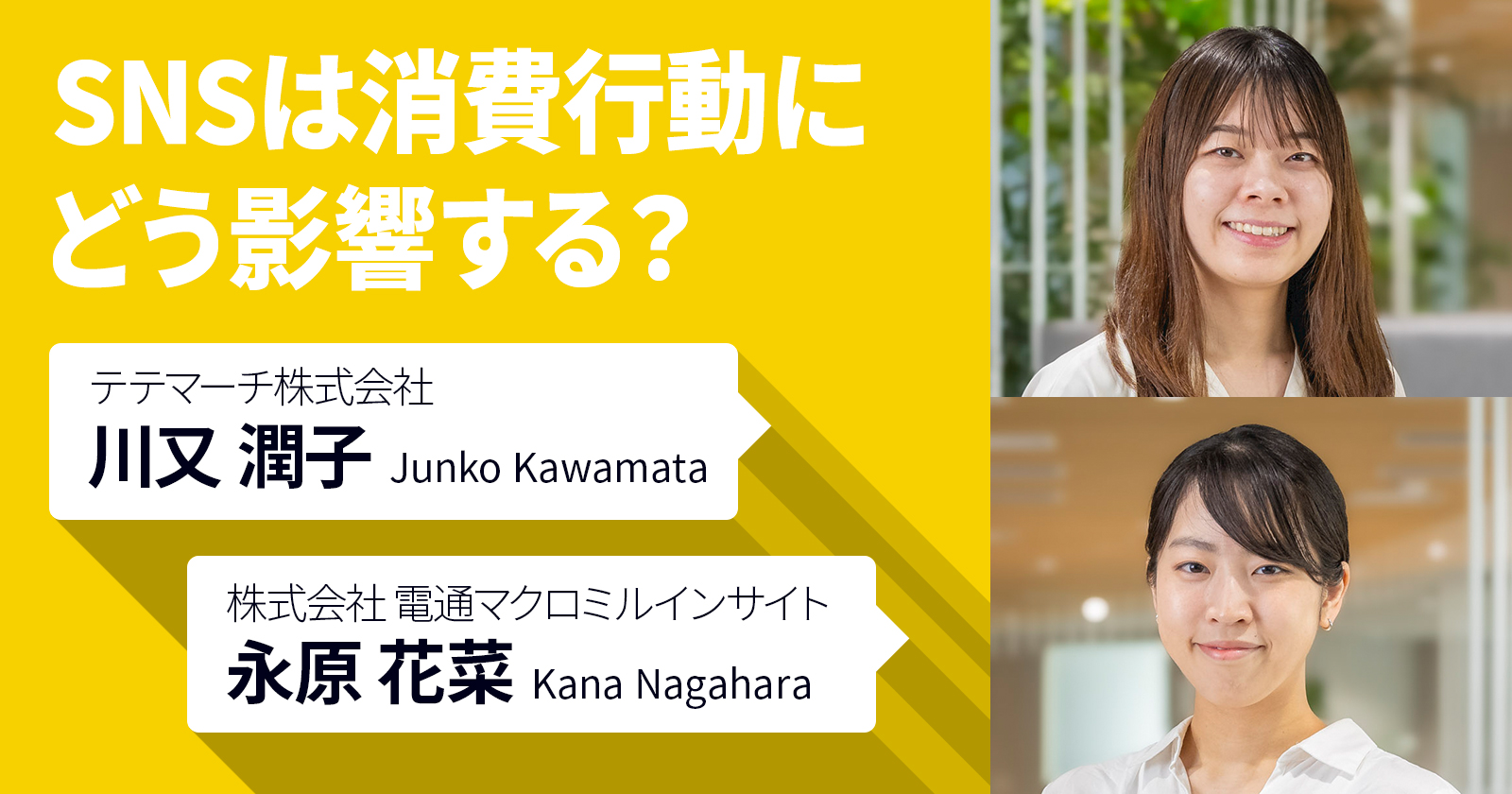Instagram・X・TikTokの使い方を2000名調査。消費行動モデルから考えるSNSマーケティング戦略(後編)

川又 潤子
テテマーチ株式会社

永原 花菜
株式会社 電通マクロミルインサイト
SNSが浸透し、消費者の購買行動にも大きな影響を及ぼす中、SNSアカウント運用やSNSマーケティングにお悩みの企業も増えています。そんな中、株式会社 電通マクロミルインサイトとテテマーチ株式会社は、SNSユーザー2,000名を対象に利用実態を共同調査しました。この調査結果をどのようにマーケティングに活用すべきか、電通マクロミルインサイトの永原花菜氏とテテマーチの川又潤子氏に聞きました。インタビュー後編では、消費者行動モデル「PERCARS(パーカーズ)」に基づくSNSの活用法、その成功事例に迫ります。
消費行動の起点は、SNSで受動的に得た情報
Q.テテマーチでは、SNS時代の消費行動モデル「PERCARS(パーカーズ)」を提唱しています。こちらはどのようなモデルでしょうか。

Q.SNSユーザーの消費行動を踏まえ、どうすればSNSをマーケティングに有効活用できると思いますか?

ターゲットの解像度を上げ、発話を生む仕掛けを投下する
Q.「PERCARS」に基づくSNSマーケティングの成功事例を教えてください。

Q.「どんどん発話が生まれた」とお話されていましたが、SNSマーケティングではターゲット層の間で話題になり、共有されていくことが大事なのでしょうか。
SNSは魔法ではない。入念なユーザー調査がマーケティングの第一歩
Q.今回の調査を踏まえ、今後のSNSマーケティングで重視すべき点を教えてください。

Q.今後もSNSを活用したマーケティングはますます影響力を強めていきそうです。

Z世代に続き、2010~2024年生まれを指す「α世代」が、デジタルネイティブとして注目されています。企業のマーケティング担当者は、より若い世代のSNS利用状況も把握し、ターゲットに対してどうアプローチをしていくか考える必要があるでしょう。今回の調査結果を踏まえ、今一度SNSマーケティングを見直してはいかがでしょうか。
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

川又 潤子
テテマーチ株式会社
Z世代マーケ研究室「lookey」
プロジェクトリーダー
1995年生まれ。Z世代マーケ研究室「lookey」のプロジェクトリーダー。2019年にテテマーチ株式会社JOIN後、SNSプランナー、プロデューサーとしてInstagram・X(旧Twitter)を中心としたSNSマーケティングにおける戦略・企画設計を手掛ける。若年層マーケティングを得意とし、大学生と企業担当者をつなぐイベント「インスタゼミ」立ち上げ。以降、SNSアカウント運用・キャスティング・キャンペーンまで本質的な企業プロモーション施策の企画、提案を行っている。

永原 花菜
株式会社 電通マクロミルインサイト
リサーチプランナー
2022年株式会社 電通マクロミルインサイト入社。食品やゲーム、不動産など幅広いカテゴリーの商材に潜在する生活者インサイトを起点に、コミュニケーションプランニングやPDCAサイクルの構築支援に従事。