企業、スポーツ団体、生活者の「スポーツの価値」を可視化する、「スポーツの地図」とは?
電通は、競技団体やリーグ、クラブなどのスポーツ団体、およびスポーツをマーケティング活用する企業の事業成長を支援し、魅力的な体験の創出など生活者にとっての価値へと循環させるための戦略フレームワーク「スポーツの地図ver1.0」(以下、スポーツの地図)を開発しました。
本記事では、スポーツの地図を開発したメンバーが集まり、スポーツコンテンツやスポーツ団体が抱える課題、スポーツの地図の開発背景とポイント、活用事例について語り合いました。

企業全体でスポーツの価値を共有できる地図が必要
川堀:始めに自己紹介を。私は、電通のスポーツビジネスソリューション局(以下、SBS局)に所属しています。SBS局は、ステークホルダーと連携し、スポーツを通して世の中にさまざまな価値を生み出す取り組みを行っている組織です。
中北:同じくSBS局に所属しています。スポーツをマーケティングに活用する企業や、スポーツ団体と向き合い、データに基づいたマーケティング戦略や企画のプランニングを行なっています。
林:私は、第5マーケティング局に所属しており、事業戦略やマーケティング関連の領域の仕事をしています。特にスポーツ関連の案件が多く、スポーツを活用した企業のマーケティング支援や、競技団体の事業戦略のコンサルティングに携わっています。
川堀:今回、SBS局メンバーや、林さんのようにスポーツ関連の案件に携わるマーケター、外部コンサルタントが集まって、スポーツの地図を作ったわけですが、まず、企業によるスポーツのマーケティング活用がどのように変化しているか、改めてお伝えしたいと思います。
大きく4つのフェーズがあったと理解しています。はじまりは、金銭的支援を中心とした寄付的な関わり方が多かったのですが、その後、競技が成長してくるとテレビに企業の看板やロゴが映るといった露出価値が生まれ、メディアとしてスポーツが捉えられるようになりました。2000年代になると、グッズを作りや販促キャンペーンに取り組むなど、単なるメディアをこえてマーケティングに活用するケースが増えてきました。
最近では、元来スポーツが持ち合わせている価値である社会や人とのつながりなどに注目が集まり、マーケティングだけでなく社会貢献や社会課題解決に資するスポーツの活用という視点も生まれ、企業がスポーツを活用する目的は多様化しています。
いまの時代、「統合諸表ver1.0」(概要はこちら)にも表されているように、企業は利益を上げることだけでなく、多様なステークホルダーに対して価値を生み出していく必要があり、解決すべきさまざまな課題を抱えています。その課題解決に、スポーツが持つ価値を活用できるのではと考える企業が増えていると感じます。
とはいうものの、具体的にスポーツにはどんな価値があり、何ができるのかがイメージできず、十分に活用できていない、活用に踏み込めない企業もまた、多いと感じています。
中北:スポーツが企業のマーケティング活動や事業成長にどのように貢献できるのか、論理的・体系的に説明できるものは、これまでほとんどありませんでした。電通でもスポーツの活用手法についてはマーケターや担当者の経験則や各々のロジックのもとに提案されてきました。
林:そうですね。企業側にもスポーツのマーケティング活用についての明確な方法論が定まっていないので、それぞれの過去の経験や実績をもとに取り組まれていることが多いのが現状です。そのため、メソッド化することによって、より多くの企業にとってスポーツを企業戦略やマーケティング戦略として活用してほしいという思いもありました。
川堀:企業は、部署によってそれぞれ違う目線や目的を持っていて、何のためにスポーツを活用しているのか、全社での共通認識を持てていないケースもありますよね。
中北:はい。共通言語が持てなかったり、部署ごとに意識しているKGI/KPIが違ったり、共通の指標を持ってスポーツをマーケティング活用する意義を語れるものがありませんでした。
林:企業課題が複雑化するに伴い、多くの企業がスポーツの価値に注目するようになっています。そんな今こそ、何のためにスポーツを活用するのか、複数の部署やステークホルダーと同じ目線や目的を持つ“羅針盤”のようなものが必要だと感じたのが、スポーツの地図の作成に取り組むきっかけとなりました。

企業、スポーツ団体、生活者の三者がWin-Winの関係になることが目的
川堀:改めて、スポーツの地図とはどのようなものか説明をお願いします。
中北:スポーツビジネスに関わる多様なステークホルダーが、共通の認識と視点を持って戦略・戦術を議論し、意思決定できるようにすることを目的としています。スポーツマーケティングの目的やKGI/KPIの設計、アクティベーションの方向性、必要なアセットの可視化など、事業成長というゴールにつながる道のりを体系的に整理し、そのゴールに到達するための「地図」の役割を果たすものです。
スポーツの地図は、企業向けとスポーツ団体向けの2種類があります。スポーツの地図を作るにあたり、スポーツコンテンツが、企業と団体の事業成長やマーケティング活動にどう寄与できるのか、その要素や要因を網羅的に洗い出しました。そして、因果関係を体系的に整理した戦略フレームワークになっています。
地図はそれぞれ別々のものではなく、例えば、スポーツ団体とともに、この地図を使ってスポーツの価値向上に取り組むことで、サポートしている企業のマーケティング活動にも還元される好循環を生み出せると考えています。
●企業のスポーツマーケティングの戦略設計をサポート(スポーツの地図 for Business Partners)
スポーツの地図は、既にスポーツをマーケティング活用している企業に対しては、現状の施策と目標との整合性を診断し、より効果的な活用方法を導き出す支援を行う。また、新たにスポンサーシップの活用を検討する企業に対しては、マーケティング課題の可視化と仮説構築を通じて、最適な戦略設計の立案をサポートする。

●スポーツ団体の事業成長にも貢献(スポーツの地図 for Sports Organizations)
競技団体やリーグ、クラブなどのスポーツ団体に対しては、ゴールを達成するための重要な変数や因子、またその因子を刺激するのに必要な要素であるアセットを体系的に整理。ゴールにたどり着くためにすべきことの設計を支援することで、スポーツコンテンツ自体の価値向上にも寄与する。

林:企業は、マーケティング活用以外にも、ESGなども含めたコーポレート活動や、インターナルコミュニケーション、企業文化づくりにスポーツを活用することもあります。そういったことも網羅できるように設計しています。また、最近ではROI(Return On Investment:投資利益率)の視点が求められるケースも増えていますが、スポーツに投資した効果も見えるようにしています。
中北:そうですね、財務と非財務の両面でスポーツの価値が可視化できていることがこの地図の特徴ですね。スポーツには、人と人とのつながり・一体感を生み出す、人を勇気づける、気分転換になる、健康づくりに役立つ、地域の活性化に貢献できるなど、いろいろな社会的な役割があると思います。スポーツの地図を活用して、企業とスポーツ団体がこのようなさまざまなスポーツの価値を再認識することで、企業、スポーツ団体、生活者の三者がWin-Winの関係になれるきっかけになればと考えています。

スポーツの地図によって、企業が享受しているさまざまな価値が見えてくる
中北:ここからは、スポーツの地図を活用した事例をお伝えします。私が紹介するのは、あるスポーツ大会のオフィシャルパートナーになったクライアント企業の事例です。スポーツをどのようにマーケティングに活用していけばよいかをスポーツの地図をもとに考えました。
このクライアントが行ったブランド調査によると、世の中からの信頼度は高く、技術力も認められていたのですが、クリエイティビティ、イノベーティブ、新しいことにチャレンジといったスコアが相対的に低かった。そこで、アクティベーション施策は、売り上げをKPIとせず、課題となる企業イメージの向上を通じて、企業ブランドのファンを増やし、社会的価値や企業価値を上げていくことでクライアントと合意できました。
さまざまなアクティベーション施策を検討する中で、その施策がどのイメージ強化に寄与し、このクライアントのファンの拡大につながるのか、スポーツの地図を使って目的から逆算しながらクライアントと施策を組み立てていきました。さまざまな施策を展開しましたが、早い段階で目的が明確に定まっていたため、大会後の成果を把握するためにどんな調査を行ってPDCAを回していけばよいかについてもスムーズに議論することができました。
川堀:スポーツの地図を使うことで現場の担当者だけでなく、経営層も含めて最終的に目指すことが理解できたので、共通認識を作るという意味でとても役立ちましたよね。他に事例はありますか?
中北:あるスポーツリーグのタイトルパートナーになっている企業に対してもスポーツの地図を活用しています。タイトルパートナーを務める意義をスポーツの地図を使って整理したところ、とても分かりやすいという声をいただきました。
この企業は、自社の認知拡大がタイトルパートナーを務める主目的だったので、企業認知がどれくらい上がったかという指標だけで、タイトルパートナーを継続するか否かを判断しようとしていました。
そこで、スポーツの地図を使うことで、タイトルパートナーを務めることにより、各チームへの営業活動のルートができたことや、社内向けには、試合のチケットが福利厚生として社員に人気があることもタイトルパートナーの成果であることを再認識していただきました。
川堀:スポーツのマーケティング活用は、いろいろな効果が出ていることに気づかないことがありますよね。スポーツの地図で俯瞰(ふかん)して見ると、実は企業が享受できている価値に気づくきっかけを与えられるということですね。

林:そうですね。採用活動に役立っていたとか。社員同士の交流につながっているとか、いろいろなところに好影響が出ているケースがあります。
これは事例ではないのですが、スポーツ×企業において、金融機関や流通系の企業などでは、本社と支店がバラバラに競技団体やチームを支援しているケースがあります。その背景には、各支店の営業活動や昔からのお付き合いといった側面があり、企業全体のマーケティング視点で見ると複雑化しているケースがあります。そういったケースでは、それぞれの支援の目的が何か、企業全体としてスポーツマーケティングをどう考えていくか整理するときにも役立ちます。
中北:確かに。他にも、スポーツのマーケティング活用では、「どのスポーツが良いのか」という話に終始することがあります。それでは目的を見失ってしまい、どこかの時点でスポーツの活用に疑問を感じてしまうこともある。そうではなく、まずは目的や意義を定めた上で競技を考える。そのように、スポーツの地図を役立てることもできるかなと思います。
川堀:スポーツ団体の事業成長という点で、スポーツの地図はどのように役立ちそうですか?
林:スポーツ団体は、自分たちが行っている競技を成長させるために、どうすれば人気が出るかということばかり考えてしまうことが多いんです。確かに、それはとても大事ですが、成長プロセスを俯瞰して考えることも必要です。例えば、競技人口を増やすという成長の方法もあれば、いろいろな観戦手法を増やしたり、パラスポーツ的な視点での成長もあります。スポーツの地図で、成長に向けたストーリーを考えるヒントになるのではないでしょうか。
中北:スポーツ団体・スポーツの中期的な成長のために、どのようなKGIを定めて、経済価値と社会価値を上げていく必要があるか、バックキャストで考えることが大事です。短期的なチケットセールスにとどまらずに、視座を引き上げるためにもスポーツの地図は役立ちそうですね。
川堀:本日、スポーツの地図について語り合って、企業、スポーツ団体ともに、スポーツの地図の活用可能性が改めて見えてきました。
林:スポーツをマーケティング活用したいが、検討には至っていない企業も多いと思います。どうしたらよいか分からない場合のきっかけにしてもらいたいですね。
川堀:スポーツは価値が見えにくい側面がありますが、その価値を明らかにしていくときにぜひ、スポーツの地図を役立ていただけるとうれしいですね。
「スポーツの地図」に関する詳細や導入に関する問い合わせ:sports-solution@dentsu.co.jp
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

川堀 登史
株式会社 電通
スポーツビジネスソリューション局 ソリューション3部
部長
入社後、サッカー事業局でサッカーの国際イベントの担当としてスポーツマーケティングの専門性を身に付ける。その後、営業局に異動し大手アパレル企業のクリエイティブ制作・プロデュースに従事、また同企業のマーケティング部へも出向しマーケティングストラテジーの構築から商品開発まで関わる。現局では、スポーツとブランド側双方の経験を生かして、スポーツにおける新たなビジネス開発やブランド側のスポーツ活用戦略構築やコミュニケーションプランニングにも取り組む。
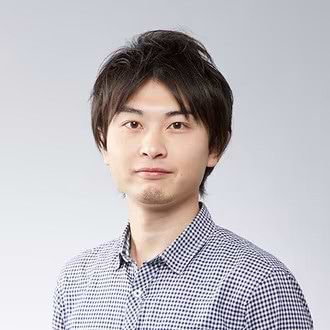
中北 隆盛
株式会社 電通
スポーツビジネスソリューション局 ソリューション3部
プランニング・ディレクター
マーケティング部門にて、商品・サービス開発・ブランディング、事業コンサルティング、都市開発等、幅広く戦略・企画のプランニングに携わる。近年は、国際スポーツ大会やサッカー/ラグビー日本代表のコミュニケーション戦略、パートナー企業の戦略・企画・PDCAなどスポーツ領域の戦略プランニングを中心に従事。日本マーケティング協会(JMA)認定マーケティング・マスター。宣伝会議「ストラテジックプランニング講座」講師。

林 将宏
株式会社 電通
第1統合ソリューション局
ソリューションプランナー
コンサルティングファームを経て入社。戦略コンサルティングとマーケティングコミュニケーションの経験を融合させ、独自の事業コンサルティングサービスを提供。

