Rokt×楽天×メルカリ なぜ今、“デジタル”リテールメディアなのか

秦 俊輔
楽天グループ 株式会社

赤星 大偉
株式会社 メルカリ

三島 健
Rokt 合同会社
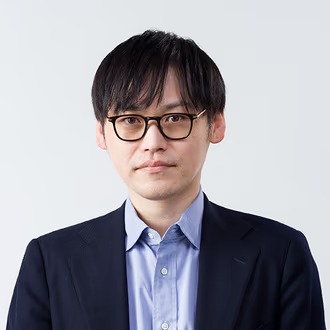
千葉 健司
株式会社 電通デジタル
去る7月25日(金)、国内外でEC領域をけん引する3社が一堂に会し、ECプラットフォームを軸に広告価値と顧客体験を両立させるデジタルリテールメディアの未来をテーマに各社の知見と事例を共有するカンファレンス「Rokt・楽天・メルカリ共催:Digital Retail Media Conference 2025」が開催されました。
記事では、同カンファレンスに参加した楽天グループ・秦俊輔氏、メルカリ・赤星大偉氏、Rokt・三島健氏をパネラーに、電通デジタル・千葉健司氏をモデレーターに迎え、デジタルリテールメディアの現在地と可能性についてディスカッションを行いました。

パネラー:
秦俊輔 楽天グループ マーケットプレイス事業 アカウントイノベーションオフィス ヴァイスジェネラルマネージャー
赤星大偉 メルカリ Head of Ads Business
三島 健 Rokt Head of Japan, Vice President
モデレーター:
千葉健司 電通デジタル コマース&プロモーション部門 部門長
デジタルの強みを生かしたリテールメディア
千葉:今、私たちは開演を2時間後に控えた「Digital Retail Media Conference 2025」の会場にいるわけですが、「リテールメディア」の前に「デジタル」とあるのが象徴的だなと感じています。いわゆる一般的なリテールメディアに対して、デジタルの視点からのアプローチに焦点を当てる意図がそこにはあると理解していますが、いかがでしょう。
秦:「リテールメディア」という言葉を日本でもよく聞くようになりましたが、メーカーやブランドの担当者の方と話をしていると、店舗内に設置されたサイネージのような、いわゆるオフラインのイメージを皆さん強く持っているようです。
これがアメリカだと、リテールメディアのイメージは日本とはまた違ってきます。市場においてAmazonをはじめとするECプラットフォーム、つまりオンラインの売り上げが大きいことから、リテールメディアのイメージもオンラインが優勢になっています。
「デジタル」と明示した今回のカンファレンスでは、オフラインではないデジタルリテールメディアが存在すること、そしてオンラインならではの価値があることを、来場者に知ってほしいと考えています。

三島:オフラインとオンラインでは、買い物行動、つまりユーザージャーニーがまるで違います。店舗だと棚の前に行って考えたり、店内をぐるっと回っていろいろなカテゴリーの商品を見たり……といった形になりますが、オンラインではまずカテゴリーで探して、そこから商品を深掘りに行って、もろもろの比較をして、これにしよう……というようにショッピングファネルが深くなっていきます。
そうなると、オフラインとオンラインでリテールメディアの役割も変わってきます。オフラインの典型的な例として店舗内のデジタルサイネージを考えると、その役割はブランドマーケティングにやや近いと思います。ファネルやジャーニーの早期のところからのアプローチになります。
一方、オンラインではお客さまが何を探しているのか、ショッピングファネルのどこにいるのかがわかるので、お客さまに示せるもの、示せるタイミング、その精度がまるで違ってきます。
オフラインは基本的には「知ってもらう・見てもらう」という認知ファネルであるのに対し、オンラインはダイレクトに「商品を買ってください・触れてください」というアプローチになるので、購入への影響も大きいのがデジタルリテールメディアの特徴ではないでしょうか。
秦:オンライン/オフラインを問わず、リテールメディアの価値の一つに「ユーザーの買い物のモードを捉えてコミュニケーションできる」ことがあります。加えて、オンラインのメリットは、その成果をトラッキングしてデータを蓄積できることです。その意味でも、今回のようにデジタルに特化したリテールメディアの特徴などについて発信していく意義はあるかと思っています。
千葉:デジタルリテールメディアには、いわゆるオフラインのリテールメディアとはまた違った特徴と役割、メリットがあることがよくわかりました。
続いて、皆さんのリテールメディアへの取り組みについて伺いたいと思います。メルカリは今年から「メルカリAds」(※)を始めましたね。
※メルカリが提供する広告配信サービス。クリック課金型広告で、メルカリ内の検索結果画面に検索キーワードなどに合わせた広告を掲載することが可能。
赤星:一定のユーザー規模を持つサービスの事業主なら、広告事業は考えると思います。私たちメルカリ中でも、その選択肢はずっとありました。と同時に、どういう広告事業がメルカリに合うのか、B to Cではなく、C to Cという独特なマーケットプレイスの上で展開される広告事業とはどういう形のものなのか、ずっと模索していました。ようやく、おそらくこの形かなというのが見え始めて、大々的にプレスリリースすることになりました。グローバルでみても、似たようなことをこの規模でやっているプラットフォームはないでしょう。とてもユニークなものになっていると思います。

千葉:メルカリ社内では、これをリテールメディアと捉えているのですか。
赤星:当初、社内ではリテールメディアについて、さほどクリアなイメージを持っていなかったと思います。ただ、GMV(※)の成長とともに、社として第2、第3の売り上げの柱をどう作っていくのかは重要な課題であり、その候補の一つにメルカリAdsがありました。昨今リテールメディアがトレンドになる中、多くの広告主や広告会社に興味を持っていただけています。
※「Gross Merchandise Value」の略で、日本語では「流通取引総額」と訳される。ECサイトやプラットフォームビジネスにおいて、商品やサービスの総売上高を示す指標として用いられる。
販促とブランドマーケティングの融合を目指して
千葉:クライアントは広告予算と販促予算を持っているわけですが、リテールメディアに対しては販促予算から当てられるケースが多いかと思います。一方で、最近は徐々に広告予算から当てる動きも広がってきているように思います。メルカリAdsの場合、どちらの予算を想定しているのでしょうか。
赤星:メルカリは広告事業をスタートしたばかりということもあって、広告予算をまずは想定するところからスタートした方がいいかなと思っています。とはいえ、ECプラットフォームが伸長してきて、広告費と売り上げのコンバージョンがちゃんと分析できるようになってくると、もはや広告費と販促費を厳密に分ける必要はないのかもしれません。現在、日本のEC化率は10%ぐらいですが、これが上がっていくと、さらにこの境目がなくなっていくのではないでしょうか。
千葉:楽天では、広告予算と販促予算についてどう考えていますか。
秦:楽天市場は「買い場である」というイメージが色濃くあるので、私たちが普段メーカーや大手企業とやり取りする予算というのは、いわゆる営業予算が大半を占めます。すなわち、EC営業予算という形です。
一方で、今後はブランド予算や宣伝予算に対しても、楽天市場および楽天グループのメディアの活用価値をしっかり作っていくことで応えられるようにしたいと思っています。販促とブランドマーケティングがどんどん融合されていくようになっていくと、私たちのようなプレーヤーの価値はどんどん上がっていくのではないでしょうか。
三島: 宣伝を「認知」、販促を「比較」「購買」のようにファネルの視点で考えたとき、クライアントがどのファネルに属していたとしても成果にコミットすることは可能と考えています。そうした観点から、広告費なのか販促費なのかという問題は、さほど意識してなくてもよいのではないかと思っています。
千葉:ユーザーの買い物モードを捉えられるという価値を最大限に生かして、販促とブランドマーケティングの融合を目指すべきだということですね。

千葉:自分たちのビジネスをさらに成長させるために、あるいは生活者により豊かな体験を提供するために、ここが突破できればというポイントはありますか。
秦:楽天市場は、コンバージョンを目的とした取り組みでは、一定の成功を収めてきたという自負があります。
マーケティング予算やブランド予算を想定した取り組みも徐々に増えてきてはいますが、まだまだ案件数でいうと限定的です。ここの領域での取り組みを増やすことができると、顧客に対してもより良い購買体験を提供できると思いますし、私たちのビジネスも拡大していくので、まさに突破したい領域です。
楽天市場を活用するときに、「指名買いでしか使わない」という方は、わずか5%に過ぎません。「とりあえず行ってみる」というモーメントであり、認知から理解・検討・購買のファネルが一気通貫で行われている状態です。だからこそ、ブランディングのアプローチが楽天市場では有効だと考えています。多くのメーカーが「アッパーファネルのことも楽天市場と一緒にやっていこう」ということになると、面白くなってくると思っています。
赤星:私たちデジタルの世界にいる人間からすると、データドリブンマーケティングは当たり前で体に染み付いています。メルカリは二次流通が主な市場ではありますが、ファーストパーティデータをたくさん持っています。
一方で、データをフル活用した意思決定やマーケティングにまだまだ躊躇(ちゅうちょ)するメーカーや広告主、事業主も少なくないようです。ですから、まずは私たちとクライアントの間にあるマーケティングに対する認識のギャップを埋めていく必要があるのかなと感じています。
三島:オンラインはマーケティングのスピードが速いですよね。そして、わかりやすい。そうなると意思決定のプロセスもどんどん速くなってきます。
秦:赤星さんがお話しされたことはすごくヒントがあって、私たちも目指したいのは、統合マーケティングプラットフォームとしてのポジショニングなんですね。マーケティングの最初のステージである商品開発の部分においても、私たちが持っているファーストパーティデータは間違いなく価値があるはずです。
ターゲットに関するデータをベースにメーカーと一緒に商品開発を行い、楽天市場でテストマーケティングを行い、どういったユーザーに刺さったか/刺さらなかったか、その理由は何だろう……と深掘りする。それに基づいて商品をブラッシュアップし、販売戦略を立てて、売っていく……というように、マーケティング全般を捉えながら、私たちはメーカーに伴走できると思っています。それは課題というよりも、むしろ機会と考えています。
千葉:特に楽天の場合、それがワンストップで全て提供できるのは強みですね。
電通グループとの連携で広がる可能性
千葉:Roktは独自のサービス提供で成功されていますが、課題はあるのでしょうか。
三島:課題はいろいろありますが、大きくは二つあります。一つは、Rokt はEC事業者に対して広告事業を始めるためのソリューションを提供しているわけですが、それをどう簡単に実装するのかということです。
もう一つは、EC事業者に対して「リテールメディアはユーザージャーニーにおける新しいチャネルですよ」「広告事業を行うことでユーザーを獲得できますよ」と説得することの難しさです。
どちらも簡単ではありません。自社で広告事業をやったことのないEC事業者は物販が収益の主戦場になっているので、広告事業については考えてもいないケースも少なくないのです。そうなると、先方のどの部署や組織の方と話をすれば良いのかが、最初の壁になります。

秦:誰と話すかというのは、確かに重要ですね。
千葉:マーケティング全体を管轄しているCMO(Chief Marketing Officer)のような立場の人と話すのが良いのかもしれません。
秦:それこそメルカリの広告事業の導入は、赤星さんがいなかったら進まなかったのではないですか? 赤星さんのように広告収益の旗を掲げた人がいたからこそ、前に進んだのではないですか?
赤星:この業界はGMV至上主義的なところがあるので、「広告事業を始めましょう」と言っても、「それでGMVが上がるの?」という話になりがちです。そこにおそらく大きなミスマッチがあるのだと思います。
Roktが提供しうる価値を考えると、最終的にはその会社のCFO(Chief Financial Officer)と話をすべきなのではないでしょうか。GMVがどうこうという話ではなく、PL(損益計算書)の話をした方がいいように思います。
秦:まったく新しい領域だから、先方のキーマンを探すのが大変ですよね。
千葉:そうしたところに電通グループの存在価値があるのかなと思っています。なぜなら、「翻訳して、きちんと相手に伝えることができる」のが電通グループの一つの強みだと思っていますし、対応できる組織と人財を持っていますから。
三島:Rokt の立場からすると、まさにそこに期待しています。Roktはプロダクトを持ってはいますが、お客さまとのコミュニケーションにおいて言語化がきちんとできていないところに課題があると感じていましたから。
お客さまと話をするとき、マーケティングのチームにアプローチするのが良いのか、ファイナンスの組織にアプローチするのが良いのか、電通グループの知見を生かしてステークホルダーの観点から解きほぐしていただけると大変助かります。
赤星:メルカリとしては、広告出稿の領域だけでなく、データ利活用の領域でも電通グループと一緒に取り組んでいきたいなと思っています。メルカリが持つデータを使って、メーカーの商品開発に生かしたり、プライシングに生かしたりできれば、マーケティングだけでなく、社会全体が良い方向にいくのではないかと考えています。
秦:私たちECプラットフォームの強みが販促領域にあるのに対して、電通グループの強みはアッパーファネルの領域にあると認識していますので、その部分で連携できたらと思っています。
具体的には、私たちが持つデータをどう活用して、どうPDCAを回していくべきか、といった部分で電通グループの知見を参考にできると、クオリティの高いアウトプットが可能になると信じています。
また、AIの活用も注目しているテーマです。電通グループのAIは広告やマーケティング領域に特化した形での開発が進んでいるので、私たちが持っているデータとうまく連携すれば、お客さまやメーカーに対してより良い体験を提供できるのではないかと期待しています。
千葉:皆さんから電通グループとの連携への可能性と期待の声をいただき、大変ありがたく思っています。
ディスカッションを通して、デジタルリテールメディアの現在地と可能性を感じることができました。また一方で、克服すべき課題もあることを認識しました。デジタルリテールメディアという新しい領域で、今後皆さんと連携できるのが楽しみですし、電通グループとしても皆さんの期待に応えられるような存在でありたいと思っています。
本日はありがとうございました。

※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

秦 俊輔
楽天グループ 株式会社
マーケットプレイス事業 アカウントイノベーションオフィス
ヴァイスジェネラルマネージャー
2009年楽天グループに入社。広告事業配属後、広告代理店担当の営業を担当し2017年には電通との合弁会社である楽天データマーケティングの立ち上げに携わる。2019年Yahoo!JAPANに入社。PayPay販促ソリューション、東京2020の企画・販売に携わる。また、ヤフー×指名手配捜査支援プロジェクトで広告電通賞 入賞。 2021年再び楽天グループに戻り、「楽天市場」とメーカーとの協業でビジネス拡大を図る部署(AIO)の立ち上げ及び、コンサル部門の責任者を務める。

赤星 大偉
株式会社 メルカリ
Head of Ads Business
デジタル広告領域に15年在籍、広告メディア会社(ヤフー・Meta・ByteDance・SmartNews)にて、ソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、広告主営業、事業責任者を経験。2023年より現職にて、メルカリの広告事業立ち上げに従事。

三島 健
Rokt 合同会社
Head of Japan
Expedia、HRSにて代表取締役を務め、大手日本企業のオンライン事業におけるデジタルトランスフォーメーションの戦略策定&推進に携わるなどテクノロジー業界で豊富な経験を持つ。その後、Googleの広告営業にてリテール市場向けプロダクトの推進を行い、2023年よりRoktへ。以降、Rokt日本代表としてEC事業者の収益増を可能とするソリューション導入に向けた支援を進めている。
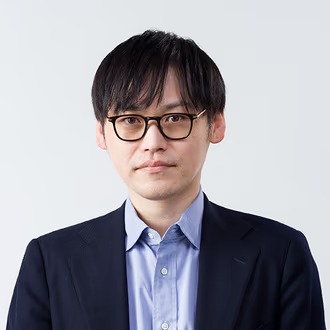
千葉 健司
株式会社 電通デジタル
コマース&プロモーション部門
部門長
大学院を卒業後、教育機関に特化した代理店を経て、DAサーチ&リンク(現:電通ダイレクト)にてデジタル広告のコンサルタントを経験。その後、電通へ出向して年間100件以上の提案/競合コンペに参加。2019年より電通デジタルに籍を移してコマース領域に従事。2025年から部門長としてECモール活用やリテールメディア、デジタル販促を含めた販促全般を統括。