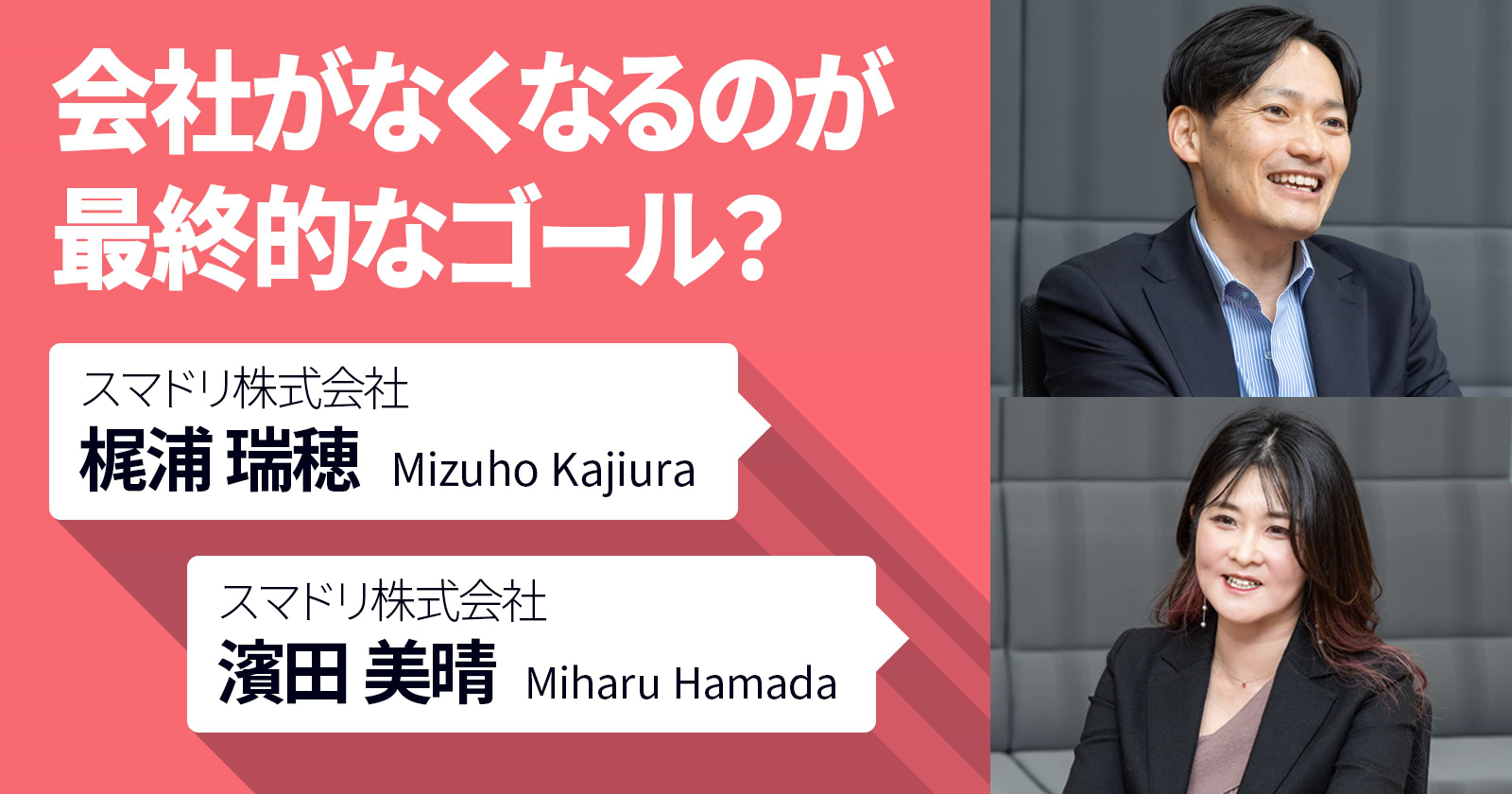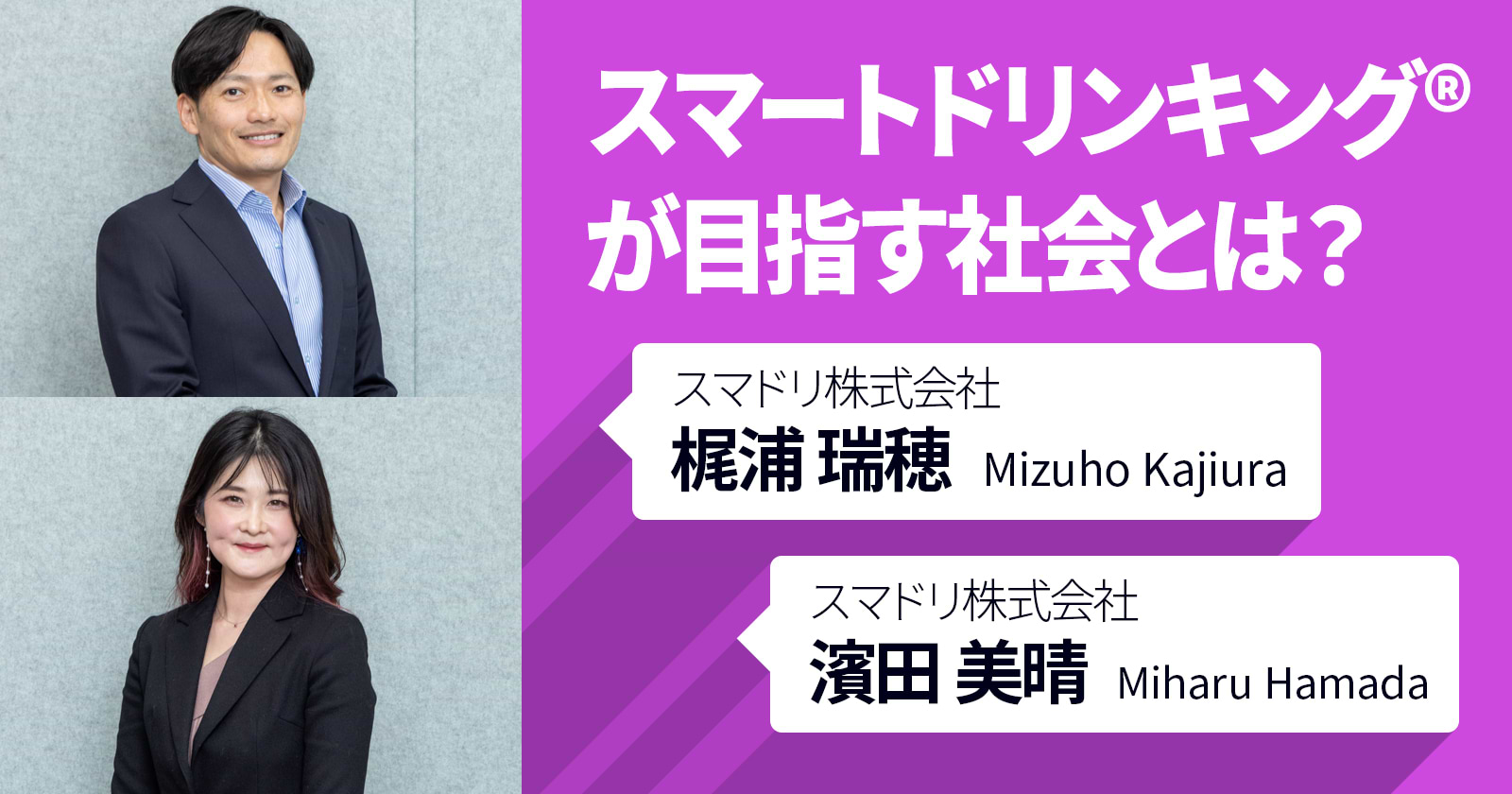ミレニアル世代、Z世代を中心に、お酒を飲まないライフスタイルが広がっています。欧米では、体質的にはお酒を飲めてもあえて飲まない「ソバーキュリアス」という価値観が注目を集めているようです。こうした流れを受け、2022年1月にアサヒビール株式会社と株式会社電通デジタルは、飲まない/飲めない人を対象にデジタルマーケティングを行う合弁会社「スマドリ株式会社」を設立しました。
代表取締役社長の梶浦瑞穂氏、創業メンバーである電通デジタルの濱田美晴氏へのインタビュー前編では、「スマートドリンキング®︎」という考え方、新たな顧客開拓の必要性についてお話を伺いました。後編では、協業する意義、スマドリ設立後の変化などについて、さらに深くお話しいただきます。
伝統あるアサヒビールが、デジタルに強い会社と組むことで価値が生まれる
Q.アサヒビールは2020年12月に、お酒を飲む人/飲まない人、双方の生き方を尊重する「スマートドリンキング®︎」を提唱しました。その後、2022年に電通デジタルとともに合弁会社スマドリを設立します。アサヒビールがデジタルマーケティングに強みを持つ電通デジタルと手を組んだのはなぜでしょう。梶浦さんは、電通デジタルのどのような面に可能性を感じたのでしょうか。
梶浦:電通デジタルは、2016年に設立された若い会社です。若くて、デジタルに強くて、お酒を飲まない方がたくさんいる。アサヒビールにないものを全て持っている点に引かれました。それに、会社を設立する前から、濱田さんにご紹介いただく電通デジタルの方々は自由で面白い方が多かったんですよね。「あ、こういう面白い会社なんだ」と刺激を受けましたし、ぜひ一緒に仕事をしたいと思いました。
 スマドリ株式会社 梶浦 瑞穂氏
スマドリ株式会社 梶浦 瑞穂氏Q.スマドリの設立にあたり、電通デジタルではどのような反応がありましたか?
濱田:社内でも「なぜ電通デジタルで取り組むのか」という声が上がったため、私たちもあらためてその意義を検証しました。アサヒビールは、これまでお酒が好きな方々を対象にマーケティングを行ってきましたが、スマドリではアサヒビールの既存のお客さまではなく、新たな層にアプローチする必要があります。ミレニアル世代やZ世代のお酒を飲まない方々にリーチするには、いろいろな手段がありますが、やはりデジタルマーケティングが有効でしょう。その意図を説明したところ、電通デジタル内でも理解を得ることができました。
Q.スマドリの事業は、これまで濱田さんが取り組んできた電通デジタルの仕事と大きく違うのではないかと思いますが、どのような点に違いを感じていますか?
濱田:電通デジタルは、ミッションとして「クライアントの事業成長パートナー」を掲げています。あらゆる企業を活性化し、世の中に好循環を生み出すことが使命です。とはいえ、アサヒビールに出向した際に、電通デジタルの枠は関係なく、アサヒビールにとって最大限のメリットを生み出すという視点を得ました。私にとっては初めての出向だったので、これまでとは全く考え方が違うんだなという気付きでもあったんです。
このベクトルを維持したまま立ち上げたのが、スマドリです。業務委託ではない合弁会社で、アサヒビールと電通デジタルが同じ立場で、同じリスクを負って、同じ目標に全身全霊で向かっていく。それは、これまでの電通デジタルの業務とは全く違いました。私は今スマドリの顧問という立場ですが、これまで通り電通デジタルの業務に100%の力で取り組みつつ、顧問業務にも100%で向き合い、200%の力を出し尽くしています。ただ、一度出向を経験したからこそ、両方の仕事ができていますが、そうでなければ難しかったでしょう。有益かつ意味のある体制だと思っています。
「スマートドリンキング®︎」の提唱により、アサヒビールの評価も変化
Q.デジタルマーケティングの戦略や手法は他社でも応用できますが、スマドリとして起業した点に独創性や価値があるように思います。濱田さんは、スマドリを設立する前後で見えている世界は変わりましたか?
濱田:電通デジタルにおけるクライアントさま向き合いの業務では、その領域が得意な社員がアサインされます。ですが、スマドリでは「スマートドリンキング®︎という理念に共感します」「私もお酒が飲めないんです」「何か新しいことに挑戦したいです」「見ているとワクワクします」という軸で、参加してくるスタッフがたくさんいます。そういう土壌をつくれたのは、大きいことだと思いますね。今では電通デジタル内においても、同じような流れが見られます。
 スマドリ株式会社 濱田 美晴氏
スマドリ株式会社 濱田 美晴氏Q.それは面白い傾向ですね。これまでは「このプロジェクトに入ってください」と、ある意味でトップダウン的に担当者が決まっていたところが、一緒に会社をつくるプロジェクトとなると、「自分も参加したい」という人が集まりチームができていく。チームの組み方も変わったということでしょうか。
濱田:その通りです。部署を問わず、参加意欲のあるスタッフをアサインしています。アサヒビールの新卒採用でも、「スマートドリンキング®︎という考え方に共感する」という学生が増えていると伺いました。
Q.アサヒビールというブランドの評価も変わり、リクルーティングにも一定の影響を及ぼしているということですね。確かに、クリエーティビティにあふれた優秀な学生の中には、ビールが苦手でアサヒビールを志望しないという方もいるかもしれません。梶浦さんは、こうした状況をどう受け止めていますか。
梶浦:私は、スマートドリンキング®︎のゴールをいくつか設定していますが、そのうちの1つが、アサヒビールを業界で一番人気がある会社にすることです。スマートドリンキング宣言やスマドリの設立によって、着々とその階段を上っていることをとてもうれしく思っています。
就活を控えた大学生から「お酒を飲めない人はアサヒビールに入社できないのでしょうか」という質問を受けることがありますが、そんなことはありません。むしろ、飲まない/飲めない人材はアサヒビールでは貴重ですから、ぜひ入社していただきたい。今は電通デジタルの若手社員が頑張っていますが、アサヒビールからもスマドリで活躍する若手が出てきてほしいと願っています。
スマドリの店舗運営に関しても、若手社員が活躍していますよ。そもそも私はお酒が好きで、アサヒビールで長年酒類を扱ってきた立場です。飲まない/飲めない方の気持ちは、若手社員の方がよく理解しているんですよね。だからこそ、スマドリが運営している、お酒を飲まない方も楽しめるバー「SUMADORI-BAR SHIBUYA」のコンセプトやメニューも、彼らの意見を重視しています。
濱田:大企業では、新人が考えた案が採用されることは、やっぱり難しいですよね。スマドリは若手にとってもチャンスがある会社だと思います。
梶浦:自分たちでドリンクメニューを考案して、自分たちでデジタルマーケティング戦略を考えて、自分たちでSNSを使って発信する。アサヒビールではなかなかチャレンジできないことだと思います。そこがスマドリを立ち上げた意義かもしれません。
お酒を飲まない人向けの商品は、お酒を飲む人にも好まれるという発見
Q.2022年1月のスマドリ設立から、約1年が経ちました。これまで、どのようなチャレンジをしてきたのでしょうか。また、今までとは違うお客さまに向き合い、今までにないマーケティングをする上で、どんなことを心掛けてきたのでしょう。
梶浦:スマドリでチャレンジしたことは、アサヒビールのこれまでと全て真逆です。ターゲットはお酒を飲む方ではなく、飲まない/飲めない方。アサヒビールで続けてきたマスマーケティングではなく、ターゲットを細かく絞ってデジタルマーケティングでアプローチする。アサヒビールはトラディショナルな浅草に本社があるのに対し、スマドリは最先端の渋谷に拠点を置く。今後どこかでつながるのだと思いますが、今はとにかく正反対のことをやり続けています。
Q.濱田さんは電通デジタルの立場から見ていかがでしょうか。スマドリを運営する上で大きなマーケティング方針があるように感じますが、これまでのデジタルマーケティングとは違う、新しいチャレンジはありますか。
濱田:自分たちで合弁会社を立ち上げ、自分たちの事業を起こすのは、とても大きなチャレンジでした。電通デジタルで受注したクライアントさま業務ではないので、クライアントさまに方針を聞くこともできません。全て自分たちで考える必要があります。こうした立場になるのは電通デジタルとしても初めてで、まだまだ課題があると感じています。
しかも、デジタルマーケティングでさまざまなことを深掘りしていく一方で、「SUMADORI-BAR SHIBUYA」というリアル店舗の運営も大きな柱。渋谷における店舗の位置付け、店舗のあるべき姿をお店のオーナー視点で考えなければならず、データの世界だけでは生きていけないということをひしひしと感じているところです。
ただ、2023年度にはデジタルマーケティングに立ち戻り、新たな施策も打ち出したいと考えています。「SUMADORI-BAR SHIBUYA」だけでなく、スーパーや飲食店、ECにもつなげて、スマートドリンキング®︎に対する人々の動向、意欲、関心を深掘りしていきたいですね。初年度はその手前の業務に追われていましたが、2年目にしてようやく大きな提案ができそうです。
Q.先ほど、梶浦さんは「今までとは真逆のことをやり続けているが、今後どこかでつながるのではないか」とお話されていました。真逆のことにチャレンジする中で見えてきたことや、そこで得た学びはありますか?
梶浦:私のような酒飲みの発想でノンアルコールビールを作ろうとすると、おいしいビールの味がする商品を目指します。要は、お酒を基準にしてしまうんですね。
ですが、飲まない/飲めない方々の多くは、そもそもビールの味が好きではありません。そのため、ジュースの延長で商品を開発することが重要。そうすると、これまで私たちが考えていたノンアルコール商品とは、フレーバーもテイストもパッケージも違う商品が生まれます。ですが、お酒を飲む方が気付いていないだけで、それはお酒を好む方も欲しい商品だったりするんですね。お酒を飲まない/飲めない方に向けて商品を作ると、お酒を飲む方も意外とその商品を選ぶんだなという発見がありました。きっと、こうやって何かがつながっていくのだと思います。
Q.素晴らしい発見ですね。一時期、ノンアルコール飲料の市場が大きく伸びてきた時期がありました。各社がこぞって商品を出し、どれもそれなりに売れていく。その戦略でもマーケットを拡大することはきっとできたと思いますが、スマドリという新会社を立ち上げ、マーケティングを変えたら、さらに大きな変化が生まれました。これは、意図的に狙ったものなのでしょうか。
梶浦:いえ、狙ったわけではありません。でも、事業とはそういうものですよね。やってみないと分からない。今、卵がやっと生まれそうなので、大事に育てたいです。
Q.最後に、今後の展望についてお聞かせください。「こういう社会を実現したい」というビジョンを教えていただけますでしょうか。
梶浦:矛盾しているかもしれませんが、スマドリの真のゴールは、この会社を閉じることなんです。もともとスマドリが発足したのは、お酒を飲む方と飲まない方がお互いに分け隔てなくコミュニケーションを取るためです。飲まない方が飲み会に参加しても、ウーロン茶だけでなくバラエティーに富んだドリンクを楽しめる。飲む方も、その日の気分や体調に応じて適量を楽しめる。そのための商品や場をたくさん用意し、両者がだんだん歩み寄っていけば、もうこの会社は要らないはずです。それが長期的な目標ですね。
短期的な目標としては、現在運営しているバー「SUMADORI-BAR SHIBUYA」から活動を広げること。現在はバーを基点に情報発信していますが、これからはそこを飛び出していろいろなことにチャレンジしていきたいと思っています。

お酒を飲む人と飲まない/飲めない人たちとの接点をつくるスマドリの事業は、アサヒビールと電通デジタルにとっても大きな刺激となっているようです。中でも、お酒を飲まない/飲めない人を取り込む施策が、結果的にお酒を飲む人にも刺さったという指摘は、示唆に富んでいます。新たなターゲット層にアプローチできる商品・サービスは、既存の顧客にとっても魅力的な商品・サービスとなり得るのではないでしょうか。デジタルマーケティングにより一層力を入れる2年目の取り組みでも、新たなヒントが見えてきそうです。