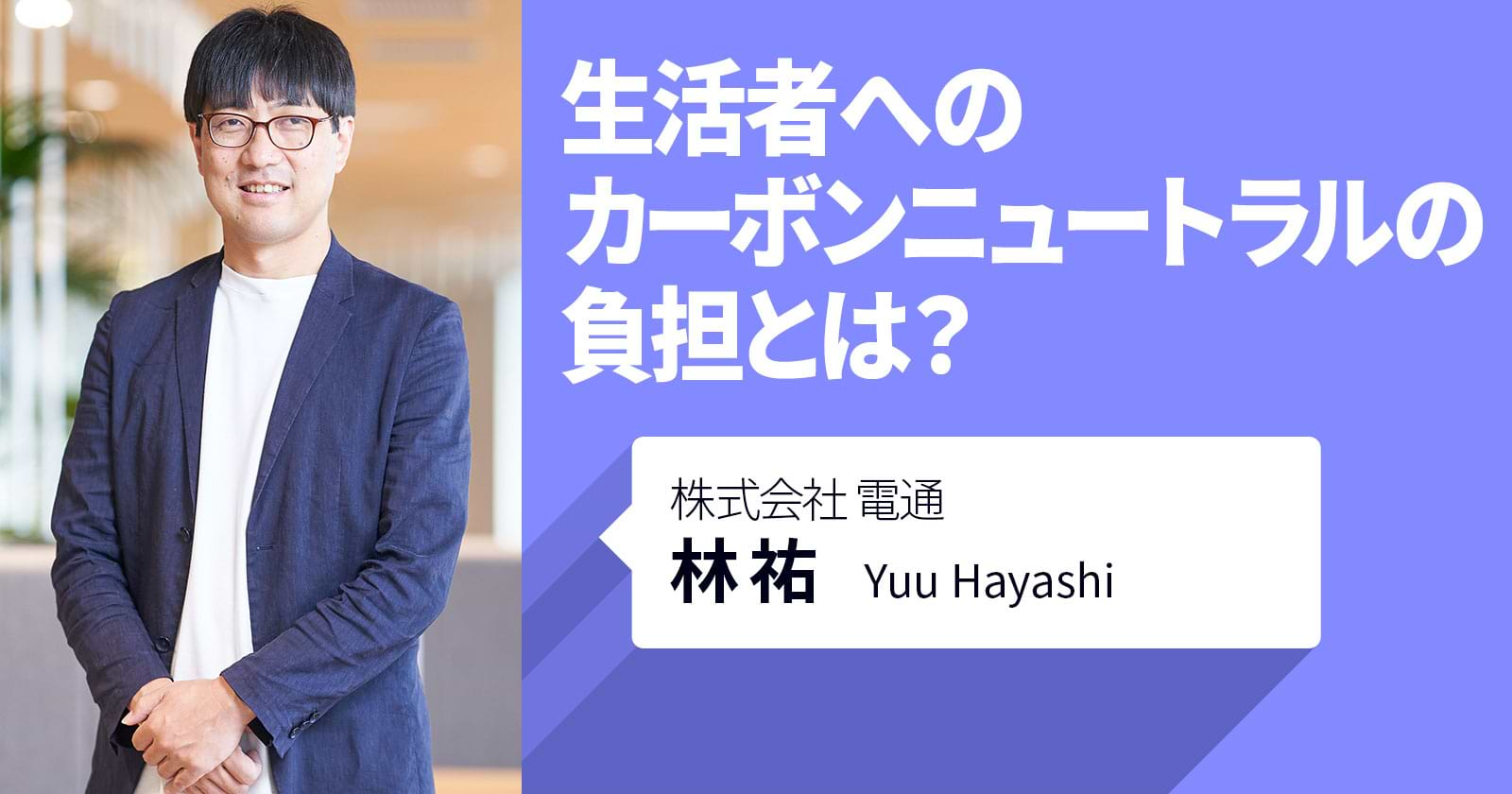株式会社 電通 では、電通グループ横断でサステナビリティに関するプロジェクトを推進する「サステナビリティ推進オフィス」および「電通 Team SDGs 」を調査主体として、2021年から「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を定期的に実施しています。2023年5月、全国15~79歳の計1,400人を対象に、最新の第10回調査結果 が発表されました。
本記事では、2022年のこちらの記事 に続き、調査を実施したプロジェクトメンバーである電通の林祐氏にインタビュー。注目すべきポイントや、この1年の生活者の意識変化について話を聞きました。
物価高が生活を圧迫。価格上乗せに厳しい目線 Q.林さんには約1年前、第6回調査結果の発表時にもお話を聞きました。この1年間で、顕著な変化はありましたか?
林: 第6回以降、調査を重ねるごとにカーボンニュートラルの実現に伴う追加コスト負担に対して、生活者の抵抗感が強くなる傾向がありましたが、今回はこれまでで最も顕著な結果が出ました。
林: 国や企業がカーボンニュートラルの取り組みを進めるために、衣食住や光熱費、医療費などの追加コストをどこまで負担できるかという調査項目では、「各支出について月6%以上価格を上乗せできる」と回答した人の割合は、1年前に比べて減少しました。
林: その背景には、電気代や食料品などの価格が上昇してきた中で、これ以上は生活費を増やせないという切迫感があると思います。今回の調査結果は、おおむねその空気を感じさせる結果となっていました。
Q.カーボンニュートラルの必要性は認識しつつも、物価高の中で、これ以上のコスト負担を受け入れるのは厳しいということでしょうか?
林: この1年で、カーボンニュートラルという言葉の認知率はほとんど変わっていません。ただ、言葉は浸透したものの、正しく内容を理解している人の割合は2割ほどで停滞しています。このことから、カーボンニュートラルの必要性について、本当の意味で自分ごととして認識している生活者はあまり多くないということも言えそうです。
Q.一時期、カーボンニュートラルについてニュースなどでもよく報じられていましたが、情報の波が一段落したということでしょうか?
林: 大きな要因として、生活者目線では新しいトピックがあまり出ていないことが挙げられると思います。2020年、菅首相(当時)は「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」と宣言しました。さらに、2021年には「2030年度までに温室効果ガスを、2013年度比で46%削減」と目標を掲げたのもかなり大きなインパクトでした。その中で、水素エネルギーを使った取り組みなどもさまざま報じられました。
株式会社 電通 林 祐氏 Q.では、今後、カーボンニュートラルは進んでいくのでしょうか?
林: カーボンニュートラルは、今後も間違いなく進んでいくでしょう。ただ、カーボンニュートラルそのものが、少し分かりにくくなっている印象があります。そもそもの発端は、地球温暖化が深刻な問題になったこと。その解決のために二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を下げ、脱炭素社会を実現することが世界共通の目標として定められました。
2023年後半から2024年にかけてカーボンニュートラルのビジネスチャンスが到来? Q.企業にとって、カーボンニュートラルは新たなビジネスチャンスになり得るのでしょうか。それとも、生活者の意識が変わらなければ、チャンスを生み出すのは難しいのでしょうか。
林: もちろん生活者の存在は重要ですが、企業にとってカーボンニュートラルをともに推進するパートナーは生活者だけではありません。株主や金融機関、行政機関、従業員やNPOなども含む全てのステークホルダーと協力しながら、カーボンニュートラルを進めることが大事なのではないでしょうか。
Q.「カーボンニュートラルに関する生活者調査」も第10回という節目を迎えました。「次回以降はこういう観点での調査を掘り下げたい」など、現在考えていることはありますか?
林: これまでは、カーボンニュートラルの認知率をはじめ、どちらかと言えばマクロ視点の、大きな意味での生活者意識を見ていくような視点が中心的な調査でした。今後はさらに生活者に歩み寄り、1人ひとりがどうすればカーボンニュートラルに取り組もうと思えるのかについて調査したいと考えています。
今回の調査では、物価高騰が続く中、カーボンニュートラルによる追加コスト負担は、生活者にとってなかなか許容できなくなっている、という結果が出ています。それでも、地球と人類の未来のことを考えると、カーボンニュートラルは進めていかねばなりません。企業側もエンドユーザーと丁寧なコミュニケーションを行い、生活者自身がどのように関わっていけるか、を促していくような取り組みを進めていくことが必要とされているのではないでしょうか。