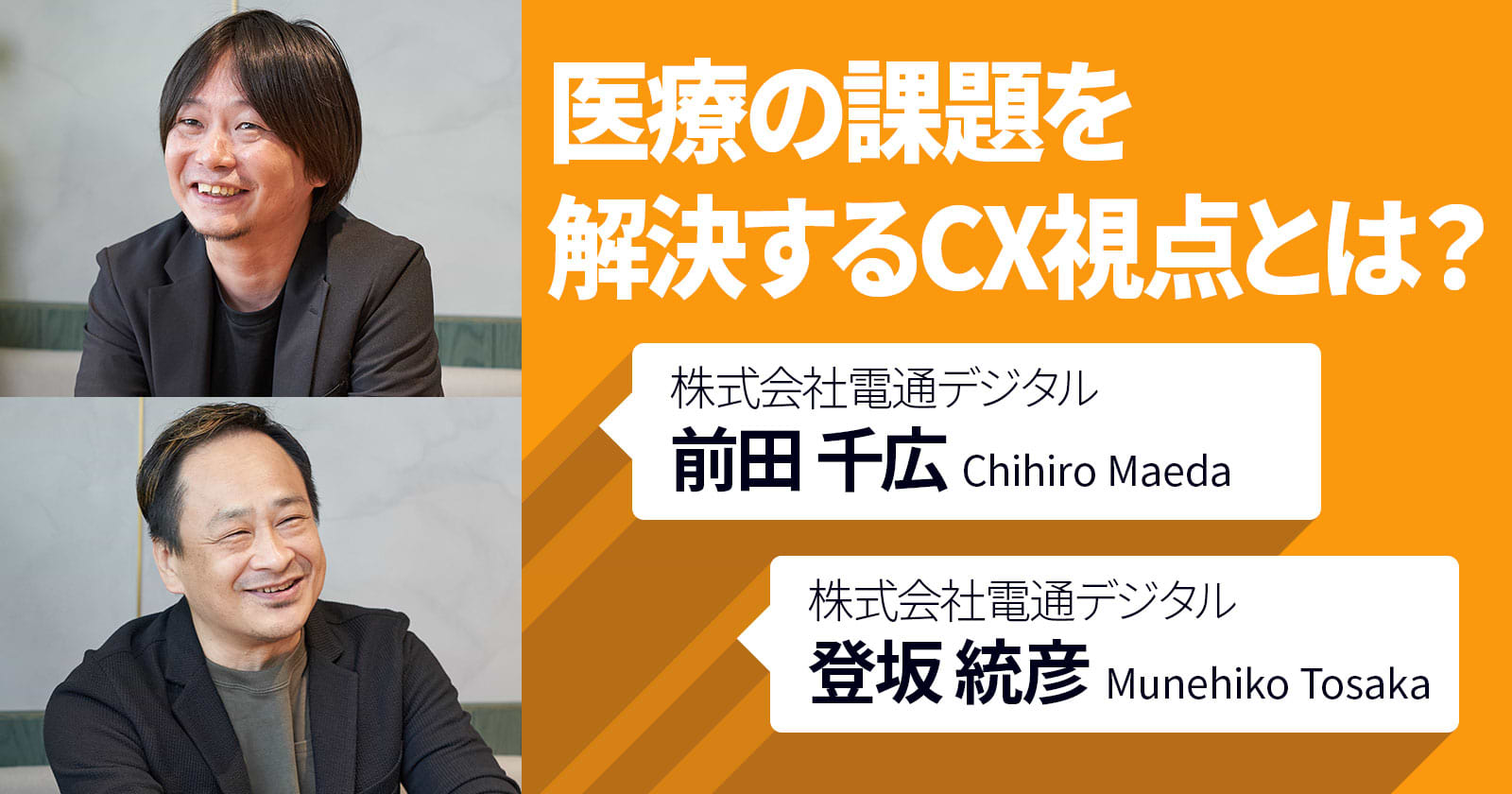ペイシェント・セントリック(患者視点の医療)が重視されるようになってきた医療製薬業界で、その実現に向けてどのような取り組みをするかが製薬会社にとっての課題となっています。そんな中、2022年5月に株式会社電通デジタルがリリースしたのが、医師や医療従事者、患者、製薬会社がより良い関係をつくるため、主に製薬会社向けに開発・提供するメディカル総合ソリューション「DDMEX(ディーディーメックス)Dentsu Digital Medical Experience Transformation」です。
DDMEXのCX戦略を手掛ける電通デジタルの前田千広氏と、ビジネスプロデュースを担当する登坂統彦氏へのインタビューの後編では、DDMEXがリリースされて約1年を経た現状や、このソリューションに込めた思いを聞きました。
DDMEXをリリースして1年、製薬企業に広まりつつあるCX視点
Q.2022年5月にDDMEXがリリースされてから1年以上経ちましたが、現状はいかがですか?
登坂:直近で最もDDMEXを導入いただいているのは、製薬会社さまが提供するデジタルチャネル(医師向け会員制サイト)のリニューアル領域です。それを中心にオムニチャネル・マーケティングのような形で有効活用していこうと取り組んでいます。会員情報などのデータをひも付けて、MRを介して効率的に医師に情報提供するシステムを作ろうと、盛んに開発が進められています。
その中で、医師の顧客体験(CX)向上を支援するために、医師のジャーニーの見直しが必要になっています。というのも、製薬会社さまは以前から医師のペルソナやジャーニーを描いていましたが、前編でお話したように、コロナ禍によって医療製薬業界は大きく変化しました。そのため、現在では、過去に描いていたジャーニーとは異なっているのではないかという疑問があるからです。
同様のことが患者さんサイドにも言えます。ペイシェント・セントリックの実現に向けて、患者さんの治療や診療のCXを向上させるために、製薬会社さまがすべき支援は拡大しています。本来、製薬会社さまは患者さんへの医薬品提供をビジネスとしていましたが、今や提供した医薬品をどう効率的に使ってもらうか、患者さんが処方薬を飲み続けるにはどんな支援が必要かといったところまで考えなければならない時代になっています。製薬会社さまは支援ツールの提供に力を入れていますが、そこでも患者さんのジャーニーを見直す必要があるようです。
それに伴い、医療製薬業界ではなじみのなかったCXという言葉も広まり始め、自社内でCXの考え方を持って、医師や患者さんに施策を打とうという動きが出てきています。外資系の製薬会社さまを中心に社内にCX専門チームの立ち上げが始まっていて、私たちはその人材育成支援として、研修やワークショップの開催、人材を派遣するといった形でサポートする機会も増えていますね。
 株式会社電通デジタル 登坂 統彦氏
株式会社電通デジタル 登坂 統彦氏日本の医療制度が抱える社会課題をデジタル技術が解決できる可能性
Q.お2人は、どのような思いでDDMEXを進めてこられたのでしょうか?
登坂:医療製薬業界のDXやデジタルマーケティングは、法規制などの影響で他業界に比べて進みが遅いという背景があります。私自身は前職で医療用医薬品のマーケティングに携わってきましたが、世の中でデジタル技術が進んでいても、製薬会社さまに対してデジタルで支援できる範囲は狭いと感じることが多く、どこかもどかしい思いを抱えていました。医師や患者さんとつながるエンゲージメントを作るには、やはりデジタルは不可欠だと考えていた時、DDMEXの立ち上げを知ったのです。そこで、DDMEXの概要を聞いたところ、私の考えとマッチしていたことから、参加させていただくことになりました。
今、日本は人口1,000人あたりの医師の数が2.6人と、OECD各国の平均と比べて医師の数が少ないと言われています。一方、国民皆保険制度により、患者さんは自由に病院を選んで受診することができ、支払う医療費も多くの人は3割負担ですから、非常に気軽で安価に医療を受けられるわけです。そのため、日本の患者さんの病院受診回数はOECD平均の2倍もあります。つまり、医師が少ない反面、患者さんの受診回数は非常に多い。それによって医師が多忙になり、患者さん1人当たりに掛ける時間が短くなるというのが現状です。その結果、患者さんには「医師の診察や指導の時間が不十分」だという不満があり、処方された薬に対しての患者さんの理解も低い状態です。
これを打開するには、たとえ医師の患者さん1人に掛ける時間が短くても、薬を飲む目的や病気への理解を促進させるツールを用いることで、製薬会社さま側から患者さんへ情報提供するという方法が1つの答えになるだろうと考えています。製薬会社さまと共に社会課題を解決し、患者さんの治療体験をより良くするにはどうするのかという部分は、DDMEXの大きなテーマですから、そこに一番やりがいを感じていますね。
前田:医療分野のデジタル化はまだまだこれからだと言えますし、医療製薬業界の危機感は高いのですが、さまざまな法規制があるため、一筋縄でいかない面も多く、医師も製薬会社さまもいろいろと模索中であるというのが現状です。こうした医療分野のデジタル化に対して、電通グループが貢献できるのは大きいことだと思います。
一方で製薬会社さまなどクライアントさまは、例えばWebサイトを作るなど何か明確な目的がないと、私たちに相談できないと思っているのではと感じています。ですから、実際はもっと前の段階である根本の課題からお手伝いできるということを、DDMEXを通じて知っていただきたいです。治療体験の向上や製薬会社さまのMRが本当に困っていることに対して、デジタルが応えられる部分はまだたくさんありますから。
 株式会社電通デジタル 前田 千広氏
株式会社電通デジタル 前田 千広氏Q.コロナ禍を経て、医療製薬業界におけるコミュニケーションのスタイルが急速に変化しています。今後の課題や展望をお聞かせください。
登坂:2024年4月から「医師の働き方改革」が始まります。医師は長時間勤務や過重労働などが当たり前で、以前から問題が指摘されていましたが、改善に向けた対処が始まるのです。そうすると医師が勤務先にいる時間が制限されるため、その時間内は診察や患者さんのための調べ物、事務作業などが優先されるだろうと思います。そのため、MRとの面談時間の優先順位は、かなり低くなると予想されます。
そういった中で、製薬会社さまと一緒に取り組むわけですが、業界のレギュレーションや国の法規制で、できないことも多々あります。私としては、社会課題や医療課題を本当に解決するには、製薬会社さまの力だけでは難しいと思っています。これからはもっと大きな枠組みの中で「医療とは何か」「健康を継続するには何が必要か」を考え、製薬会社さまに限らず、多様な企業や保険者、自治体に話を伺いながら、健康・医療やヘルスケアの切り口を展開していきたいと思っています。
前田:今は、治療用にアプリが処方される時代になってきました。そういったように今後、デジタル技術でQOL(クオリティーオブライフ)を上げていこうという時に、テクノロジーに対して制度が追いついていない世の中をどう変えていけるかが、私たち電通グループのチャレンジになると思います。そして、そんなプロジェクトをクライアント企業さまと一緒に考えながら取り組めると良いなと思います。ですから無理難題なことかもと感じても「まずはご相談ください」とお伝えしたいですね。

患者と医師のより良い治療体験を実現するべく、製薬会社をデジタル技術でサポートするDDMEX。さらには、社会課題の解決にもつながるなど、大きな可能性が秘められていると言えそうです。