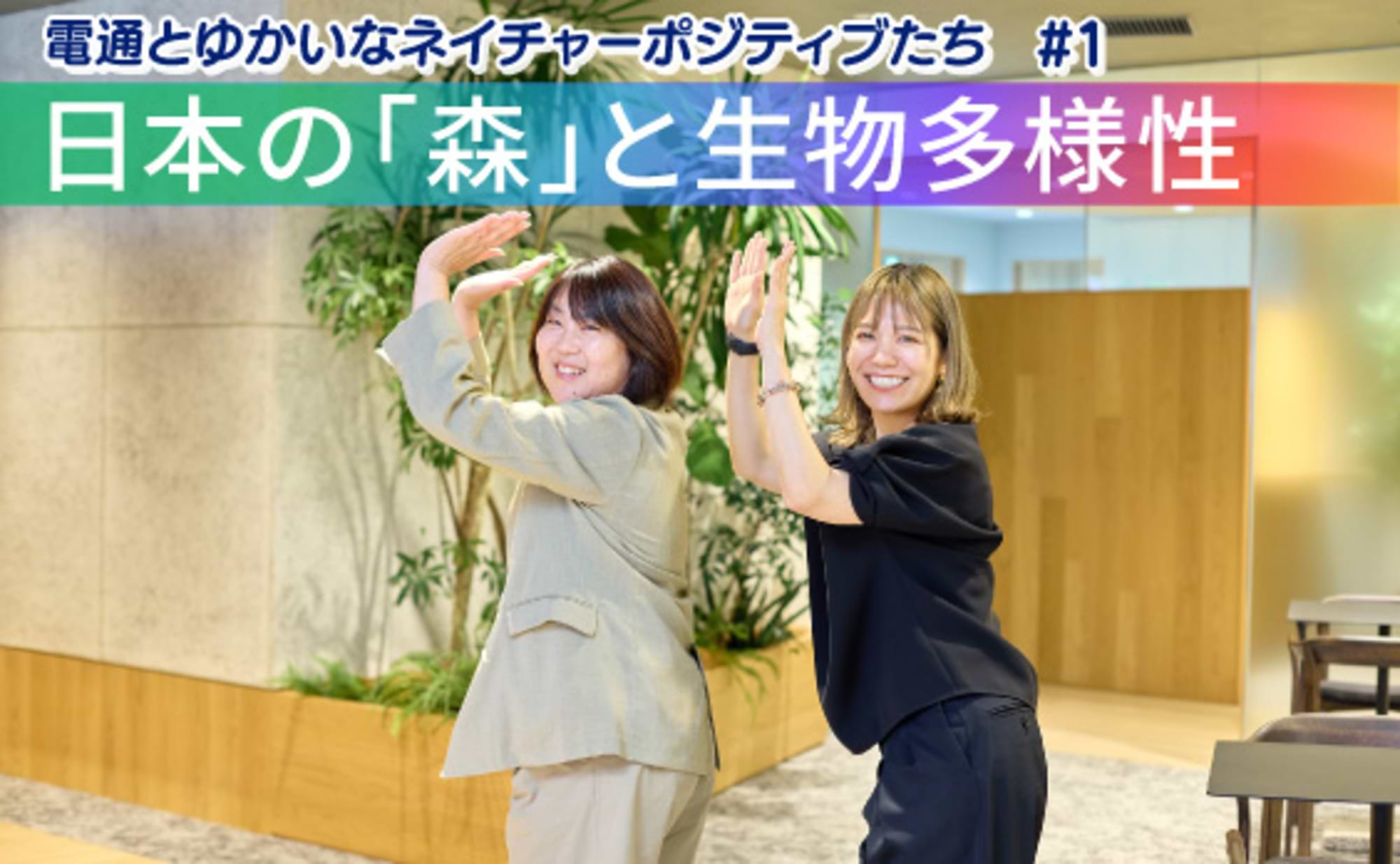自然に近い海を水槽の中に再現することで、今まで困難だった海洋研究を可能にする株式会社イノカの「環境移送技術」。この技術を活用し、企業の生物多様性に関わる取り組みを支援する取り組みが始まっています。株式会社 電通のサステナビリティコンサルティング室は、イノカCOOの竹内四季氏を訪ね、同社が持つ技術の可能性や、ビジネスにおける生物多様性問題の位置付けについてインタビューしました。
後編では、日本における海洋研究の重要性や課題、さらにはイノカのビジネスのもう1つの柱である教育事業についても深掘りしていきます。聞き手は、電通サステナビリティコンサルティング室の澤井有香氏が務めます。
海洋分野は島国の日本が世界をリードできる貴重な領域
澤井:あらためて、海の生物多様性を守ることがなぜ大事なのか、竹内さんのご意見を聞かせてください。
竹内:陸上の生物と比べると、海洋の生態系についてはまだ分かっていないことがたくさんあります。言い換えれば、まだまだ無限の可能性を秘めている分野なんです。例えば、海洋生物が持つタンパク質や化合物は種によって異なるので、それを使って新薬を創り、人間の治療に役立てることができると言われています。あるいは、画期的な機能を持つ新素材を生み出すことができるかもしれません。そのようなポテンシャルが大きい自然資本を未来に残すためにも、生物多様性を守ることが重要だと私は考えています。
 株式会社イノカ 竹内 四季氏
株式会社イノカ 竹内 四季氏澤井:では、海の生物多様性を守っていく上で、今日本はどのような課題を抱えているのでしょうか。
竹内:一番の課題は、海がどうなっているのか、現状把握ができてないことだと思います。日本では「磯焼け」と言って、今まで海藻が生えていたエリアで海藻が育たなくなる現象が問題になっています。このような問題の解決策を探るには、海藻がなくなった現在の海と海藻が生えていたときの海の状態を比較する必要があります。ところが今の海を測定することはできても、海藻が生えていた時のデータはありません。そのため比較ができず、分析しようがないのです。当社の環境移送技術がさらに普及し、あらゆる海のデータが蓄積されるようになれば、このような比較分析も容易になると思います。
何と言っても、日本は世界第4位の海洋体積を誇る国ですから、海洋生物、海洋性資源が非常に豊富です。よって、うまくいけば日本が先行して研究を進め、スタンダードをつくり、世界をリードしていける領域だと思います。当社もいずれは日本の海だけでなく、世界中の海を再現する取り組みを行いたいと思っています。
自然の面白さをエンターテインメントとして伝える教育事業
澤井:海洋は生物多様性だけでなく、気候変動や地球温暖化の問題とつながる部分も大きいですよね。
竹内:そうですね。前編で「ブルーカーボン」についても紹介しましたが、海洋生物がCO2を吸収するインパクトは、陸上生物の倍はあるのではないかと言われています。ただ、きちんと測定されているわけではありません。陸上においては、森林のCO2吸収量をもとに、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」が制度化され、さまざまな企業・団体によって取り組まれていますが、海においてはまだそうした仕組みはつくられていません。日本ではアマモという海藻が出すCO2量などの研究が進んでいますが、まだまだこの分野は黎明期。これからさらに力を入れていくべきだと思います。
澤井:今までのお話で、海の生物多様性を守る取り組みの重要性がよく分かりました。私どももそのような企業さまの取り組みをご支援する立場なのですが、どんな優れた取り組みであっても、生活者に共感いただかないことには持続できないので、生活者をいかに巻き込むかが重要だといつも感じています。そういった意味でも、イノカさんが創業期から力を入れている教育事業は、非常に意義のある取り組みだと思います。

竹内:ありがとうございます。当社の教育事業はエデュケーションとエンターテインメントを掛け合わせた「エデュテインメント」をコンセプトにしています。従来の環境教育はやや意識の高い人向けという面もあり、子どもには楽しめないものも多かったように思います。でも自然とは本来、とても面白いものです。そこで、われわれの教育事業では自然の面白さを伝えることを何より重視しています。その上でこれからの時代に大切な、正解のない課題に挑戦する人材を育てるべく「不思議を見つける」「仮説を立てる」「検証する」「発表する」といったサイエンス教育の要素を盛り込んでいます。
澤井:商業施設などで展開している「サンゴ礁ラボ」はご家族から大好評のようですね。
竹内:はい。「サンゴ礁ラボ」では、子どもたちが「秘密研究機関イノカ」の見習い研究員となり、ミッションをクリアしながら、自然を守るヒーローを目指します。そんな世界観のもと、私を含めたスタッフも研究員として登場します。サンゴに触ってもらい、死んでしまったサンゴと比べてもらったり、匂いを嗅いでもらったり。そんな生々しい体験は他ではなかなかできないと思います。お子さんは目をキラキラさせていて、保護者の皆さまも一緒に楽しんでくれています。教育事業の対象は小学生が中心ですが、最近は中高生と共同研究のようなことも始めています。
多様な企業とパートナーシップを組み、人と自然が共生できる世界を目指す
澤井:単純に環境に良い、海に良いからと言われても、どうしても自分ごととして捉えられない人も多いですよね。そう考えると、まず「自然を楽しんでもらう」という視点はとても大事だと思いました。生物多様性に関するクライアント企業さまの施策を私どもがお手伝いする時に重要なのが、その企業ならではのストーリー、なぜその会社が取り組まなくてはならないのかといった文脈づくりです。企業の取り組みを生活者にいかに届けるかといった点で、イノカさんと電通グループが協業できることもあるのではないかと思います。
 株式会社 電通 澤井 有香氏
株式会社 電通 澤井 有香氏竹内:そうですね。企業が海洋保全を目的とした取り組みを推進するには、多少値段が高くても消費者が環境に良いものを買うことが必要な場合もあります。でもそのような製品の価値を上手に伝えるのはけっこう難しいですよね。海は普段、生活者が意識する機会が少なく、距離が遠いところもあります。だからこそ、より多くの人に海に関心を持っていただくための世論やムーブメントづくりを、生活者とのコミュニケーションのプロである電通グループのような企業にぜひお願いしたいところです。
澤井:冒頭でも触れましたが、生物多様性は気候変動などと違って数値化しにくい面があります。私もクライアント企業さまの取り組みをご支援する上で、まずはフィールド調査を行い、現状を見える化することが大事だと常々思っていました。この点でもイノカさんの力をお借りし、企業活動と海の生物多様性の関係を明確にした上で、生活者と企業との関係性を再構築する。そんなことがこれからできたらいいなと思いました。では最後に、イノカさんの今後の抱負をお聞かせください。
竹内:イノカは「100年先も人と自然が共生できる世界の実現」をビジョンに掲げています。でも本当にそのビジョンを実現するには、現状のままでは100年はかかるのではないかとも感じています。もっともっと科学的な知見を積み重ね、新たな研究開発を進め、社会の仕組みも変えていかなくてはなりません。ですから、私どものビジョンに賛同し、一緒に取り組んでくださる多くのパートナーを求めています。そのようなパートナーとともに、人間と自然が共生できる社会に向けたチャレンジをしていきたいと考えています。

海の生物多様性や海洋資源は、本来は日本が世界をリードし得る分野です。この分野の取り組みを進めるためには生活者の理解や共感が必要であり、その上でもイノカが取り組む教育事業は大きな役割を果たしていると言えるでしょう。
また、サステナビリティコンサルティング室は、今後もこれからのサステナビリティビジネスにおける次世代オピニオンリーダーとなる方々にお話を聞いていきます。自社のビジネスと自然環境との関わりをあらためて考える際に、お役立ていただけそうな情報をこれからも発信してまいります。