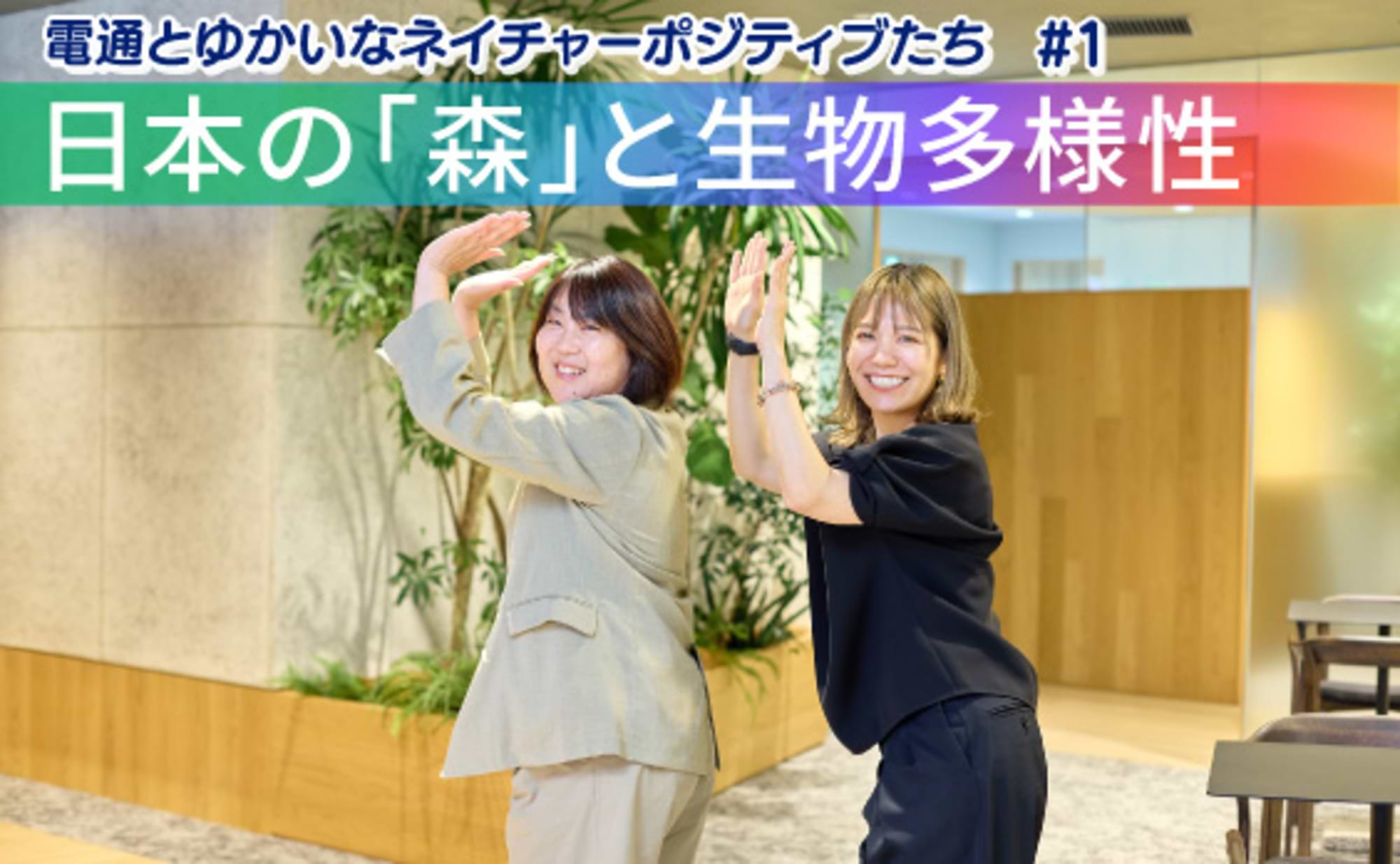「生物多様性保全に取り組んでいるが、企業の価値につなげられていない」
「長年続けた環境活動の投資効果を問われ、事業とのひもづけを問われている」
日本では2005年の愛知万博前後で生物多様性が社会課題として注目され、世界的に見ても長年にわたって生物多様性に関連する活動を続けている企業が数多くあります。しかし、世界に先駆けて始めた自然保全活動が今、競争優位性を持っているとは限らず、コストカットを求められる中で継続が難しくなることも。そもそもなぜ長年やっているのかを問われても説明がしにくいなど、冒頭にあげたような悩みを持つ企業も多いのが現状です。
また、日本では2027年3月期から、一部の大手企業有価証券報告書でのサステナビリティ開示が義務付けられ、対象企業は順次拡大される予定です。企業は生物多様性保全にどのように取り組み、企業価値をどう示していけばよいのでしょうか。
本記事では、日本の森を盛り上げ、次世代へつなげることを目指す株式会社モリアゲの森林業コンサルタント 長野麻子氏と、電通サステナビリティコンサルティング室の澤井有香氏にインタビュー。企業が取り組む自然保全活動の現状や苦悩、活動を企業の強みにするための方法について話を聞きました。

<目次>
▼世界3位の森林率を誇る日本。「生物多様性」と「森」の関係は?
▼TNFD情報開示だけでなく、行動の質が問われるように
▼自然保全活動を企業の強みにする5つの視点
▼成功例の横展開も、地域の独自性と掛け合わせるとオンリーワンの活動になる
先進国で3位の森林率を誇る日本。「生物多様性」と「森」の関係は?
──初めに「生物多様性」と「森」はどう関係しているのか教えてください。
澤井:最初にお伝えしたいのは、生物多様性は“いきもの”の種だけでなく、森や里山といった生態系、遺伝子など地球の自然すべてを含みます。そして、その自然と共生するための活動こそが、生物多様性を考えるうえでの核となります。私たちは自然から多くの恩恵を受けており、生物多様性の保全とは、自然とともに生きる未来をつくる取り組みでもあります。
森林もその一例です。動植物を守るだけでなく、水を蓄える機能によって水資源の保全にもつながります。水はすべての人、多くの産業にとって欠かせない資源であり、水源地を守ることはビジネスの土台となる“共生”の実践だといえます。なお、環境省が認定する自然共生サイトの多くも、森林に関わるものです。

長野:日本の国土の約7割は森林で、先進国(OECD加盟国)の中でも日本はフィンランド、スウェーデンに続いて第3位の森林率を誇ります。これだけの人口と経済規模を持ちながら森を維持している国は他にありません。

──森林を保全する企業は、どのように見られるのでしょうか。
澤井:もちろん投資家や環境保全に関わる団体・専門家からの要請もありますが、最近では企業の森林保全活動が、共感やエンゲージメントを育むひとつの手段としても注目されています。
長野:「当社の若手社員が、森林保全活動に誇りを持ってくれているから続けている」とおっしゃる企業もあります。
澤井:若者の間では「自然界隈」という言葉がSNSで使われ、自然を大切にし、自然の中で癒やされる時間を持とうとする姿勢が広がっています。そうした価値観と、企業の取り組みが重なる場面も増えている印象です。
長野:人材は企業にとっての資産であり、ウェルビーイングを目指して、森林を活用したメンタルヘルス対策などの取り組みも有効です。ドイツでは、医師が「1週間森に行きなさい」と処方するケースもあり、健康保険が適用されることもあります。まさに「森の処方箋」ですね。
TNFD情報開示だけでなく、行動の質が問われるように
──生物多様性に関する企業の取り組みのトレンドには、どんなものがありますか?
澤井:昨年は、企業からTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)(※)に関するお問い合わせが多くありましたが、今年は「TNFDに対応し始めたけれど、これから何を求められるのか分からない」という声が増えています。TNFD自体は各社進めており、そこだけでオリジナリティを出すのは相当難しい。ですから、その企業らしい「行動」で示す方法をお勧めしています。
※=TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)
企業・団体が経済活動による自然環境や生物多様性への影響を評価し、情報開示する枠組み

長野:陸の生き物の8割は森に棲んでいるので、森林保全はネイチャーポジティブに貢献できます。企業の森林保全活動をどう企業価値につなげていけるかは、私自身も研究中です。むしろ企業と一緒に価値を作っていきたいですね。
澤井:森林活動をCSRの延長で続けている企業もありますが、その価値や意義をうまく言語化できていないケースも多く見受けられます。「企業価値には結びついていないが、世間体を考えるとやめにくい」といった声もある一方で、その取り組みの積み重ねは、かけがえのない大きな財産です。生物多様性が求められる今こそ、その活動を企業の価値や未来への投資として捉え直すチャンスなのではないでしょうか。
長野:実は1990年代にも、企業の森林保有が盛り上がりを見せました。そして現在、第2次ブームが来ていると感じます。ただし、ブームで終わらせてはいけません。森林は世代を超えて存続するからです。
モリアゲでは「一社一山」を提唱しており、一つの企業が自分事として森に長く関わることを勧めています。そうした継続的な関わりこそが、企業価値につながると考えています。
澤井:取り組みの価値を、自らの言葉で説明できることも重要ですよね。
長野:最近では計測技術やシミュレーション精度が向上し、森林保全による効果を定量化できるようになってきました。水源涵養(すいげんかんよう)や土砂流出防止といった効果を数値で示すことで、企業の取り組みが評価されていくはずです。
自然保全活動を企業の強みにする5つの視点
──電通で作成した「自然保全活動を企業価値として示すための5つの視点」についてご説明いただけますか?
澤井:生物多様性は地域ごとに状況が異なるので、「なぜその地域なのか」「どんな意志で取り組んでいるのか」をストーリーとして論理的に伝える必要があります。下記はその伝え方の視点です。長野さんにぜひご意見をいただきたいです。

澤井:1つ目が「面積」です。30by30(2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保全しようとする目標)の観点から、保全面積を示すことが重要です。自然共生サイトの登録状況に加え、海外でも評価されているOECM(民間や地域による保全活動を国際的に認定する枠組み)への対応も含めて伝えられると、より信頼性が増します。さらに、気候変動との連携を考えられるとベストです。
2つ目は「お墨付き」。企業の保全活動を評価・支援してくれる専門家の存在は欠かせません。長野さんのような専門家と協働できると、活動への解像度も上がります。
長野:ただし「お墨付き」には注意が必要だと感じます。外部評価や認証を取りたい気持ちは理解できるのですが、多くのコストと時間がかかることもままあります。
私は最初に「お墨付き」から入ることはお勧めしません。まずは、その地域で自然観察に取り組んでいる人たちを支援したり、地域の大学や団体と共創したりするなど、地域と共に知見を深めるプロセスに意義があると思います。認証に頼らなくても、地域で実践を積み重ねること自体が大切と考えています。
澤井:確かに。専門家以外にも、各地域の生物多様性に知見のある方がいらっしゃると思うので、まずはその地域に詳しい方にご意見を伺ってもいいかもしれませんね。
3つ目が「効果の可視化」です。生物種の増減だけでなく、防災やヒートアイランド緩和など、保全の多面的な効果を社会に伝えることが必要です。単に「森は素晴らしい」だけでは伝わらないからです。
長野:効果の可視化は、森が当たり前の存在である地域の人たちにとっても、企業の発信を通じて「森にはこんなお宝があったんだ」と再発見することができると思います。そうした価値の交換が生まれることに期待しています。
澤井:4つ目は「地域課題」。地域と手を結び、保全を通じて課題解決に結びつける視点です。
長野:地域の方が気づいている課題と、外部から見えてくる課題の違いもあるので、お互いの視点を交換しながら取り組むと有意義ですね。自治体が住民を巻き込みながら街づくりに取り組む流れの中で、森林保全にも企業の視点が加わると面白い展開が生まれるかもしれません。
澤井:企業・地域・生物多様性という三者が支え合う「三方よし」の関係が築けると、活動も持続していくと思います。
最後、5つ目は「広がり」。1~4の要素がしっかり実践できていれば、他の場所でも横展開できる取り組みになっていくはずです。
成功例の横展開も、地域の独自性と掛け合わせるとオンリーワンの活動になる
──長野さんが関わってこられた活動で「広がり」に該当する事例はありますか?
長野:群馬県のみなかみ町では、20年以上イヌワシを守る森づくりに取り組んでいます。狩場の創出や森の再生を通じて、イヌワシの繁殖成功につながったんです。その横展開として、今年から山形県金山町でも地域と連携しながら新たな価値づくりを進める予定です。同じテーマでも場所が違えばその土地ならではのものになります。だからこそ、企業側の思いだけを押し付けるのではなく、地域との対話を通じて形をつくっていくことが大切です。価値の見つけ方を地域に学び、歴史と文化をリスペクトする姿勢があれば、無理なく継続的に関わっていけると思います。
澤井:生物多様性の保全においては、“どこで”取り組むかという場所の視点がとても重要です。実際、TNFDでも最初のステップは「場所の特定(Locate)」から始まります。
場所を特定するということは、その土地に根ざす自然環境や文化と深く関わっていくものです。まさに、地域は最大のステークホルダーといえます。地域らしさと企業らしさが重なり合うことで、独自のストーリーが生まれ、取り組みもより魅力的になっていくはずです。
──最後にお伺いします。お二人にとって森の魅力とは何でしょうか?
長野:実際、森に行くと圧倒的に気持ちがいい。それはきっと人類が森から生まれ、自然の中に戻りたいという本能があるからだと思うんです。森に興味がない人もだまされたと思って、一回行ってみてほしいです(笑)。
生物多様性の話にも通じますが、人間も自然の一部。人は自然を観察したり触れ合ったりすることで、人としての感覚を取り戻せるような気がしています。ネイチャーとウェルビーイングは、きっと切り離せないものなんでしょうね。
澤井:私もキャンプが大好きで、週末は大体森にいます(笑)。5つの視点を語った後でなんですが、「森っていいな」と感じる、そんな素直な気持ちこそがすごく大事だと思うんです。生物多様性の大切さをロジックで積み上げていくことももちろん必要ですが、理屈だけで人は動きません。
世の中に少しでも森に興味や関心が芽生えることで、そこから始まる行動が生物多様性を守る力になります。森に心が動く瞬間が、生物多様性のスイッチになる。そんな感覚的な実感こそが、本質的な自然の大切さを理解し、未来を豊かにしていくのだと信じています。
──本日は貴重なお話をありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?
著者

長野 麻子
株式会社モリアゲ
准木材コーディネーター 森林浴ファシリテーター
代表
農林水産省に入省後、バイオマス活用、食の安全・安心確保、食品ロス削減等の業務に携わり、2018年から林野庁で木材利用を促進する「ウッド・チェンジ 」運動を立ち上げ。2022年に農水省を早期退職し、「日本の森をモリアゲる」をミッションに掲げる株式会社モリアゲを起業。持続可能な未来には豊かな森が不可欠だと考え、山を守る人を応援し、森を想う人を増やす活動を推進。

澤井 有香
株式会社 電通
サステナビリティコンサルティング室
コンサルタント
HR系のクリエイティブ会社を経て、電通へ入社。ビジネスプロデューサーとして飲料/食品/AI/化粧品業界を担当し、ブランド業務を中心に、広告制作・新商品開発・事業立ち上げ等、活動。保護猫を家族に迎え入れたことをきっかけに、社会課題への意識が高まり、サステナビリティコンサルティング室へ。現室では、生物多様性を中心にさまざまなサステナビリティ領域で活動中。猫とビールとキャンプを愛する。