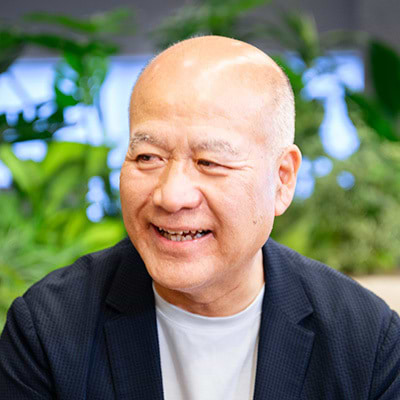あらゆるバイアスを壊し、自らアーキテクト(全体設計者)として社内の事業変革を遂行しているトップエグゼクティブの方々に話を聞きながら、その神髄に迫る本連載。
今回のゲストは、パナソニック オートモーティブシステムズ代表取締役 社長執行役員の永易正吏氏です。パナソニックグループの持株会社制移行に伴い、2022年に設立された同社は、モビリティサービス事業に強みを持ち、「クルマでの移動体験」に新たな価値を提供し続けています。
2024年には、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーというビジョンを策定。ビジョン開発の経緯やビジョンに対する思いについて、変革のパートナーとして伴走する電通の田幸佑一朗氏と小林麻里絵氏がインタビューしました。

(左から)電通 小林麻里絵氏、パナソニック オートモーティブシステムズ 永易正吏社長、電通 田幸佑一朗氏
「100年に一度」の大変革期を勝ち抜くための戦略的な経営投資を
田幸:御社とは1年半以上にわたりご一緒させていただいています。まずは御社の概要をお聞かせください。
永易:私たちは2022年にパナソニックの事業会社として発足しました。ミッションは、「一人ひとりのより良いくらしの実現のため、持続可能なモビリティ社会を創造する」です。カーナビやディスプレーオーディオ、電子ミラー等、多彩な車載システムをグローバルに展開し、安心・快適なモビリティ体験を国内外の自動車メーカーに提供しています。
田幸:御社といえば、2023年11月に発表されたパナソニックグループからのカーブアウトが印象に残っています。どのような背景があったのでしょうか。
永易:自動車業界はいま、「100年に一度」とも言われるような大変革期を迎えています。電動化や自動運転などの技術開発が活発化しており、技術革新のスピードも速く競争がますます激化しています。そんな業界で私たちが勝ち抜いていくには、自社の強みをしっかりと発揮し、勝負できる分野に戦略的に投資していくことが不可欠です。

パナソニックは100年以上の長い歴史の中で、時代に応じて事業のポートフォリオを変えてきました。企業として、どの分野にどれだけの資本を投入できるのか。いわゆる「キャピタルアロケーション(資本配分)」は常に見直されており、それは車載事業においても例外ではありません。私たちは車載機器、特にコックピット領域でグローバルに一定のポジションを確立してきましたが、グループ全体の資本戦略の中では、資本を投入すべき領域ではないと判断されました。
一方で、この領域はまだまだ成長の可能性があると私たちは考えています。だからこそ、自分たちの意思と力で積極的に投資を進めていく必要がある。その実現に向けて、2024年にアポロ・ファンドとパートナーシップを組み、自立した形で成長を目指すタイミングだったと捉えています。
田幸:パナソニックグループ全体の視点で見れば、資本の使い方に関する戦略的な判断ですよね。一方で御社の視点で見れば、自社で資本を集め、成長分野に投資していく体制を整えていける。成長や変革への可能性が広がっていくという前向きなお話だと感じました。
世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げる意義とは
田幸:私たちにはビジョン開発時にお声がけいただき、最終的に世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを採用いただきました。どのような経緯でご相談いただいたのでしょうか。
永易:実は会社を設立した2022年に、ミッションと一緒にビジョンも設定していました。ですが、ビジョンに盛り込みたい要素が多岐にわたってしまい、かなりの長文になってしまったんです。ビジョンは誰からもわかりやすいことが理想で、ワンフレーズやワンワードで表現したいと考え、ご相談しました。
小林:新しいビジョンをつくるにあたって当初のビジョンを拝見したとき、「愛を持って」という言葉がとても印象的でした。永易社長が「愛」をビジョンに盛り込んでいた背景をぜひお聞きしたいです。
永易:若いころの経験が影響していると思います。27歳で初めて海外赴任をして、課長として働いていたのですが、1カ月で現地の部下が全員辞めてしまったんです。日本では平社員でしたから当時はイケイケで(笑)、そこまで気に留めていませんでした。しかし、尊敬していた上司から「お前には愛がない!」と、ものすごく怒られたんです。「上司と部下という関係上、時には厳しいことも言わないといけないけれど、その裏には必ず愛がないといけない。そうでなければ信頼関係は築けない」と指導してもらいました。この後も、僕の心にはずっと上司の言葉が残っていて、「愛」はとても大事にしたい言葉なのだと思います。
小林:今のお姿からは想像できないエピソードですね。私は永易社長の「愛」に加えて、ビジョン作成時に参考としていただいた資料に「感謝」や「笑顔」、「心動かす出会い」といった感情キーワードが見られたのも御社らしさを感じていました。
永易:パナソニックの創業者である松下幸之助は、「より豊かなくらしをおくりたい」という人々の願いを満たすことに企業の役割があると考えていました。その思いが根底にあるからこそ、パナソニックは人やくらしに寄り添った事業を多く展開しているのだと思います。ですから、自然に「人」や「感情」などを大切にしたいという考えが育まれているのかもしれません。
僕は何かを決めるときは、損得ではなく「誰かが幸せになれるか」という判断基準をできるだけ持ちたいと思っています。ビジネスなので理屈ももちろん大切ですが、自分の心、感情にも正直でありたいですね。
小林:まさに、そんな永易さんや会社の皆さんの思いをビジョンに反映したかったんです。「人の“心”に寄り添う」という御社の姿勢をどのように価値として言い換えるべきか考え、「移ごこち」という言葉を提案させていただきました。御社の商品群を拝見すると、単にスペックを高めたものではなく、使う人の感情や日常にまで目を向けたものづくりをされていることが伝わってきます。「心」に寄り添うからこそ「心地よさ」という価値まで到達できると感じ、「移ごこち」と表現しました。「移ごこちデザイン」というキーワードをご提案したとき、「これだ!」とおっしゃっていただきましたよね。
永易:ガツン!ときましたね。すばらしいと思いました。私たちのバックボーンであり、最大の強みでもある「人に寄り添う姿勢や心」を生かして提供できる価値を、ワンフレーズで表現していただけたと感じました。
それと、「デザイン」という言葉もとてもよかったです。私たちはずっと「モノ」を売ってきた会社ですが、例えば快適な移動空間から生まれる「コト」を売ることもあるなと。それを総称できる言葉としてグッときました。
小林:ありがとうございます。「デザイン」の部分は「クリエーション」などの代案も含めてご提案し、社員の方々と、最も自社らしい動詞はどれかと議論を重ねた部分ですよね。結果的に人を中心に考え実現するものがデザインであるということで、デザインに決定したんです。ここは皆さんとの共創で生まれた部分でもありますね。
田幸:社員の皆さんが「自分たちは何業です」と言いやすい言葉を開発したいと考えていました。一見、御社はBtoB企業ですから技術からの発想になりがちです。しかし、ビジョン開発を進めていく中で、高度な技術や性能だけではなく、その先の笑顔や心動かす出会いを見つめているのだと感じました。私たちも自信を持ってつくり上げることができたビジョンです。
永易:確かに、かなり前から「当社は何屋なのか」という話がありました。ビジョンを提案していただいて、“私たちは「移ごこちデザイン」屋である”という共通認識を持てるようになり、本当によかったです。
余談ですが、ビジョン策定のあと、「移ごこちデザイン」の紹介動画も制作しましたよね。この映像は展示会などで繰り返し上映しており、複数の自動車メーカー幹部の方々にもご覧いただいています。その中のお一人からは、「こうした取り組みを私たちがやりたかった」とのお言葉をいただきました。また、「居心地」ではない「移ごこち」という表現に共感してくれたメーカーの社長もいらっしゃり、業界関係者の方々に思いがしっかり届いている手応えを感じています。
「移ごこちデザイン」は社会課題の解決にもつながっていく
田幸:ビジョン開発と合わせて、御社がデザインする「移ごこち」の提供価値を1~5つ、そして無限大という表現で計6つに紡ぎあげた移ごこちデザインキャンバスも制作しました。僕はここに御社の事業部の英知が結集されていると感じ、とてもいいなと思っているんです。同時に制作したオウンドメディア移ごこちデザインスタジオでも、キャンバスやそれをひもといたコンテンツを掲載しています。
永易:移ごこちデザインキャンバスで、社員の「移ごこちデザイン」への解像度が上がったと思います。自分が担当する事業や商品、技術がどの「移ごこち」の開発につながっているのかがわかりやすいですよね。
僕がこのキャンバスを見て感じたのは、「移ごこち」が社会課題の解決そのものにもつながっていくということです。人は必ず移動しますが、現状はまだまだストレスや不安が多い。少子高齢化や交通手段の不足といった課題も含めて、モビリティを取り巻く問題は今後ますます深刻になっていきます。これは日本だけでなく、グローバルな社会課題でもあります。
当社のミッションは「持続可能なモビリティ社会を創造する」こと。だからこそ私たちは、誰もが安心して、自由に、ここちよく移動できる社会をつくっていかなければならない。これを僕は求めていたんだと改めて気づくこともできました。
<後編に続く>