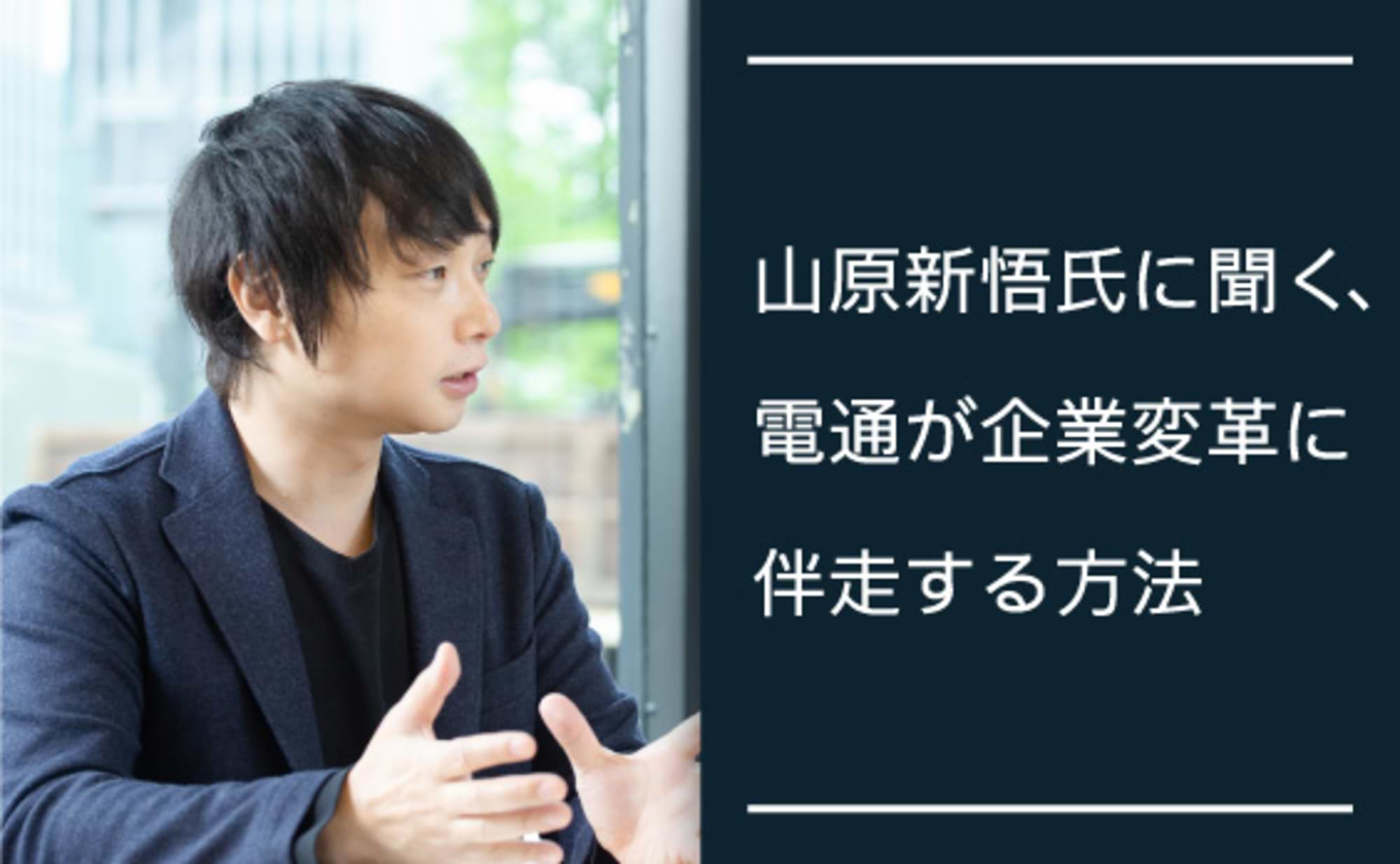あらゆるバイアスを壊し、自らアーキテクト(全体設計者)として社内の事業変革を遂行しているトップエグゼクティブの方々に話を聞きながら、その神髄に迫る本連載。
今回のゲストは、旭化成 ライフイノベーション事業本部で感光材事業部長を務める加藤昭博氏です。
ケミカル、生活製品、繊維、建材などの総合化学メーカーとして、幅広い分野で事業を展開する旭化成。感光材事業部では、フレキソ印刷用の感光性樹脂版や製版装置の製造、販売を長年にわたり行ってきました。そんな中、事業部発足から50年という節目の2023年9月、印刷業界の常識を覆す“ある変革”を打ち出しました。
それは、印刷現場から有機溶剤(※)をなくすソリューション「Solvent ZERO」の発信です。
“いのち”と“くらし”を想い続けてきた旭化成だからこそ、働く人や環境を守りたいという信念のもとスタートしたこの「溶剤ゼロプロジェクト」ですが、そこに至るまでにはさまざまな紆余(うよ)曲折や高い壁が立ちはだかりました。
今回は、同プロジェクトのパートナーとして伴走し、水性フレキソ印刷の啓発と普及促進などをともに行う電通の渕暁彦氏がお話を伺います。
※有機溶剤
ソルベント、トルエンなど他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称。


フレキソ印刷の普及に立ちはだかる2つの大きな壁
渕:じつは加藤さんとお仕事をご一緒するまで、フレキソ印刷というものをあまり知りませんでした。まずは、感光材事業部で取り扱っているフレキソ印刷や感光性樹脂について教えてください。
加藤:フレキソ印刷とは、凸版印刷の一種で、製版する時に感光性樹脂を使うのが特徴です。感光性樹脂は、紫外線に当てると固まる性質があり、この特性を使って凹凸を出して版(樹脂版)を作ります。この樹脂版のプレートを印刷機に巻き付けて、紙やフィルムなどにインクを転写させていきます。ただ国内のパッケージ印刷において、98%を占めているのが銅メッキなどを施した金属のシリンダーを版として使うグラビア印刷(凹版印刷)であり、残り2%がフレキソ印刷という現状です。

渕:フレキソ印刷は日本に比べて海外では、普及しているそうですね。
加藤:そうなんです。印刷する際に水性インクが使え、環境にもやさしいということもあり特に欧米では、かなり普及している印刷方式です。アメリカでは、パッケージ印刷の8割くらいはフレキソ印刷だともいわれています。ただ、日本では、段ボールの印刷に使われるのが中心で、まだまだグラビア印刷が市場を独占している状況が続いています。
渕:日本ではなぜフレキソ印刷がなかなか普及しないのでしょうか?
加藤:大手の印刷会社が、パッケージ印刷用のグラビア印刷機を設備投資して備えているということもありますし、印刷を発注するメーカーさんの中には、印刷=グラビア印刷という固定観念を持っている方も非常に多いのです。そもそもフレキソ印刷自体が知られていないという課題があり、フレキソ印刷といっても「なにそれ?」と思われてしまう……。
こうした背景もあり、私が事業部長になった2020年に、電通さんはじめ広告会社の方々に向けて「フレキソ印刷を知っていますか?」といった内容のセミナーを開催したんです。セミナーにはさまざまな広告を担当するクリエイティブの方にも多く参加していただいたのですが、皆さん共通して、フレキソ印刷=段ボール印刷という認識があり、「カラー印刷できるんですか?」「フレキソ印刷ってモノクロ印刷ですよね」とおっしゃっていたんです。
渕:フレキソ印刷を知っている人でも、誤った認識をしていたり、印刷技術が飛躍的に進化していたりすることを知らない人が多かったのですね。
加藤:そうなんです。実際は、もちろんカラーもできますし、細かい点が表現できるので写真もきれいに印刷できます。そういったことが全く認知されていないという現状に、私ども感光材事業部の人間は非常にショックを受けまして、このままではダメだと……。フレキソ印刷に関わる事業を50年弱やってきたにもかかわらず、ここまで認知されていないということは、同じやり方をこのままやっていても何も変わらないのではないかと思ったのです。そこで、まずはフレキソ印刷を市場で正しく認知してもらう活動を、電通さんに協力していただきながらやっていこうと動き出しました。

渕:こうして旭化成さんと電通でフレキソ印刷を推進するためのプロジェクトチームが発足されたんですよね。その中で、私も加藤さんの商談に同席させていただく機会が何度かあり、まず実感したのが、印刷を発注するメーカーさんのフレキソ印刷に対する固定観念を覆すのは想像以上に難しいということです。
加藤:皆さんフレキソ印刷は品質が悪いと思っているので、フレキソ印刷を紹介してもそれで印刷の質が悪くなって、商品自体の売り上げが落ちたらどうするんだという話になってしまうんです。
また、フレキソ印刷の実物を見ていただき、品質には問題ないと感じていただいても、今度はコストの壁が出てくる……。
渕:まさに認知の壁とコストの壁が立ちはだかっていたんですね。実際に、他の印刷方法に比べてフレキソ印刷はコストがかかるのでしょうか?
加藤:グラビア印刷が普及し過ぎているということもあり、製版にかかるコストなど単体で見ると、たしかにフレキソ印刷の方が高いんです。ただ、フレキソ印刷は印刷スピードが速くロスが少ないというメリットがあります。
たとえば5000m分のパッケージ印刷の依頼があった場合、グラビア印刷で刷ると、印刷機の調整などを含め7000m分刷る必要があるところ、ロスの少ないフレキソ印刷では5500m分で済みます。結果的に機材やインクの使用量が減るため、トータルで見たらフレキソの方がコストを安く抑えることが可能になります。とはいえ、発注側は目に見えるコストに目がいってしまうので、「グラビアの製版のコストはこんなに安いのに、フレキソは高い!」という印象を持ってしまうんです。こうしたコストの壁も、フレキソ印刷がなかなか浸透しない原因のひとつだと感じています。
原体験のエピソードが、ブレイクスルーのきっかけに
渕:プロジェクトチームの活動を開始した当初は、「環境にやさしい」「CO2の排出が抑えられる」などSDGs視点でのアプローチを基本としていましたが、最終的には「環境にやさしいのはわかるけど、コストは高くなるんだよね」と言われて悔しい思いをしたのをはっきり覚えています。
何か打開策はないか。チーム内で議論していく中で、以前に加藤さんからお聞きした、海外の営業担当をされていた時のエピソードを思い出したんです。
加藤:あれは25年くらい前に海外営業を担当していた時の実体験でしたが、私自身、忘れられずに心にひっかかっていて……。それを渕さんや電通の皆さんにお話ししたんですよね。
印刷現場では、さまざまな用途で有機溶剤が使われます。印刷で使用するインクの成分にもトルエンなどの有機溶剤が使われているほか、製版時にも、版の洗浄などに有機溶剤が使われます。そのため、国内の印刷現場や製版現場では換気設備などを設置して、臭気が室内に充満しないように十分な対策が取られているのですが、当時の海外、とくにアジアでは環境整備が進んでいない現場がほとんどでした。
そんな中、営業担当として台湾の製版会社を訪れた際に、締め切った製版室で作業員たちが保護メガネやグローブなどを着けずに有機溶剤を使っている光景を目の当たりにしました。換気もされていないため、室内にはツーンとした有機溶剤の臭いが立ち込めており、労働環境はお世辞にも良いとは言い難いものでした。またある時には、その製版会社を経営するご家族に赤ちゃんが生まれたのですが、その赤ちゃんは日中、有機溶剤を扱う製版室の隣の部屋で寝かされていたのも衝撃的でした。
その様子を見た時に、この環境に疑問が湧きました。もちろん、私は営業担当なので、自社製品をたくさん使ってもらって利益を上げないといけないのですが、人としてこの環境は良くないという想いを漠然と、でも強く感じたのです。ただ、当時はまだフレキソ印刷の技術も進化しておらず溶剤を使用しない水現像樹脂版も開発されていなかったため、自分の中でモヤモヤとした思いだけが残っていたんです。
渕:私自身もこのエピソードは強烈に印象に残っており、ずっと気になっていました。これまではこのプロジェクトの活動の軸をCO2の削減においていたのですが、チーム内で議論を重ねる中で、もしかしたらCO2削減よりも「有機溶剤をなくします」と言った方が賛同してくれる人が多いのではないかという意見が挙がったのです。

企業のパーパスを体現する「溶剤ゼロプロジェクト」がついに始動
渕:さっそく私たちは、知り合いの印刷会社の人たちに「溶剤を使わないというコンセプトの製版機器や版材があったら導入したいですか?」とリサーチをしてみたんです。すると、「現場から溶剤をなくすことができれば、労働環境改善はもちろん、働き方改革につながる」と前向きな反応があり、これはいけるかもしれないと確信めいたものを感じました。
それですぐに加藤さんに、「印刷現場から溶剤をなくしていきませんか?」という提案をしたのです。
加藤:この話を聞いた時に、私は心の奥でずっとモヤモヤしていたものがスッっと軽くなった気がしました。見方を変えるだけで、これまで当たり前だと思って見過ごされていた部分(印刷現場で溶剤を使うこと)にも、変革が起こせるのだなと。
渕:ここから「溶剤ゼロプロジェクト」が本格的に動き出しましたね。
加藤:プロジェクトの方針が決まったことで、私たち旭化成がやるべき開発目標なども明確になり、ステークホルダーに向けてどんなメッセージを発信すればいいのかが見えてきました。それがちょうど2022年の夏ごろだったと思います。
渕:そうですね。この発想の転換が私たちのブレイクスルーだったと感じています。

(後編に続く)
この記事は参考になりましたか?
著者

加藤 昭博
旭化成 株式会社
ライフイノベーション事業本部
感光材事業部長
92年に旭化成に入社以降、一貫して感光材事業に従事。欧州の販売会社に通算9年間在籍した経験があり、その際現地で広く普及しているフレキソ印刷に触れ、そのポテンシャルに感銘を受け、日本・アジアにおいて啓蒙活動を継続。

渕 暁彦
株式会社 電通
トランスフォーメーション・プロデュース局 統合変革プロデュース1部長
IGPプロデュサー/BXディレクター
事業変革・企業変革を起点とした事業成長支援および変革基盤プロデュース業務に従事。クライアント企業に必要な事業変革・企業変革の統合設計から、業務と組織・人財領域を横断した実践アクションの設計・運営支援を行う。