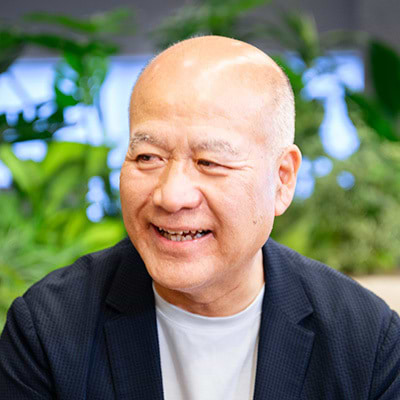あらゆるバイアスを壊し、自らアーキテクト(全体設計者)として社内の事業変革を遂行しているトップエグゼクティブの方々に話を聞きながら、その神髄に迫る本連載。
前編では、パナソニック オートモーティブシステムズ代表取締役 社長執行役員の永易正吏氏に、ビジョンである世界一の「移ごこちデザイン」カンパニー策定の経緯や背景をお話しいただきました。後編では引き続き、永易社長にビジョン策定を経て考えるモビリティの未来や、事業変革について、電通の田幸佑一朗氏と小林麻里絵氏が伺います。
前編:パナソニック オートモーティブシステムズ永易社長×dentsu BX 車載事業会社から「移ごこちデザイン」カンパニーへの変革

(左から)電通 田幸佑一朗氏、小林麻里絵氏、パナソニック オートモーティブシステムズ 永易正吏社長
クルマの「知能化×多様化」時代における「移ごこちデザイン」とは?
小林:世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーというビジョンに加え、ステートメントも作成しました。特に「居ごこちや着ごこちや寝ごこちのように、「移ごこち」のよい世の中にしたい。」という冒頭の文章は永易さんからも好評をいただき、「世の中に対してこれぐらい大きな価値を届けていきたい」とおっしゃっていただいたのが印象的でした。
田幸:こうしたエンドユーザーを表現する言葉を、BtoBの会社が掲げるのはインパクトがありますよね。これからのモビリティ業界をカーメーカーの皆さんと一緒にリードしていく、一緒になってモビリティの未来をつくっていくという意思の表れにも受け取れると思います。
永易:数年前から私たちはBtoBだけど、BtoBtoCでもあると考えていました。C、つまりエンドユーザーをわかろうとしないと、新たな価値を生み出すことはできない。メーカーの要望に忠実に対応するだけではダメだと思ったんです。EVやSDV(Software Defined Vehicle)など、クルマの技術革新が目覚ましい中で、カーメーカーもどのようにオリジナルの価値をつくり、差別化していくか悩まれています。これからはカーメーカーの「共創パートナー」として、一緒に答えを見つけていくような関係を築けないと、この業界では生き残れないでしょう。
田幸:モビリティ業界でトピックとなっている、「クルマの知能化、多様化」にもつながるお話だと感じました。知能化×多様化という文脈の中で、御社としてはどのように「移ごこち」をデザインしていこうとお考えでしょうか。
永易:今後「移ごこち」をつくっていくのは、ソフトウエアやAIの技術だと思います。知能化の中心にあるのがSDV、つまりスマートフォンのように、ソフトウエアのアップデートで機能を進化させていくクルマでしょう。そして、SDVを実現するために不可欠なのが、HPC(High Performance Computing)です。これは、膨大な情報をリアルタイムで処理したり、ユーザーの状態を分析して環境を自動で整えたりといった、高度な判断や制御を支える頭脳の役割を担う技術です。
当社にはテレビや携帯等の開発経験者が多数所属しており、ソフト開発において大きな強みがあります。こうした卓越した技術を生かし、HPC事業にさらに注力していきます。私たちは理想的なSDVを実現していく存在にならねばなりませんし、僕はなれると思っていますからね。
そしてもう一つ、多様化に通じる部分が当社のイノベーションである「キャビンUX」です。私たちはこれまで、人の状態を読み取るセンサや、環境を調整するデバイスを開発してきました。これからはそれらをもっと高度につなぎ、人の気持ちや状態に合わせて動くような技術へと進化させたいと考えています。例えば顔の表情や血流などから感情を読み取り、それに合わせて光や音、空調などを自動で調整する。そうすることで、一人ひとりに合った快適な「移ごこち」を届けられるようになると思います。
つまり、ソフトウエアやAIでクルマの「知能化」を進めながら、人に合わせて変化する「多様化」も実現していく。その両方を支える技術を、私たちはすでに磨いてきていると自負していますし、今後も強化していくつもりです。
経営の筋肉質化やDEIの推進 永易社長が進める変革の取り組み
田幸:多様性の話にも通じると思いますが、永易社長自らDEI(Diversity・Equity・Inclusion)の推進を担当されていますよね。
永易:そうですね。社長に就任したタイミングで、自らDEIの担当を引き受けました。まずは自分自身の意識を率先して変革し、会社、そして業界に変革のきっかけを生み出したかったんです。社内をあらためて見渡すと、業界柄かやはり男性が多く、考え方や価値観もまだまだ画一的だと感じています。僕は、同じ考えの人が集まる会社では、新しい価値は生まれないと思っています。性別・国籍・キャリア・ライフスタイルなど、多様な背景を持つ人たちが集まり、挑戦できる環境こそが新しい発想や事業につながっていくはずです。
小林:先日「ここちよさの深掘り」というテーマで永易さんとビジュアルセッションを実施しました。その際、「ここちよさは世代や性別、人それぞれの価値観などによって感じ方が全く違うかもしれない」というお話になり、若手の社員の方々にも「ここちよさ」に関するセッションを実施させていただきましたよね。すると、本当に人それぞれで違いがあって。適度な緊張感がここちよいという方もいれば、フェスのようなにぎやかさが好きな方、一人の時間が大切な方など、人の数だけここちよさがありました。やはり御社がつくる「移ごこち」も画一の価値観でつくられたものではなく、多様であることが理想的とお話ししたことが印象に残っています。社員の多様性を大切にするという視点は、永易さんが先ほどお話しされていた、“一人ひとりに合った「移ごこち」を提供する”ことにつながるように思いました。
永易:多様性を重視することは、いくら経営が変わろうと続けていかなければいけないことだと思っています。トップが変わったら文化も変わるというのはよくないですよね。
田幸:パナソニックグループからカーブアウトされていますが、それでも創業者は変わらないということは、従業員の皆さんも矜持として持ち続けていらっしゃるように感じていました。不変のものを大切にしながらも変えていくべきところは変えていく。まさに御社は変革期にあるように思います。
私が永易社長の変革で印象的だったのが「経営の筋肉質化」というキーワードのもと、事業部制を廃止されたことです。100年近く本社グループが培ってきた在り方を変えていくのは相当な決断だったと思いますが、どのような背景があったのでしょうか。
永易:もともと我々の事業は、お客さまごとに地域でしっかり納入していく必要があることから、地域軸でグローバル展開してきました。ただ、その一方で、長年「ジャパンセントリック(日本中心)」な体制が残っていたのも事実です。
これまでの「グローバル事業部軸経営」は、事業部長が事業単位で意思決定を行う形で、一気通貫で動きやすいというメリットがありました。しかし、オペレーション面では縦割りになりやすく、特にサプライチェーンの連携や生産性の面で非効率が生じていたのも事実です。また、お客さまにとって社内の部署の違いは関係なく、「会社としてどう対応してくれるか」が重要です。組織もお客さま目線に立ち返った在り方が必要なのではと感じ、地域軸での経営体制へと大きく舵を切りました。まだ始まったばかりで未知数な面ももちろんありますが、私たちにとって大きな変化点になったと思います。
田幸:まさに「移ごこちデザイン」への考え方と同じですね。永易さんは「ユーザー視点」で物事を考え、変革を起こしていらっしゃるのだと思いました。
すべての人がストレスフリーで移動し、QOLが上がる未来をモビリティでつくる
小林:永易社長が見つめるモビリティの未来についておうかがいしたいと思います。永易さんは、“一つ一つの「移ごこち」が、社会課題と密接に関わっている”とお話しされています。特に永易さんが重要と捉えている、移動にまつわる社会課題にはどのようなものがあるのでしょうか。
永易:私が目指すモビリティの未来は、すべての人がストレスフリーで移動できる社会をつくることです。そのために特に重要視しているのは、高齢化などによる「移動弱者」をどう救うかです。移動が困難になると、生活の満足度や幸福度が下がってしまいます。「行きたいときに、行きたい場所へ、ストレスなく移動できること」が非常に大切ですし、そんな世界を目指したいと思っています。
また、今注目されている「地方創生」もモビリティの活性化と深く関わっており、自動運転の導入や過疎地での移動支援は、まさにそのカギを握っています。ただし、法制度や安全性といったハードルも多く、そうした障壁をどう乗り越えていくかが重要です。こうした課題を私たちだけで解決することは難しいので、多様な会社と連携しながら取り組んでいきたいですね。
多くの課題がある一方で、モビリティには「楽しさ」を生み出す力もあると感じています。例えば、スポーツ観戦や観光といった非日常の体験を支える移動の価値。それから最近気になっているのが「推し活」です。地方で行われるコンサートなどのイベントと移動とを絡めて何かできるのではないか。これは地方創生にもつながると思いますし、新しい事業として挑戦していきたいと考えています。社会課題の解決と、人々の心を動かす体験の両方に貢献していきたいです。
田幸:これから先、さらに高齢化が加速する中で必要不可欠な取り組みですよね。御社が描くモビリティの未来を実現するために、会社として大切にしていることや社員の皆さんに伝えていることはありますか?

永易:私たちの最大の強みは人です。これは自信をもって言えます。社員一人一人がもっと挑戦できるようになれば、さらに強い会社になっていくはずです。つまり、当社の進化は、社員が挑戦しやすいカルチャーをつくれるかどうかにかかっているともいえます。
そのために大切にしているのは、「ゼロベースで考える」ことです。この思考ができれば、過去のやり方にとらわれず、今やっていることが本当に必要かという視点のもと、これまでと違った判断軸が出てくると思うからです。
もう一つ「失敗を許容するカルチャー」をつくることも重視しています。特に、失敗したときに「なぜ」は絶対に聞かないようにと繰り返し伝えています。「なぜ」ではなく「今後失敗しないためにどうするか」を建設的に考えられる風土をつくる。社員が失敗を恐れることなく、安心してトライできる環境を育てていきたいと思っています。そのうえで、社員には「健全な危機感」を持つようにと伝えています。危機感ばかりをあおると人は萎縮してしまいますが、健全な危機感を持つことは挑戦するうえでも大事な基盤になるはずです。
小林:個人的な思いになりますが、御社の皆さんはとても謙虚でいらっしゃいますし、自社の価値をことさら強くはアピールされない印象もあります。でも、実際にお話をうかがうと、とても独自性のある事業を手掛けられていて、細やかなインサイトの捉え方や、ユニークなソリューションなど、思わず誰かに伝えたくなるようなお話ばかりです。また、社員の方々のプロフェッショナリズムやお人柄に、感銘を受ける場面もたくさんあります。
だからこそ御社がすでにお持ちの価値を、外からの視点で引き出し、言葉にして世の中に伝えるお手伝いができればと思っています。
田幸:御社は今、大きな変革の真っただ中にあります。私たちが貢献できるのは、コミュニケーションやクリエイティブといった人の心に届ける力を通じて、御社の変革をドライブすることだと考えています。皆さまの思いや意志を「戦略」や「施策」という形で可視化する。それを多様なステークホルダーに浸透させていくことで、期待を生み出し熱量を高め、変革を駆動させる原動力をつくる。そんな存在でありたいと思っています。
永易:ありがとうございます。これまでの取り組みを振り返ると、「移ごこちデザイン」という言葉を生み出していただいたことには、感謝の思いしかありません。ワークショップをはじめ、さまざまなプロセスを通じて、私たちは“ともに価値をつくっている”という実感を強く持っています。だからこそ、これからも変わらぬ共創パートナーとして、私たちの変革を多方面から支え、力を貸していただけたら心強いです。