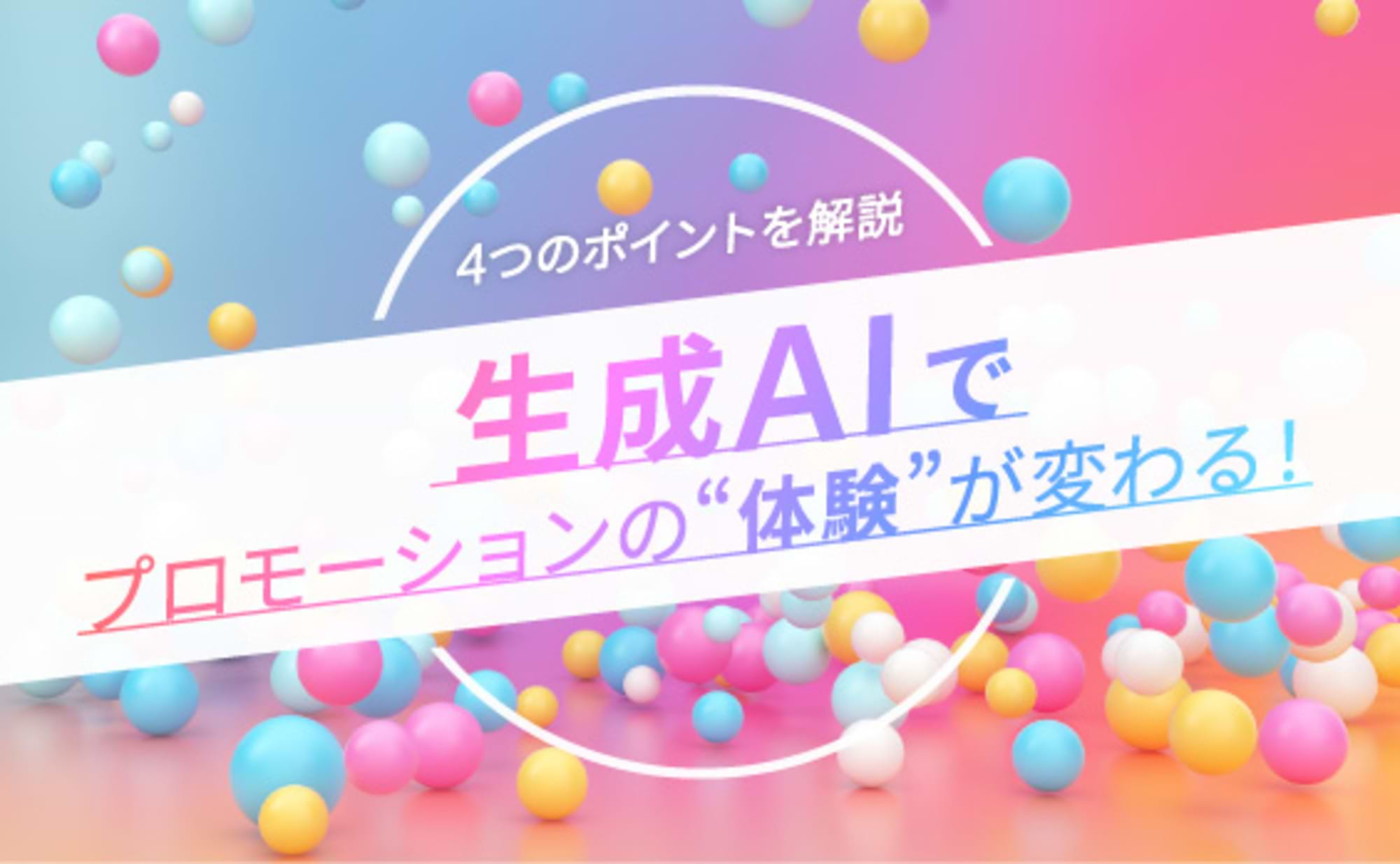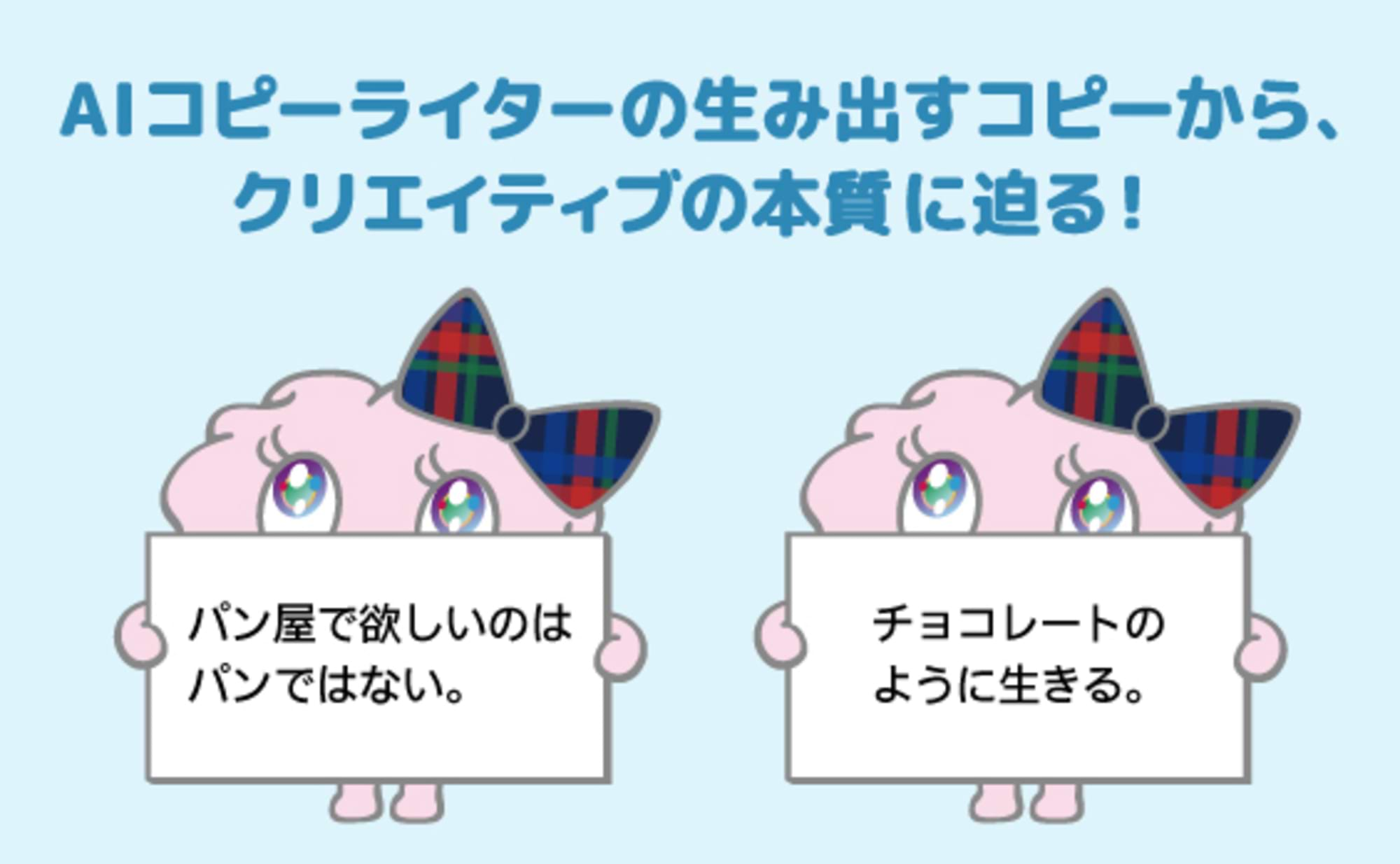AIで完結させない“余白”が生む体験価値。マキアージュの生成AI×プロモーション実践例

広告やマーケティングの分野では、生成AIの活用に向けた動きが加速しています。電通グループでも、生成AI×プロモーションを通じて、ユーザー体験の価値を高める取り組みを積極的に展開しています。
本記事で取り上げるのは、資生堂「マキアージュ」ブランド誕生20周年のリブランディング施策として展開された「おしゃべりメイク診断」。企画・開発・体験設計を担った電通の尾上永晃氏、村上晋太郎氏、D2C IDの高橋大輔氏に、プロジェクトの経緯や生成AIの設計、イベントの手応え、そして生成AI×プロモーションの可能性について聞きました。
【「おしゃべりメイク診断」とは】
資生堂「マキアージュ」20周年を記念して開発された、生成AIによる対話型メイク診断コンテンツ。チャット形式の会話を通じて、その日の気分や好みに合ったメイクとマキアージュ商品を提案する。2025年2月には、東京・表参道でリアルイベント「CHOTTO‑SHITA PARTY(チョットシタパーティ)」を開催。「おしゃべりメイク診断」を活用したヘアメイクアップアーティストによるメイク体験、プリクラやフォトブースでの撮影、パーティ体験など、新たな可能性を引き出されたいつもと“ちょっとちがう自分”に出会う楽しさを実感できるだけでなく、その気持ちをみんなでシェアし互いに肯定し高めあう体験を提供した。
https://www.maquillage-chat.com
Z世代との新たな関係構築を目指した、マキアージュ20周年リブランディング
──今回のプロジェクトの背景について教えてください。
尾上:資生堂さんの「マキアージュ」は、言わずと知れた人気のトータルメイクアップブランドで、今回のプロジェクトはその20周年を機に立ち上がったリブランディング施策です。長年トップを走ってきたブランドですが、ユーザー層の年齢が上がってきたことや、韓国コスメの台頭や新興ブランドの登場もあいまって、Z世代を中心とした若年層との接点に課題がありました。
一般的にZ世代の傾向として「自分に自信が持てない」「失敗したくない」という心理があると言われています。情報過多な環境や炎上リスクへの恐れから、変わることやチャレンジすることにハードルを感じている方も少なくありません。そういった若い世代に対して、マキアージュというブランドがどう背中を押せるかがリブランディングのオリエンでした。
──初期段階では、どのような議論があったのでしょうか?
尾上:資生堂クリエイティブのチームと電通チームが一体となってワンテーブルで調査・議論を重ねました。その中で見えてきたのは、Z世代は「自分だけ目立ちたい」といった個の欲求よりも、互いを肯定し合う関係性を大事にしているという点です。
「界隈」と形容されるような共同体の中で、自分の存在が認められることに価値を感じている。メイクという行為についても、仲間同士で「それ似合ってるね」と声をかけ合い、肯定感を高めていく文化があるという意見も出ていました。
これまでの化粧品広告は、「あなたはもっと輝ける」「あなたはもっと自信を持てる」といった“個”を前提にした語りが多かったですが、今回のリブランディングでは「関係性」を中心に据え、「みんなで高め合おう」という方向にシフトしています。

──ブランドの語り口も変わったということでしょうか?
尾上:そうですね。ブランド側が「あなたはもっといける」と言っても、相手には響かないことが多い。むしろ“うるさい”と感じられてしまうかもしれない。「みんながいる」「一人じゃない」と語りかける方が、今の価値観には合っている。その輪の中にマキアージュというブランドが自然に存在している、そのようなあり方を目指しました。
──その考えを具体的にどうプロモーションに落とし込んでいったのでしょうか?
尾上:共感を得るためには、ブランドが言葉だけで背中を押すのではなく、行動で示すことが重要です。友だちや参加者と一緒に楽しみながら、ブランドのメッセージを体感できる。そのようなリアルな場を作る手段として、ポップアップイベントを提案しました。ただ、当然ながらイベントに参加できる人数には限りがあります。より多くの人にブランド体験を届けるためのウェブコンテンツが必要だと考えました。
高橋:コンテンツの中身について議論を重ねる中で、「診断結果が想像を超える体験になると面白いよね」といった話が出てきて、AIを活用する案が浮上したんですよね。
尾上:はい。世の中にはイエベ/ブルベ診断のように、自分に似合うメイクを提案するAIは既にあります。ただ、私たちが目指したのは「その先」でした。あらかじめ自分の手に届く範囲を決めてしまいがちな世代に対して、「もっといけるかもしれない」「新しい自分を試してみよう」と背中を押してあげたい。すなわち、ユーザーの想像を超えるような提案を届けることが、ブランド体験の価値の一つになると考えました。
まるでプロに背中を押されるようなリアルな体験を、AI診断で再現
──実際に「おしゃべりメイク診断」はどのように企画・開発していったのでしょうか?
村上:先ほど高橋さんが述べたように、「生成AIで思いがけないメイク提案を実現したい」というところからスタートし、すぐにプロトタイプ開発に取り掛かりました。実は最初に作った試作は、心理テスト風のAIチャットだったんです。たとえば「都会に向かう道と森に向かう道、どちらを選びますか?」といった質問を重ねて診断結果を出す形式でした。
でもこれがクライアントにも、社内のメンバーにも大不評でして(笑)。「やらされている感が強い」「雑誌の心理テストと変わらない」というフィードバックをもらいました。そこから細かく試作を繰り返し「AIとの会話そのものを楽しめるチャットアプリ」という方向に舵を切りました。

──診断で用いられる会話の設計にはどのような工夫をしましたか?
村上:ヘアメイクアップアーティストさんへのヒアリングを行ったのが大きなヒントになりました。「どんなメイクがしたいですか?」といった直接的な質問よりも、「最近ハマっているものは?」「休日はどんな風に過ごしていますか?」といった雑談的なやりとりから、相手の雰囲気を掴んで提案しているという話を聞いて、これはAIにも応用できそうだと。
試しに、好きな食べ物や音楽について対話を重ねてみると、そこからメイクの提案に自然とつながっていく。その“脱線しているようで徐々に核心に迫る”感じが、まさに生成AIの強みで面白いと思いました。
──会話形式となると、キャラクターの設計も重要になりそうですが、そこにはどんな工夫を凝らしたのでしょうか?
村上:はい。どんな個性を持ったAIにするかも重要な要素でした。今回はターゲット層の当事者であるメンバーたちの意見を軸に5つの個性をつくりました。褒め上手な執事、占い師の女子高生、包容力のあるバーテンダー、歯に衣着せぬ人生の先輩、ノリのいい絶賛MC……といった個性豊かなキャラです。
キャラがかぶらないように相関図にプロットし、「この性格が足りないね」と調整しながら設計していきました。個性のプロンプト設計は、コピーライティング的なセンスが求められる領域で、人間味や体温感を出すためのチューニング方法はかなり試行錯誤しました。キャラクター案や会話パターンなどは一度社内で設計した上でクライアントに提案し、フィードバックを受けながらブラッシュアップしていきました。使用するコスメの色味も、マキアージュに実際に存在するアイテムに合わせて細かくチューニングしています。

──AIの制御や調整面で苦労したことはありましたか?
村上:想像していたよりも苦労は少なかったです。タイミング的に生成AIの性能がかなり向上していた時期だったので、たとえば「使える色はこれだけにして」と指示すれば、かなり正確に守ってくれる。とはいえ、生成AIツールの性質上、同じような提案を繰り返しがちになるので、そこは乱数やバリエーションを意識的に加えるなど、微調整が必要でした。
高橋:指示を詰め込みすぎると、精度が落ちることもありましたよね。
村上:そうなんです。条件が多すぎると、AIが忘れてしまうこともあるので、裏側で定期的に思い出させるリマインダーのようなプログラムを入れています。こうした細かなチューニングは、生成AIを有効活用する上で欠かせない工夫だと思います。
高橋:村上さんに企画から実装まで一貫して担当してもらえたことは、かなり心強かったです。通常の案件だとAIの開発・実装は制作会社にお願いすることも多いのですが、開発・検証のプロセスをチーム内で完結できたことで、プロジェクトのスピードが格段に上がりました。

──「ブランドらしさ」はどのように表現していったのでしょうか?
村上:最新のLPなどを研究しながら、ユニークなユーザー体験とブランドのトーンを両立するUI/UXを丁寧に設計しました。また、会話内容についても、ネガティブな表現を避ける、ブランドのタグラインと一致した表現にするなど、細かい部分まで配慮しています。
高橋:今回のリブランディングでは、ロゴやカラーリングなども刷新されていました。その中で「どこまでなら、“マキアージュらしさ”が保てるのか?」というラインを探りながら進めていきましたよね。キャラのイラストに関しても悩みましたが、結果的にブランドの親しみやすさを補強するような存在になったと感じています。
村上:そうですね。今回は特に、AIに愛着を持ってもらうことを意識しました。最近はAIというと、どうしても冷たい印象や警戒感を持たれることもあります。だからこそ、「このAI、ちょっと好きかも」と思ってもらえるようなコミュニケーションやキャラクターデザインを目指しました。
──イベント設計の工夫についても教えてください。
尾上:イベントで重要だったのは、体験の最後に「気分が上がって出ていける」こと。そして、体験のあちこちに“シェアしたくなるポイント”がちりばめられていることでした。そこはZ世代当事者のメンバーたちの「こういう要素があると楽しい」といった声を積極的に取り入れてコンテンツを構成しています。
高橋:体験要素がそろってきた段階で、改めて「このイベントで何を持ち帰ってもらうのか?」という全体設計を振り返る場面もありました。メイク体験・プリクラ・フォトブースなど、イベントとしての“密度”をしっかり持たせながら、全体のコンセプトと齟齬のない構成に落とし込んでいます。
──メイク体験は即興性が高く、オペレーションが難しそうですね。
高橋:そうですね。ヘアメイクアップアーティストの方々は日替わりのシフト体制でしたが、中心となる方にはAIの設計段階からご協力いただき、フィジビリティも含めて綿密に確認していただきながら、全体の流れを設計しました。日々コミュニケーションを取りながらブラッシュアップしていく形式で、オペレーションは丁寧に整えていったつもりです。
また、診断結果はユーザーのスマホで確認できるように設計し、シェアしやすいように工夫しました。AIの“腕前”を感じてもらい、それがさらに拡散されていく。その循環がうまく回ったのは、体験とテクノロジーをしっかりつないだからこそだと感じています。

“技術だけじゃない”体験設計が導いた高い満足度
──イベント当日の反応はいかがでしたか?
高橋:アンケートやSNS上のコメントを見ても、「AIが楽しかった」という声が多く寄せられていました。実際のメイク体験に至るまでの導入として、AI診断という変わったステップを踏む構成が印象に残っていたようです。診断自体が楽しく、会場全体のコンテンツとのつながりも自然だったと思います。
──ヘアメイクアップアーティストの方々の反応はいかがでしたか?
高橋:メイクさんたち自身もすごく楽しんでくれました。イベント自体をお祭りのように盛り上げてくださって、空気感が素晴らしかったです。AIの診断結果からインスピレーションを受けてメイクをするという、新しいプロセスを面白がってくれていたのが印象的でした。
──ウェブコンテンツとしての反響はいかがでしたか?
高橋:ウェブコンテンツは、イベントと並走する体験として用意していたものですが、公開初月から一定数の利用がありました。何かが当たるキャンペーンでもなく、IPやタレントさんの力に大きく頼っているわけでもない。それでもこれだけ継続的に利用されているのは、診断コンテンツそのものに価値があるからだと感じています。
──クライアントの反応についてはいかがでしたか?
高橋:マキアージュとして、ここまでコンテンツを押し出したイベントは初めてだったようで、かなり新鮮だったのではないかと思います。AIの導入も初めてで、そこへのチャレンジも含め、全体としてとてもポジティブに受け止めていただきました。印象的だったのは、クライアント側の方々もとても楽しんでくださっていたことですね。プライベートで再訪いただくケースもありました。

村上:個人的にすごくいいなと思ったのが、イベントの最後に登場する「褒め部隊」というスタッフたちが、お客さまのことを全力で褒めてくれる仕組みがあったことです。それがすごく褒め上手で。生成AIをフル活用した診断から始まり、プロのメイク体験を経て、最後は人間がしっかりと肯定してくれる。体験全体を通じて、来場者の自己肯定感を高める流れが作れていたと思います。
高橋:「褒め部隊」は、その場の空気を温かく包み込んでくれる存在でしたね。
村上:技術だけに振り切るのではなく、人の温度感がちゃんと伝わる構成になっていた。それが最終的に、来場者の満足度につながっていたと感じています。
高橋:こうしたイベントは、ともすると技術ドリブンになりがちですが、今回はブランド体験を重視した構成にしています。AIというテクノロジーを生かしながらも、人のぬくもりや手触りを失わなかったことが、この企画の大きな成果だったと思います。

AIで完結させない。余白と人の“汗感”が体験価値を高める
──今回のプロジェクトを振り返って、生成AI×プロモーションを成功させる上で大事だと感じたポイントは何でしょうか?
高橋:前回の記事でも少し触れましたが、「AIを使っていること」自体を前面に出す時代は、もう終わりつつあると感じています。技術の面白さを打ち出すのではなく、人が思わず体験したくなる仕掛けや、自然な導線をどう作るかがより大事になる。その意味でも、今回は「個性的なキャラと会話する楽しさ」を起点に体験を設計したことが良かったと思います。
村上:実際、今回の施策では「AI」という言葉をタイトルに入れていません。「おしゃべりメイク診断」という名称にしたのは、あくまで体験が主役であるべきだと考えたからです。
尾上:メイク診断にありがちな、画像で完成形を見せるのではなく、テキストベースで提案して、その続きを人間が仕上げる。この“余白”があることで、AIというよりも体験そのものが印象に残るようになったのかなと思います。
村上:広告って、これまで「一つの憧れ」を提示するものでしたが、生成AIは、あらゆる個性に合わせた提案ができるんですよね。極端にいえば、全員を肯定できる。これはマキアージュが目指したブランド像ともマッチしていて、大きな気づきになりました。
尾上:その人が何を望んでいるのかを会話の中から掘り起こし、本人も気づいていなかった「なりたい自分」を見つけるプロセス。それがAIを通して自然に引き出せるようになったのは大きいですね。
高橋:軽く話しかけているうちに、自分の好みや理想のメイク像が言語化されていく。診断を通じて「自己認識」や「自分の中の欲望」に気づいていくという点も、プロモーション体験として面白かったと思います。
村上:人間とAIの役割分担について考えると、AIは集合知として機能しますが、「誰がやったか」「どこでやったか」といった文脈を作る力は人間にしかない。たとえばプロのヘアメイクアップアーティストに施術してもらったという体験の価値。それはAIだけでは作れない部分だと思います。
尾上:AIで完結させるのではなく、人間の試行錯誤のプロセスやがんばった痕跡など、“汗感”を組み合わせることがプロモーションを成功させるポイントの一つといえるかもしれない。

──他に生成AIを活用したプロモーション事例で印象的なものはありますか?
尾上:味の素(株)さんと一緒に取り組んだ、うま味マッチングサービス「ウマッチ」というプロジェクトがあります。うま味調味料「味の素®」をいろんな食材にかけてみようというキャンペーンで、「うま味のマッチング診断」をAIで行うという内容です。
味の素®って、卵かけご飯やカレー、みそ汁など、どんな料理にも合う調味料なんですよね。「何にでも合うなら、“出会い”をテーマにしたAIによる提案型にしたほうが面白いんじゃないか」という発想から、マッチングアプリのようなUI /UXで食材とのマッチングを楽しんでいただくことを目指しました。

村上:今回は人ではなく“食材”に個性を与えるという試みにチャレンジしています。「おしゃべりメイク診断」では5つの個性を設計しましたが、「ウマッチ」では生成AIの力を使って食材100種に対して個性を形成し、それぞれのキャラと対話しながら運命の組み合わせを見つけ出す体験設計にしています。
また、ウェブコンテンツなので、ユーザーの負担を減らすためにフリーワード入力だけでなく、AIが自動生成した会話の選択肢を選ぶこともできるようにしています。
そして、今回も生成AIだけに頼るのではなく、人の“汗感”を組み合わせています。AIで100種の食材を集めることもできるのですが、実際にいろんな料理に味の素®をかけてみる“食べ比べ会”を開いて、人力でも食材を集めました。その“人間のセンサー”で得た発見を、AIの生成力で対話型コンテンツに落とし込んだ。そこもポイントですね。

尾上:これはプロモーションとは別の視点になるのですが、「おしゃべりメイク診断」や「ウマッチ」の取り組みを通じて、生成AIの活用が“ブランドらしさ”の形成にも役立つのではないかと考えています。たとえば、診断の中で出てくる言葉に「これはちょっとブランドイメージと違うかも」といったフィードバックがあると、そのプロセスを通じて逆に「ブランドらしさとは何か」が浮き彫りになってくるんです。
マキアージュや味の素®のように、ブランド自身が言葉で語る機会が少ない場合、生成AIで擬人化したブランドとの対話が、ブランドの言語表現として機能する。これからは、生成AIを使ってブランドを磨いたり、ブランド理解を深めたりすることもできるんじゃないかと思いました。
高橋:とても面白い視点ですね。生成AIはその技術的な新しさに目が向きがちですが、本質的には体験設計の一要素です。今回のプロジェクトはそのバランスを意識的に設計できた好例だったと思いますし、今後もブランドやユーザーにとって意味のある“使いどころ”を見極めながら、さらに新しい活用方法にもチャレンジしていきたいですね。
この記事は参考になりましたか?
著者

尾上 永晃
株式会社 電通
なんでもありで臨機応変なコミュニケーション設計を得意としている。最近の主な仕事は「もしも東京の真ん中に、山があったら。」「みんなでピノゲー」「カップニャードル」「藤原竜也CookDo」「#667通のラブレター」「サンクチュアリ:ジャイアント猿桜像」など。ACC BC部門審査委員長や「コピー年鑑2022」編集長も務め、そのストレスの影響からか痛風発作が頻発。体質改善に挑みながら8時間寝ている。

村上 晋太郎
株式会社電通
大学院での人工知能系の研究経験と、エンジニアとしての開発経験を活かし、データを起点とした表現を中心に、映像からアプリケーションまで領域横断的な企画を得意とする。

高橋 大輔
株式会社D2C ID
D2Cに入社後、株式会社電通に駐在。2024年より現職。CXコミュニケーションのプロデューサーとしてSNS/PR/WEB/イベント/OOHを連動させた話題化目的のプロモーションや、TVCMを軸にフルファネルで連携させるCXプロデュースの実績多数。主な仕事に、ピノゲー、褒めらレーニア、カップニャードル、マウントレーニア30周年、23時の佐賀飯アニメ、リラックマとカオルさん、PLAY THE GIFT、DIC岡里帆など。