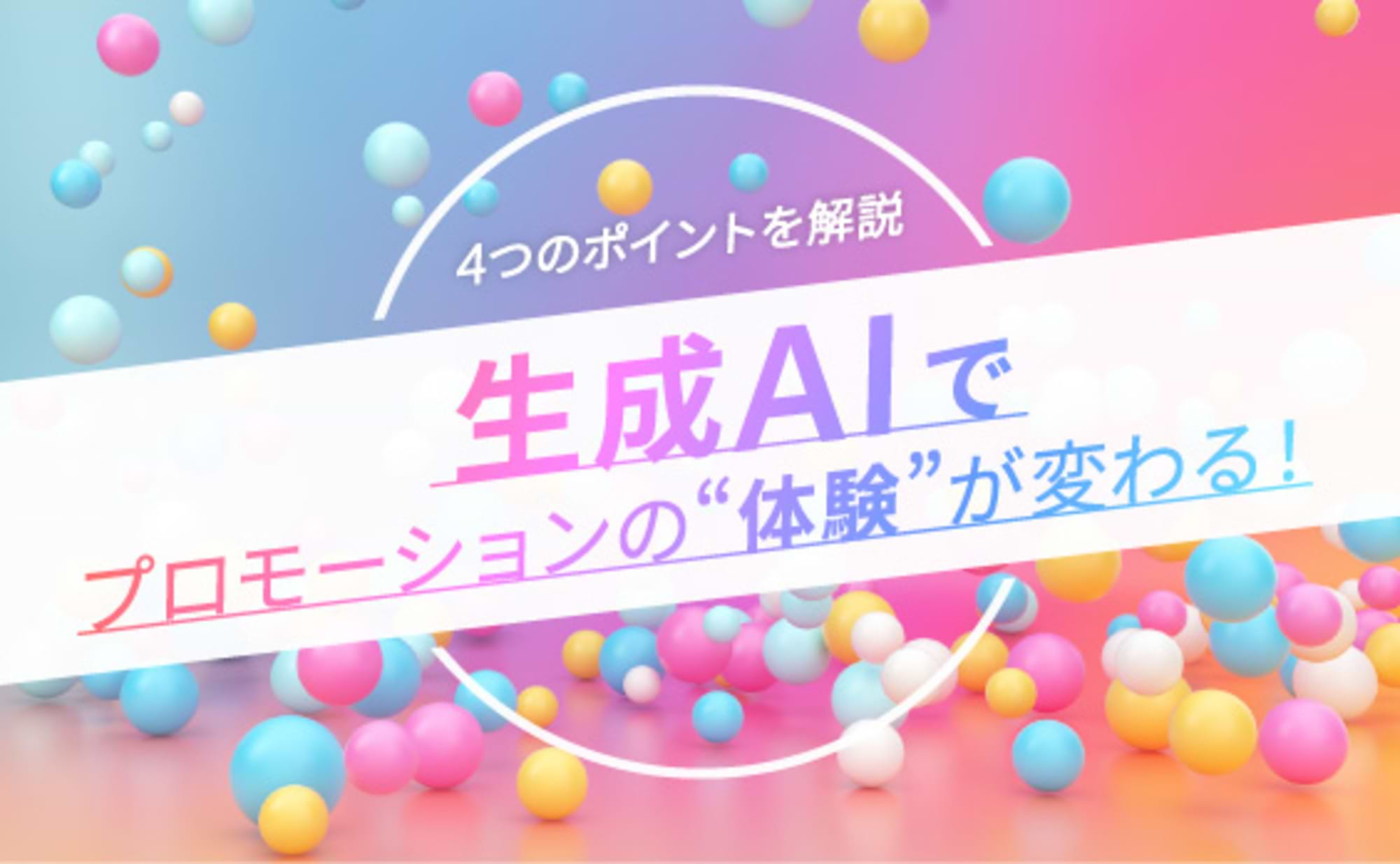生成AI × プロモーション成功のカギ!押さえるべき4つのポイント

生成AIを業務効率化ツールとしてではなく、広告プロモーションの体験価値を高める手段としてどのように活用できるのか?生成AIを用いた多種多様なプロモーション施策を展開するD2C ID取締役CPO(Chief Planning Officer)/エグゼクティブプロデューサーの高橋大輔氏が、具体的な活用ポイントや成功事例を交えながら解説します。
生成AIの進化により、プロモーションのあり方も変わってきています。AIの活用といえば業務効率化の話題が先行している印象ですが、プロモーションにおいても顧客体験(CX)を意識した生成AIの活用が増えています。ここ数年、生成AI活用の施策をお手伝いしてきた経験を踏まえて、「AIを使う」が目的にならず、どのように活用すれば勝算があるのかをまとめてみたいと思います。
生成AIをプロモーションに組み込む際、見落としがちなポイントがいくつかあります。単に話題の技術だからといってAIを活用するのではなく、施策の本質的な目的に合っているかを事前に検証することが重要です。以下にチェックポイントとしていくつか挙げてみました。
1. AIを使う目的は明確か?
生成AIを活用する目的が「AIを使う」ことになってしまうケースは少なくないです。本来の目的は「プロモーション成果を最大化すること」にあるべき。とすれば以下のような役割は相性がよいと考えています。
• UGCの発生
AIがユーザーの入力内容に応じて、AIがコンテンツを生成(ハルシネーション等を回避するための制御も可能)。
SNSで自然にシェアされる仕組みを作る。
• コンテンツのレコメンド
ユーザーの興味に基づいてパーソナライズされた情報を提供し、新たなコンテンツとの出会いをつくる。
• 理解促進
AIと対話するなかで商品やサービスの理解を深める。
これらは一例ですが、プロモーション施策とAI活用の目的が結びついているかを確認することが重要です。
2. AIを使わないとダメ?
「AIを使った施策」というフックだけでは体験の動機づくりが難しいです。「AIだからこそ提供できる価値」に目を向けたいものです。
よくAI施策を代替できそうなものとしては、有限の選択肢を組み合わせた「ジェネレーター」「診断コンテンツ」「チャットボット」「シミュレーションゲーム」などがあります。これらの施策で体験価値を創出できるのであれば、わざわざAIを使う必要はありません。
AIが介在することで無限の選択肢が生まれるという前提で、ユーザーの体験価値を設計できると良いでしょう。以下はプロモーション施策でAIを生かしやすいポイントです。
• 「自分ならではのパーソナライズ感」
ユーザーの入力に応じて異なるアウトプットが生成されることで、唯一無二の体験が生まれる。自分が介在することによって生まれる結果は、前述したUGCと相性が良いです。
• 「予想できない結果」
AIが良い意味での予測不能なアウトプットを生むことで、ユーザーが驚きや楽しさを感じ、拡散につながる。
逆に、既存の手法で実現できる施策に無理にAIを組み込むと、「AIを使ったこと」が前面に出てしまい体験の動機がぼやけてしまいます。
3. 体験内容とAIの親和性を考える
生成AIには、音声・画像・テキストといったさまざまな種類があり、施策の目的に応じて最適な生成AIを選択する必要があります。
[音声生成AI]
音声を生成するAI。活用する上で想定できるチェックポイントはこちらです。
- 音声の提供の仕方は適切か(テキストや画像生成が良いということはないか)。
- AIならではの音声体験が提供できるか(例:「あの有名人の声で話す」「パーソナライズされた応援メッセージ」など。事前収録した音声の組み合わせを超えた体験が提供できるか)。
- 変なことを言ってしまわないか(音声が読み上げる元となるテキスト生成の方で制御を加える必要がある)。
- “AI味”はある程度出るが問題ないか(声を商売にされている方の歌やセリフの価値を下位互換する見え方にならないように注意)。
[画像生成AI]
画像を生成するAI。基本的にこちらもAIを活用する良し悪しがどこにあるかの検討が必要です。
- AIを使うことで、撮影やデザインでは難しいバリエーションを実現できるか。
- AI特有の「違和感」が発生しても問題ないか。
- 人の顔などリスクの高い領域にAIを適用する必要があるのか。
撮影した画像などはレタッチでフォローができますが、体験までにかかる時間やそれにかかるコストはもちろん少ない方が良いので、「生成されたままが面白い」が成立するところまで企画を練る必要があります。
[テキスト生成AI]
いちばん馴染みのあるテキストを生成するAIです。
- 有限な選択肢の組み合わせで代替できるものになってはいないか(診断コンテンツなどは特に代替されやすいジャンルです)。
- 既に提供されているテキスト生成AIの提供価値を超えて、わざわざ体験したいものになっているか。
- 変なことを言ってしまわないようにNGワードの設定やプロンプトによる返答範囲の制御など、安全性の確保ができているか。
- 対応言語を定義できているか。
生成AIごとの特性とチェックポイントでした。関係者で合意しながらAIの行動範囲を定めていくことで、プロモーションの効果やユーザー体験の質を高めることができます。
4. その施策、どう広める?
生成AIを活用した施策は、まだまだプロモーション導入としては手探りなところもあり施策の目線合わせに骨が折れると思います。つくるのに大変で、どこでどうお披露目して、どんな広まり方が期待できるのかの設計まで行う必要があります。
基本的なプロモーションの成功を担う変数は「SNS」「PR(メディア露出)」「AD(広告)」。とくに「SNS」「PR」で自走できる状態を獲得するのが望ましいです。前述のAIならではの活用ポイントを踏まえて、事前に想定しておくべきチェックポイントを整理します。
[SNS]
- 体験の動機はシンプルで強いものになってるか。
- ユーザーが生成結果をシェアできる設計になっているか。
- SNSで投稿される際にハッシュタグや施策タイトルなど話題を統一できる設計になっているか。
[PR]
- 記事化のポイントが整理されているか。
- AIコンテンツ+αでのメディア向けの武器があるか。
- メディアバリューになりうるAIコンテンツの体験数が計測できるようになっているか。
事例1:音声生成AIを活用したプロモーション
森永乳業『さらばAI森田に褒めらレーニア』

さらば青春の光・森田さんが“小さいことほど”褒め倒す!“褒めボイス”生成AI。この施策では、特設サイトを通じて、ユーザーが「褒められたいこと」を入力すると、森田さんの関西弁による“褒めボイス”が生成される仕組みになっています。AI音声の生成には、森田さんが事前に目的を知らされずに収録した200パターン以上のフレーズが活用されており、どのような入力にもユーモラスな反応を返す設計となっています。
小さな出来事でも過剰に褒めるというコンセプトがユニークで、自己肯定感を高めるという心理的な要素も加わり、SNSで話題を集めました。さらに、生成された音声は簡単にシェアできる仕様になっており、ユーザーが楽しみながら拡散しやすい仕組みが整えられています。お笑い芸人とのコラボによる親しみやすさと、AIならではのパーソナライズド体験が融合したことで、広く注目を集めたプロモーションとなりました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000021580.html
事例2:テキスト生成AIを活用したレコメンドサービス
集英社『DEAIBOOKS』

AIとの会話を通じて、自分にぴったりのマンガを発見できるレコメンドコンテンツ。AIキャラクター「会原ぴたり」との対話から、ユーザーの趣味嗜好に合ったマンガを提案するサービスです。キャラクターデザインを『【推しの子】』の横槍メンゴさんが担当し、声優の伊藤美来さんがキャラクターボイスを務めるなど、エンタメ性の高い演出を設計。
このように、AIを単なる技術としてではなく、エンタメ要素と掛け合わせることで、マンガ好きのユーザーに親しみやすい形で提供している点がポイントです。Xでシェアできる設計を入れることで、ユーザー起点での新たなコンテンツとの出会いが自走する構造としております。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000557.000011454.html
事例3:画像生成AIを活用したプロモーション
D2C ID『Parallel Realms Through AI』

『Parallel Realms Through AI』は、画像生成とChatGPTによるテキスト生成を用いて、AIにより生成された架空の自分と出会うことができるディスプレー体験。入力した体験者名と、カメラで撮影された画像から、もしかしたら存在したかもしれない架空の自分の姿と紹介文、人生の中で叶えたいことが生成され、語られます。
AIを使って生成された自分と出会う、ミステリアスな体験です。D2C IDで定期的に実施しているIDEATIONSというR&Dプロジェクトで誕生し、実際に2024年クライアントワークとしてイベントのメインコンテンツとして発展しました。
https://www.youtube.com/watch?v=8pOlsETPPwU
まとめ
生成AIのプロモーション活用は、AIを単なる技術導入としてではなく、ユーザーにとっての体験価値をどう設計するかが鍵となります。
特に、AIならではの強みや、音声/画像/テキスト生成の特性を生かし、「パーソナライズされた体験」 と 「予測不能な楽しさ」 を提供することで、ユーザーの関与を高めることができます。そして、「SNS」や「PR」での自走拡散するための設計を考えることが重要なポイントです。
生成AIの進化はとても早いので、この記事で触れた前提も変わっていくかもしれません。技術の進化を捉えるのはもちろんのこと、プロモーションで培った企画や実行の体感と合わせて、クライアントが安心して投資できる生成AI活用プロモーションを心がけていきたいと思います。
【D2C ID】
電通グループのD2Cグループ一員として、統合マーケティングやデジタルプロモーション、インスタレーション企画・実施、メディア制作・運営などの事業を展開。デジタルとリアルの体験をシームレスにつなぎ、価値ある顧客体験の企画から社会実装まで伴走する「CX CRAFTS」を強みに掲げる。
https://www.d2cid.co.jp
この記事は参考になりましたか?
著者

高橋 大輔
株式会社D2C ID
取締役CPO/エグゼクティブプロデューサー
D2Cに入社後、株式会社電通に駐在。2024年より現職。CXコミュニケーションのプロデューサーとしてSNS/PR/WEB/イベント/OOHを連動させた話題化目的のプロモーションや、TVCMを軸にフルファネルで連携させるCXプロデュースの実績多数。主な仕事に、ピノゲー、褒めらレーニア、カップニャードル、マウントレーニア30周年、23時の佐賀飯アニメ、リラックマとカオルさん、PLAY THE GIFT、DIC岡里帆など。