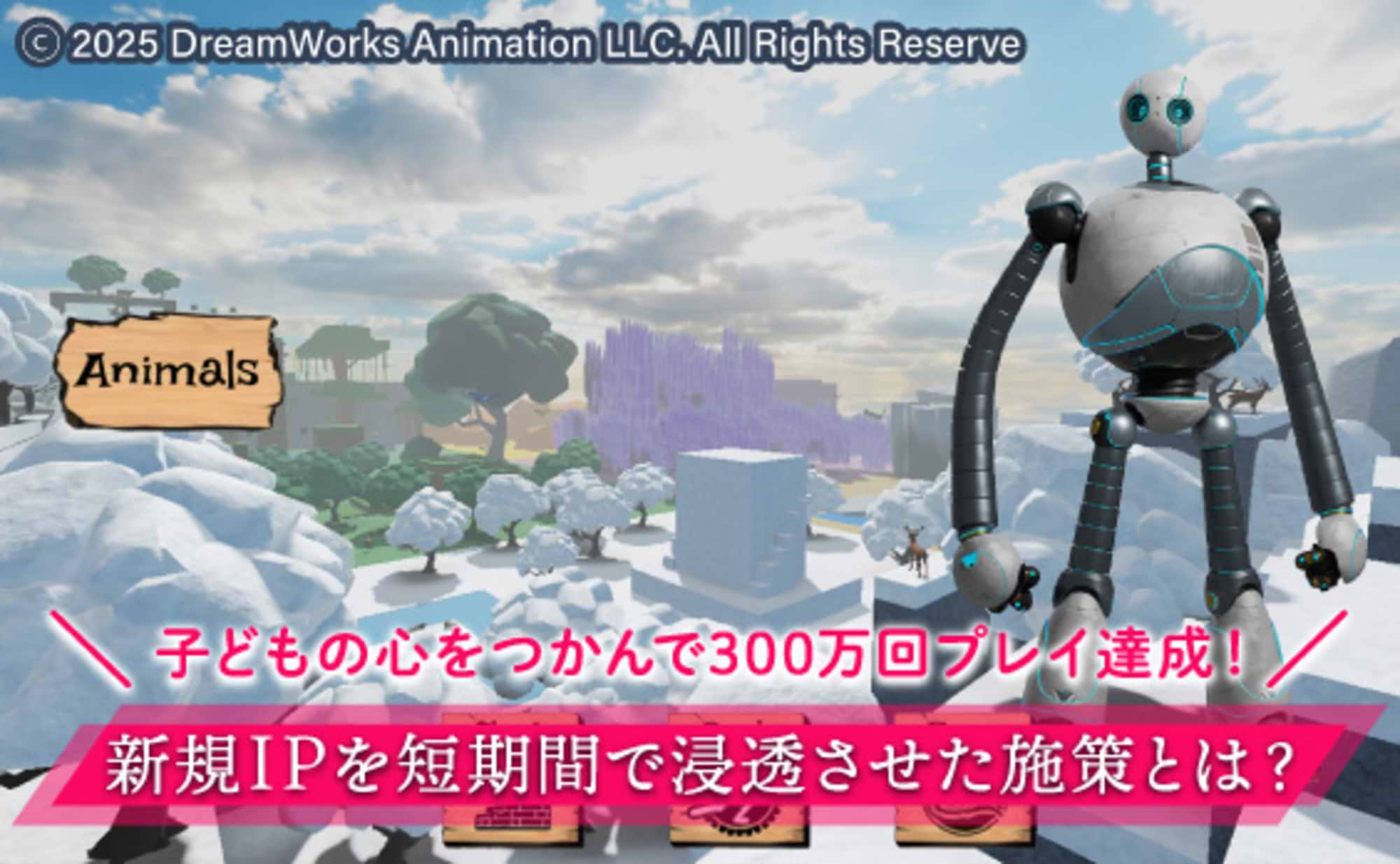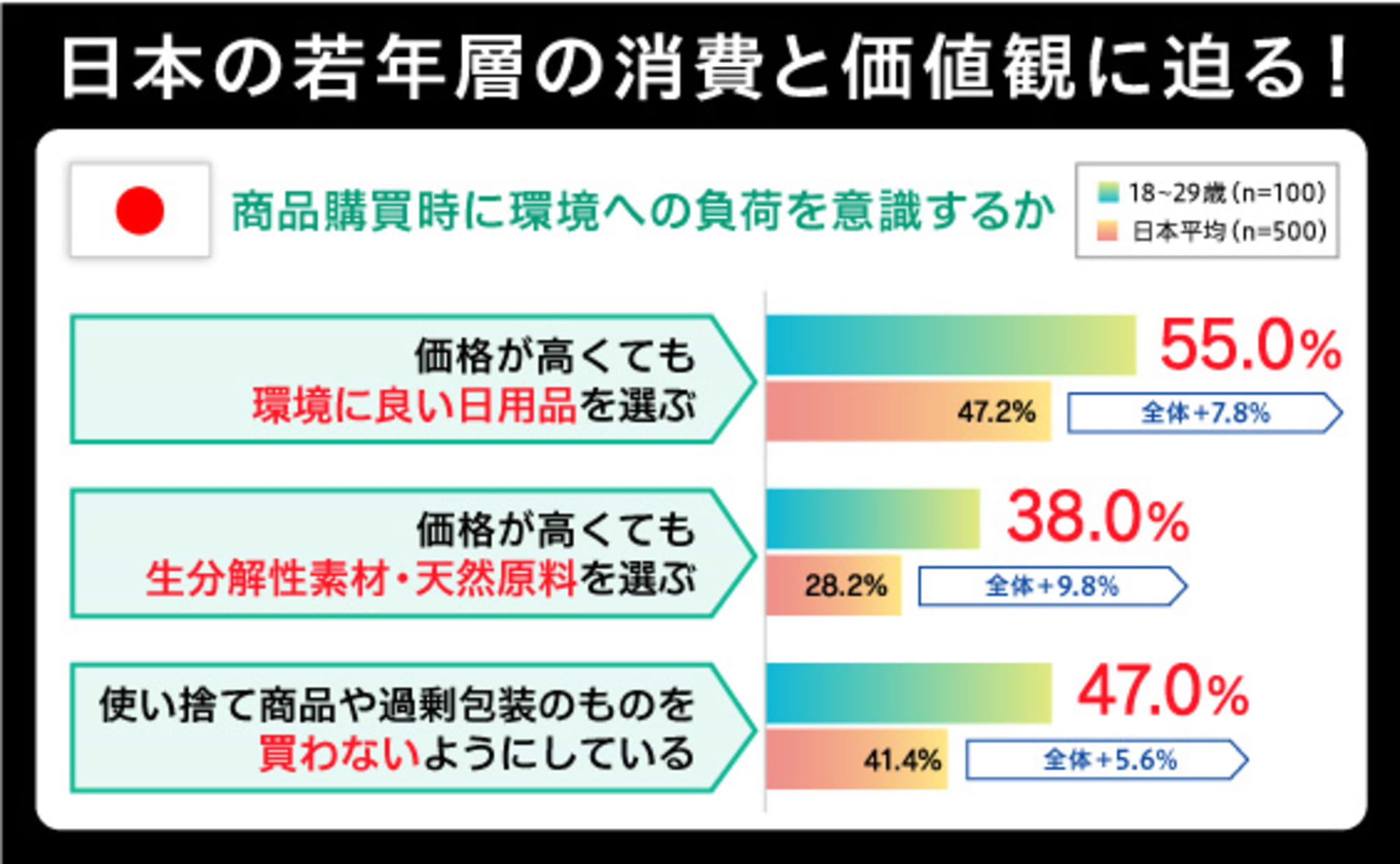300万回プレイ達成!α世代に効く「プル型」のマーケティング施策って?

一般に、新規コンテンツのプロモーションは難しいもの。中でも、ファミリー向けコンテンツで、若年層(子ども)へのアプローチに苦労しているプロモーション担当者も多いでしょう。
そんな中、無料ゲームを用いたプロモーションが若年層に大ヒットし、累計300万回プレイを達成した施策が、「野生の島のロズ:ロズの動物探しアドベンチャー」です。
本施策は、ドリームワークス・アニメーション制作の映画「野生の島のロズ」のプロモーションの一環として実施。世界最大の没入型プラットフォーム「Roblox」上で、主人公のロズを操作する無料ゲームとして公開されました。
いかにしてRobloxユーザーを引きつけ、ロズというキャラクターへの“愛着”を獲得したのか?プロモーション施策をリードした電通グループの小田岳史氏と、映画「野生の島のロズ」のプロモーションを担当した電通の高橋ゆり氏、ゲーム開発を担当したambr(アンバー)の添田光彰氏が振り返ります。
<目次>
▼「能動的な体験」で、ロボットの主人公・ロズへの愛着を生む
▼スピード感あるアップデートが、Robloxでのヒットのカギ
▼国内外への発信力を生かし、長く愛されるファンダムを築いていきたい
「能動的な体験」で、ロボットの主人公・ロズへの愛着を生む

──まず、Robloxでの映画プロモーション施策のコンセプトについて教えてください。どのような経緯でプロジェクトが始まったのでしょうか。
小田:私は電通グループで、投資や出資も含んだ国内外のパートナーとのアライアンス構築と、共同での事業/ソリューションへの落とし込みを担っています。今回活用した没入型プラットフォーム・Roblox、そしてゲーム開発を担った日本のスタートアップ企業ambrとの協業も、その一環です。
Robloxは世界各国でα世代やZ世代の若年層から絶大な人気を集めるプラットフォームで、数多くの企業やブランドがゲームやアイテムを配信するなどの形で参入しています。
関連記事:α世代も夢中!約8000万人が毎日遊ぶ“没入型ソーシャルプラットフォーム”の衝撃
そして今回、高橋さんのエンターテインメントビジネス・センター(EBC)から新しいプロモーション手法の相談を受けた「野生の島のロズ」(以降「ロズ」)は、ファミリー層、特に子ども向けの映画だったため、これはRobloxと相性が良いなと感じたのです。
高橋:本作のメインターゲットの一つである子どもにリーチできるメディアは、限られます。その点Robloxは、α世代と呼ばれる若年層のユーザーが圧倒的に多いプラットフォームなので、私も「ロズ」のプロモーションにはぴったりだと思いました。
また、本作は児童書が原作で、映画化はこれが初めてです。そこで、まずはユーザーに、ロボットの主人公・ロズや、物語を知ってもらう必要がありました。その点、バーチャル空間(※1)でロズのアバターを通した能動的な体験をユーザーに提供できれば、キャラクターに親しみを感じてもらえるのではという期待がありました。
※1 バーチャル空間=Robloxにおける、ユーザーや企業が制作した独自の世界のこと。多くのバーチャル空間はゲームとして提供される。英語版では「Experience」という名称。
小田:「ロズ」は米国でもRobloxを用いたプロモーションを実施しており、既にRoblox用のロズのアバターがつくられていました。日本でのプロモーションでもこのアバターを利用しながら「プレーヤーがロズになって動物を探す」という映画のコンセプトにも合ったゲームをつくることにしました。
このゲーム設計からフィールドデザインまでを手がけたのが、添田さんをはじめとするambrの開発チームです。提供できる素材がロズのアバターと一部BGMのみという中、ほぼゼロからゲーム開発をしていただきました。
添田:私は普段ambrで、CG制作をメインに担当しています。今回はディレクターを担当し、プレーヤーのキャラクターやフィールドのデザインを行いました。当社とパートナー企業合わせて5人の少人数チームで、約2カ月の制作期間でゲームを完成させました。
小田:ambrは、東京ゲームショウのバーチャル会場の制作/運営などのプロジェクトに加えて、自社プロダクトとして国内外で100万以上のユーザーを集めるアバター集中支援アプリ「gogh(ゴッホ)」も手がけています。そうしたIPも含んだコンテンツづくりの経験や企業文化が、Robloxでのバーチャル空間(ゲーム)制作にもふんだんに生きていると感じています。
──ゲーム開発というと、もっと長い期間をかけて大人数で行っているイメージがありましたが、少人数のチームで、しかもわずか2カ月で開発されたのですね。CGアニメーション映画のゲーム化という点で意識したことはありますか。
小田:まずはambrの制作チームにも映画を観てもらい、ゲームにどう落とし込むかを話し合いました。作品について全く知らない人たちに向けてのプロモーションなので、あえて映画の情報量を多く詰め込みすぎないようにしたのもポイントです。

添田:Robloxでのゲーム開発には、プレーヤーの肌感覚を理解する必要があります。せっかくRobloxを活用しても、 あからさまに「大人が宣伝色を押し出したコンテンツ」は、プレーヤーから「ゲームを分かっていない」と言われてしまいます。
当社では、Robloxユーザーの感覚を理解するために、毎週社員みんなでRobloxのプレイ会をやっていて、「ここが面白かった」「じゃあ次のゲームに組み込んでみよう」といった感じでユーザー感覚を養い、リリース後のゲームも改善を繰り返しています。
小田:今、添田さんがおっしゃったようなRobloxのユーザー特性を踏まえ、ゲームデザインについては、「Robloxユーザーにとっての面白さ」を一番のベースにしつつ、映画の魅力も知ってもらう、ちょうどその中間を担うようなゲームを狙いました。
そこで、Robloxの人気ゲームジャンルの1つであるFind系ゲーム(マップ上のアイテムやキャラクターを探して集めるゲーム)に、「ロズが野生の島で動物と出会う」という映画のテーマを落とし込むことにしたのです。
添田:Robloxでは、みんなが好きな「いつもの定番」ジャンルがいくつかあります。そして、斬新さやオリジナリティよりも、「いつもの定番」が好まれる傾向が強くあります。Find系はその一つですね。今回はプレーヤーがロズの姿になって、マップ上にいる20匹の動物を順番に見つけていくというシンプルな構成にしました。
──遊びの面ではどんな特徴がありますか?
添田:プレーヤーは、動物を見つけるごとに、その動物と関係する新しい「スキル」を手に入れていきます。最初は2本足で歩行とジャンプしかできないロズが、例えば鹿を見つけたら4本足で速く走れるようになったり、カニを見つけたら爪先立ちで岩壁を登れるようになったりするんです(笑)。
高橋:この「ロズのアバターが島を走り回って動物たちを探していく」過程が、まさに映画におけるロズが野生の動物たちの仲間として受け入れられていく物語と重なっているんですよね。実際に映画の中でも動物たちを探すシーンがありましたし、映画のテーマである「多様性」や「共存」という要素にも通じるゲームになっていました。
結果として、プレーヤー体験の中でロズというキャラクターに愛着を覚え、さらに作品のテーマにも触れられるという、期待以上のアウトプットになったと思います。
スピード感あるアップデートが、Robloxでのヒットのカギ

──映画の公開2週間前にゲームをリリースしてから、順調にプレーヤーを獲得していき、映画公開後すぐに目標プレイ数だった10万人を超えたそうですね。
添田:Robloxは、プレーヤーの滞在時間や流入・離脱ポイント、再訪率などの分析機能が充実しています。開発側はその反応を見てアップデートを繰り返し、プレイ数を伸ばしていけるのが特徴です。
滞在時間や再訪率が伸びると、ホーム画面のレコメンデーション(おすすめ)にも表示される可能性が上がるので、さらなる流入も見込めます。今回はレコメンデーションにうまく載ることができたのが、成功の要因の一つでした。
小田:他のUGC(※2)コンテンツプラットフォームなどと同じく、Robloxにはユーザーが楽しんでいる優れたコンテンツを発見し、さらに多くのユーザーにレコメンドするアルゴリズムが備わっています。添田さんのお話にあったように、開発者向けの分析機能が優秀なので、改善によるプレーヤーの行動の変化を数字で分析し、PDCAを回せるのも面白いポイントです。
※2 UGC=User Generated Contents、ユーザー生成コンテンツ。Robloxはクリエイターエコノミーに力を入れており、バーチャル空間(ゲーム)やアバター、販売されているアイテムの大半は、ユーザーが作成したもの。
添田:今回もリリース当初、20%のプレーヤーが1匹目の動物を見つけるまでに離脱していることが分かったので、「プレイ開始後すぐに見つかる場所」に1匹目の動物を配置し直したら、プレイの継続率がぐっと上がりました。
小田:それからは、動物の数を20匹から50匹に増やすなど、短いサイクルでアップデートを繰り返していきました。結果として、リリース後約3週間で20万回プレイを突破。その後レコメンデーションによる流入が一気に増えて、最終的に7月14日時点で300万回プレイを達成しました。プレイ回数は300万回ですが、レコメンデーションでユーザーの画面にサムネイルが表示されたインプレッション数は、6700万回以上に及びます。

──プレーヤーの分析をしながら、どんどんアップデートしていくことで、アルゴリズムを味方に付ける方法で伸ばしていったんですね。
添田:最初のFindを改善してから、どんどんプレイ回数が伸びていきましたね。また、ゲームの難易度は、 “Robloxネイティブ”である社員のお子さんに遊んでもらったりして、調節していきました。あとはRobloxでは「小さな成功体験」をたくさん積ませることが重要なので、動物が見つかったときの「おめでとう」の仕掛けなども工夫しました。
小田:結局、広告からの流入はわずかで、最終的には、ホーム画面およびフレンドのレコメンデーションからの自然流入が9割近くを占めました。最後に行ったアップデートでは、2回に分けてアバターアイテムを500個ずつ配布したのですが、1時間半で配布終了になるほど、ユーザーが盛り上がってくれましたね。
3月時点でいったんアップデートは終えたのですが、その後もアップデートを続けたらどこまで伸びていただろうと妄想してしまうくらい、いい結果が得られました。
──目標の30倍ものプレイ回数を獲得できたポイントはどこにありますか?
小田:今回の成功は、添田さんたちが日々スピード感をもって分析と改善のサイクルを回してくれたことが大きく、重厚長大な開発チームだと難しかったと思います。ユーザーからの反応を踏まえた改善を重ねることが必要なRobloxでは、小さく始めてブラッシュアップしながら効果を伸ばしていくのも、いいものづくりにつながるのではないでしょうか。
高橋:予算については、映画のプロモーションにおけるRobloxの影響力が未知数な中での試験的な施策だったこともあり、莫大な予算はかけられませんでした。小規模にもかかわらず予定していた以上の結果を出したことで、特に若年層向けのRobloxでの施策の効果をしっかり証明することができました。
また、成功のポイントとして、「野生の島のロズ」には原作となる児童書はあったものの映画としては新しいIPだったからこそ、アメリカ本国(権利者であるユニバーサル・ピクチャーズ)も、IP活用方法については寛容だったことも挙げられます。比較的自由度高くゲームの世界観に落とし込めたので、それが成功要因になったのかなと思います。
私は本国との連絡を密に取りながらゲームの監修をしたのですが、今回はRobloxユーザーに楽しんでもらうことを優先し、Robloxの仕様や好まれるゲーム性などを大事にしながら、映画の世界観を落とし込むことができました。
──自由度高くというのは、具体的にはどんなことでしょうか?
添田:例えばFind系ゲームの定番として、空中に足場があってどんどんジャンプして登っていったりできるんですが、映画はリアルな野生の島なので、もちろんそんな足場はありません。でもRobloxユーザーにはそういう遊ぶためのギミックが期待されているので、ゲーム内にはそうした要素も盛り込みました。

高橋:作品によって条件が異なりますが、今回の日本での成功を踏まえて、Robloxとのコラボレーションの形はいろいろ考えられそうです。
国内外への発信力を生かし、長く愛されるファンダムを築いていきたい

──今回の施策を通して、改めて感じたRobloxでプロモーション施策を行う利点は何ですか。
小田:Robloxを用いた施策の特徴はいくつかありますが、まずはコミュニケーションが特に難しいα世代のターゲット層にリーチできること。それも、ユーザーの能動アクションを引き出す「プル型」の施策がしやすいことが挙げられます。
広告の中には「プッシュ型」で、ユーザーからすぐにスキップされてしまうようなものもあると思います。しかし本施策では、平均プレイ時間7.4分というエンゲージメントを獲得しました。Robloxのレコメンデーションで表示されたバーチャル空間に来てくれるユーザーは、自分の意思で能動的にIPやブランドと触れ合ってくれるため、結果として自然とエンゲージメントが高くなるのです。
もちろんその前提として良いゲームをつくることが不可欠ですが、このようなエンゲージメントを得られるメディアは他にそうないと思います。

──Robloxは開発者向けの分析機能が充実しているということですが、今回ユーザーの属性などはどんな傾向がありましたか。
小田:まず特徴的だったのは、全体の39.1%が「9歳未満」のプレイで、全世代で最大であったことです。当初の想定通り、ターゲットの子どもに楽しんでもらえていたというのが一つ。また、日本向けの施策だったにもかかわらず、オーガニックに世界中のプレーヤーに楽しんでもらえたということも挙げられます。

添田:Robloxは自動翻訳機能に力を入れていて、ゲームなどのUGCを公開すると自動的に多言語に翻訳されます。そのため、低コストで全世界のユーザーにフラットにアプローチできるのが大きな利点ですね。
小田:今回も、あくまでも映画の日本公開に合わせた国内向けのプロモーションだったものの、アメリカからのプレーヤーが最も多く、最終的に約180か国以上からプレーヤーが集まりました。
つまり、Robloxは日本のIPを海外に発信していくのにも有効な施策であると感じています。日本のコンテンツやIPを全世界に波及させるという点で、グローバルネットワークを持つ電通のポテンシャルを発揮できる余地が大いにあると思います。
──映画のプロモーション施策としては、今後Robloxはどのように活用できそうですか。あるいは今回課題に感じたことがあれば、教えてください。
高橋:今回の施策が実際、映画への送客につながったのかの効果測定はできていないので、その点は課題として残りました。例えば海外の他映画作品のプロモーションとしては、Roblox内に映画のバーチャル空間をつくったうえで、バーチャル空間内に映画チケットの購入動線を置いて販売促進に成功したアメリカの事例もあります。若年層が大半を占めるプラットフォームで商品の購入を促す取り組みを日本で実現するのはだいぶハードルが高いですが、このようなことが日本でもできるようになれば、今回できなかった効果測定ができるようになるかもしれません。
一方で個人的には、Robloxは購買促進というよりも「ファンを形成するプラットフォーム」として捉えられるといいのかなと思っています。プロモーション期間に限った単発のものだけでなく、長期的にアップデートを続けて、能動的に映画の世界に触れ続けてもらい、ファンの愛着を育てるようなコンテンツを発信するのに向いていると思いますし、そうした形をつくることが理想ですね。
添田:既存のIPをRobloxに持ち込むケースは多いですが、逆にRobloxの中の独自コンテンツがIP化していくケースも多いんですよね。既存IPであっても、Robloxでヒットすれば、その要素をRoblox外に波及させていくのも面白そうです。今回に限らず、ambrではRobloxユーザーに受け入れられるためのノウハウが蓄積されているので、今後もいろんなIPでゲーム開発をしていきたいです。
小田:今回の若年層向けの施策では、Robloxを活用し、そのカルチャーに向き合うことで1つの成功事例をつくることができたと思います。IPホルダーの方々のコンテンツをグローバルに届けていく上で、Robloxを用いた施策は大きな可能性を秘めていると感じています。
一方で、コミュニティのカルチャーや話法に向き合うことは、Robloxに限らず重要です。IPやブランドを届ける際には、そのコミュニティやユーザーに向き合って届けたいコンテンツとの接着点をデザインすることで、着実にヒットを生むことができるはず。ユーザー体験に向き合いながら、今後もIPホルダーの皆さまと一緒に、Robloxなどのプラットフォームを活用して、コンテンツのファンダムを育てていける存在になれたらと思います。
「野生の島のロズ」はAmazonプライム・ビデオ、U-NEXT、Apple TV+、Huluほかにて配信中!
この記事は参考になりましたか?
著者

添田 光彰
株式会社 ambr
ディレクター/CGデザイナー
設計事務所での業務を通して3DCGの制作について学ぶ。その後メタバース業界で経験を積んだのち、ambrの社風やビジョンに共感し入社。器用大富豪をモットーに、最近では3DCGの制作に加えて、ディレクター業やAIを用いたコーディングなどにも幅を広げながら活動。

小田 岳史
株式会社 電通グループ
グローバルビジネス開発センター、電通ベンチャーズ
株式会社電通グループおよびCVC電通ベンチャーズで、投資/出資も通じたアライアンス構築、事業開発にグローバルで取り組む。主にメディア・コンテンツ・ゲームなどエンターテインメント領域を中心に担当。

高橋 ゆり
株式会社 電通
エンターテインメントビジネス・センター
プロデューサー
シンガポール育ちのミレニアル世代。学生時代に日本の大学とパリ政治学院の2つの学士号を取得。人生の半分近くを海外で過ごし、外から見た日本のエンタメ力に魅了され、電通に入社。グローバルメディアおよびデジタルメディアプランナー、グローバルビジネス開発などを経て、現在は洋画ビジネスにフィールドを転向。主に洋画作品の日本におけるマーケティングを担当している。