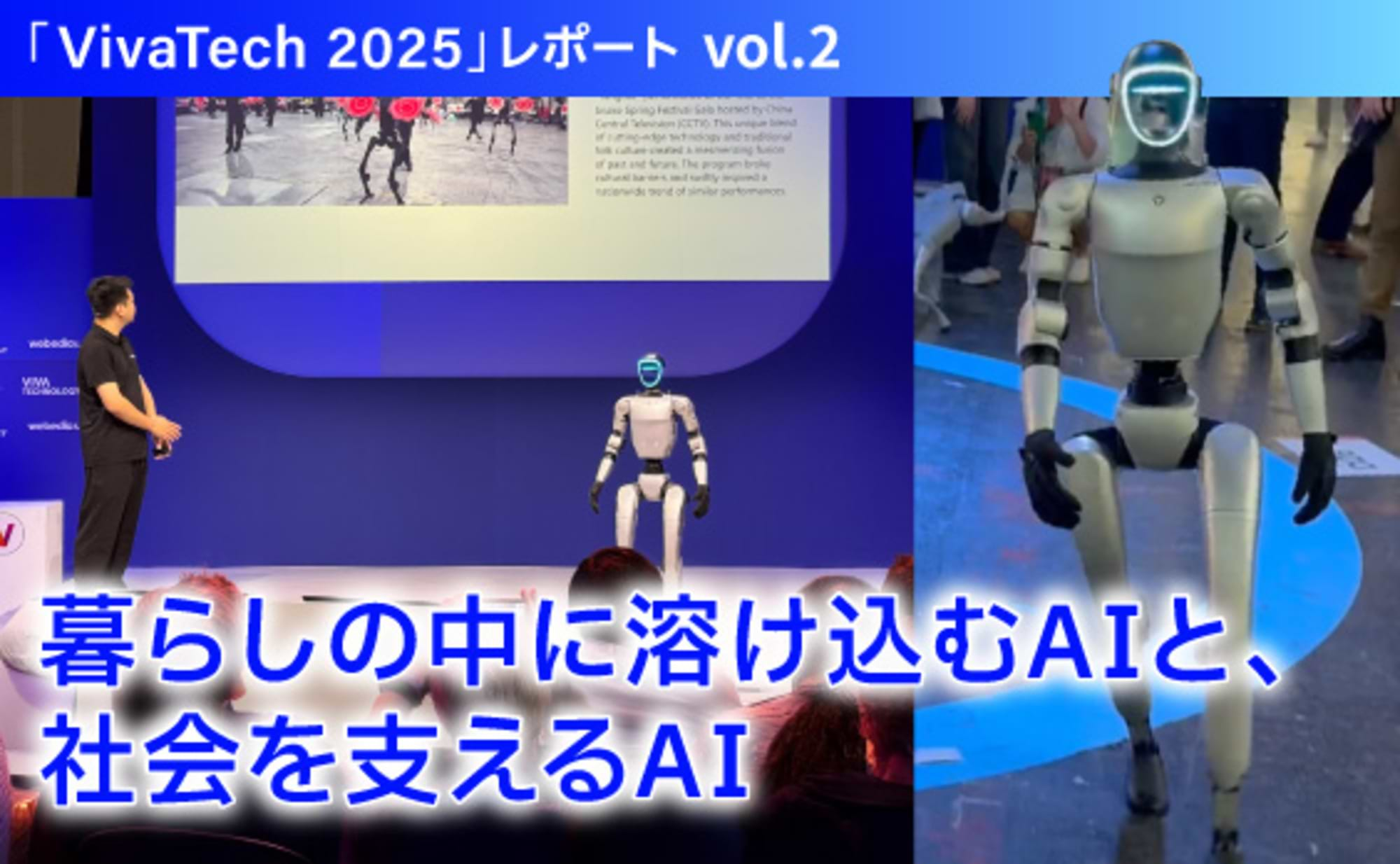こんにちは、Dentsu Lab Tokyoの なかのかな です。ラボのR&D活動の一環として、2025年6月11日〜14日にフランス・パリで開催されたヨーロッパ最大級のテックイベント「Viva Technology 2025」を視察してきました。後編では、大手企業とスタートアップのコラボレーション事例や国別ブースの様子をお届けします。
LVMHはブドウから店舗までAIを活用

会場中央に構えられたLVMHブースでは、傘下のメゾンとコラボレーションする15社のスタートアップが紹介されていました。レース状の内装は昨年のLVMHイノベーション・アワードの受賞企業Aectualが担当しており、リサイクル素材と3Dプリント技術が活用されています。

モエ・エ・シャンドンでは、ブドウの病気や傷を見分けるシステムにAIを活用しています。農業用画像解析ソリューションを提供しているHiphenとの協業で、6000枚以上の注釈データつきブドウ画像で訓練したアルゴリズムは、1万6000パレットを超えるブドウの品質評価を3週間で終えられるようになったそうで、2024年に全てのモエ・エ・シャンドンのプレス機に導入されています。パートナー農家向けには写真の中央の黒い機器のような移動可能な検査キットも開発しています。
ブルガリは、AIでジュエリーのトレーサビリティを実現。Dev4Sideとの協業により、人の目には見えないマイクロサイズで彫り込まれたシリアル番号を専用アプリで読み取ることで、真贋(しんがん)や産地といった情報を確認したり、サポートを受けたりすることができます。

AIで商品画像の制作デモを行っていたのがルイ・ヴィトンです。Rigstersのロボットカメラで商品を360°撮影して3D化、OKCCの生成AIソリューションによりブランドに合わせた背景を作り出すことで、ウェブサイトやキャンペーンのローカライズに役立つとしています。
ディオールはオンライン体験のパーソナライズ化にAIを用いていました。提携先のKahoonaはサイト訪問者の振る舞いからデジタル・プロファイリングを行い、実店舗の経験豊富な店員のように顧客のプロファイルや行動を予測し、個々のニーズにリアルタイムに応えることができるようにするソリューションが評価され、LVMHイノベーション・アワードで最優秀ビジネス賞を獲得していました。
生成AIを用いたビジュアルが印象的だったロレアル

未来的なビジュアルが目を引いたロレアルブース。昨年のVivaTechで発表された社内向け生成AIラボCREAITECHは、各ブランドに対応した商品開発や広告制作を高速化する目的で作られており、来場者がブランドに即した画像や映像の生成を体験できるコーナーもありました。

AIを活用したマルチブランドのビューティーマーケットプレイスNoli(No one like I(ノリ)は、ロレアルが設立したスタートアップで、NVIDIA(エヌビディア)、アクセンチュア、マイクロソフトとの協業を発表しています。ユーザーの「ビューティープロファイル」をもとに、製品をマッチングするAI診断ツールを搭載しており、100万件以上の肌スキャンデータと数千の製品の配合データをAIが分析し、ユーザー一人ひとりの肌質や悩みに合わせて複数ブランドから最適な製品を自宅に届けてくれるそうです。
環境負荷を抑えながら高品質な製品づくりを目指す、サステナブルなAI活用事例もありました。香水の原料となる植物を栽培する垂直農業システムは、フランスのInterstellar Labが開発したもの。同社は宇宙ステーションや火星などでの食物生産技術を開発しています。従来の品質を保ちながらも水や栄養の最適化で資源の消費が少なく、輸送にかかるエネルギーも削減できるそうです。
また、育てた植物から香り成分を抽出するための新しい技術も紹介されていました。加熱や冷却ではなく空気の流れによって揮発した香り成分を集める手法で、これまでの手法ではできなかった香り成分を抽出することができるそうです。
鯨からがんまでAIで見分けるカナダ
今年の国カナダのブースは中央に人形ロボットAmeca(アメカ)を設置。イギリスのEngineered Arts社のロボットですが、応答にはカナダのIVADO LABSのプログラムが使用され、AIやブースの質問に対して答える仕掛けで人を集めていました。Viva Techで今年新設された「Tech for Change」アワードのファイナリストに選出されていたReveal AIは、光学的手法とAIを組み合わせることで、生体内でのリアルタイム分子診断ができるツールを展示。がん手術の際の切除する領域を正確に判定することで再発率を下げることができるそうです。
その他にも、コンテナや倉庫などへの商品の最も効率的な積み方を3Dビジュアルで提案するソフト、鯨など海洋哺乳類を自動検出することで船への衝突防止や生態調査などに活用するツール、猫の痛み度合いを表情から推定する獣医師向けアプリなどさまざまなスタートアップがAIを応用したビジネスを展示していました。
アフリカテックアワードでもAI関連企業が受賞

フランスという地理的・言語的な親和性から、VivaTechにはアフリカからの出展が例年積極的に行われているそうです。今年はセネガル、コートジボワール、初出店のギニアなど8カ国がブースを構えていました。4回目になるAfrica Tech Awards(アフリカテックアワード)では、eコマース&フィンテック部門でナイジェリアのZeeh Africaが受賞。銀行口座を持たない人が多数いるため、スマートフォンの取引履歴や行動パターンデータをもとにAIで信用評価を行う仕組みが評価されていました。グリーンテック部門では、AIを活用した家庭用エネルギー管理プラットフォームを開発した南アフリカのPlentifyが受賞していました。
「誰のために、誰のデータで、誰によって設計されるべきか」って誰が決めるの?
VivaTech 2025では、「AI」がまさに主役。会場のあちこちでその文字を見かけ、ラグジュアリーブランドから医療、環境、金融まで、さまざまな分野でAIが活用されている様子が紹介されていました。大手企業とスタートアップが手を組み、社会課題の解決や新たなビジネスの創出に取り組む姿も目立ち、AIが私たちの暮らしに深く入り込んできていることを実感できるイベントでした。
一方で、AIの開発には膨大なデータと計算資源が必要なため、どうしても一部の巨大企業や国家に技術が集中しがちです。そうなると、どんなデータを使うか、どんな価値観で設計するかといった判断も、限られたプレイヤーに委ねられてしまいます。これは、情報の偏りや、私たちの生活に影響を与える意思決定の偏向につながる可能性があります。
こうした懸念に対し、少数言語に対応したAIの開発や、各国が自国のデータを自国内で管理する「データ主権」の動きも進んでいます。地域に根ざした技術開発は歓迎すべき流れですが、同時に、国や地域ごとにAIのルールや価値観が分断されてしまうリスクもはらんでいます。グローバルな協調とローカルな自立、そのバランスをどう取るかが、これからの大きな課題です。
今回のイベントを通じて強く感じたのは、AIを社会にどう実装していくかを考えるうえで、「誰のために、誰のデータで、誰が設計するのか?」という問いが、ますます重要になっているということです。そしてその問いに答えるのは、企業や政府だけではなく、私たち一人ひとりかもしれません。
今回の視察では、Dentsu Lab Tokyoでも「こぼれ話」をご紹介しています。視察に関する詳細なレポートもご提供可能(有償)ですので、お気軽にお問い合わせください。