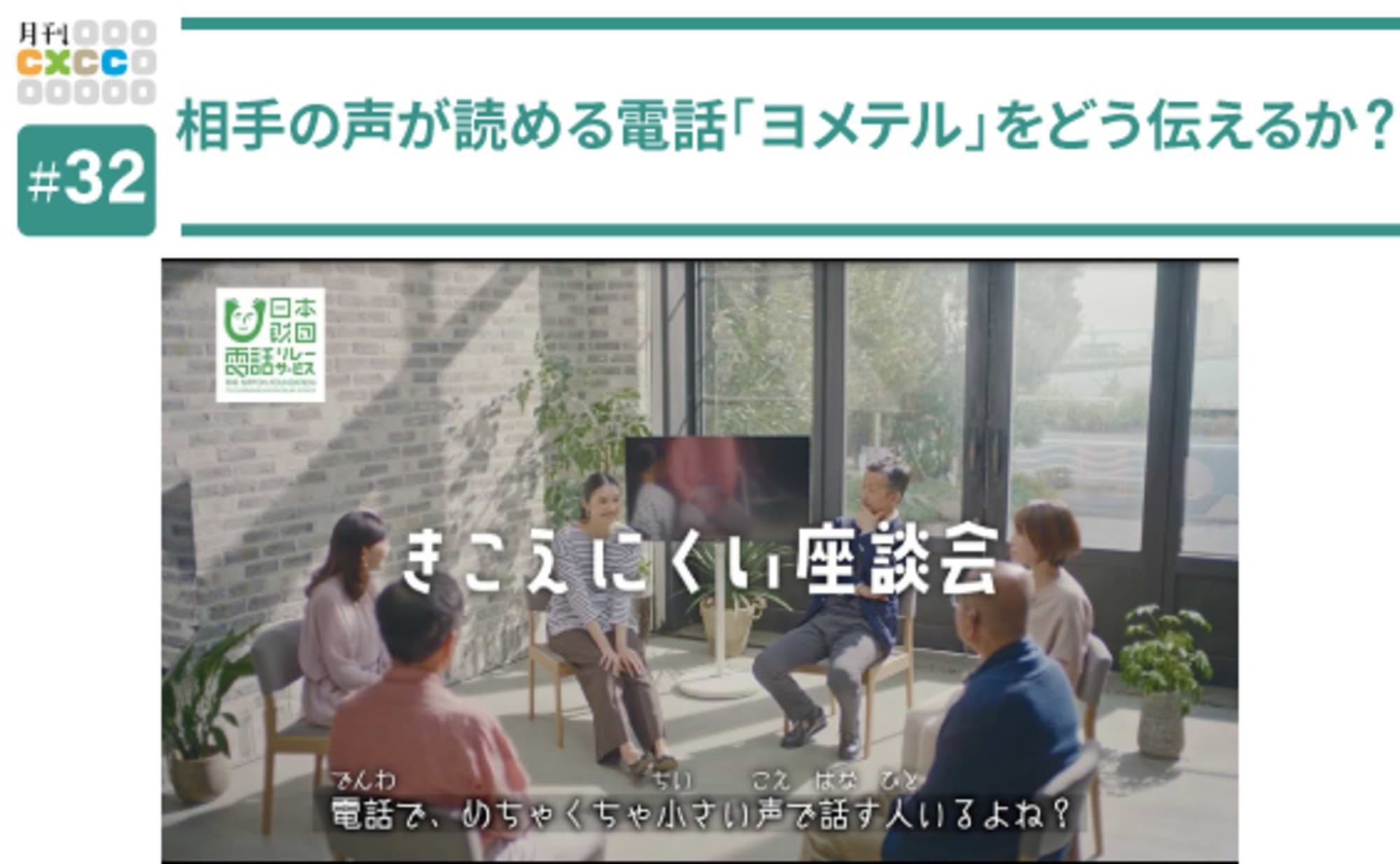AIとともに、あるかもしれない未来を旅行する。「ITOCHU SDGs STUDIO」企画展で見えた、テクノロジーとの向き合い方
日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーが情報発信する連載が「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。
今回は、伊藤忠商事が運営する「ITOCHU SDGs STUDIO」の展示において、電通CXCCが2024年に関わった2つの事例、企画展「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」と、常設展「地球のあした観測所」についてご紹介します。
特に企画展の事例においてはAIを積極的に活用し、密度の濃いコンテンツをスピーディに仕上げられたのが特徴でした。企画に関わったクリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジストの大瀧篤氏と、クリエイティブディレクターの小池宏史氏にAIを活用したCXづくりについて話を聞きました。

電通
zero/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジスト
大学・大学院でのAI研究と惑星探査車開発を経て電通入社。現在は、リアル体験×テクノロジーのクリエイティブを武器に、企業・国家事業のソリューションやR&Dプロジェクトに関わる。PARCOグランバザール2024「MATSUKEN PARADE!!」/ 2025「西川貴教/来れそうかい?」、セイコーグループ2024 SEIKO HOUSE GINZA「時の龍」ショーウインドー/ARショー演出など。世界ゆるスポーツ協会 理事/スポーツクリエイターとして「トントンボイス相撲」など多数の新スポーツを企画開発。Cannes Lions、ONE SHOW、CLIOをはじめ、ACC賞、文化庁メディア芸術祭など国内外で100以上の受賞。著書に「クリ活2 クリエイターの就活本:デジタルクリエイティブ編」。
【小池宏史氏プロフィール】
電通
カスタマーエクスペリエンス・クリエイティブ・センター/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/プランナー
デジタル〜リアルのメディアやデバイスにおいてプランニングとクリエイティブディレクションを統括。マス広告やサービス・プロダクト開発から、TV番組、映画・演劇演出、展覧会・デジタルインスタレーション、タレントプロデュース、ゲーム開発等のエンターテインメント領域まで、幅広くコミュニケーションに関わる体験設計に携わる。Cannes Lions、D&AD、THE ONE SHOW、ADFEST、グッドデザイン賞、新聞広告賞、文化庁メディア芸術祭、等での受賞歴あり。
「ITOCHU SDGs STUDIO」で行った2つの展示
月刊CX:まずは、今回の企画についてそれぞれ簡単に説明をお願いします。
大瀧:伊藤忠商事がSDGsに関する情報を発信する施設「ITOCHU SDGs STUDIO」のリニューアルにあたって、企画展「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」と、常設展「地球のあした観測所」の2つの展示を同時に担当させていただきました。
「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」は、2024年7月18日から9月23日の2カ月間開催しました。

これは“AIが考えた「あるかもしれない未来」への旅を通じて本物の未来に思いを馳せる”をコンセプトに、移動や食、住環境、自然などの6テーマを取り上げ、SDGs達成のためにどのようなアクションが必要かを伝える展示でした。
本企画は、未来を描いた展示映像やビジュアル、VRコンテンツなどのアウトプットのほぼ全てをAIを用いて制作しているのが特徴です。企画のコンセプトや展示会のステートメント、全体のトンマナを決めるロゴや空間の造作など、大きなディレクションに関わる部分については、もちろん私たち人間が行いつつ、各コーナーの制作物はAIを用いて各担当のクリエイティブテクノロジストたちと練り上げていきました。
月刊CX:具体的にはどのようなものを制作されたのですか?
大瀧:一例を挙げると、AIが予測した未来の動物の姿を伝える「未来に出会う!?サファリ&サブマリンツアー」というブースでは、多様な進化をとげた生き物のひとつとして「熱反射ライオン」という生き物を展示しました。

AIが導きだした「地球温暖化が進む未来では、体内の熱を逃がしやすいように耳が大きくなっているのではないか」という仮説を基に、テキストや音声、グラフィックもすべてAIで生成しました。

月刊CX:「地球のあした観測所」についても教えてください。

大瀧:「地球のあした観測所」は、伊藤忠商事の各カンパニーの事業とSDGsのさまざまな取り組みを紹介する常設展です。パネルや映像などをただ見るだけの展示ではなく、大型のデジタル地球儀「SPHERE(スフィア)」やApple Vision Proを活用した体験型の展示方法を採用し、各カンパニーの事業内容をわかりやすく、少しでもインタラクティブに伝えることをチームで心がけました。

「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」のテーマがはるか先の未来であるのに対し、こちらの展示では伊藤忠商事の現在の取り組みをテーマにしています。いま私たちが行っている毎日の活動は、いい明日を作るためにしているものであるはず。そうした意味合いを込めて“あした”というネーミングにし、最新の技術を使って伊藤忠商事の活動やチャレンジを伝えることを意識しました。
答えを提示するのではなく、考えるきっかけを与える展示に
月刊CX:「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」は、旅行というテーマも今回の企画にフィットしているように思います。
大瀧:今回は常設展のリニューアルと同タイミングでの実施ということもあり、過去の企画展以上にSDGsを網羅的に扱うことが命題にありました。
地球や社会のために大切だと頭でわかっていることを、正面から正しく言われるだけでは、ココロもカラダも動かないのが人間ですよね。人としてあたり前に存在する欲望や感覚にうったえるものをベースにした方が、行動に移しやすくなりますし、結果的にSDGsにつながります。
その上で、移動や食事など自分ごと化できる身近な問題がすべて集約されているのが“旅行”という体験だと考えました。地球の未来は僕たちの生活の延長線上です。「楽しむ中で自然とSDGsに触れられるといいよね」ということで、旅行というフレームを選びました。

誰しも旅行に出かけたときは心がワクワクすると思うんです。今回の企画はそうした心が動く瞬間を大事にして制作しました。制作全体の思想として、答えを提示するのではなく考えるきっかけをつくることを意識しています。
「未来はこんなふうに良くなるかもしれないし、もしくはちゃんと取り組まないとこんなふうになってしまうかもしれない」とメッセージを投げかけつつ、楽しみながらSDGsを学べるように「未来旅行」というテーマでアプローチしました。
小池:展示をめぐってパスポートにスタンプを押していく体験設計も功を奏したように思います。それぞれの展示を見ていくことで疑似的に旅行を体験したことになり、全体をつなぐ世界観を具現化するアイテムになっていました。パスポートが一気に体験の質を深めてくれましたし、とても良いアイデアだったと思います。

月刊CX:それぞれ、来場者の反響はいかがでしたか?
大瀧:どちらの企画も、とても楽しんでいただいていました。親子だったり、友人グループだったり、カップルだったりと、多様な方々が来場されていたのも印象的で。「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」では、展示を見ながら同行者と「未来はもしかしたらこうなるかも」と話している方も見かけて、私たちが提示した「!?」という問いに向き合っていただけているのだと感じて、とてもうれしかったですね。
小池:「地球のあした観測所」では、最先端の空間コンピューターであるApple Vision Proを導入したことで、最新ガジェットをワクワクしながら試しているお客さまもいました。

大瀧:「SDGsについて考えよう」とストレートに言われるとハードルが高いですが、エンタメとして自分ごとにできるCXづくりができたと思います。伊藤忠商事の担当者の方々にも非常に喜んでいただけました。
AIは人間と手をつないで共により良い未来を作っていく存在
月刊CX:「きみとAIの!?(ワンダー)な未来旅行展」は、一気通貫のAI活用がとてもユニークですね。そもそもAIを活用しようとしたきっかけはなんだったのでしょう?
大瀧:AIを活用するアイデアは、こちらから伊藤忠商事のSDGsスタジオチームに提案しました。小池さんとChatGPTや生成AIを使ったアウトプットのプロジェクトを探していく中で、今回の企画はAIとかなり相性がいいと感じたのです。
AIは人間と比べると、主観というものがなく、世界中の膨大なデータから解を導き出すことができる、フラットな存在だと思います。誰かひとりの思想ではなく、世の中のことを中立的な視点で考える必要があるSDGsというテーマにおいては、AIが真価を発揮するのではないかと。世の中にあるファクトや論文をベースにAIとともに考えることで、フラットかつ人間が議論したくなるような余白あるメッセージを構築できました。
小池:企画が立ち上がった当時は、AIを使ったコンテンツが世の中に広まり始めたタイミングで。その当時から「AIは敵なのか、味方なのか」という論争が巻き起こっていて、人間と相対する存在としてAIを置く見方も多く目にしていました。
そういう背景もあり、今回の展示では“AIは人間と手をつないで、共により良い未来を作っていく存在”だと感じてもらいたい思いもありました。制作にAIを使うことで、私たちも「AIでここまでできるんだ」と驚かされましたね。
月刊CX:AIを活用していく上で、苦労した点があれば教えてください。
大瀧:AIによるハルシネーション(AIが事実とは異なる情報を生成する現象)のケアは、非常に苦労しましたね。若手のメンバーと一丸となって、論文や研究データを確認してファクトチェックを入念に行いました。
また、生成された画像についても「現実と違う」「崩れている」といった点はもちろんチェックしていました。たとえば未来の国のパンフレットを作るときには「この国には環境条件からこの動物はいないはず」など、細かく確認しましたね。通常のプロジェクトは制作に時間を要しますが、今回は作った後のコンテンツチェックに時間をかけました。
ちなみに、データは伊藤忠商事の担当者の方々ともシェアし、共に多角的にチェックしていただきました。生成AIは多くの可能性を秘めている半面リスクも伴うため、制作過程からクライアントの皆さんと擦り合わせながらプロジェクトを進行することが非常に大切です。

小池:ファクトチェックに苦労した半面、AIで制作をする恩恵は非常に大きかったです。今まではSDGsの中のひとつをテーマにした展示が多かったのですが、今回は「SDGsの17テーマをすべて盛り込みたい」との要望を受けていました。
人力の進め方では実現できない工数とスケジュールでしたが、AIによって作業スピードが上がり、クオリティも担保しながら、結果すべてのテーマを盛り込めたのです。
常日頃からアイデアを考え、新技術で誰よりも早く形にできる準備をしておくことが肝心
月刊CX:今回の企画を振り返っての感想を教えてください。
大瀧:今回の企画でさまざまな研究や課題に触れ、世界を良くするための技術や研究がこれほど多くあると知り、未来に希望が持てるなと非常にワクワクしました。多くの人にこのことを知ってほしいですし、テクノロジーとクリエイティブをかけ合わせた社会実装を推進している身としては、大きなポテンシャルを感じましたね。また、AIへのディレクションや多角的なファクトチェックを通して、自然と私たち自身もアップデートされていくというのは面白い発見でした。
月刊CX:両事例はAIと最新技術の活用が印象的だったと思います。最後に、今回の体験を踏まえて今後のクリエイティブに生かしたいことがあれば教えてください。
大瀧:今回の企画はAI時代の新しいものづくりのプロトタイプができたことが、非常に大きかったように思います。生成AIの知見もチーム全体で蓄積できました。
また、すぐに実現が難しいアイデアでも、AIのテクノロジーが追いついてきて、ある日急に実現できるようになる可能性もあるのだと気がつきました。実際に、今回の企画を進める中でAIの進化を感じる場面が多くて。「クオリティ的に限界だろうし、方向転換をせざるを得ないか……」と悩んでいた翌日に新サービスが出たり、アップデートされたりして課題がふと解決されたことがあったのです。
クリエイティブジャンプを実現するためには、日頃からアイデアをためておいて、AIが進化した瞬間に誰よりも早く形にできる準備をしておくことが重要だと思いました。今後も、さまざまなところにアンテナを張って、最速でプロトタイピングしていきたいです。
小池:テクノロジー界隈やサイエンス界隈がポジティブになっているなと肌で感じましたし、今回はそのムードを反映できた展示だったように思います。
80年代や90年代の高度経済成長時代には、科学至上主義が過剰に進み、その副作用として環境問題や社会課題を生んでしまった側面があります。その後、持続可能性や倫理面での課題に直面し、技術革新が停滞しがちだった時期もありました。2024年は、そうした行き詰まり感に直面していたテクノロジーの状況が、AIの登場によって再び可能性の扉を開いた年だったのではないかと感じます。
AIに関わって未来のものづくりのエッセンスに触れる中で、そういった扉が開き続ける面白さや期待を実感しました。環境負荷を抑えつつ人々の創造性を広げ、社会課題の解決にもつながるような取り組みが加速していく未来。今後の制作でも、そうした視点を忘れないようにしていければと思います。
〈電通メンバークレジット〉
Executive Creative Director:小池 宏史
Creative Director / Creative Technologist:大瀧 篤
Creative Director:尾崎 賢司
Copywriter:伊藤 みゆき、高階 壮秀
Art Director:各務 将成
Creative Technologist:若園 祐作、藤 大夢、斧 涼之介、厚木 麻耶、戸松 嶺太郎 、横山 魁
Business Producer:内山 瑞貴、白石 一将
(編集後記)
今回は伊藤忠商事が運営する「ITOCHU SDGs STUDIO」の2つの展示企画について話を聞きました。
AIの活用が印象的でしたが、AIは人間と対置されるのではなく、良きパートナーであり、未来のものづくりには欠かせない存在であるように感じました。
今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記お問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。ご愛読いつもありがとうございます。

電通CXCC 木幡 小池 大谷 奥村 古杉 イー 齋藤 小田 高草木 金坂
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者
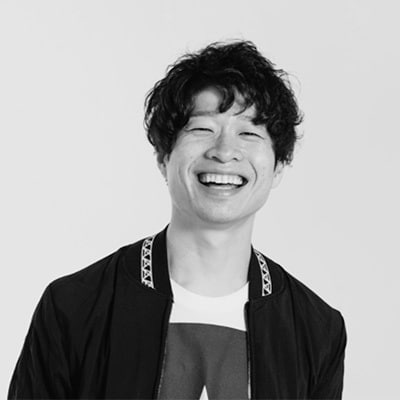
大瀧 篤
株式会社 電通
zero/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/クリエイティブテクノロジスト
大学院までAI研究と惑星探査車開発に取り組み、 電通入社。プロモーション、PR領域を経験後、クリエイティブ試験合格を経て現職。2023年よりクリエイティブディレクター。リアル体験×テクノロジーのクリエイティブを武器に、企業・国家事業のソリューションやR&Dプロジェクトに関わる。主な仕事に、PARCOグランバザール2024-2025 CMからデジタルまで統合コミュニケーション、SEIKO HOUSE GINZA インタラクティブショーウインドウ演出、北京2022/東京2020オリンピック日本代表選手団壮行会 総合演出、JOC 日本オリンピックミュージアム設立、東京2020パラリンピック開会式/閉会式 テクノロジカルコンテンツ、遠隔コミュニケーションプロダクト「気配の花」、ゆるスポーツ「トントンボイス相撲」企画開発など。世界三大広告賞のCannes Lions、The One Show、Clio Awardsをはじめ、ACC賞、文化庁メディア芸術祭など国内外で100以上受賞。電通インターンシップ「テクノロジーとアイデアの学校」座長(2024〜2026)。著書に「クリ活2 クリエイターの就活本:デジタルクリエイティブ編」。世界ゆるスポーツ協会 理事/スポーツクリエイター

小池 宏史
株式会社 電通
カスタマーエクスペリエンス・クリエイティブ・センター/Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブディレクター/プランナー
デジタル〜リアルのメディアやデバイスにおいてプランニングとクリエイティブディレクションを統括。マス広告やサービス・プロダクト開発から、TV番組、映画・演劇演出、展覧会・デジタルインスタレーション、タレントプロデュース、ゲーム開発等のエンターテインメント領域まで、幅広くコミュニケーションに関わる体験設計に携わる。Cannes Lions、D&AD、THE ONE SHOW、ADFEST、グッドデザイン賞、新聞広告賞、文化庁メディア芸術祭、等での受賞歴あり。

月刊CX編集部
株式会社 電通
CXCC(CXクリエーティブセンター)
電通のCX専門部署「CXCC」メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載「月刊CX」の編集チーム。局内または社内の優れたCXクリエイティブの成功事例を取材することで、CXクリエイティブの本質や可能性を解き明かす。コアメンバーは、木幡容子、小池宏史、大谷奈央、奥村広乃、古杉佑太郎 、イースピン、齋藤敬介、小田健児、高草木博純、金坂基文で全員CXCC所属。