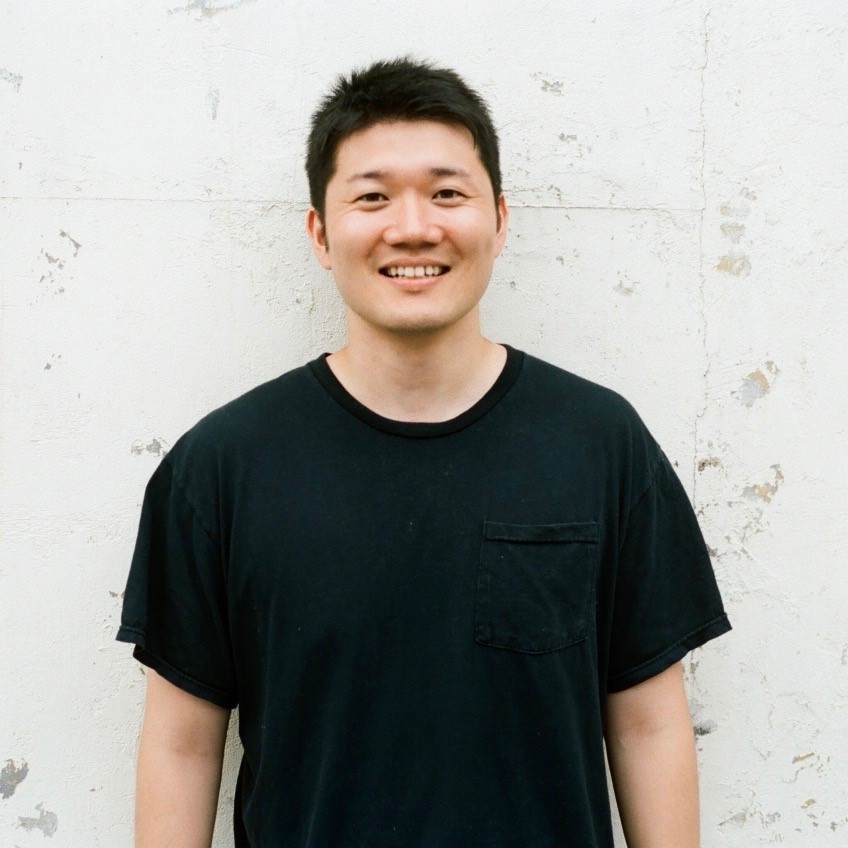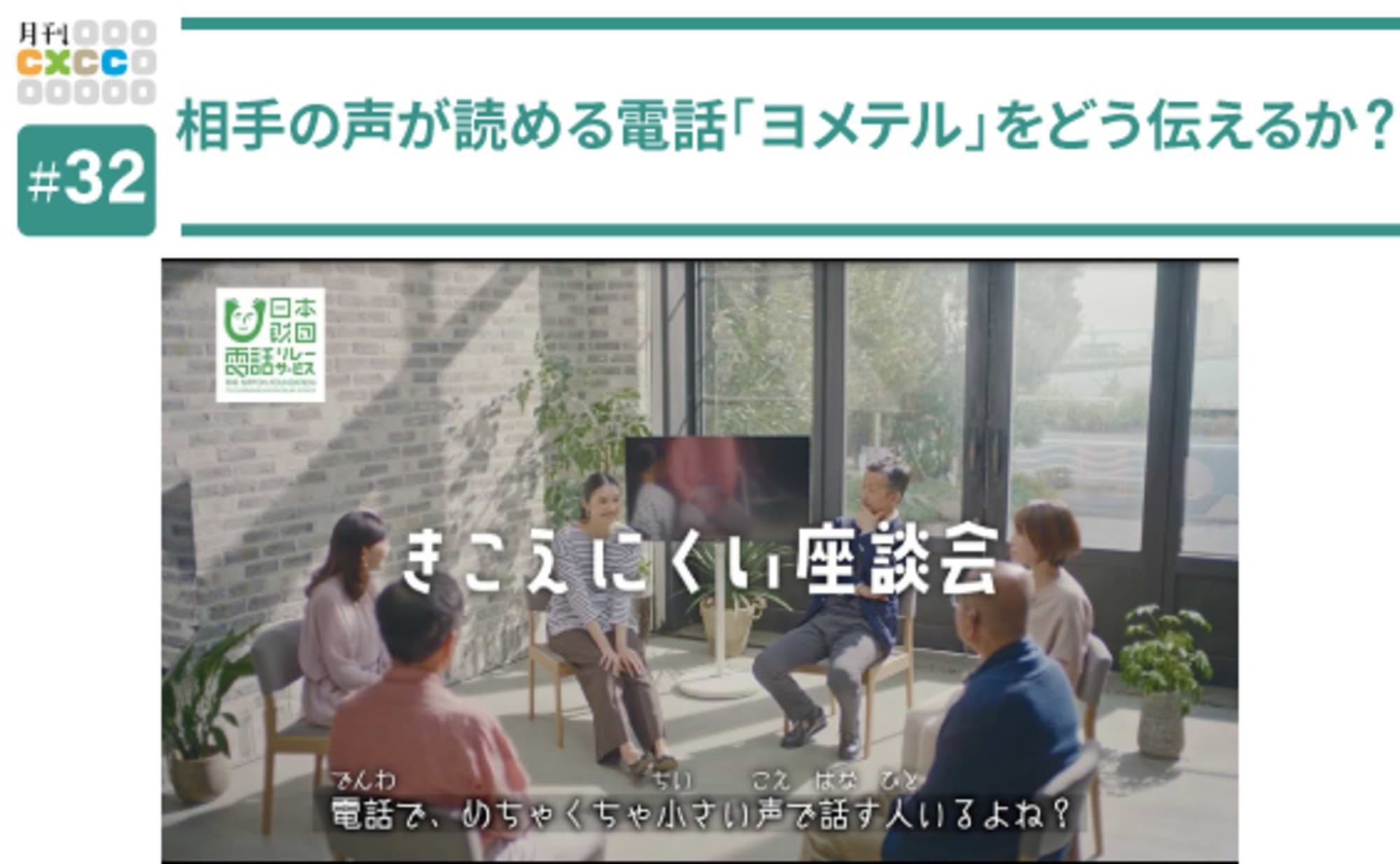日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーが情報発信する連載が「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。
今回ご紹介するのは、2024年7月19日に発足した、クリエイティブ領域に特化したDEIコンサルティングチーム「BORDERLESS CREATIVE(ボーダーレス クリエイティブ)」です。
どのようなチームで、どのようなクリエイティブを世に送り出しているのか。同チームのメンバーであるクリエイティブディレクターの阿部広太郎氏に話を聞きました。

【阿部広太郎氏プロフィール】
電通
カスタマーエクスペリエンス・クリエイティブ・センター
クリエイティブディレクター
電通入社後、人事局に配属。クリエイティブ試験を突破し、入社2年目からコピーライターとしての活動を開始。現在、CXクリエイティブ・センター所属。自らの仕事を「言葉の企画」と定義し、広告クリエイティブの力を拡張しながら領域を超えて巻き込み、つながり、助け合う対話型クリエイティブを実践する。著書に「待っていても、はじまらない。ー潔く前に進め」(弘文堂)、「コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術」(ダイヤモンド社)、「それ、勝手な決めつけかもよ? だれかの正解にしばられない『解釈』の練習」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、「あの日、選ばれなかった君へ 新しい自分に生まれ変わるための7枚のメモ」(ダイヤモンド社)。
DEI視点で世の中の課題を解決する「BORDERLESS CREATIVE」
月刊CX:「BORDERLESS CREATIVE」とは、どのようなチームなのかを教えてください。

阿部:「BORDERLESS CREATIVE」は、クリエイティブ領域に特化したDEIコンサルティングチームです。同じくCXCCに所属する橋口幸生CD(クリエイティブディレクター)と立ち上げました。DEIとは「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」の頭文字を取ったもので、近年クリエイティブにおける重要なテーマとなっています。
海外ではDEI視点のコンサルティングを行う会社が注目されつつありますが、国内ではそのような企業や団体がまだまだ少ない状況です。本チームでは、DEI領域の知見が豊富にあるクリエイターと、当事者・専門家が連携し、広告企画や新規事業開発など課題発見から企画制作までワンストップで担っています。さまざまなDEIテーマのクリエイティブ業務に携わり、数多くの広告賞を受賞してきた実績があります。

阿部氏が携わった、目の見えない方の優れた手指の感覚を生かしたメークレッスン。ポーラ「鏡を使わないメークレッスン」
※画像をクリックすると、動画を見られます
月刊CX:チームを立ち上げた理由を詳しく教えてください。
阿部:これからのクリエイティブにDEI視点は欠かせないものだと考えています。
世の中にはだれかのコンプレックスを刺激してしまうものや、人の心を傷つけてしまう広告があり、いわゆる“炎上”しているコンテンツもしばしば目にします。企業側が意図していなかったメッセージが広がってしまうケースもあり、それは企業にとっても受け取り手にとっても幸せなことじゃないと思います。
社会的にポジティブなメッセージを広げていくためには、ただNG表現に気をつけるのではなく、専門的な視点に基づいた企画づくりこそが重要だと考えています。そのために企画や制作における進め方を「BORDERLESS CREATIVE METHOD」としてまとめています。
月刊CX:「BORDERLESS CREATIVE METHOD」とは何か具体的に教えてください。
阿部:全体の進行やつくり方です。これまでのクリエイティブの現場では、「クライアント」と「広告会社」の間で無意識のうちに引かれていた境界線があったと思います。提案する側と、提案を受けて判断する側といったようなイメージで、意見がぶつかり合い強い葛藤が生まれる……なんてケースもあったかもしれません。
しかし、クライアントも広告会社も、同じゴールに進んでいく仲間ですよね。そのために企業のブランド担当者と、当事者・専門家、広告をつくる私たちで三角形をつくり、それぞれのノウハウを生かしながらより良いコンテンツをつくるための枠組みが「BORDERLESS CREATIVE METHOD」なんです。
阿部:もしかしたら、「それができるのは理想だけど実際やるのは難しくて……」と思われた方もいるかもしれません。しかし、これをやってみると本当に共創が生まれますし、新たな景色が見えるようになると考えています。
また、宣伝会議とタッグを組んで、「BORDERLESS CREATIVE SCHOOL」というDEIクリエイティブを体系的に学ぶ講座も立ち上げました。こちらは企業のブランド担当者やプランナーなど多くの方に受講していただきました。
相手の声が読める電話「ヨメテル」とは
月刊CX:阿部さんが担当されている事例についても教えていただけますか。
阿部:私が「BORDERLESS CREATIVE」の発足前から携わっている「相手の声が読める電話『ヨメテル』」の話をさせてください。こちらは、法律に基づいた公共インフラとしてのサービスで、2025年1月23日からサービスの提供が始まりました。私たちのチームでは、ネーミングやロゴデザイン、コミュニケーション開発などに携わりました。

相手の声が読める電話「ヨメテル」30秒CM
※画像をクリックすると、動画を見られます
月刊CX:サービス内容の詳細を教えてください。
阿部:サービス内容の詳細としては、ヨメテルは、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人(以下、きこえにくい人)へのサービスとして、通話相手の声を文字にする電話アプリです。24時間・365日、双方向での利用ができます。通話相手の声を文字にすることで、電話でのコミュニケーションをスムーズにする、法律に基づいた公共インフラとしてのサービスです。
現在、日本には加齢も含めると聞こえにくさのある人が約1400万人以上いると推定されます。国民全体の約10%が、何かしらの原因で聞こえにくさを感じているのです。
これまでにも、法律に基づいた公共インフラとして、聴覚や発話に困難がある人ときこえる人との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができる「電話リレーサービス」がありました。
一方、「ヨメテル」は「電話で相手先の声が聞こえない/聞こえにくいことがある」と感じていて、自分の声で相手に伝えたい人が登録利用の対象です。きこえにくい人が普段どのような悩みを抱えているのか、どのように伝えていけば良いかを考え抜いて制作しました。
月刊CX:リリース後に何か反響などはありましたか。
阿部:はい。サービス提供開始後、ご利用いただいた方から「電話で友達が話すときに聞き返すことなく同じタイミングで笑い合えたのがうれしかった」という感想や、中途失聴者の方から「電話する喜びを思い出した」という感想をいただきました。その感想を聞いた時は、本当にうれしかったです。これから「ヨメテル」を必要とする人に、さらに届いていってほしいと思っています。
月刊CX:「ヨメテル」のコミュニケーションをつくる上で、気をつけていたことはありますか?
阿部:「ヨメテル」のユーザーとなる当事者の方たちと「広報戦略会議」を立ち上げて、本サービスのコンセプトや「きこえにくい座談会」のトークテーマについてなど、多様な角度から何度も対話を重ねながら企画を進めました。
その上で、特に注目したのが、通話の冒頭に流れる「自動音声ガイダンス」です。「電話リレーサービスのヨメテルです。あなたの声を文字にして、相手に表示します。はっきりとお話しください」というガイダンスをはじめて聞いて切ってしまうケースがあるとわかりました。そのため「ヨメテル」の認知を高めることも大切なミッションにしています。

交通広告
やさしい世の中にしていくために、対話を繰り返していく
月刊CX:「ヨメテル」を通して、阿部さんが得た気づきを教えてください。
阿部:「きこえにくい人」にお話を伺って改めて感じたのは、実際のきこえにくさは人によって本当に全然違うものなんですよね。加齢できこえにくくなる方もいれば、高い声がきこえにくい、低い声がきこえにくいなど、“難聴”といっても、その症状は人によって異なります。
当事者の方にじっくりお話を聞くことで、電話で相手の声を聞くときに耳にスマホをぐっと押し当てることや、数字はメールでやり取りするように意識しているということなど、わかったことがたくさんありました。取材をすることで、より多くの方に寄り添えるコンテンツが生み出せるのだと実感しています。
また、キャッチフレーズを書く私たちの仕事は、人の想いをキャッチすることなんだと思います。私自身、人の想いをキャッチできる人間でありたいとより一層感じましたし、今後も対話を繰り返しながらいいクリエイティブを生み出す人でありたいと思っています。
月刊CX:最後に、阿部さんが今後挑戦したいことがあれば教えてください。
阿部:今は仲間を増やすことが非常に大事だと考えています。DEIの領域が広がってきている中で、企業でも積極的にDEIに取り組んでいこうと旗を掲げてくれる方がいると、ここからさらに人が人を想うやさしい世の中になっていくと信じています。
広告や広告クリエイティブは、人や社会の役に立てると信じていますし、一瞬ではなく、ずっと心に残る何かをつくれるはずだと本気で思っています。広告クリエイティブが広告だけではなく、社会の役に立てることを実現し続けていきたいです。
そして、ゆっくりでも確実に、社会を変えていくような「やさしい衝撃」をつくり続けたいです。人の意識を変え、行動を促し、最終的には社会をより良い方向へと導いていく。一つ一つのプロジェクトが、未来への種まきとなり、やがて大きな変化を生み出す。そのような可能性を信じて、これからも情熱を持って仕事をしていきたいです。
(編集後記)
今回は、2024年7月19日に発足した、クリエイティブ領域特化型のDEIコンサルティングチーム「BORDERLESS CREATIVE(ボーダーレス クリエイティブ)」と、そのチームメンバーが担当した「ヨメテル」についてお話を伺いました。
より良いクリエイティブをつくっていくためには、DEIの視点は不可欠。そうした中で見えない境界線(ボーダー)をいかに探して、対話して寄り添っていくのか、が肝心なのだと思いました。
今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記お問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。ご愛読いつもありがとうございます。

月刊CX編集部
電通CXCC 木幡 小池 大谷 奥村 古杉 イー 齋藤 小田 高草木 金坂