生成AIは人間の人間らしさを拡張し、世界をつなぐ?

日立製作所と電通、電通デジタルの3社による共創プロジェクト「AI for EVERY」は、生成AIを用いて生活者と企業、社会のより良い接点を構築し、さまざまな社会課題を解決しようというプロジェクトです。
フードロスを減らすために生まれた「今日の気まぐレシピ」は、その一つ。「社会課題」という大きなテーマを生成AIで解決するには、一つ先を行く「発想力」と「実装力」が必要です。
前編に引き続き今回も、プロジェクトを主導する日立製作所(以下、日立)の越智啓之氏と赤司卓也氏、Dentsu Lab Tokyoの越智一仁氏、岸本和也氏、電通デジタルの高橋優太氏に、各社の考える「実装力」や、生成AIとともに描く未来や希望についてお聞きしました。
※同姓の越智氏が2人いるため、日立の越智氏は「越智(日)」、電通の越智氏は「越智(電)」と記載します。
アイデアを“絵に描いた餅”にしない。社会インフラの実装を担う日立

ここからは、日立と電通グループの「実装力」について深掘りして伺います。日立の越智さんは主にサービスやソリューションの実装のお仕事が多いそうですね。課題解決に向けて、実際に発想を実現して機能させるという点で、日立さんが普段からどのように取り組まれているかを伺えますか。
※今日の気まぐレシピ=
日立の在庫管理システムや需給予測・受発注システムを基に「売れ残りそうな食材」を高精度に予測し、電通クリエイターの知見を学習した生成AIがその食材に関連するユニークなレシピやクーポンを生成。電通デジタルが提供する「∞AI Ads」のノウハウを活用し、これらのレシピやクーポンを、販促素材として自動生成し、店舗のアプリや店頭サイネージなどで配信する。(現在フィジビリティスタディ中)

越智(日):それでは、日立が日常的な社会課題に取り組んだ事例について、二つお話しいたします。一つ目ですが、日立はJR東日本さんと一緒に、鉄道路線の運行システムを開発しています。この取り組みは、首都圏の在来線の運行を管理するシステムや保守業務にAIエージェントを適用した事例であり、安全で持続可能な鉄道運行の実現をめざし取り組んでいるものです。
日立はこうしたシステムの運用管理に長年取り組んでいますが、年を追うごとに働き手の数は減っており、さらにシステムがバージョンアップすることで仕様が増えてメンテナンスも複雑になっています。何か問題が起きたときに、就業経験が浅い方でもすぐに扱えるようにするにはどうすればよいのかという課題もあります。そこで、これらの課題に対しては、生成AIにマニュアルなどの情報を取り込み、何か問題が起きたときに人間を支援できるように、今、検証を進めているところです。働き手不足という日本全体の社会課題と、システムそのものの複雑さに生成AIでアプローチするということですね。
日立、JR東日本における輸送の安定性向上に向け、鉄道運行管理システムにて初めてAIエージェントを活用する共同検証に合意
二つ目の話ですが、日立がダイキンさんと一緒に行っている、生成AIを活用した工場設備の異常の発見に関する検証です。生成AIが図面の情報を読み取って、工場設備の細かい構造を把握し、異常がある場合はその前後に問題がないかを確認してから原因らしきものを回答します。検証中ですが、非常に精度が高く、一般的な保全技術者が回答するのと同程度のことができます。
ダイキンと日立が協創、工場の設備故障診断を支援するAIエージェントの実用化に向けた試験運用を開始
このように日立は、時代ごとにtoB領域のお客さまの課題に対して、さまざまな技術でアプローチすることで解決してきました。しっかりと課題を把握し、そこに日立が持っている技術——例えば生成AIなどのIT技術もそうですし、他にもエネルギーをはじめとする科学技術の強みもたくさん持っていますので、それらを組み合わせながら解決に向かっていくことが、日立の使命だと思います。
越智(電):やっぱり日立さんは本当に社会に入り込んだサービスを実装されているので、ダイナミックさが、私たちが主に取り組んでいる広告領域とは全然違いますね!日立で長年デザインを担っている赤司さんにお伺いしたいのですが、「デザインと発想」という視点で見たときに、日立さんの実装力をどのように感じていらっしゃいますか。
赤司:僕はずっと日立でデザインの仕事をしている人間なので(笑)、他社と比較ができないんです。ただ、社会インフラを作っている会社なので、最初から実現する見込みの薄い“絵に描いた餅”として進め、結局何も実現しないということがないようにはすごく気をつけていますし、そういう企業文化で育ってきています。要は「デザイナーがアイデアを発想しました、実現してください」という仕事の仕方では、何も実現しないんです。
だから、最初からエンジニアやアーキテクトと一緒になって“よーいどん!”で動くとか、AIを活用するなら越智さんのような実装をする人と一緒に動くということは、ずっとやってきていることですね。
そして、早め、早めにフィジビリティ(実現可能性)についてチェックを入れています。技術的に実現できるかだけではなくて、実行する時に人や組織の観点で課題が無いかどうかも大切になるので、そういった準備を一緒に考えていかないと、今考えている発想の善しあしがジャッジできないんです。
越智(日):ここまでは日立の社内について主に話してきましたが、BtoB領域で社会実装するためには、1社だけではなかなか難しいです。対象領域におけるオペレーションを推進している会社さんと一緒に取り組まないと、「ものだけがある」みたいなことになってしまうんです。
つまり日立の行う社会実装とは、実際にオペレーションに取り組んでいるエンタープライズ企業と、いっしょにオペレーションを作り込むことが非常に大きなウエイトを占めていると思います。ただ、技術だけあればいいということではないんですね。
1億人規模の「AIペルソナ」で実装前の検証を行う電通

越智(電):続いて電通グループの「実装」についてお話しできればと思います。私は普段、Dentsu Lab Tokyoという組織でデジタルやテクノロジーを使ったクリエイティブに携わっていますが……電通ももちろんフィジビリティを意識しながらアイディエーションしていくけれど、序盤は結構、無邪気だったりするというか(笑)。その点、社会インフラを実装する日立さんは、電通よりも実現可能性への意識がかなり高い印象を受けました。電通グループのお二人は、何か違いを感じましたか。
高橋:実装という観点でいうと、電通グループは、コミュニケーションや表現を通じて「人の心を動かす」ことが、ゴールに設定されることが多いと思います。ただ、実際どれくらい人の心が動くかは、暗黙知に頼っている部分も大きくて、成果をどこまで約束できるかというと、やってみないと分からないという、難しい面もあります。それに類似事例があまりないようなコミュニケーションを手掛けることが多いのもあり、「実装後」について保証しにくい点を悩ましく思っていました。
ただ、最近の生成AIの発展により、実装の面まで意識したプランニングも増加しつつあります。例えば国内電通グループには「People Model」というものがあります。これは大規模生活者調査をもとに、仮想空間上で1億人規模のAIペルソナを作って、その中で広告表現をシミュレーションしたり、模擬的なインタビューをしたりできるようになっているんですね。
こうして、これまでにない新しい表現については、生成AIを使うことで「どれぐらい人の心が動きそうか」をある程度検証しつつ、初めての表現として社会に送り出すことを両立できるようになると思います。従来のようにやってみなくては分からないところがありながらも、それはある程度AIの中で試せるようになりつつあるというのが、国内電通グループの実装領域における直近の動きですね。
岸本:先ほど、日立さんがJR東日本さんと一緒に運行システムを開発している話を伺って、電通のクリエイティブでは考えられない、ものすごい堅牢さを感じました。
私たちの実装についてお話しすると、所属するDentsu Lab Tokyoでは、「クリエイティブテクノロジスト」というクリエイティブ職内の技術担当とフィジビリティを詰めつつ、生活者の方や目の前の人の心がどうすれば動くのか、整合性をすり合わせてプランニングすることが多いです。しかし、やっぱりインフラレベルの社会実装にまでは思い至れない。その点、日立さんはそもそもの能力が違うとも思うんです。
越智(電):たしかに、お互いが持っている能力や文化は、大きく異なると思いますよね。日立さんがこれほどまでにフィジビリティを意識していることや、取り組みの規模、期間、領域など、何をとっても電通グループと企業文化が違うなと、正直圧倒されています。
今回のコラボレーションでは、私たちは日立さんの「実装力」に期待を掛けているんです。期間が短く、影響を与えられる部分が狭いという電通グループの弱点が、日立さんと一緒に取り組むことでダイナミックな成果に転換できるんじゃないかと楽しみになっているところです。
生成AIが人間の人間らしさを拡張していく未来はある!

越智(電):今後、生成AIを利用していくと世界がどのように変化していきそうか、希望も込めて議論できればと思います。
……どうなっていくんでしょうね。例えばアバターのように、店員さんがAIであるようなことは入り口としてありえると思います。AIが活躍する方法っていろいろあるような気がしていて。みなさん、どうお考えですか。
岸本:手段はどんどんそろっていくので、AIにできることもどんどん増えると思うんですよ。それゆえに、人間が「どうしたいか」「どうなるとより良いのか」という意思を明確にした方がいいかなという気持ちがあります。
多分今後は、生成AIを使うことで、人に寄り添ったサービスやプロダクト、インフラがもっと作られるようになると思います。どういうことかというと、例えば今のいわゆるマルチモーダルなAIは、文章や音声、画像などいろいろなものを一気に入力しても理解してくれるし、あるいはその場で解釈して返答してくれたり、ざっくり言うとかなり「空気を読んでくれる」ようになりました。
こうなってくると、AIがもっともっと人の気持ちに寄り添ったり、場の雰囲気を読んだりもできるし、より高度な表現ができるようになります。さらに、さっき高橋さんがおっしゃったPeople Modelの例にあったように、AIが「この表現は人々にどう伝わるか」というシミュレーションを事前にできるようになっていくかもしれない。
そんなふうに進化していく中では、AIが「人に取って代わる」よりは、「人に溶け込んでいく」ことを目指せるといいのではないかと思います。そのための手段はどんどんそろってきていますよね。
越智(電):なるほど。変な思いつきだと思われるかもしれないのですが、例えば、打ち合わせの雰囲気が良くなるようにAIが手伝ってくれる、なんてこともあるのかもしれないですね。参加者それぞれのバックグラウンドを読んで、アイスブレークをしてくれるとか。
岸本:沈黙が訪れたら空気を読んで突っ込んできたり、「そろそろ飽きてきましたね」とコメントを差し込んでくれたり(笑)。そういう役割は、マルチモーダルな生成AIが、人間たちの「ことば」だけでなく、「表情」や「音」などの情報を取り込めるようになると実現できるのかなと思います。
越智(電):日立のお二人はいかがでしょう。
越智(日):未来の予測は、なかなか難しいですね。ただ言えるのは、コンピュータープログラムとのやり取りが、プログラミング言語ではなく自然言語になったというのが、やっぱり一番大きな変化なのかなと思います。
例えばAIチャットボットは、自然言語の中にある意味的な「深さ」や「幅」をかなりいい感じに理解してくれます。だからできることがものすごく多くなったし、プログラマーじゃない人でもかなり高度にAIを使えるようになりました。そうした変化は、やっぱりインターフェースが自然言語だからというのがものすごく大きいと思っています。
今後はさらにAIの能力が拡大・拡張されていき、AIエージェント同士がコミュニケーションし、複雑な課題解決もどんどんできるようになっていきます。操作できる対象もコンピューターの中の世界だけではなく、例えば人がブラウザをマウスで操作するのを生成AI上でシミュレートできるようにもなっています。
さらにその先のことですが、未来ではロボットとのコミュニケーションがもっともっと簡単になっていくかもしれない。今、世界はインターネットという通信でつながっていますが、生成AIによって、もっと「つながり」が意味的に広がっていくと思います。世界とつながるためのコストはもっと安くなっていきますし、つながるときの情報のやりとりの深さ、意味的な深さは、自然言語をインターフェースにすると、どんどん発達するでしょう。それが将来、一体何になるのかっていうところは……どうなるんでしょうねえ(笑)。
越智(電):今のお話を伺っていて、生成AIは「いろんな人の力を拡張できる能力」を高めていくんじゃないかという気がしました。 例えば「プログラミングの知識はないけど、すごくセンスのよい人」のアイデアを、生成AIによってデザインやアプリケーションなどに置き換えることができて、それを求めている人が購入できる……みたいなことも実現していくのではないかと。それがいろんな領域で起こる気がしています。赤司さんはいかがですか?

赤司:うちの越智さんが、私の伝えたいことを結構話してしまったのですが(笑)。マン・マシン・インターフェースとしてのAIが世界を変えていくという流れは、絶対にあるじゃないですか。コードやプロトコル、キャリブレーションやパラメーターを一切操らなくても、何か価値交換が生まれるって、すごいことですよ。私は、「人間の仕事はAIに代替されて、仕事を失っちゃうよね」っていう話よりは、こちらの議論をもっともっと盛り上げていきたいんです。
もう一つ、私は、先ほどの「人と人をつなぐコスト」の話が大好きなんですよ(笑)。前編で、日立で取り組んでいる「ビジョンデザイン・プロジェクト」活動の話をしたんですが、社会課題においては結局何らかの「新しい関係性」みたいなものが社会に登場しないと、その価値って実現されないじゃないですか。例えばフードロスが社会課題だとして、フードロスをしている現場と生産者の間に「新しい関係性」を作り出してあげて、そこにサービスを通さないと、フードロスの解決は実現しない。でも今までは、その「新しい関係性」を作るコスト、つまり「つなぐ」コストがものすごく高かったんです。
あるいはギグワーカーの世界でも同じで、例えば僕が一対一で高橋さんと仕事を交換したいと思っても、高橋さんは僕を信頼しうる情報を持ってないので、信頼してもらえないわけです。結局その信頼情報は誰かが作り出さないと、ギグワークやCtoCのような話も実現しません。
じゃあそこは誰がつなげてくれますか?というと、なかなかビジネスにするのが難しい。データはありますよね。それに人と人をつなぐことで社会が良くなることも分かっていますよね。でも、できない。この「できないもどかしさ」も、生成AIで「つなぐ」コストが下がれば、実現できるかもしれないと思うんです。
AIエージェントが、これまで社会インフラの中であまりにコストが高すぎて「つなげなかったもの」を、「つないでくれるピース」になったら、できることはめちゃくちゃ増えると思いますよ。
越智(電):面白いですね!生成AIによってもたらされる効率化を考えてしまうと、「人はAIに代替されちゃうんじゃないか?」と、つい想像してしまいます。しかし今のお話を伺うと、やっぱり生成AIで目指すべきは、人の存在価値がすごく担保されていて、人と人がマッチングして新しい価値が生まれていくというところにあるんですね。本当に「目からうろこ」の話でした。高橋さんはいかがですか。
高橋:まず前提として、いろいろな生活領域に生成AIが拡張していくトレンドがすでに動いていますし、今後、多くの人がアクセスできるようになるというのもおっしゃる通りだと思っています。
例えば、私自身はコードを書けなかったんですが、今はAIに頼むことでプログラミング言語であるPythonを書いてもらうことができます。人間の力をAIで拡張することで、いろんな可能性が生まれます。もう少し進化すると、例えばシニアの方が肉声でAIに話しかけるだけで、介護に関する情報を簡単に得られるような世界が広がっていくのかなと思います。
そこで、「人間が根源的にやりたいこと」と「AIにお願いしてもいいこと」をいかに分けるかということが、今後の論点として大きくなっていくと思っています。「AIが何でもできる」からこそ、「人間があえて何をやりたいか」ということを、より問い直す機会が訪れるのではないかと。
そういう意味では、人間の人間らしさを担保できるシステムづくりであるとか、逆に人のミクロな視点で「そもそも人が持つ欲求とは何なんだっけ?」とか、「これから社会がどのように移り変わっていくのか?」というようなことを行ったり来たりしながら、AIを通じて社会のあり方をよりよくしていけたらと思います。日立さんと電通グループがタッグを組むからこそ、「人間らしさを拡張していく」という軸がぶれないAIの社会実装を実現できると思います。
越智(電):〆としてふさわしいお話をありがとうございます(笑)!このAI for EVERYのプロジェクトも、今のような発想で、人と人をつなぎ、人の能力・価値を拡張していくAIのあり方を提示していけるような、そんな取り組みになるといいなあと、聞いていて思った次第です。
高橋:人を置き去りにもしないし、“絵にかいた餅”で終わらせない。あくまでも実装力をもって取り組む。そのバランスを取ることが大切だと思います。
越智(電):ありがとうございます!今日は非常にエキサイティングな、本当に楽しいお話ができました。今後ともよろしくお願いいたします。
※掲載されている情報は公開時のものです
バックナンバー
著者

越智 啓之
株式会社 日立製作所
AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット
GenAIソリューション&ビジネス ディレクター
ソフトウェア開発、データサイエンスとデータエンジニアリング、社会課題解決のための新事業開発を推進。現在は、生成AIを基軸に新たな価値の提案とビジネススキームの構築に取り組んでいる。
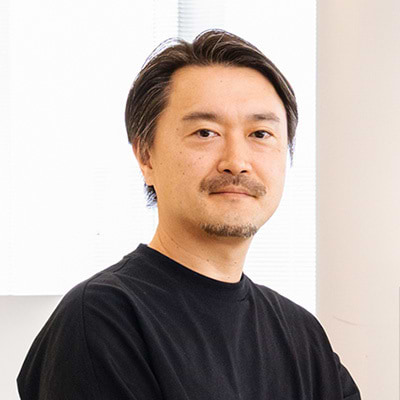
赤司 卓也
株式会社 日立製作所
AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット
デザインスタジオ ディレクター チーフデザインストラテジスト
ビジョン駆動の協創をリードし、現在は顧客協創、人財育成などあらゆるビジネス活動にデザインの力を生かす取り組みに注力している。
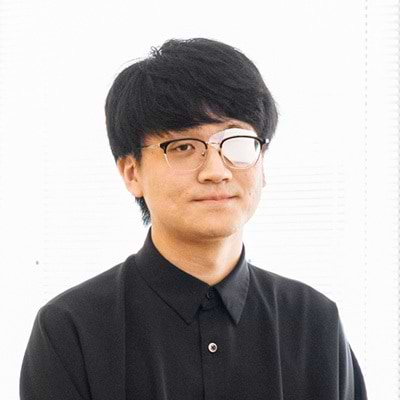
高橋 優太
株式会社 電通デジタル
コンサルティング&プロデュース領域 トランスフォーメーションストラテジー部門
プランナー
広告運用、サイト制作ディレクション、ソーシャル/オウンド分析などデジタルマーケティング関連業務に幅広く従事後、官公庁やトイレタリーを中心に、マーケティング戦略や顧客体験等のコンサルティングを推進。日立製作所との共同プロジェクト「AI for EVERY」にて、生成AI関連のコンサルティング・新規事業開発等を担当。

越智 一仁
株式会社 電通
Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブ・ディレクター
得意分野は主に、映像表現、デジタル、PRなど。それらを掛け合わせて、手法にとらわれないニュートラルなコミュニケーション設計で、課題解決を行う。

岸本 和也
株式会社 電通
Dentsu Lab Tokyo
クリエイティブテクノロジスト/コミュニケーションデザイナー
クロスメディアマーケティングの分析・プランニング業務に従事したのち、クリエイティブ局に異動。サーベイ〜企画〜プロトタイピングを通じて技術の「間違った」使い方を模索し、近年は生成AIや音・音楽に関わる案件を中心に取り組む。


