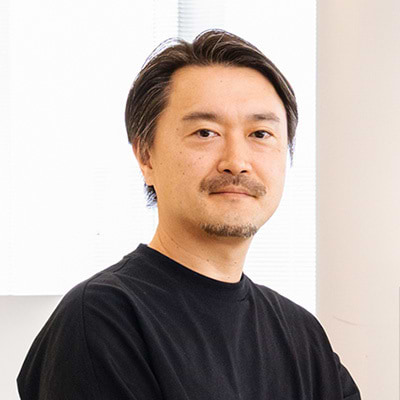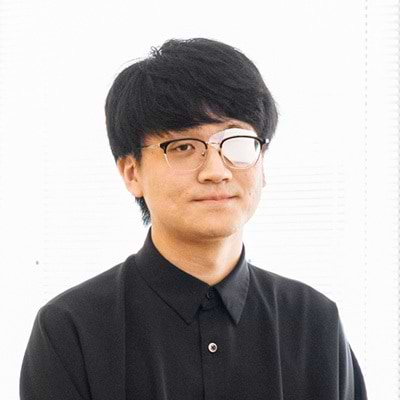左から日立製作所 赤司卓也氏、越智啓之氏、電通デジタル 高橋優太氏、電通岸本和也氏、越智一仁氏
日立製作所と電通、電通デジタルの3社による「AI for EVERY」は、生成AIを用いて生活者と企業、社会のより良い接点を構築し、さまざまな社会課題を解決しようというプロジェクトです。
フードロスを減らすために生まれた「今日の気まぐレシピ」は、その一つ。「社会課題」という大きなテーマを生成AIで解決するには、一つ先を行く「発想力」と「実装力」が必要です。
今回は、プロジェクトを主導する日立製作所(以下、日立)の越智啓之氏と赤司卓也氏、Dentsu Lab Tokyoの越智一仁氏、電通の岸本和也氏、電通デジタルの高橋優太氏による座談会をお届けします。
「今日の気まぐレシピ」の話を入り口にしつつ、お互いの発想力と実装力、さらには生成AIの真価に至るまで、日立と電通の化学反応でお話は多方面に膨らみました。
※同姓の越智氏が2人いるため、日立の越智氏は「越智(日)」、電通の越智氏は「越智(電)」と記載します。
日立と電通のかけ算。技術起点+課題起点で生まれた「今日の気まぐレシピ」

電通 越智一仁氏
越智(電):本日は「AI for EVERY」の参画メンバーである日立のお2人と、電通グループの3人で、「今日の気まぐレシピ」のことや、各社の生成AIへの向き合い方など、幅広くお話しできればと思います!
最初に簡単に自己紹介をすると、私はもともとコピーライティングやCM制作を経験してきましたが、現在はDentsu Lab Tokyoという組織で、デジタルやテクノロジーを使ったクリエイティブに携わっています。AI関連の取り組みが多いこともあり、今回「AI for EVERY」のプロジェクトに参画しました。
岸本:私も同じくDentsu Lab Tokyoに所属していて、テクノロジーを用いたコミュニケーション施策やツール開発に携わってきました。現在は生成AIや音/音楽を用いた取り組みが多く、サーベイからプランニング、プロトタイピング、たまに実装までを行っています。
高橋:私は電通デジタルで、普段は企業のDXやデジタルマーケティングを支援するコンサルティングを行っています。「今日の気まぐレシピ」では、岸本さんたちと一緒に企画提案を行いました。
越智(日):私は日立でマシンラーニングやデータサイエンスのコンサルティング、技術支援を主に行っています。「AI for EVERY」では、電通グループさんとの協業に関する取りまとめを担当しています。
赤司:同じく日立で、デジタルビジネスに関する部署のデザイン部門を率いています。もともとはゴリゴリのプロダクトデザイナーで、エレベーターや医療機器などのハードウェアのデザインをしていました。当社の事業の広がりに沿って、プロダクトからインタラクション、サービス、そしてエクスペリエンスと、領域を変えながらデザインの仕事をしています。
越智(電):ありがとうございます!本日は、座談会を通して、日立さんと電通グループそれぞれの「発想力」や「実装力」の違い、あるいは共通点を浮き彫りにしていければと思います。
まずは「AI for EVERY」の取り組みと、第一弾のソリューションである「今日の気まぐレシピ」について、どのような発想から生まれたのか、プロジェクトの立ち上がりから参加している電通デジタル高橋さんにお聞きしてよろしいでしょうか。
※今日の気まぐレシピ=
日立の在庫管理システムや需給予測・受発注システムを基に「売れ残りそうな食材」を高精度に予測し、電通クリエイターの知見を学習した生成AIがその食材に関連するユニークなレシピやクーポンを生成。電通デジタルが提供する「∞AI Ads」のノウハウを活用し、これらのレシピやクーポンを、販促素材として自動生成し、店舗のアプリや店頭サイネージなどで配信する。
高橋:もともと日立さんの「Lumadaアライアンスプログラム」に電通デジタルが参画し、DX領域において共創していたんです。その中で、日立さんは現場で働くフロントラインワーカーへの支援が得意であるとか、電通デジタルにはtoC領域の技術やマーケティングの知見があるといった、お互いの得意領域への理解が深まりました。
そんなお互いの強みを組み合わせると、toB領域もtoC領域も広くカバーしながらさまざまな社会課題にアプローチできるのではないかという発想から、生成AIサービスのプロジェクト「AI for EVERY」が生まれました。
そして「今日の気まぐレシピ」ですが、日立さんと電通グループの強みを組み合わせるという大前提のもと、両者にどういう接着点があるのか、技術と社会課題の両面からすり合わせていきました。その結果、日立さんで実績のある「需要予測」と、電通グループが得意とする「広告配信」や生成AIを用いたクリエイティブ、その技術や知見を掛け合わせると、社会課題である「フードロス」にアプローチできるのではないかというところから始まっています。
日立さんにフードロス解決のアイデアをお持ちした際に、「レシピ生成なんかもいいね」というコメントをいただいたり、電通の岸本さんたちに知恵をお借りした際にもレシピ生成のアイデアをいただいたりしました。それらを総合的に取り入れた結果、レシピ生成を行う「今日の気まぐレシピ」という形に昇華していきました。
越智(日):ちなみに日立の需要予測システムとは、その日にどういった製品や食材が売れていくか、どのぐらいの需要があるかを、これまでの実績データや、いろいろなパラメーターから予測するというものです。
越智(電):「日立さんの需要予測技術を使って、フードロスを減らす」という技術面でのアイデアが一つの出発点だったんですね。もう一方で社会課題の面からフードロスという題材を選んだとのことですが、これはどのような経緯で題材が思い浮かんだのでしょうか。
高橋:大きく二つあります。一つは、私や他のメンバーに、社会問題まわりのインプットが比較的多かったことです。電通デジタルでは、ソーシャルデータから社会課題を考察するといった試みを過去に行っており、広く社会課題に対する知見がたまっていたので、「この技術は、あの課題に当てられそう」といったなんとなく当たりがついていました。
もう一つは、電通グループならではの「生活者視点」です。例えば私は、前述の社会課題分析で「スーパーマーケット」がキーワードに上がったときには、営業の邪魔にならない程度にスーパーへ足を運んでみて、商品がどういった買われ方をしているのかを観察しました。そこで、買う、買わないの判断が値引き商品に左右されているという気づきがあったり、「一回かごに入れた商品は値引きしませんよ」という店側の値引きに関するやり取りを見かけたりしたことで、これは生活者の課題になり得ると思って掘り下げていきました。

電通デジタル 高橋優太氏
岸本:あとは、国内外の広告産業やサービスデザインなどの事例から得られた示唆を踏まえて、企画をブラッシュアップしましたね。私自身も過去にフードロスで規格外野菜を扱う企画も立案してきたので、その延長線上で今回の技術は「もしかしたらハマるかも」と思って提案した次第です。
Dentsu Lab Tokyoでは、よくクライアントのR&D(研究開発)部門の方と一緒に課題解決に当たるんです。そうしたときは、まずクライアントの技術シーズを調べたり、それらに隣接する世の中の技術の使われ方や捉え方を下調べした後に、「技術起点」で発想することが多いです。
一方で高橋さんとも共通しますが、「課題起点」で考えることも多くあります。社会課題を解決するために、そもそも技術に頼らないやり方はあるか、論文やオープンソースのコードといった、どのような技術を組み合わせるとより効果的に課題解決できるのかを、技術起点と課題起点を行ったり来たりしながら考えています。
「社会起点の日立」「人起点の電通」の、発想力・実装力が融合すると?

日立製作所 赤司卓也氏
越智(電):日立さんは、「今日の気まぐレシピ」というアイデアについてどう思われましたか?
赤司:生活者の心理って、実はものすごく“瞬間、瞬間”に表れるじゃないですか?「フードロスになりそうな食材を買うのは社会的にいいことだけど、この食材で何を作ろうかな?」といった、ユーザーが見せる一瞬の迷いに対し、「レシピ生成」によって後押しをしてあげられる。つまり「人の行動を変える最後の一押し」として、すごくよい発想だと思いました。
ちなみに私たちもかなり現場観察をして、生活者の行動を見るんです。社会課題を見つめるうえで一番分かりやすく考えやすい単位って「地域」だと思いますが、「その地域の中で、ある社会課題が、なぜ課題になっているのか?」を調査することが大事だと思っています。
日立で、地域という単位で地産地消に取り組んだケースを一つ紹介します。東京都国分寺市には、市内の農家が生産する野菜を「こくベジ」と名付け、PRするプロジェクトがあります。「こくベジ」には生産者もいて、かつ「こくベジ」を使って料理を提供するレストランもあり、農家からとれたての野菜を集荷し、飲食店に配達し、それぞれのお店で市民の皆さんが食べることができます。地産地消が一見うまく回りそうにみえますが、プロジェクトメンバーや農家さんにお話を重ねるうちに、生産者から消費の現場に届ける「移動の手段」が課題になっていることが分かりました。
もちろん「こくベジ」に関わる方々は頑張って野菜を運んでいるんですが、地域の地産地消を目指す上では、流通と市民参加を組み合わせること。つまり、“お店に野菜を運ぶ”というプロセスにも市民に参加してもらい、地域の文化や営みを醸成しながら「移動」の課題を解決してみようと、市民も参加して移動させる取り組みを行いました。何が具体的な課題になっているのかを見てから、解決方法を考えていくというケースになりました。
越智(電):現場主義的というか、リアリティを大切にして本当の課題をリサーチしていく日立さんの姿勢に「なるほどな!」と思いました。電通も、もちろん現場を見ることを大切にしていて、いろいろとアイディエーションしているんです。だけど日立さんと電通グループでは文化も接している課題も違うため、発想や実装に違いがあるように思います。例えば日立さんのユニークな取り組みに「ビジョンデザイン」がありますが、これについて詳しく伺えますか?
赤司:日立は「社会イノベーション」というパーパスを掲げているので、社会課題を自分ゴトとして捉えたり、人と社会がどうやって幸せになるかを大事に考えたりするデザイナーやエンジニアが多い印象です。そんな中で、私は「ビジョンデザイン・プロジェクト」という活動を行っています。これは一言でいうと「未来を描くための日立のデザインの活動」です。
ビジョンデザインを立ち上げた15年前は、スマートシティ、スマートファクトリーなど、「スマート」という言葉が社会的にはやっていた時期でした。2016年に日本政府が公表し、当社の会長であった中西宏明が朝日地球会議2018のスピーチで述べた「Society 5.0(ソサエティ5.0)」という取り組みを日本政府が公表しました。その中で実現を目指すものとして提示された概念が、Super-smart society(スーパースマートソサエティ)、つまり超スマート社会です。
でも、そこで考えたのですが、「スマート」という言葉は、ビジネス上ではOptimization(最適化)やAutomation(自動化)、Efficiency(効率化)といった文脈で使われることが多いですよね。だけど本当はThoughtful(思慮に富んだ)やClever(賢い)といった意味もあります。
つまり、最適化、自動化、効率化の道が、本当に人間にとって幸せなのか?「社会イノベーション」に取り組むデザイナーとして、僕らはその問いで立ち止まる必要がありました。それで始めた活動が「ビジョンデザイン」なんです。
越智(電):Society 5.0が示す「スマート」は、必ずしも表層的な「スマート」を指していないのではないか?という仮説があったのですね。「そもそも新しい技術は、本質的に、人間のためになるのか?」という問いを出発点にされたと。
赤司:はい。もちろん、最適化、自動化、効率化によって、便利にはなるはずなんです。何かの作業を自動化すれば、今までやっていたことがなくなって、違うことに時間を使えるかもしれない。でも「本当に、それで幸せになるのか?」というのは、違う幸せの姿も探らないと分からないことだと思ったんです。
そこで「ビジョンデザイン」という活動を始めたわけですが、ただ「スマート」にするのではなく「スマートを超えるところを探そう」という「Beyond Smart(ビヨンドスマート)」という活動コンセプト名をつけました。デザインチームとして「技術が人にもたらすかもしれない課題のようなものを、日立の中から出していかねばならない」と思って、勝手に使命感に燃えていました(笑)。
越智(電):「ビジョンデザイン」では、「新しい技術が意図せずにもたらしてしまうかもしれない問題」にも目を向けていらっしゃいますね。
赤司:社会の中に、データ分析やそれに伴うトランスペアレンシー(情報の透明性)が入り込んでしまったときに、人は怖い思いをするかもしれないと思っています。例えば、病気になる確率が数字で表されるようになった場合。「あなたは30%の確率で病気になります」と言われると、そうなる前の社会と比べて、病気に対する距離感がぐっと縮まるんです。そのときに「数字を気にせずに生きていこう」と考えるのか。それとも30%にとことん向き合って10%にできるような暮らしに変えていこうとするのか。最終的には自分の「態度」の問題になるのですが、やはり変えないと生きづらくなるんじゃないかと。
この未来洞察は一つの例ですが、こういった例を他にもたくさんつくったんです。日立は将来、生活者、ひいては人の価値観がどのように変わっていくかという視点を持つ必要があると考えており、「きざし」と呼ぶ視点集を作っています。2010年にまとめたリサーチは「25のきざし」と名付けたのですが、これは2025年を想定して作ったものなので、今年「これは本当に起こった」「予想以上に進んでいる」といった答え合わせをしたいと思っています。やはり新型コロナウイルスの影響は大きく、「15年後の当たり前」になると予想したものが、コロナ禍で急激に「当たり前」になったものもあって、面白いんです。

※ビジョンデザインより
越智(電):なるほど!日立さんと電通グループでは、発想法や実装法に違いがあると思っているのですが、お話を伺っていると、実は目指すところに共通点があるなと感じました。機能と感情という観点で、機能面では社会の最先端を追いかけていくような動きがありつつ、一方で人の感情に注目したときに、その機能にどんな価値があるかを考えている点が似ていますね。
高橋:私の中で日立さんは、社会システムやインフラに深く関与されている会社というイメージがありました。でもそれだけじゃなくて、「社会」という大きなものと、「一人一人の人」というミクロなものを両方見られるような体制があって、そこを行ったり来たりしながら最終的に世の中を変えるアプローチをしていらっしゃると思います。そこは電通グループも同じなんです。
「人と社会を行ったり来たりしながら課題を発見し、解決する」という共通点はありつつ、日立さんは実装力を生かして「社会」の側からアプローチするのに対し、電通グループは「人」の側から意識・行動を一つ一つ変えて、世の中に対して変化を促していると思います。最終的にどちらの側からアプローチするのかという点が、両者の違いかなと感じました。
ちなみに、先ほど「きざし」の話をされていましたが、電通グループにも同じように「電通未来曼荼羅」という中期未来予測ツールがあります。今後、社会が中長期的にどのように変化していくかを、まずファクトから想像し、生活者の生活がどう変わるかをまとめているもので、そこも日立さんとの共通点ですね。
越智(日):私もやはり、やりたいことというか、「こうあるべき」という世界観は似ていると思いますね。先ほど、toB領域もtoC領域も広くカバーしながらさまざまな社会課題にアプローチしたいという話が出てきましたが、受け手の側からするとBtoBとBtoCの区別ってないですよね。
UX(ユーザーエクスペリエンス)を考えるときに、BtoBとして価値を提供するプレーヤーと、BtoCとして提供するプレーヤーが一緒になって一つの体験価値を実現しているんだと思うんです。おそらく、日立と電通グループさんはそういう意味で良い組み合わせだと思います。
C(コンシューマー)の方が悩む最後の一押しのところは、電通さんのコミュニケーションの力で気持ちを動かす。そのバックグラウンドで「仕組み・仕掛けとしてはこうなっていなきゃいけない」という部分を日立が提供するという形かなと。
お互いに組むことで新たな視点が生まれ、「もう一歩先」の発想が出てくる

電通 岸本和也氏
越智(電):まさしくお二人がおっしゃる通り、より生活者寄りの接点を多く持ち、課題解決するのが電通で、その生活者の奥にある社会との接点を大きく持っているのが日立さんなのかなと思います。岸本さんはどう感じましたか?
岸本:電通では、メディアをはじめとした生活者とのさまざまな接点のことを「コンタクトポイント」と呼んでいますが、そのコンタクトポイントで生活者とどのようなコミュニケーションを取るかをあれこれ考えてうまく表現しようとするところが、まさに電通の仕事領域なんですね。
例えば、先ほど赤司さんが「30%の確率で病気になってしまうとき」という話をされていましたが、生活者とのコミュニケーションの施策や、プロダクトやサービスにそのまま「30%の確率で病気になります」と直接出してしまうと、やはり生活者は少し「ウッ」となるのではないか、という感覚は持っています。
そこで、例えば「そろそろ危ないよ」とキャラクターに言わせてみるとか、プロダクトが振動してアラートを出してくれるような仕組みにするようなことを考えるんです。われわれはよく「チャーミングな伝え方」「コミュニケーションデザイン」と言ったりするんですけども、「どうしたらより良く伝わるか」ということは、生活者の方と向き合う中で常に考えていますね。
高橋:企業のコミュニケーションにおける、戦略から成果物の細部までを磨き上げられるのが、電通グループの強みですよね。「今日の気まぐレシピ」一つとっても、単純にフードロスを解決することだけを考えると、何もレシピにせずとも、売れ残りそうな食材を値引きするだけでいいと思うんです。しかしそれだけをやってしまうと、値引きをしすぎて企業のビジネスが維持できなくなってしまうかもしれない。
その点、「レシピ生成」というのは、生活者の方に値段以外の食材・商品の「価値」を提供する、つまり見せ方を変えるという、まさに電通らしいアプローチです。商品の価値を落とさずに、いかに買ってもらうかという。
越智(電):ちょっとした工夫ですよね。「売れ残っているから安いのです」と言われても、気持ちが動かないし。そうではなく、「これとこれを組み合わせると、こんなにおいしいものができます」というように、ポジティブに伝えていく点は、電通の考えるやり方、デザインかなと思います。

日立製作所 越智啓之氏
越智(日):今のお話を伺って思うことがあります。日立がtoBのお客さまと課題についてお話ししていると、「そのお客さまの課題の捉え方」に視点が限定されてしまい、その視点で想像しうる社会・未来を実現するにとどまることが多くなります。それを、もう一歩先へ、もっとスマートに、もっと新しい良いものにするためには、さらに一歩視点を広げる必要があります。
例えば、配車サービスの「Uber」。タクシー事業者ではない一般の方のリソース(車)を利用してサービスをするという発想自体が、すごく新しかったですよね。利用者と提供者をうまくマッチングするためのアプリケーションがあり、経路探索などいろいろな技術の組み合わせで実現しています。
日立の関わったサービスではないのですが、例えばもしも、タクシー会社さんと日立だけで話をしていたら、そのような発想はなかなか生まれにくいかなと思います。利用者の「すぐに配車されて、安く目的地に着きたい」という課題と、提供者の「車も暇もあるからサポートできる」という発想を組み合わせていったことで生まれたサービスなんですね。
つまり、電通さんと組んで、課題というものをクライアントだけでなく世の中や生活者にまで広げて考えてみると、「よりスマートに」ということを実現できるのではないかと思いました。「AI for EVERY」は主にBtoBtoCを想定していますが、toC、つまりエンドユーザーの課題発見にも期待しています。
越智(電):Uberの話はよく分かります!電通サイドももっといろんな生活者課題を解決したいんですが、広告をベースにしているわれわれができる範囲は結構限られていて、そこまで本格的な実装や課題解決まで到達できないこともあります。平たく言うと、「表現」で終わってしまうことが結構あるんです。インフラとかは、とてもじゃないけど作れない。でも日立さんと組めば、その先の実装まで実現できるかもしれません。
広げるのが得意な電通と、実装力のある日立さん、お互いの良いところを生かして、いいバランスでBtoBtoCの課題解決を実現できるのではないかと思いました。
後編へ続きます。