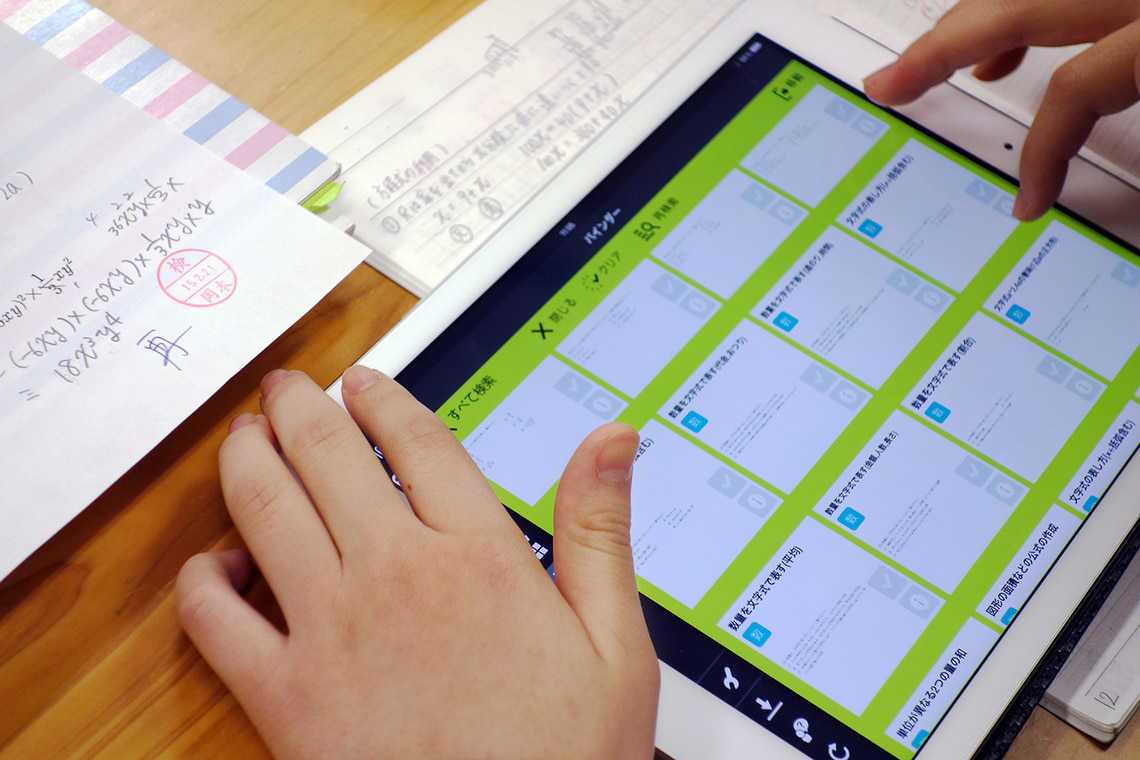ビジネスにインクルージョンを実装するなら、当事者との共創がカギになる
インクルージョン(包摂)の重要性は誰もが口にするものの、いざ実装となると、なかなか進まないことが多いのではないでしょうか。
特に、「当事者の視点をどのように事業に取り込み、事業成果につなげるのか?」という問いに対し、明確なモデルが少ないまま、現場は模索を続けています。
本連載では、こうした悩みにヒントを示すべく、インクルーシブデザインの「実装」に取り組む専門家や現場の声を交えながら、実践的な視点でひもといていきます。
第1回は、共に「インクルーシブデザイン」をテーマにした研究開発に取り組む、筑波技術大学と電通グループ3社(電通、電通総研、ミツエーリンクス)のメンバーによる座談会です。
4者はそれぞれの強みを生かし、インクルーシブな思想を取り入れた企業の事業・サービス開発や課題解決に取り組んでいます。なぜこのプロジェクトが立ち上がったのかを伺いました。
筑波技術大学
日本でただ1つの視覚障害者と聴覚障害者のための高等教育機関。視覚障害学生が学ぶ「保健科学部」、聴覚障害学生が学ぶ「産業技術学部」に加え、2025年から、両障害学生が情報アクセシビリティに関する情報科学と障害社会学を学ぶ「共生社会創成学部」が新設された。

「経済合理性」と「共創」の両輪がインクルージョン実装のカギ
山田:まず私から自己紹介をすると、私は電通のサステナビリティコンサルティング室(SC室)という部署におります。この部署はさまざまなサステナビリティ課題を起点に企業の事業成長を支援しています。そこで、昨年まで同室に出向していた電通総研の関島さんと、インクルージョンの実装についてよく話していたんですよね。
関島:電通総研は、シンクタンク、コンサルティング、システムインテグレーション機能を有する電通グループ企業で、私自身はOpen Innovationラボという組織で、長年、教育にテクノロジーを活用した、個別最適化をキーワードとした「アダプティブラーニング」の研究開発をしてきました。子どもたちにはそれぞれ特性があって、これからは個々の得意や好きな部分を生かすための学びが必要であり、従来のような一斉型の授業では対応しきれていない。そこをIT活用で解決していくという研究です。
3年前に電通のSC室に出向となり、DEIに関わるようになって、個々の特性や多様性の理解とデジタル化によるアプローチという点で通じるものがあるなと感じていました。山田さんと社会に対して影響を与えるような取り組みを、一緒に何かできないかという話になり、アクセシビリティの専門性をもつミツエーリンクスさんにもお声がけしたわけです。
木達:ミツエーリンクスは2024年4月に電通総研の完全子会社として、電通グループに加わったウェブ制作会社です。私自身はウェブサイトの構築・運用に幅広く関わっており、中でもアクセシビリティの専門家として20年以上取り組んでいます。ウェブ制作におけるアクセシビリティとは、障害者・高齢者だけでなく、さまざまなユーザーがサイトの機能を利用できるという、ひらたく言えば「みんなが使える」品質特性のことです。
山田:この電通グループ3社に加え、当事者との共創という観点で、ぜひ一緒に取り組みたいということでお声がけしたのが、谷先生の筑波技術大学でしたね。
谷:私は筑波技術大学で副学長をしています。大学での専門は機械工学ですが、いろいろなことをしていて、特別支援学校高等部を回りながら学生募集なども行っています。今は共生社会創成機構という組織にも属しており、電通さんとのお仕事も担当しています。
共生社会創成機構について少し説明すると、学外機関との連携を通じて、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目標にした組織です。共生社会を「つくってもらう」のではなく、障害の当事者が主体となって「つくっていく」。この組織の立ち上げと時期を同じくして、2025年から共生社会創成学部という学部を新設しました。

山田:障害当事者が主体となって、「共につくる」ことが、企業におけるインクルージョン実装でも重要なポイントだと思います。そのため、筑波技術大学の学生の皆さんのお力が必要だと考え、お声がけさせていただきました。
ここでプロジェクトの背景となる社会的な動きについて振り返ります。まず2024年4月に、障害者差別解消法の改正法が施行されました。大きなポイントが、民間企業に対しても合理的配慮が義務化されたことです。これは、電通はもちろん、電通が取引している企業にも関係がある話で、いろんなところでこの法律に対応するアプローチのあり方を模索する動きがあったんです。
しかしインクルージョンや当事者との共創は、経済合理性の観点から少し距離があるテーマだと思われているところが一部にはまだあり、その動きは十分ではありませんでした。そこに私は強い危機感を覚えました。障害とは特別なことではありません。日本で急速に高齢化が進む中で、障害者も増加するというデータがあります。インクルージョンや当事者との共創は、コミュニケーションとアイデアを生業にする私たちが先頭に立って取り組むべきことであり、社会のためになることはもちろん、より大きな機会創出にもなると考えたのです。
関島:当事者と一緒にビジネスに向き合うことによって、「経済合理性」と「共創」が両立する、それらが両輪で回るような実装モデルをつくりたいと、山田さんからご相談いただいたのが始まりでしたね。
電通からの意外な問い合わせ
山田:企業の課題に応じて、当事者との共創で、ビジネスにインクルージョンを実装する。この話を進めていくに当たって、なかなか理解を得られない葛藤がありましたよね。「経済合理性があるのか」という問いに対しては、マーケット環境の説明が必要です。n=1の話ではなく、ある程度定量的なデータを把握し、これだけの母数があるからマーケット的に価値があるんだ、この取り組みに合理性があるんだと答えられなければなりません。
山田:今回の取り組みの大きなポイントが、当事者との共創です。そのため、筑波技術大学の学生の方々とぜひ一緒に取り組みたいと考えたのですが、私たちからの連絡を受けての第一印象は?
山田:その後、たくさんの先生たちと対話をさせていただいて、「経済合理性と共創が成り立つ社会や企業のモデルをつくりたい」という思いをお伝えし、ようやくスタートできました。木達さんは、関島さんからプロジェクトに誘われたと思いますが、どんな印象でしたか?

山田:同感です。ただ集まって、それぞれがいつもやってきた仕事のやり方である課題を解決しようとしても、成り立たない。あくまでも「そのチームとしての」新しいアプローチをちゃんとつくる必要があるんですよね。
社会貢献を通じて「経済も」回していくことが本来のあり方
山田:「当事者との共創」って、いろいろな企業で取り組み始めてはいるんですが、ある議題について当事者と企業が対話した事実そのものをアピールポイントにして、そのまま終わってしまっているケースが多いんですね。本来はちゃんと一緒になってビジネスになるように、実装して回していくことが、僕らの仕事には求められていると思います。谷先生のところに相談に来る企業は、具体的なビジネス課題をお持ちの方が多いのでしょうか。
山田:たしかにどちらも重要ですよね。私が考えているのは、やはり経済が回っていく基盤があった方が、社会貢献にしても長く続いていくのではないかということです。

山田:「誰もが使える」ことが、ビジネスとしても、社会貢献としても意味があるということですね。だけど、切り離されて論じられがちであると。
山田:目に見えるデータが足りていないということですよね。関島さんも、社内での交渉に苦労されていました。
山田:だからこそ、ある程度の総量を把握できるデータ基盤やプラットフォームが必要なんですよね。その開発に当たっては、電通に投資してもらえないか相談したのですが、ただ「投資してほしい」ではなかなか難しい。「いろいろなクライアントと実装の経験値を積み重ねていって、最終的に必要な仕組みのあり方を見つけていきます」という言い方をしたら、話が進み始めましたね。「1つ1つのプロジェクトの先に、最終的な仕組み化の話があるんです」というアプローチだと合意形成ができたのは学びになりました。
インクルージョンで障害のある人も、そうでない人も生きやすい社会に
山田:学生の皆さんはこうした企業との共創や、インクルーシブな社会に対してどういった思いを持っているのでしょうか。
山田:当事者との共創といったときに、学生が企業にどういう関わり方ができるのか、谷先生はどういうイメージをお持ちですか?
山田:その部分は、われわれ電通グループが担うべき部分もたくさんあると思います。社会から障壁を取り除くためにも、まず当事者との接点が必要という部分もありますよね。

木達:ウェブに限っていうと、あるガイドラインにのっとってつくることで、ある程度障害者の方も使いやすいウェブサイトやデジタルコンテンツにすることはできるんです。ただ、やはり最終的には実際に障害者の方に使ってもらわないと分からないこともあります。
谷:障害のある人が豊かに暮らせるということは、当然ながら障害のない人だって豊かに暮らせる環境なんですよね。それに、私たちだって誰だって年齢を重ねれば、見えなくなって聞こえなくなるわけです。元から障害のあった方は訓練されているから平気なことでも、あるとき老化で見えない・聞こえないとなると、とても孤独になるんです。そういう人が救われる、そういう人をなくすことを最終的には目指していきたいですね。
私は耳が聞こえますが、最初にこの大学に来て、聴覚障害者向けの授業を見たんです。これが手話を使わない私にとっても、すごく分かりやすかったんですよ。まず板書をしっかり書きます。適当に書かないんですね。その上で、振り返ってしっかり前を向いて手話を使って話すんです。その授業は、聞こえる人から見ても、取ったノートを後から見たいというくらい良い授業になっている。それこそが目指すべきあり方かなと。
木達:ウェブの世界ではSEO(検索エンジン最適化)がとても重視されてきました。そんな中で私が申し上げてきたのが、「障害者にとって使いやすくすることは、検索エンジン対策にもなるんですよ」ということです。検索エンジンって「目」で情報を取っているわけじゃなくて、サイト上にあるデータをソフトウエアが機械的に処理して意味を読み取っているわけです。それって視覚障害者の方が使うスクリーンリーダーにどうやってうまく情報を読み込ませるかという話と、技術的には極めて近いことをやっているんですね。

・dentsu JapanのDEIサイトはこちら
https://www.japan.dentsu.com/jp/deandi/
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

谷 貴幸
国立大学法人 筑波技術大学
副学長 共生社会創成機構長 産業技術学部 教授 博士(工学)
1995年筑波技術短期大学 機械工学科 助手に着任。2005年東京大学大学院 精密機械工学専攻 国内研究員。同年より筑波技術大学 産業技術学部 准教授。2014年より同大学 教授、2020年より産業技術学部長、2023年より副学長、現在に至る。学内では教務、学生委員会委員長、高大連携事業等を担当。生産加工に関する研究に従事し、工作機械振興財団論文賞(2回)、電気加工学会論文賞受賞(4回)を受賞、電気加工学会常務理事などを務める。

木達 一仁
株式会社 ミツエーリンクス
エグゼクティブ・フェロー
宇宙開発関連組織でウェブマスターとしての経験を積んだ後、IT業界へ。以来、ウェブコンテンツの実装工程に多数従事。2004年より株式会社ミツエーリンクスに参加、現在はエグゼクティブ・フェロー。クライアントワークとしては、主にフロントエンドの設計や実装、関連ガイドラインの策定に従事。

関島 章江
株式会社電通総研
スマートソサエティセンター スマートソサエティコンサルティング部
シニアプロデューサー
長年システムエンジニアとして企業の基幹・業務系システムの開発や運用に従事。2010年社内の事業企画コンペ応募を機に、Open Innovationラボへ異動。以後「教育×Tech」を軸に事業開発、教育DXに携わる。テーマは「アダプティブラーニング」。個々の特性を認知し、特性を生かしあえる社会の実現を目指している。著書「日本のICT教育にもの申す!」。

山田 健人
株式会社 電通
サステナビリティコンサルティング室 企業価値コンサルティング部
シニアコンサルタント/プランナー
電通入社後、食品メーカーや不動産デベロッパーを中心に、ブランド戦略や統合的なコミュニケーション支援に従事。2016年以降は、不動産業界でのサステナビリティ視点に基づく情報設計やブランド再構築を推進。2023年よりサステナビリティコンサルティング室に所属。「ビジネス×DEI」を主軸に、企業へのインクルーシブデザイン導入や共創型ワークショップ設計などを通じて、持続可能な価値創出を支援している。