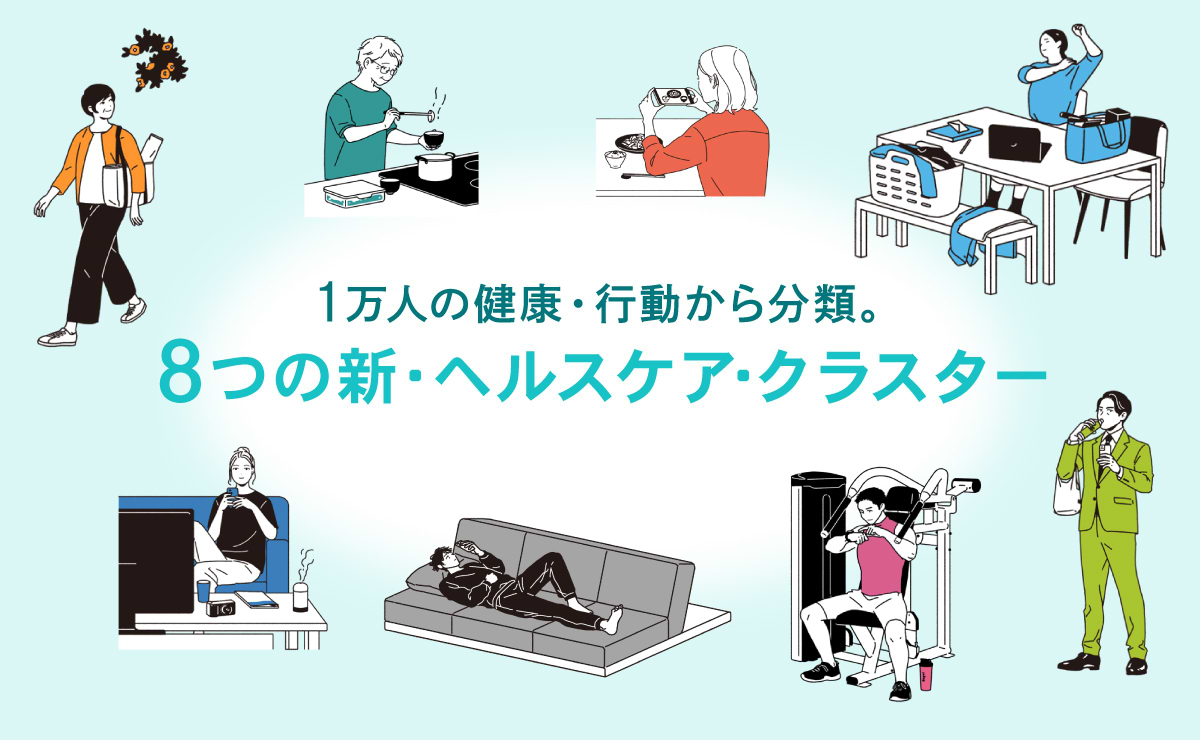データドリブンなマーケティングでクライアントを支えるべく、新時代のモデル「Marketing For Growth」を掲げる電通。
これまでさまざまな形で「PR」に携わってきたメンバーが、統合プランニングやマーケティングに「PR発想」をプラスするためのバーチャル組織「PRUS(プラス)」を発足させました。本連載では、PRUSメンバーが、まだまだ誤解されがちなPRの本質と、それがなぜ今あらゆる企業活動に必要なのかをひもといていきます。
前回に続き、「たのしいさわぎをおこしたい」をスローガンに、PR発想を軸としたコミュニケーションで社会課題にも向き合うPR・コミュニケーショングループ、サニーサイドアップ取締役の松本理永(まつもと・りえ)氏に、電通 第6マーケティング局の藤田悠斗氏と姜婉清(きょう・えんせい)氏が、お話を伺いました。

左から、藤田悠斗氏(電通 第6マーケティング局)、松本理永氏(サニーサイドアップ取締役/公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 副理事長)、姜婉清氏(電通 第6マーケティング局)
分断や壁を乗り越えて共創するには?
姜:PRの本質から企業発信の現在地、“巻き込み力”の設計について、松本さんにお話を伺っていますが、いろんなステークホルダーの方々と協業すれば、もっと良いプロジェクトが生まれるはずだと思っても、実際にはなかなかそう簡単にいかない場面もありますよね。私自身も以前、ある協賛プロジェクトの提案をした際に、「とても社会性のある良い企画ですね」と評価はいただきながらも、「グループ会社間の協業は難しい」「調整にエネルギーがかかる」といった理由で見送られた経験がありました。
松本さんも、さまざまな企業と協働する中で、そうした壁にぶつかったことは多くあると思います。そんなとき、どのように向き合い、乗り越えているのでしょうか?
松本:確かに簡単なことではありません。企業にはそれぞれの事情があるので、「分かってはいるけど、簡単には動けない」ということも多い。だからこそ私は、経営層や意思決定層の視座を少しでも変えていけるように働きかけることを意識しています。その際に重要なのが、共感いただける規模の成功事例です。「こんな連携によって、社会的にも事業的にも大きな成果が出ている」と示すことが、背中を押す説得材料になると思っています。

藤田:組織の分断って、なかなかすぐには解消されないですよね。だから私も、「この構造はすぐには変えられない」と受け入れた上で、目の前の担当者にどれだけ真摯に向き合えるかを常に考えています。一人一人のマインドに働きかけていくこと、それが小さくても確実な突破口になると思うんです。
松本:おっしゃる通りで、クライアントの皆さんも、「社会に背を向けることはできない」という感覚はこれまで以上に持たれていると思います。むしろ、「社会をどう味方につけていくか」が事業の成長において不可欠な視点になってきていますよね。
PRのプロとして私たちは、「どこに石を投げたら、どんなふうに波紋が広がっていくか」をある程度予測できます。その知見をもとに、社会に届くためにはどこを動かすべきか、誰を巻き込むべきか、構造的にご提案できることがある。そこを一緒に考えられるようになってきている実感はあります。
藤田:社会を味方にしていく。そのためには、企業も社内外の分断を超えて、本当の意味で共創していく必要がありますよね。
姜:分断を越えて、同じ視線で未来を描けるか。そのための関係性をどう築いていけるかが、これからのPRにも、そして企業の発信全体にも求められる力なんだと感じます。
![]()
社内から始めるPR発想の社会変革
藤田:ここまで外部のステークホルダーを巻き込む方法について伺ってきましたが、やはり社内を巻き込む力が変革のエンジンになると感じています。たとえば、御社では独自の福利厚生「32の制度」をはじめ、ユニークな社内施策が多く実施されていますよね。特に「32の制度」は社員の皆さんを巻き込んでいくための仕組みの一つだと思うのですが、そもそもこの取り組みを始められたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?
松本:社会を動かす前に、まずは自分たちの組織からどう「たのしいさわぎ」を生み出すことができるか。その問いから、私たちの制度設計が始まりました。自分たちがどんな会社でありたいのか、どんな人たちとどんな環境で働きたいのかを、メンバーと対話していったんです。その中で、「もっと仲間のことを知りたい」「もっと自分を高めたい」などといった声がたくさん出てきました。
そこから、「こうありたい」を実現するために必要な制度を一つずつ考えていったんです。たとえば、書籍代を補助する「サニー文庫」制度は自己研鑽、音楽・映画・演劇・スポーツなどのエンタメ費用を補助する「たのしいさわぎ創造支援」制度は外の世界からインプットする力を育てるものです。そういった制度を体系的に整理していった結果が「32の制度」なんですね。
![]()
藤田:それぞれの制度が単なる福利厚生にとどまらず、「どのような社会にしたいのか?」という外部に向けたメッセージにもなっているように思います。
松本:そうですね。たとえば「Dear WOMAN」制度の卵子凍結保存の費用補助はまさにそうです。この制度は単にサポートを提供するだけにとどまらず、自分の人生や働き方、将来について早い段階から考えるきっかけになってほしいという思いで導入しました。
私もサニーサイドアップグループ代表を務める次原も、働きながら子どもを授かりましたが、同じように懸命に働いてきた仲間たちが「知らなかったから」「間に合わなかったから」という理由で苦労した例も見てきました。もちろん、子どもを持つことが良い悪いということではなく、自分の人生でいつ選択をするときがくるのか、そしてそのときに、どんな選択肢があるかを知っていることが、とても大切なことだと思っています。
姜:ありがとうございます。本日は、PRの本質から始まり、時代の変化への向き合い方、共感を広げる巻き込み力や分断を超えた共創の可能性、そして社内から生まれる変革まで、幅広くお話を伺いました。改めて、PRの視点がさまざまな側面から社会と企業をつなぐ大きな力になることを実感しました。この視点を、これからのマーケティングにどう生かしていけるか、私たちPRUSチームもさらに探究していきたいと思います。