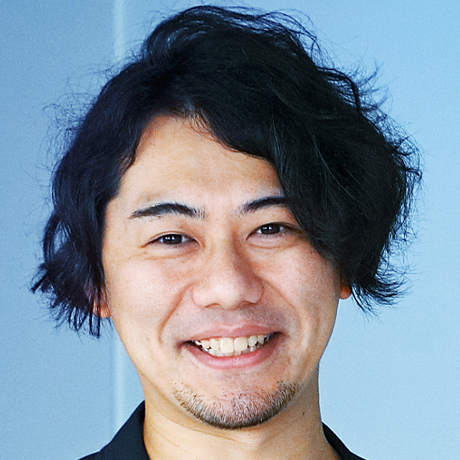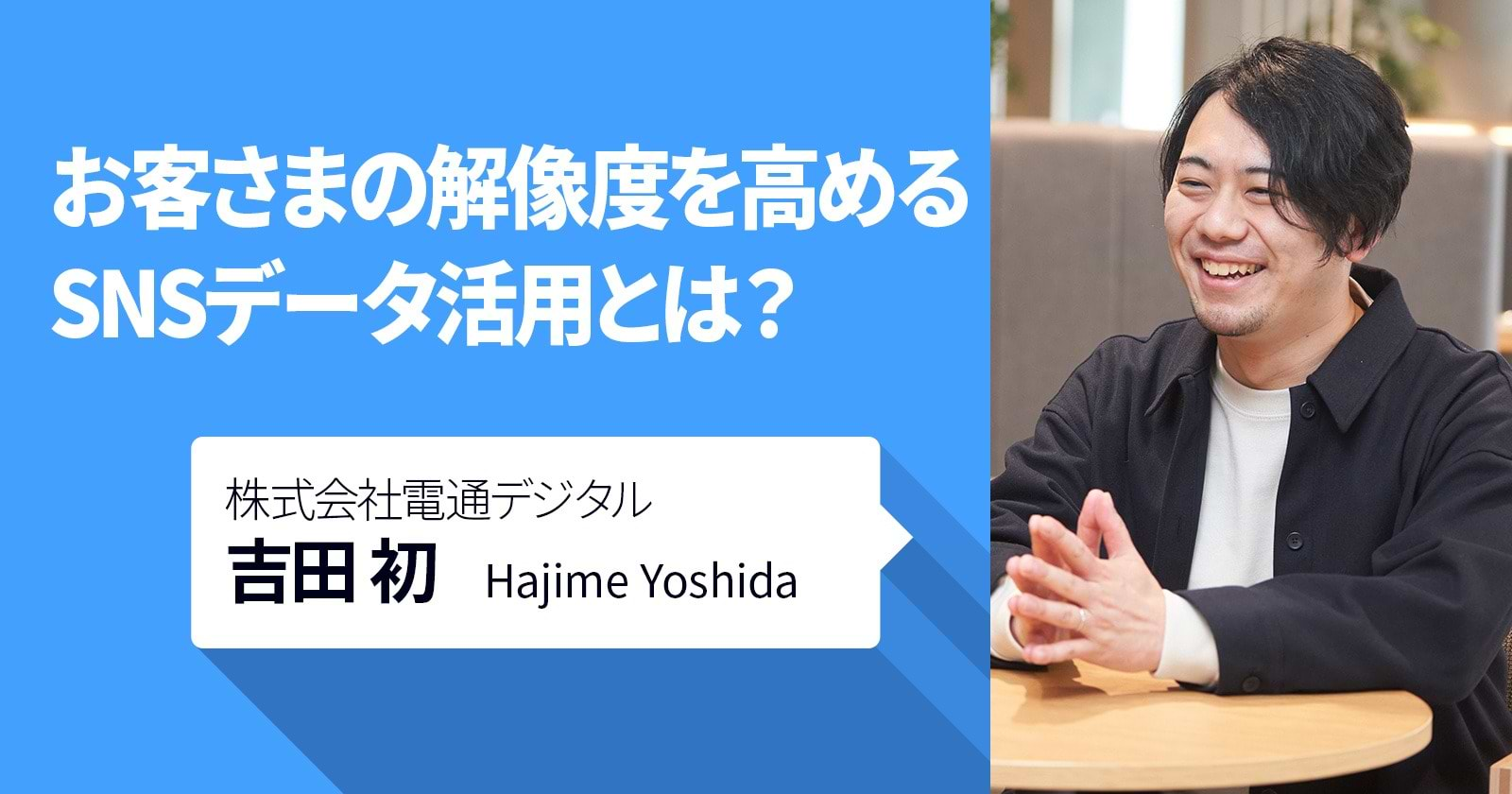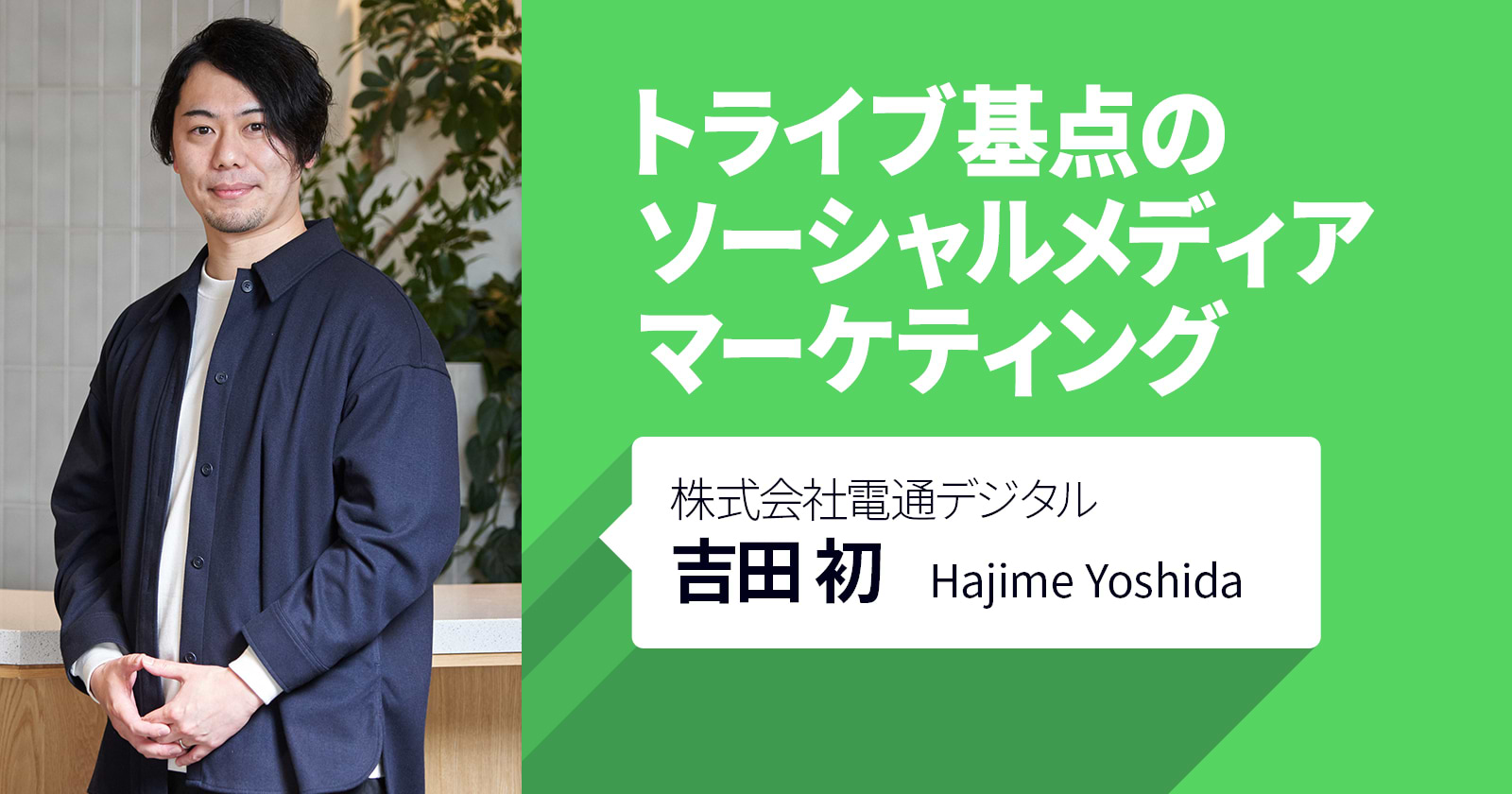「Tribe Driven Marketing(トライブドリブンマーケティング)」は、共通の興味関心・ライフスタイルを持つSNSユーザーの集団「トライブ」を基点としたマーケティング手法です。「SNS運用に役立てたい」「デジタル広告の効果を高めたい」といった企業の声に応える他、企業・ブランドのファン獲得、商品開発などにも活用が広がっています。
今回、株式会社電通デジタルの吉田初氏にインタビューを行い、Tribe Driven Marketingだから成し得るお客さま起点のマーケティングについて、詳しい話を聞きました。後編では、活用事例を挙げつつ可能性をさらに探っていきます。
SNS上での発話数を捕捉し、広告効果を長期的に評価
Q. Tribe Driven Marketingによって、どういったご相談に応えているのでしょうか。活用事例をお聞かせください。
吉田:電子機器メーカーA社さまからは、「Z世代に製品を広めたい」というご相談を受けました。そこで、SNS上でA社製品について発話しているZ世代ユーザーのデータを分析したところ、その製品があることで「アイドルの推し活がはかどる」「電子コミックをより楽しめる」といった、機能よりも体験価値が評価されていると分かりました。
一方、競合B社の製品愛用者のトライブを見ていくと、「画質が良い」などの機能について語られる傾向がある。つまり、B社の製品は機能をアピールするのが有効ですが、A社の製品は「この機器があることで日々の暮らしがどう変わるか」という体験価値を訴求すべきだと分かったのです。そこで、Z世代の多様なトライブが、それぞれA社の製品を持つことでどんな体験ができるのかを考え企画提案を行いました。このように、Tribe Driven Marketingによって、ターゲットのニーズを深く掘り下げることができると考えています。
 株式会社電通デジタル 吉田 初氏
株式会社電通デジタル 吉田 初氏Q.お話を伺い、Tribe Driven Marketingはターゲティングツールではなく、マーケティングフレームだということがよく分かりました。ターゲットとなるお客さまが好むもの、求めるものを把握し、それに合わせてマーケティング戦略を立案する。さらに、前編でお話されていたように、SNSの発話数と売り上げが一定の相関関係にあるという条件が生じれば、SNSを活用しての中間指標も立てられます。これからのマーケティング基盤の1つになる可能性を感じましたが、いかがでしょう。
吉田:そうですね。これまでのSNSマーケティングは、企業の投資対効果が分かりにくい一面がありました。例えば、SNSで広告を打ったものの、すぐには売り上げに結び付かないケースがそうです。とはいえ、広告によってSNS上での発話数が増え、ファンも増えているのであれば、長期的に見れば効果があったと言えるでしょう。Tribe Driven Marketingは、こうした評価のベンチマークにもなります。発話数がどれだけ増えたのか、その中に新規ユーザーがどれだけいるのか、ターゲットに届いているのかなど、さまざまな視点でモニタリングし、分析・報告できるのが、これまでにない特徴です。
Tribe Driven Marketingが可能にする次世代PDCA
Q.Tribe Driven Marketingは、次世代PDCAを可能にするとのことですが、この点について詳しくお聞かせください。
吉田: Tribe Driven Marketingはユーザーを興味関心のトライブで見ていくという発想に加えて、ユーザーと企業の関係値をスコア化し、ロイヤリティーまで区分することもできます。広告でサービスを認知した、企業投稿に反応した、誰かの投稿をシェアした、キャンペーンに参加した、実際に体験してみた、いつも愛用しているなど、ユーザーごとにステータスは異なり、企業との関係値(理解度・好意度)の深さにも違いがあります。こういったユーザー属性(トライブ×ロイヤリティー)を軸にPDCAを行うことが可能です。
例えば、SNSアカウントを運営するある企業は、フォロワーを増やすことではなく、ユーザーとのより良い関係性を築いていくことを考えていました。そこで、SNS上のユーザーが同社に対してどんなリアクションをしているかを分析し、将来的にファンになってくれるかもしれない“潜在層”から、自発的にポジティブな発話をしてくれる“コアファン”まで、数段階のロイヤリティーでユーザーを分類しました。
ロイヤリティー別に各施策の反応を見ると、異なるトライブで反応があることが分かりました。普段反応してくださるコアファンが望むコミュニケーションはもちろん大事ですが、一方で、潜在層が反応するものとの違いが分かったことで、ユーザーのロイヤリティーごとにコミュニケーション設計をし、異なるクリエーティブでの広告アプローチを多層的に考えていくようになりました。このように、トライブ軸でPDCAをアップデートしています。
Q.Tribe Driven Marketingと相性の良い商材はあるのでしょうか。
吉田:ユーザー数が多く、SNSでの盛り上がりが売り上げに直結するtoCの商材は特に相性が良いと考えられます。例えばエンターテインメントコンテンツ、コンビニやファストフードの商品などは分かりやすい例です。
一方で新たなマーケットやニッチな商材に関しても、必ずどこかにコアとなるトライブを見つけられると思っています。
Q.具体的に、ニッチな商材でTribe Driven Marketingを用いてマーケティング施策のご提案をした例はありますか。
吉田:ある案件で、虫対策に関する商材をゴルフ愛好家やフェスに行く若者にアピールしたいというオリエンテーションを受けました。ですが、ターゲット層は本当にそこで合っているのかと考え、SNSで虫への困りごとについて発話している方々のデータを収集しました。その中で目立っていたのは、昆虫や野花の写真家トライブ、子育てトライブ、ニュース高関心トライブでした。つまり、昆虫の写真を撮りに草むらに入ることが多いので虫の被害を気にしていた方や、子どもが虫の被害に遭わないように注意喚起する方、それらの情報に興味を持った方々です。
当初想定されていたターゲットを否定するものではありませんが、今その話題に強い興味・関心のある方々に注目されなければ商材の認知は広まりにくいと考え、まずは短期的なターゲットトライブとしてご提案しました。
このように、クライアント企業さまの商品・サービスが何であっても、具体的なターゲットを発見し、コミュニケーション戦略を考え、広告でのターゲティングまで一気通貫でのご提案を行っています。
Q.最後に、SNSデータ活用の可能性についてお伺いします。Tribe Driven Marketingによるソーシャルメディアマーケティングの構想、展望についてお聞かせください。
吉田:各種SNSを横断したデータを用いてのマーケティング支援については、まだまだ可能性を感じています。プラットフォームごとの特性も多様ですし、トレンドも日々変わっていきますが、SNSデータを最大限活用できるよう拡張をしています。
その上で、私たちが達成したいのは、お客さま起点マーケティングのNo.1になることです。Tribe Driven Marketingの発想を生かして、クライアント企業さまの先にいる生活者にSNSを通して最大限向き合う。そうすることでマーケティング施策の質を高め、クライアント企業さまの目標達成に貢献していこうと思っています。

Cookie規制などが進む中で、新たなマーケティングアプローチの1つとして、SNSデータからお客さま理解を深めるソーシャルメディアマーケティングの重要性が高まっています。SNS上のユーザーをトライブ単位で分析し、お客さまの趣味嗜好やニーズを深掘りするTribe Driven Marketingは、ターゲットとなるお客さまの解像度を高め、施策の効果を高めるお客さま起点のマーケティングフレームと言えるのではないでしょうか。