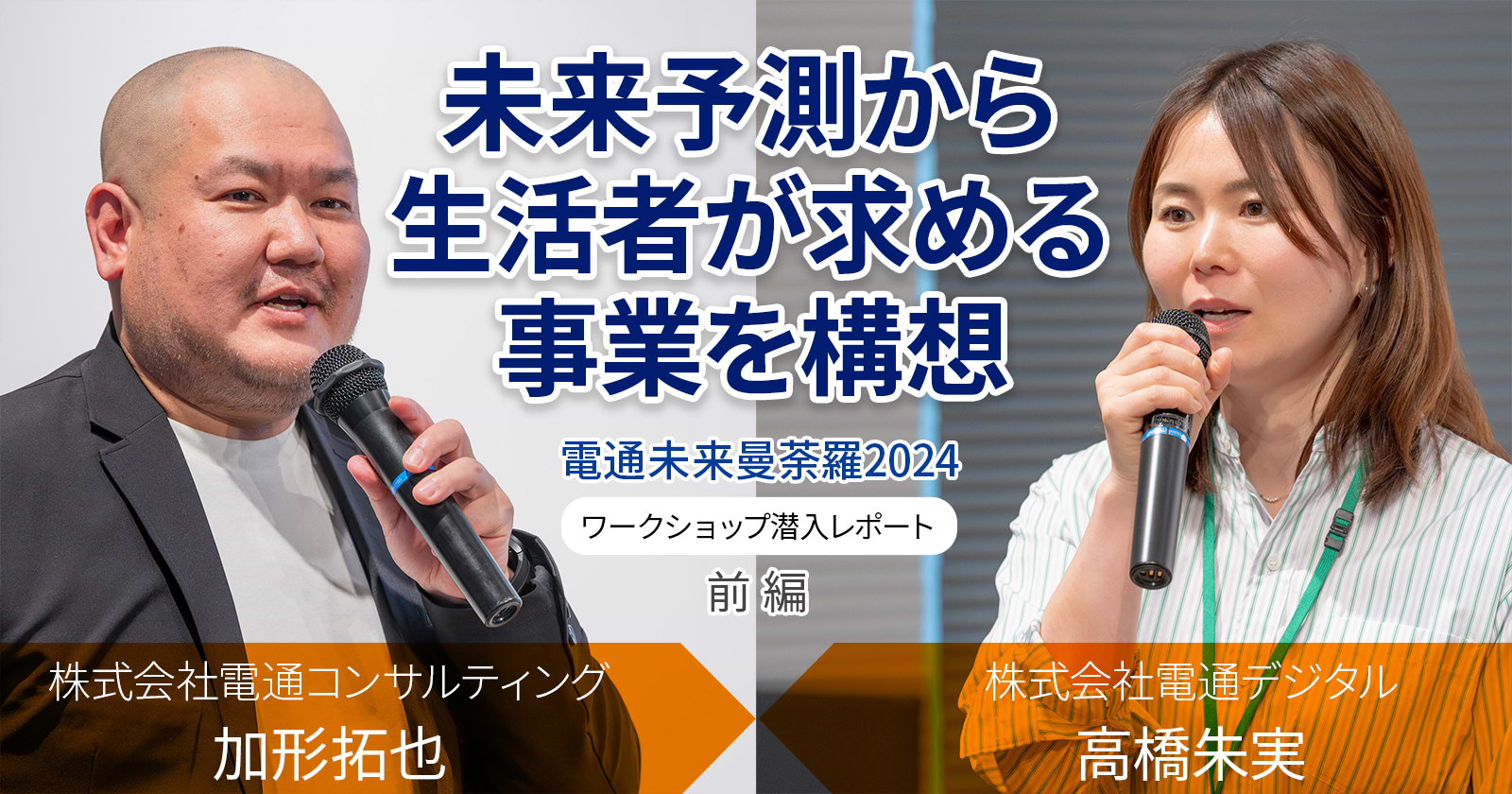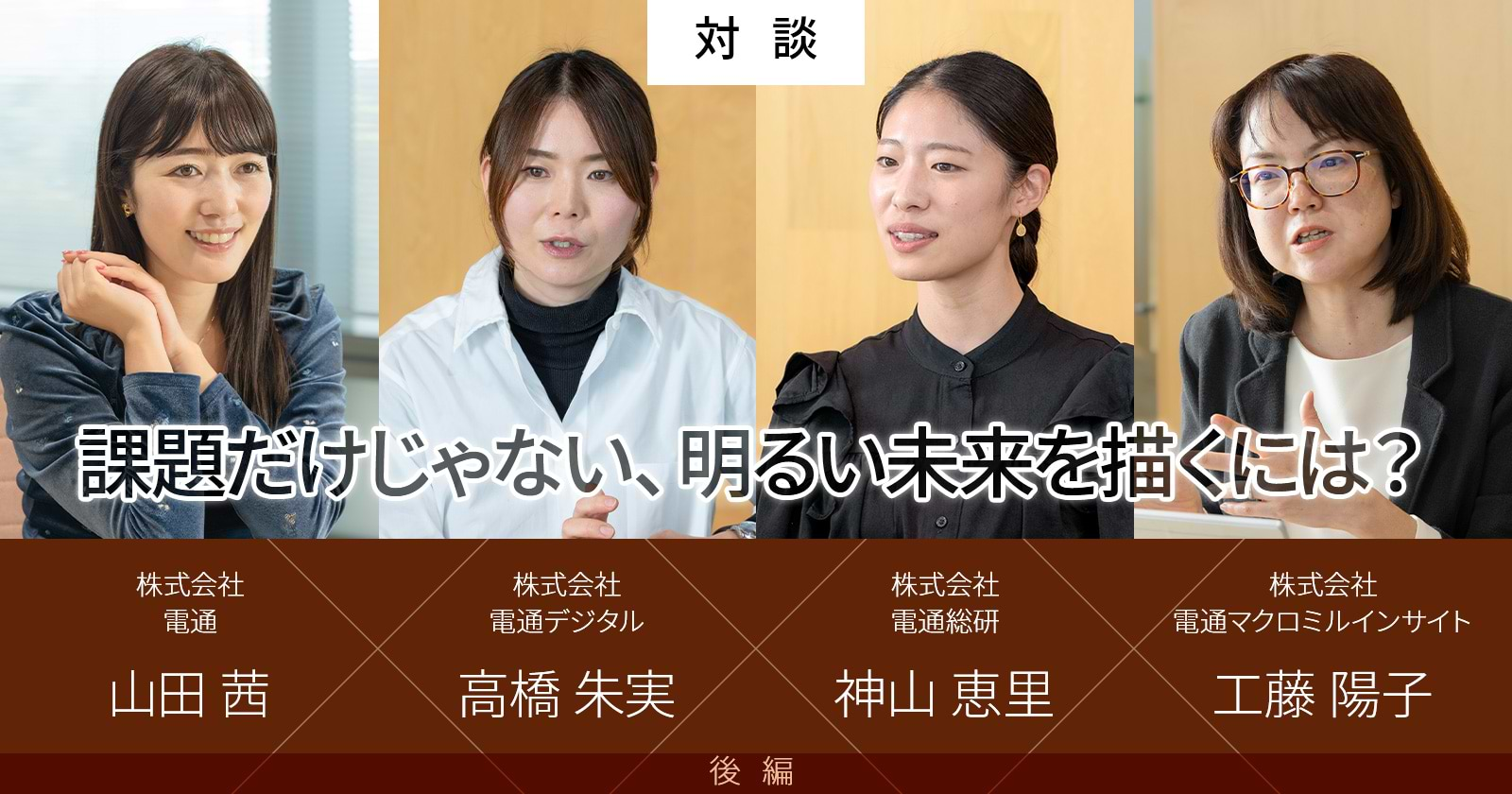電通グループの横断組織「未来事業創研」が、2023年12月にリリースした「電通 未来ファインダー100」。2040年の未来の暮らしを構想し、新たなビジネスチャンスを発掘するツールとして開発されました。本記事では前後編にわたって、開発に携わった未来事業創研メンバーの株式会社 電通 山田茜氏、株式会社電通デジタル 高橋朱実氏、株式会社電通総研 神山恵里氏、株式会社 電通マクロミルインサイト 工藤陽子氏による対談を実施。後編は、本ツールを構成する8カテゴリー・100テーマのうちそれぞれが注目しているテーマや、「電通 未来ファインダー100」がアイデア創出にどのような好影響をもたらすかについて語り合います。
未来では非効率的なモノやコトを「あえて」選ぶ?
山田:前編に続いて、それぞれが注目しているテーマについてディスカッションしていきたいと思います。神山さんはどんなテーマを選びましたか?
神山:私が選んだのは「自動最適化」です。今の世の中には「自動化」「効率化」「最適化」といったキーワードがあふれていますが、人の感覚や思考って、もっと奥が深い気がしていて。最適化が進むほど、人は逆のものが欲しくなり、非効率的なモノやコトに価値が生まれる可能性があると思っています。
 株式会社電通総研 神山 恵里氏
株式会社電通総研 神山 恵里氏高橋:最近読んだ書籍の中に「効率化して最適化すればするほど、人間は新しいタスクを生み出す」といったことが書かれていたのを思い出しました。「最適化、効率化すると楽になると思われているけれど、果たして本当か」という問いにもつながると思いますし、そういう視点は事業を創造する上でも重要だなと思います。
山田:誰かにとって最適化したいポイントが、別の人にとっては最適化せず残しておいてほしいポイントである可能性もあって、そこが面白いところですよね。未来では、全部を最適化できるツールはあるけど、「あえて使わない」ものを1人ひとりが選択していくことになるかもしれませんね。
同じテーマでも着眼点は人それぞれ
高橋:私は「アート」というテーマを選びました。「電通 未来ファインダー100」には「 “共感の通貨”としてアートが、新しい経済圏を生み出す」「権威ではなく個人の支持や共感によってアート価値が決まり、収入の高低にかかわらず自分の感性にあったアートを楽しむ」というアートの立ち位置の未来予測が書かれていて、とても興味深いです。アート作品が投資信託商品になるような、そんな感覚を覚えました。これからは、世の中の人たちが何を求めているかを考え、資産価値をきちんと計算して作品を市場に出していく、金融マンのようなアーティストが増えていくのかもしれないですね。
 株式会社電通デジタル 高橋 朱実氏
株式会社電通デジタル 高橋 朱実氏神山:実際、アートとビジネスは昔から密接に結びついていたのに、それについてあまり触れてはいけないような雰囲気がありましたよね。もっとアートをビジネスとして捉えても良いと思います。特に日本人はアートを買わない、と言われていますが、2040年にはアートの捉え方に多様性が生まれ、みんながもっとアートに触れて、気軽に買う時代になったら素敵だなと思います。
工藤:アートには、視点を変えたり、発想の幅を広げたりする役割もありますよね。美術のリテラシーがなくても、世の中に対する見方を変える手段として、アートが身近になっていくといいなと思いますね。
山田:前編も併せて、ここまで3つのテーマについてディスカッションしてきましたが、同じテーマでも着目点が人それぞれで面白いですよね。クライアント企業さまを対象としたワークショップでも、いつもさまざまな意見が飛び交うので、新しい商品やサービスのヒントがそこかしこに散らばっているなと思います。
私が選んだテーマは「幼児の教育」です。これは「電通 未来ファインダー100」で私が担当しているテーマでもあるのですが、カードには「幼児からのさまざまな学習履歴がブロックチェーンに蓄積されて履歴書として評価される」という未来予想を書きました。学歴や職歴で人を表現する従来型の履歴書って、もう古くなっているんじゃないかと思うんですよ。勉強以外の部分だったり、学歴・職歴だけではすくいきれないその人の人生の軌跡が評価される世の中になったら素敵だなと思いました。
 株式会社 電通 山田 茜氏
株式会社 電通 山田 茜氏工藤:今の教育って、スキル、偏差値、受験みたいな方向と、オリジナルキャラを作っていこうみたいな方向に二極化している気がしますよね。本人の好きなことを見つけて、伸ばしていけるのが1番だと思うので、その手助けになるかもしれませんね。
山田:そうやって、幼児期から触れてきたものや、インプットしてきたもの、考えてきたことがブロックチェーンに蓄積されて、履歴書になる未来が訪れたらどうなるか? という問いかけは、教育業界じゃなくても、事業創造のヒントになり得ると思います。
多様なツールを用いて未来にポンッとジャンプする
高橋:「電通 未来ファインダー100」は、ワークショップのアイディエーションツールとして非常に完成度が高いと思います。カードは表面と裏面があり、裏面には2040年の未来に向けて、現在起きている具体的な兆しと、2040年の未来で起こり得ることや、そこにどのような機会が存在するのかという「未来チャンス」が書かれていますが、ヒントだけにとどめて見る人の解釈やアイデアの創発を促しているところが絶妙だと思います。
 「電通 未来ファインダー100」の裏面
「電通 未来ファインダー100」の裏面
(実際にはグレー箇所に、現在起きている具体的な兆しの事例と、2040年の未来で起こり得ることが記載されています。)神山:多角的な視点から書かれているところも良いですよね。「今、こんな事例があります」といった兆しとしての事例もあれば、「逆にこういうニーズもあるかもしれないよ」といった1人だけでは思いつかないような予測が並列で書かれていて、思考が広がりやすい作りになっていると思います。
工藤:「食の不足」や「日本の少子化」など深刻さを内包するテーマもありますが、メンバーが気を付けていたのは、決して悲観的な未来予測にならないようにすること。「こういう未来を作っていきたい」「こういう未来にすればいいんだ」と、ポジティブな未来を思い描ける起点になると思います。
 株式会社 電通マクロミルインサイト 工藤 陽子氏
株式会社 電通マクロミルインサイト 工藤 陽子氏山田:実際のワークショップでは参加された方が「当たり前かなと思うんですけど……」と言いながら発表してくださるアイデアが、全然当たり前じゃないのが面白いです。枠にとらわれず、その人らしいアイデアが出てくるところが、このツールの魅力だと思います。
未来事業創研では、「電通 未来ファインダー100」以外にもさまざまなツールを開発しています。例えば、人の欲求は普遍的なものだけど、欲求の満たされ方は時代によって変わることに着目して「じゃあ、未来はどういうふうに欲求が満たされるんだろう?」と考えるヒントになるツールなど。今現在の課題だけを語るのではなく、視点を未来にポンッとジャンプさせるためのツールを用意しているので、他のツールとも組み合わせてぜひご活用いただきたいと思います。

未来事業創研のメンバー4人がそれぞれテーマを持ち寄り、さまざまな角度から「ありたき未来」を描いた今回の対談。「電通 未来ファインダー100」を用いたワークショップでは、このように「ありたき未来」への想像を膨らませることができます。