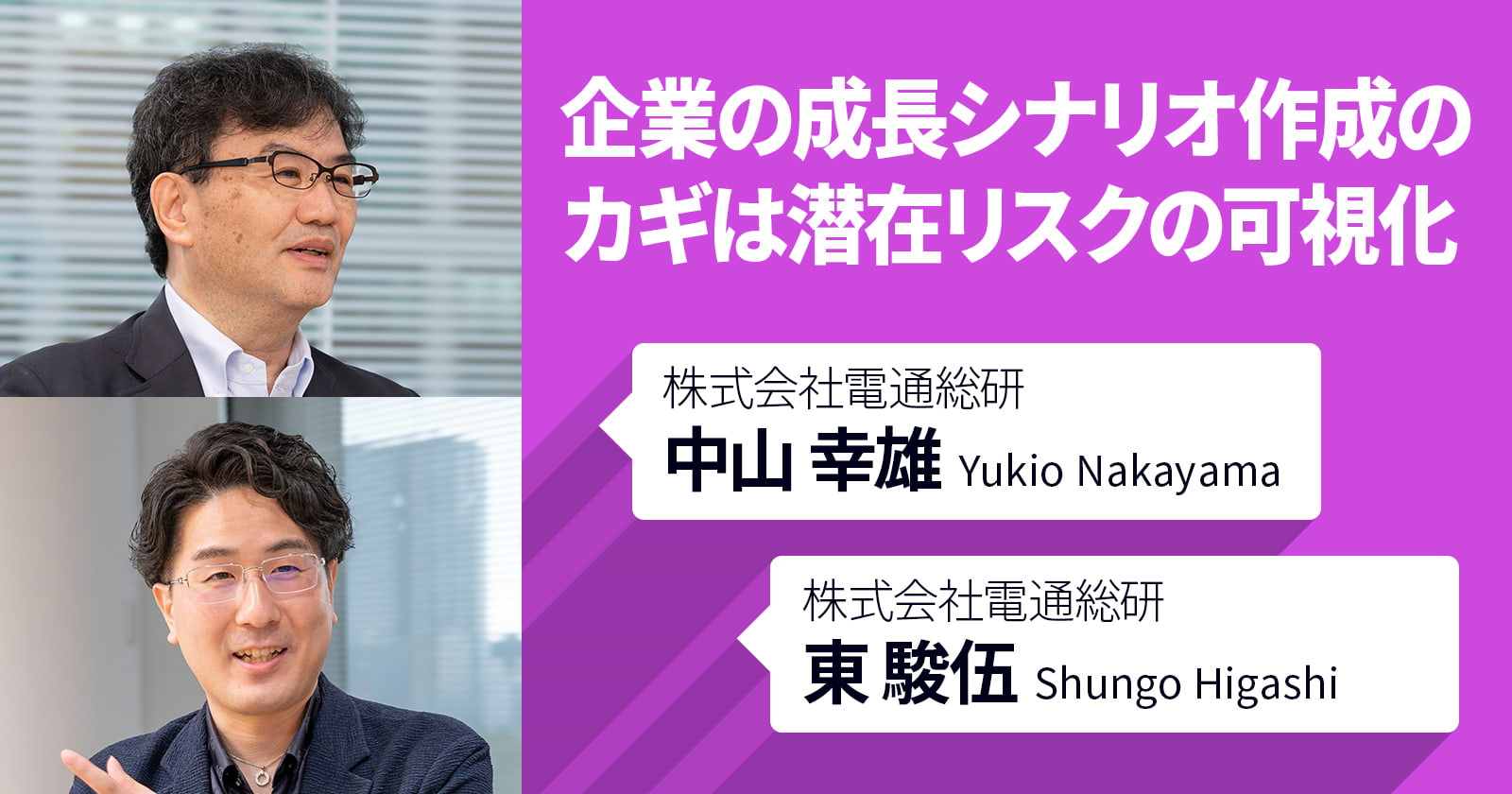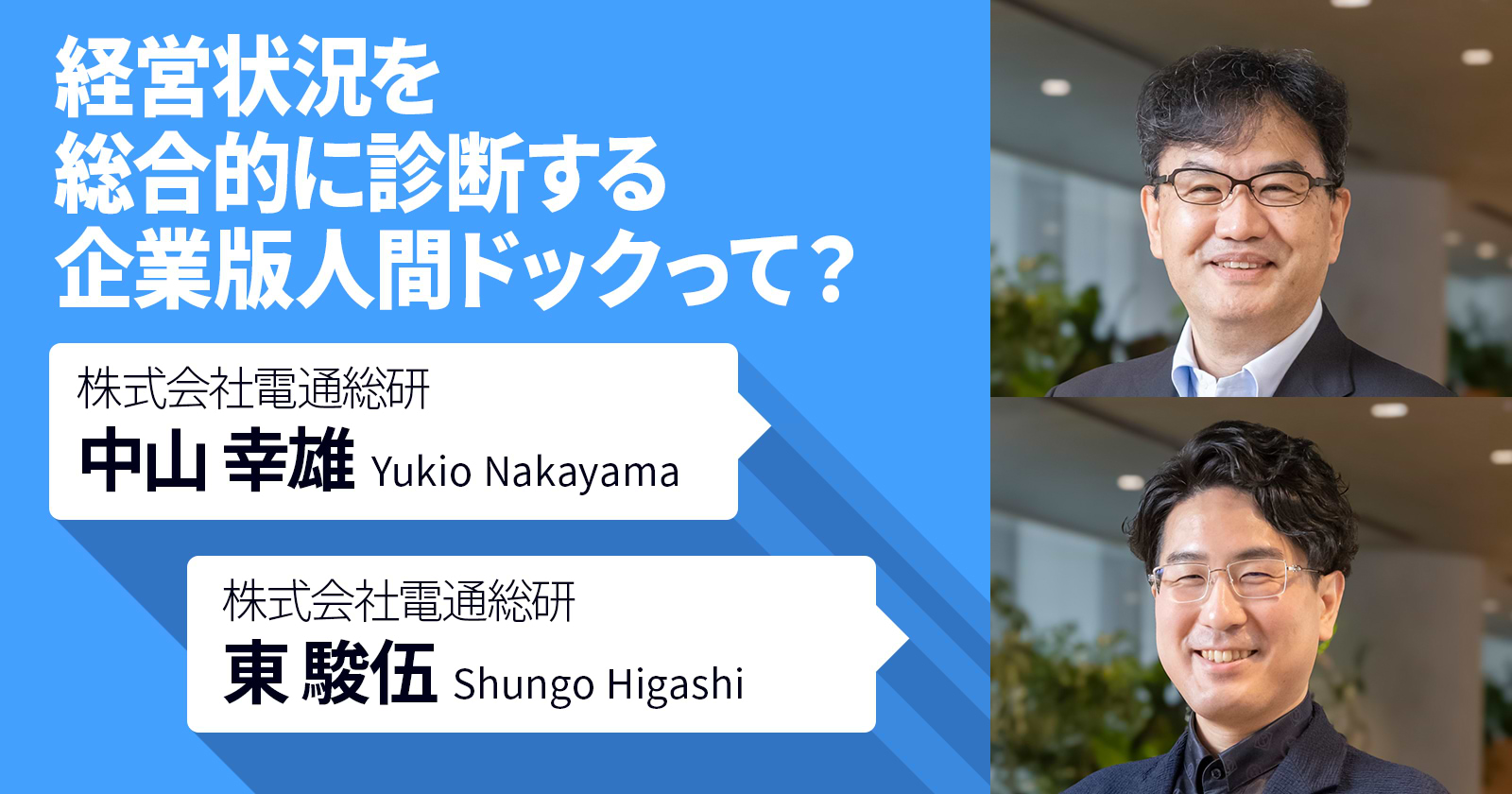近年、人財の能力を引き出し、企業価値の向上を目指す「人的資本経営」の重要性が高まっています。2023年には上場企業を対象に人的資本情報の開示が義務付けられ、非上場企業においても経営戦略と人財戦略の連動が加速しています。とはいえ、人的資本経営のメリットを理解していながらも、自社の現状を客観的に把握し、適切なアプローチを見つけられずにいる企業も少なくありません。
こうした中、株式会社電通総研 では、人的資本開示診断ツール「羅人盤 (らじんばん)」の提供を始めました。本記事では前後編にわたり、電通総研の中山幸雄氏と東駿伍氏に、羅人盤の開発背景や特徴、企業が今取り組むべき人的資本経営へのアプローチについて聞きました。
人的資本は、企業の新たな価値基準 Q.2023年3月期から、有価証券報告書の提出義務がある上場企業などに対してサステナビリティ情報開示の一環として人的資本情報の開示が義務化されました。情報開示の現状や、課題点をお聞かせください。
東: 人的資本は、企業が価値を生み出す源泉です。人的資本の情報を開示することで、その企業がどのような形で人財に投資しているのか、また人財に関してどのような経営上のリスクや課題があるのか、対外的に示すことになります。少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化する中、貴重な労働力に対してどのような取り組みをしているのか、後継者育成はできているのかなど、開示情報からは企業価値や将来性も浮き彫りにされます。
株式会社電通総研 東 駿伍氏 中山: 有価証券報告書に記載する人的資本情報は、企業によって記述量が大きく違います。欧米ではヒューマンキャピタルレポートを別途発行し、数十ページにわたって情報開示をする企業もありますが、日本ではそこまで取り組む企業はまだ少ないのが現状です。人的資本情報開示のガイドラインは国際標準規格ISO 30414がベースになっていますが、そもそも国際標準化機構(ISO)は欧州発祥です。人種や宗教の異なる人々が働く欧米ではダイバーシティ経営が根付いており、人的資本経営に関して日本に先んじているという背景もあります。
Q.現在、日本企業は人的資本についてどのようなリスクや課題を抱えているのでしょうか。
中山: まず採用と退職が挙げられます。具体的には、キャリア採用でスキルのある人財が集まらない、入社してもすぐに辞めてしまう、10年以上のキャリアを持つベテラン社員が退職し、ノウハウともども他社に流出してしまうといったリスクや課題です。
東: 企業の後継者不足も大きなリスク・課題です。いくら優れた人財がいても、社長次第で会社の経営状況は大きく左右されます。培ってきた技術をどのように継承していくのか、後継者育成はできているのか。企業の持続可能性を示すことも、投資家にとって安心材料です。
Q.他に、投資家が注目する人的資本の情報はありますか?
中山: 従業員のエンゲージメントは、労働生産性と相関関係にあると言われます。そのため、有給休暇取得率やテレワーク実施率など、エンゲージメントに関わるデータは投資家も注目しています。例えば今でいうと「AI」を使いこなす「AI人財」が多ければ、「この企業は伸びる」と投資家は感じる傾向があります。投資家に“未来”を感じさせる情報を開示することが、ポイントと言えるでしょう。
株式会社電通総研 中山 幸雄氏 「羅人盤」は企業版人間ドック Q.2025年2月、電通総研は人的資本開示診断ツール「羅人盤」の提供を開始しました。こちらはどのようなツールでしょうか。
東: 「羅人盤」をひと言で表わすなら、企業版の人間ドックです。人間ドックでは、さまざまな検査により健康状態を把握し、その結果に基づいて生活習慣を改善していきます。同じように「羅人盤」では、企業の人的資本経営について国際標準規格ISO 30414に基づいて診断し、投資家やステークホルダーが求める情報開示が、どの程度行えているのかを可視化することができます。さらに、ガバナンスなどのリスクについてもアセスメントできるツールとなっています。
Q.「羅人盤」では、どのようにして人的資本経営状況を分析するのでしょうか。
東: ISO 30414が定めている指標をベースに、チェック項目を設けています。これにご回答いただくことで、ISO 30414への準拠度や人的資本開示の成熟度などをマトリクスやグラフで可視化します。
羅人盤 分析結果のサンプルイメージ 東: リスクや成熟度の分析だけでなく、ISO 30414の認証取得支援、リスクマネジメント支援など、その次のアクションにつなげるためのソリューションも提供しているのが特徴です。
Q.「羅人盤」の独自性や、ネクストアクションにつなげられるポイントを教えてください。
東: 人的資本情報を可視化するだけでなく、顕在化していないリスクを分析し、次の一手を導き出せるのが「羅人盤」独自の特徴です。HUMAnalytics (ヒューマナリティクス)」をはじめ、人事戦略のコンサルティングサービスや人事領域のソリューションを幅広く提供してきました。例えば、「羅人盤」により労務分野にリスクがあると診断されたら統合HCMソリューション「POSITIVE (ポジティブ)」、セキュリティー分野で従業員のリテラシーを向上させる必要があるなら情報セキュリティー教育基盤「KnowBe4 」などと連携することも可能です。逆に、優れている点が多いのであれば、自社ブランディングや社内外への情報発信について、株式会社 電通 と協力して支援することもできます。オール電通により、ワンストップでご支援できるのが、強みです。
大航海時代、船を進める指標は海図と羅針盤でした。人的資本経営に取り組む企業を船に見立て、目的地へと導くのが「羅人盤」です。自社の現在地や課題を知るためにも、まずは「羅人盤」でアセスメントするのが第一歩。それは、人的資本の情報開示が義務化されていない中小企業にも、大きな効果を発揮するはずです。後編では、「羅人盤」の導入事例、今後のサービス拡張について伺います。