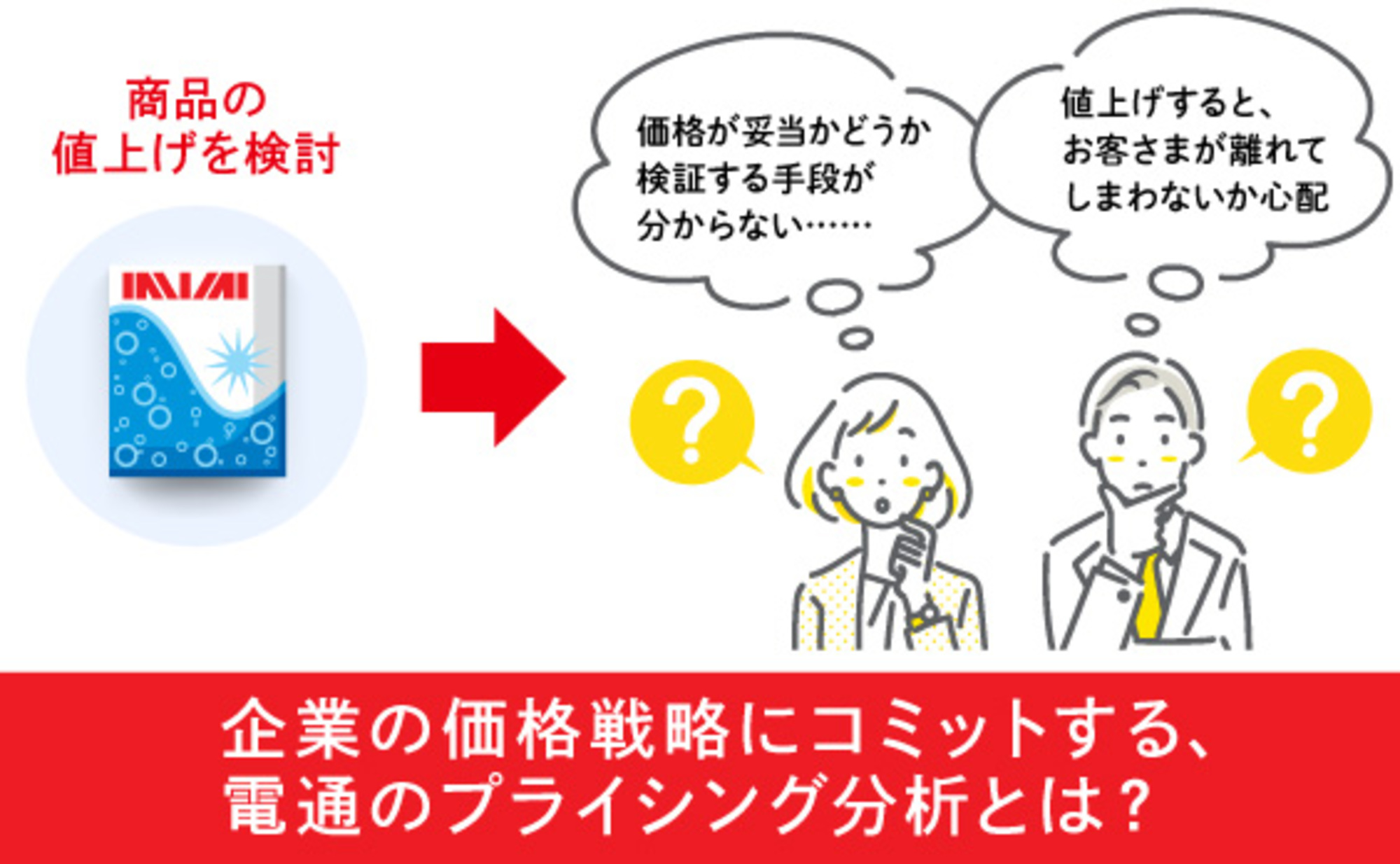原材料費や人件費などのコストの上昇により、モノの値段が上がっている昨今。消費者は「価格」に敏感になり、これまで以上に「商品やサービスの価値」を考えるようになっています。
本記事では、今の時代のプライシングについて考えながら、2025年1月にローンチした、電通の価格分析サービス「Marketing For Growth With Pricing(以下、MGP)」の開発の背景をお伝えします。
意見を交わしたのは、クライアントのマーケティング支援に長く従事している電通の統括執行役員・深田欧介氏と、MGP開発メンバーの香取拓実氏。「コストと利益をベースにした価格設定」から一歩踏み込み、「商品やサービスの価値に基づく価格設定」へ。MGPが目指すプライシング支援について語ります。

(左から)香取拓実氏:価格分析サービス「MGP」の開発・運営メンバー。前職のテーマパーク運営会社では、チケットの価格戦略に携わった。深田欧介氏:統括執行役員として、電通のさまざまなマーケティングセクション、約1000人のメンバーを束ね、クライアントのマーケティング支援を行っている。
今必要なのは、「価値に基づく価格設定」
深田:MGPの話をする前に、今の時代のプライシングの課題などを考えてみたいと思います。最初に、香取さんは、前職のテーマパーク運営会社で、チケットの価格戦略に携わっていたわけですが、その価格戦略とはどのようなものか簡潔に教えてください。
香取:私は、前職でマーケティングセクションに配属されたタイミングが、ちょうどテーマパークのチケット価格が大きく変わる時期でした。それまで一律の価格で販売されていたチケット価格を見直し、需要に応じて価格を変動させる「変動価格制」を初めて導入しました。
コロナ禍になってからは入場制限により、集客数を増やして売り上げを最大化することが難しくなり、お客さま1人当たりの売り上げを最適化する必要性がより高まりました。売り上げの中でもチケット価格は大部分を占めており、これまで以上に利益獲得の重要な要素になっていく過程を当事者として実感しました。
深田:変動価格制を取り入れた効果はいかがでしたか?
香取:繁忙期、中間期、閑散期で価格を変えました。以降も社会の状況やアトラクションの体験価値を踏まえながら価格を見直していき、適切に運営することができました。「正確な価格分析ができるのか」「新しい価格設定が消費者に受け入れられるのか」といったさまざまな論点を踏まえ、緻密に調査や分析を行った結果だと認識しています。
深田:なるほど。エンターテインメント業界や、観光・鉄道業界など、変動価格制を取り入れる企業は増えてきていますよね。「プライス」は、マーケティングの4要素(プロダクト・プライス・プレイス・プロモーション)の一つですが、今、どの企業も大きな悩みを抱えています。原材料高など、これまでにないコストの上昇が起こっていて、「どうしたら価格を上げられるのか」「どこまで上げるのが妥当なのか」「上げずにすむ方法はないのか」といった課題に直面しています。
香取:おっしゃる通りですね。これまでは、「コストが増えた分を単に価格に上乗せする」といった手法で価格設定を行うことも少なくなかったと思います。ですが、消費者個人の細かいニーズに対応した商品やサービスがあふれている昨今では、消費者が商品やサービスの価値を今まで以上に真剣に考えるようになっています。すなわち、企業のマーケティングにおいて、「価値に基づく価格設定」の重要度が増してきていることを強く感じます。
深田:電通は長年、さまざまな企業のマーケティング活動をサポートしてきたわけですが、現在、広告会社からIntegrated Growth Partner、すなわち、企業の事業成長を幅広く支援するパートナーになろうとしています。マーケティング領域においては、これまでプロモーション支援が中心でしたが、そこで培ったリソースをプライシングにも生かしていきたいと考えていました。香取さんたちからMGPの企画を聞いたときは、「これだ!」と思いましたね。
香取:MGPを企画したのは、これまで売る側の視点が比較的多かった価格設定の考え方から一歩踏み込み、人基点でも「心地の良い」価格設定を行う後押しができないかと思ったからです。
「消費者が想起している価格」を調べる、これまでにない価格調査を実施
深田:電通報読者に向けて、電通の価格分析サービス・MGPのポイントを改めて教えてください。
香取:前回の記事でも述べたのですが、ポイントは大きく3つあります。
1つ目は、個別のブランドについて、「消費者が想起している価格(RP:Recall Price)」と、「実際に販売されている価格(LP:List Price)」を比較できる点です。両者のギャップを可視化することで、自社ブランドはどこまで販売価格を変えられるポテンシャルがあるのかが分かります。
2つ目は、「消費者が想起している価格(RP)」と、実購入データを掛け合わせて分析することで、販売価格の変更が、需要・売り上げにどれくらい影響するか予測できることです。
3つ目は、「消費者が想起している価格(RP)」に寄与している価値を可視化できることです。商品には「情緒価値」と「機能価値」があり、それらの中で細かい価値に分かれます。消費者がどんな価値を強く感じているかはブランドによって異なります。それを明らかにすることで、納得のいく値上げが実現できると考えています。
深田:「消費者が想起している価格(RP)」に着目した点が、MGPの大きな特徴ですね。
香取:その点が、これまでの価格調査や分析と異なる部分だと考えています。「いくらならこの商品を買いたいですか?」といったことを聞く調査は今までもありました。ですが、値上げが続く今の時代では「安い方がいいに決まっている」という答えが返ってくる可能性が高く、適切な価格設計が難しくなってしまうと考えました。
私たちは最終的に、「商品の価格が、商品のどんな価値に結びついているか」を明らかにしたい。そのためには、この商品はいくらぐらいの価値があるか、消費者が想起する価格を調べる必要があると考えました。このような価格調査はこれまでにないと思います。
値上げは、消費者とのコミュニケーション力も求められる
香取:自社商品の値上げ幅を検討したり、シーズンごとに価格を変えるといったオプションを設計しようとした際に、競合との比較は意思決定する上で大事な要素になります。どうしても自社の調査で得られるデータだけだと限界がある。電通は、商品カテゴリーごとに多くのブランドの価格を調査・分析できる基盤があります。
深田:人基点で、他社のことも見ながら価格分析をしていくのですね?
香取:加えて、MGPは、分析結果をコミュニケーション領域まで一貫してつなげられる点も大きな特徴です。世の中を見ると、値上げする際に、リリースや広告を出して消費者とコミュニケーションを取った結果、そのコミュニケーションが受け入れられるものとそうでないものがあると思っています。ですから、リリースや広告の打ち方も考えなければなりません。そのときは、消費者のインサイトを考える力や、適切なコミュニケーションを実現する企画力が求められます。
深田:その点において、電通は、これまで広告会社としてプロモーション領域で培ってきたリソースがある。
香取:はい。人基点で、価格分析からコミュニケーションまで一貫して行っていくにあたり、電通のコミュニケーション設計力が生かせるはずです。
価格を理由に商品を買わない消費者を減らしたい
深田:最後に、MGPについて今後の展望を聞かせてください。
香取:商品やサービスを買わない理由に「価格」を挙げる消費者を減らすことが最終的に目指すところです。価格を理由に買わないということは、商品に価格以上の価値を感じてないということですから。そうならないように、価値にひもづいた価格設定ができる仕組みを整えていきたい。MGPのローンチは、そのスタートだと思っています。
深田:電通では、MGPとは別に、値上げ時代においても選ばれ続けるブランドの理由を探る研究を行っています。そこで出た一つの答えが、「エンゲージメント」でした。調査の結果、価格の安さを理由に買っていた人と、ブランドが好きで買っていた人では、値上げしたときの離脱率が大きく違っていた。だからこそ、「一度購入してくれた人に愛され続けるブランドを育てていきましょう」ということを結論にしているのですが、エンゲージメントこそが「消費者が想起している価格(RP)」に大きな影響を及ぼしているんだと感じます。
香取:たしかに。エンゲージメントの高いブランドの商品であれば、値上げしても離れない顧客が確実に存在するとは思っています。一方で、そのことに気づかないまま数十年が経過している企業も少なくないはずです。中長期で消費者とのエンゲージメントを作り、その基盤を強固にするという点では、CRMを見据えて、中長期的に適切な価格設定を支援していけるよう、MGPの中身をブラッシュアップしていきたいですね。
深田:AI時代に突入し、統合的な分析が簡単にできるようになると、過去の需要・供給データを基にしたダイナミックプライシングがより普及していくはずです。しかし、いきなり価格を上げると全く売れなくなることも起こり得る。プライシングは、供給が増えたら価格を下げ、需要が増えたら上げればいいといった単純なものではないということですね。適切な価格設定に向けて、需要と供給のマッチングを統合的に分析して、データドリブン、AIドリブンにコンサルティングを進めていく必要がある。それが、MGPの先に求められていることかもしれません。
今は原材料高に起因する価格設定に頭を悩ませている企業が多いですが、今後、それこそAIが普及してくると、業務効率化がどんどん進んでいく。そうすると、人件費などは安くなる。つまり原価が安くなった分、商品の価格は下がって当然という世の中になっていくかもしれません。
香取:さまざまな変動要素がこれから出てくることを考えると、ますますプライシングに関して、企業が向き合わなければいけない場面が増えていくはずです。そうした際に、MGPが企業を支援する一助になれば幸いです。