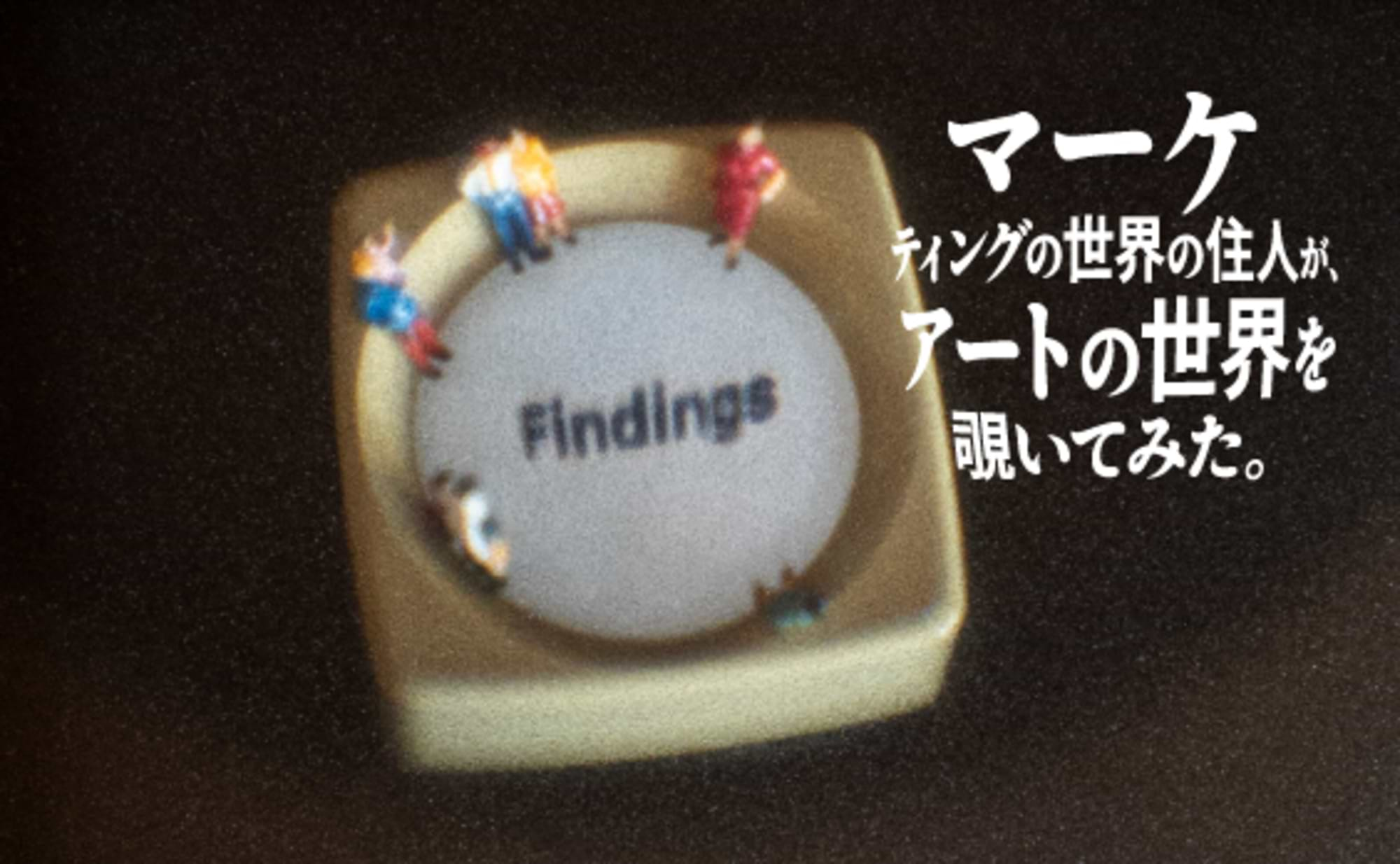【Reflection】

「あの展覧会、素晴らしかったですね!」
そんな雑談を、社会課題を背景に制作している旧知のアーティストである林田真季さんとしていた。この熱量を雑談からもう一歩だけ進めてみたいと思った。思い切って連絡を取ってみた。

舞台はアーティゾン美術館(東京・京橋)。
「ARTIZON」とは、「ART」と「HORIZON」を組み合わせた造語だそうだ。実際に足を運んでみると、約3000点のコレクションを背景に、教科書でも見たことがあるようなとても有名な作品をリアルで目にすることができる。
今回、林田さんとの雑談のきっかけになった展覧会「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展(2025年6月24日-9月21日)を担当された学芸員の上田杏菜さんに、アートの地平を押し広げる一つの象徴的な事象、「オーストラリア美術コレクション」のお話を中心に伺った。より深い対話になるよう、聞き手は林田真季さんにお願いした。
美術館に行くと価値観が揺さぶられたとか、景色が変わったとか、そんな言われ方をよく耳にしたりもするが、その舞台が東京駅から歩いてちょっとのところに、本当にあるのだ。(宮川裕)


◆
──私は今回の展覧会を観る前と観た後で、「アボリジナル・アート」と聞いて思い浮かぶものががらりと変わりましたが、「アボリジナル・アート」とは何を指すのでしょうか?
オーストラリアの先住民の人たちの芸術であるというのが大前提にあります。そして「アボリジナル・アート」と呼ばれる場合は主に視覚美術をさしています。伝統の部分と現代社会を反映している部分の二つの側面があり、両方をオーバーラップさせて作品を制作している作家もいれば、どちらかを追求している作家もいます。
オーストラリアの先住民の文化は、現存する世界最古の文化形態の一つと言われています。彼らは文字を持たなかったので、芸術的・身体的な表現を用いて文化を紡いできました。そういった部分がアートとして表出したものが伝統の側面にあたります。たとえば儀式のときに身体に施すボディ・ペインティングのデザインを絵画のモチーフにしたり、「ドリーミング」という神話の物語を砂に描いたりするのですが、砂絵の模様が絵画作品になっている場合などがあります。
現代社会の反映としてのアボリジナル・アートについては、イギリスの植民地としてたどってきたオーストラリア社会の歩み、その歴史が強く影響しているところがあります。先住民の人たちが経験してきたできごとを現代の作家はもう一度見つめ直して、アボリジナルの歴史としてもう一度つなぎ直す、語り直す作業をしている。現代社会において彼らが日常的に経験していること、ポジティブであってもネガティブであっても、それを着想源として作品に反映しています。伝統の面と、歴史と地続きの現代社会が反映された面が作品になっている、それがアボリジナル・アートの全体像だと思っています。

ノンギルンガ・マラウィリ《ボルング》2016年、天然オーカー・樹皮、石橋財団アーティゾン美術館
© the artist ℅ Buku-Larrŋgay Mulka Centre
──アボリジナルのバックグラウンドを持つということは、オーストラリアではどのように捉えられているのでしょう?
オーストラリアでは、作家へのレジデンスプログラムやフェローシップなどで、アボリジナルのバックグラウンドがないと応募できないものがあったりします。キュレーター職でも、アボリジナルのルーツを持っている人が優先される場合もあります。当事者の目線を大事にするという側面もありますし、オーストラリアは多文化主義を掲げているため政策的な面もあります。今やアボリジナルのバックグラウンドしかもっていない人はあまり多くはなく、ヨーロッパ系やアジア系などのミックス・ルーツをもつ人のほうが多いと思います。自分の中に複数のルーツがあったとして、どのアイデンティティを打ち出すかといったときに、アボリジナルのルーツを選択する作家はけっこう多いですね。
また複数のルーツ、言わばいくつものレンズを複層的にかさねて作品を制作し、それによって面白いレイヤーを生み出していたりします。やっぱり、こういうことがアートが可能にする語りの豊かさなんだなと思います。いろんなストーリーを引き出しながら、一つの作品にそれらを要素として入れることができる。現地に行くと、そういう作家は本当に多く活躍しています。
──アーティゾン美術館のオーストラリア美術のコレクションは、アボリジナル・アートの比率が高いことがユニークですよね。また、その中でも女性作家の作品を多く収集している印象を受けました。そこにはどのような意図があるのでしょうか?
オーストラリアの現代美術は女性作家の活躍が顕著であり、その多くが先住民のバックグラウンドを持っています。当館がオーストラリア美術のコレクションを拡充していく中で、必然的に女性作家の作品が増えていき、現在ではコレクションの約7割が女性作家によるもので、その全員がアボリジナルをルーツに持っています。オーストラリア美術を収集し始めたころは、作家の性別にこだわることなく、良い作品を集めていこうというところからスタートしていたのだと思います。
そこから、研究や展示活動などを通じて作品の背景やテーマをより深く掘り下げていく中で、現在のコレクションのかたちが形成されてきました。「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展は、これまでの収集活動と研究の成果でもあります。
イワニ・スケースの《えぐられた大地》という作品を本展で展示しましたが、これは2024年に新収蔵しました。微量のウラン酸化物が含まれた42個の吹きガラスからなる作品で、オーストラリアのウラン資源採掘とそれによって引き起こされる環境問題をテーマにしています。ウランはもちろん核兵器の原料となる元素であり、 それは冷戦期にスケースの祖先の土地で行われたイギリスによる核実験と深く関わります。1956年から1963年にかけて行われた核実験は、いまだにそこに戻ることはできない状況をつくったわけですが、それはオーストラリアでもあまり語られてこなかった歴史です。日本は唯一の被爆国ですが、作品鑑賞を通じてこういったオーストラリアの歴史にも思いを寄せる、共感することができるのではないか。つまりわれわれにとってアボリジナル・アートとは、異国の文化を受容するためだけのもの、ではないと考えています。時代も場所も違いますが、そういったものを超えられるのがアートの持つ力なのだと思っています。今も世界で核武装による脅威はずっと続いていますが、作品や展覧会を通じて、そこに対する問題意識を持ち続ける、そういうふうに続いていくといいなと。

イワニ・スケース《えぐられた大地》2017年、ウランガラス(宙吹き)、石橋財団アーティゾン美術館
© Courtesy the Artist and THIS IS NO FANTASY
また、この展覧会におけるコレクションの活かし方として、マーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリの《私の祖父の国》を展示の最後に持って行ったというのがあります。5階から4階に降りると、印象派や日本の近代洋画などを中心としたコレクションを紹介する展示室になるのですが、一気にモダンの作品群の世界になります。ガボリの作品は抽象的な絵画なので、4階とうまくつなぐ意図もあり、最後に展示しました。彼女のコミュニティは伝統的な視覚表現をもともと持っておらず、またガボリは西洋の美術教育も受けていないため、作品に描かれるイメージは作家自身の内側から出てきた独自の表現です。アボリジナル・アートはこういうもの、という固定したイメージがあった人にとっては、そこをきれいに打ち破ってくれる作品だと思います。私たちが持っている固定観念を解放してくれる、そんな作品も当館のコレクションです。

10月からは「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」展を開催予定です。ジャム・セッションは、現代作家が当館学芸員と協働して当館のコレクションを選び、作家自身の作品とともに新しい見せ方を提示する企画です。その一つとして、参加作家である山城知佳子さんが選んだ作品が、ジンジャー・ライリィ・マンドゥワラワラの《四人の射手》でした。土地創造神話(ドリーミング)の物語が具象的に描かれている作品で、当館のいろいろな企画でアボリジナル・アートの多様な表現を紹介できることは、コレクションとして作品を収蔵していることのメリットです。
さらに、オーストラリア美術の話でいうと、2026年1月には、リンディ・リーという作家の屋外彫刻が完成する予定です。両親が中国からの移民ということで、彼女はいわゆる移民2世のオーストラリアの作家です。この作品は、当館の屋外彫刻プロジェクトの作品の一つです。ご期待ください。
──アーティストとキュレーターは厳密には役割が違うとはいえ、私はキュレーターも広義な意味での「アーティスト」だと思っています。上田さんはキュレーターとしてどのようなことを心がけているのですか?
キュレーターとして心がけていることは、まず、先人たちがいて自分がいる、ということ。印象派などの展覧会に比べると日本でのアボリジナル・アートの展覧会って本当に数は少ないんですが、私がすごく影響を受けた2008年のエミリー・カーマ・イングワリィの展覧会も、それを開催しようと尽力した方々がいました。アボリジナル・アートの魅力を日本に紹介しようとしてくださった方々が、世代を超えているんです。もちろんまだあまり日本で紹介されていない分野であるのは事実ですが、実は地道に活動をしている美術館や研究者の方々がいて、自分はその延長線上に今いるだけと思っています。同様に、当館のアボリジナル・アート・コレクションを鑑賞して興味を持ち、この分野の展覧会をやってみようと行動を起こす人が未来に現れるかもしれない。徐々に醸成してくる、根付いてくるものだとすると、長いスパンで見ていくものなのかなと思っています。

また、幅広いコレクションを収蔵している美術館のキュレーターとして、他の分野のコレクションについても知識を深め展示活動をおこなっています。他分野の作品を知ることで、自身の専門分野を相対的に見直すことができ、新たな視点を得るきっかけにもなります。その上で、自分の専門性、私であればオーストラリア美術だったりしますが、そこで最善を尽くしてやる。たとえば、イワニ・スケースの《えぐられた大地》を収集候補として提案したとき、まわりは必ずしももろ手を挙げて賛成、というわけではありませんでした。というのも、当館では絵画以外のアボリジナル・アートを収蔵するのは初めてで、しかも素材がガラスという点も、新たな試みだったからです。そのため作品の背景や価値を共有するのにいつもより時間がかかりました。今回の展覧会で初めて展示したのですが、「これは収集してよかったね!」と納得の声が上がるようになりました。作品はシンプルな見た目で美しいため、来場された方々は、きれいという印象だけで終わってしまうのかな、もう一歩先のところまで掴んでくれるのかな、と少し不安な部分がありました。でもSNSなどで反応を見ていると、深く掴んでくださっている方がけっこう多くて。思った以上に来場してくださった方々はテーマをきちんと受け止めてくれている、というのが素直な実感です。
──最後に、ビジネスパーソンがアートに触れることについて、上田さんのお考えを聞かせていただけますか?
私は、アートは私たちが生きる社会の一部だと思っています。アートの先には、社会があって自分がいる。アートを見ていると、その先に今の自分が見えてくる。今の自分はどういう状況なのかとか、そこから先どうなりたいのかとか、そういうことをリフレクションとして戻してくれるのがアートだなって感じています。
ビジネスパーソンにおけるアートと考えたとき、アートという新しい知識を増やしてビジネスパーソンとしてのボキャブラリーを増やす、そういうことよりも、自分の内側に何か戻してくれるもの。そう思うと、そんなに敷居が高いものと思わず、ふらっと美術館に行って、素の自分のままで作品と向き合って、そこで素直に対話してみてはどうでしょうか。作品との対話だけど、多分その先には自分との対話がある。アートにはそういう見方もあるということを、ビジネスパーソンの方にも知ってもらえるといいな、と思っています。

◆
自分になじみのない歴史や文化、社会課題を背景とするアート作品ならびに展覧会は、それらを通してただ「知る」だけではなく、自分たちの生きる社会や文化と照らし合わせて思いを巡らせるものという考えに、私は強く共感しました。アートという手段でメッセージを伝える醍醐味はここにあるように思います。(林田真季)

画像制作:岩下 智
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

上田 杏菜
石橋財団アーティゾン美術館
学芸員
石橋財団アーティゾン美術館学芸員。 早稲田大学第一文学部総合人文学科美術史学専修卒業、アデレード大学大学院(オーストラリア)にて学芸員・博物館学修士課程取得修了。南オーストラリア州立美術館インターンを経て現職。

林田 真季
アーティスト
東京を拠点に活動するビジュアル・アーティスト。現代の消費活動にまつわる社会的課題をリサーチし、そこにフィクションや主観的推測を織り交ぜながら、さまざまな技法を用いた写真作品や、主に写真を媒体とするインスタレーションとして表現する。同時に、写真を消費財として捉えることで、その環境との相反する関係にも目を向け、デジタル時代における写真メディアの物質性や複製性を問いかける。近年では、植物や自然素材を活用した写真技法に注力している。 2007年関西学院大学総合政策学部卒業。2023年ロンドン芸術大学ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション MA Photography 修了。第17回 shiseido art egg入選。