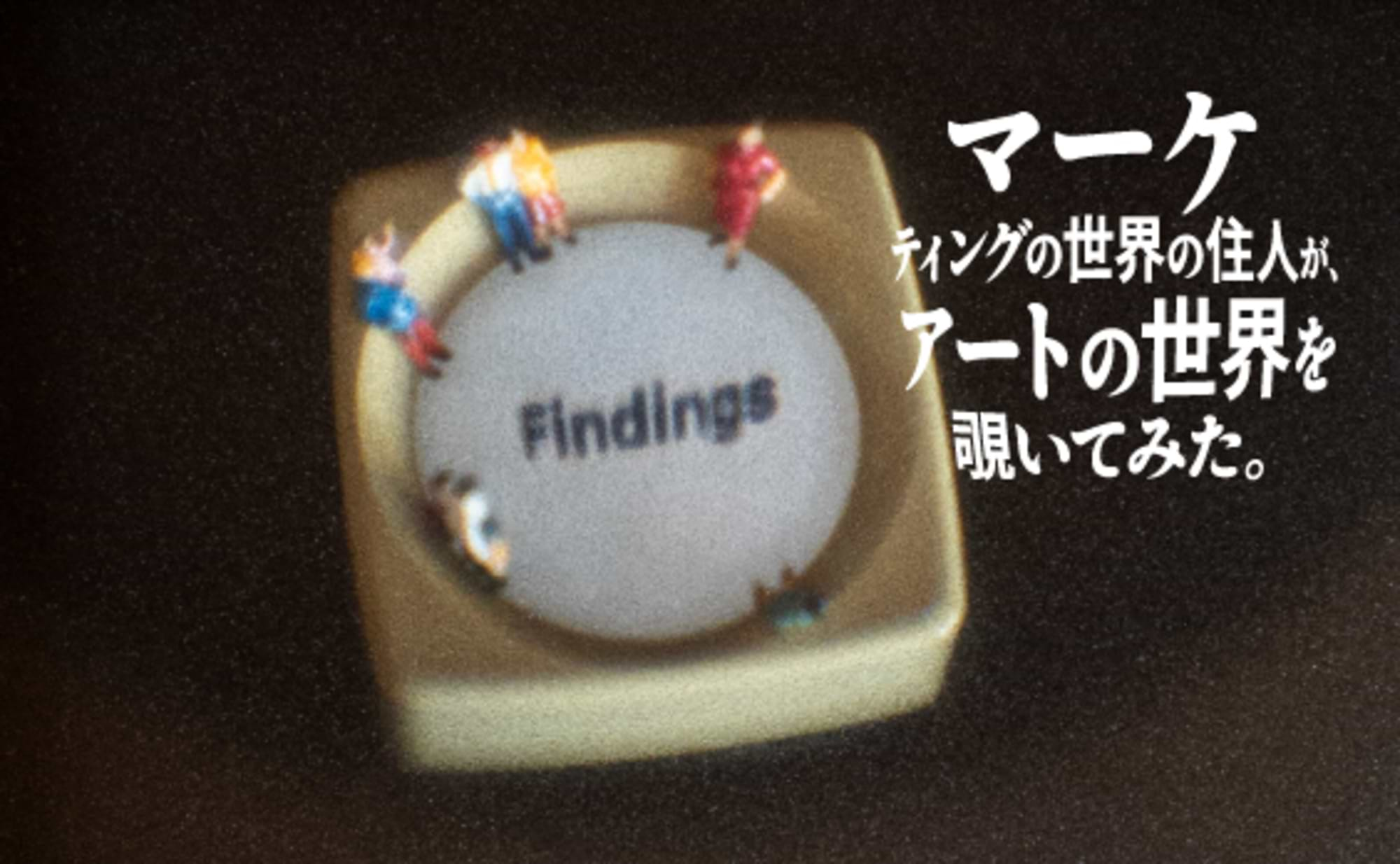電通・宮川裕による連載「マーケティングの世界の住人が、アートの世界を覗いてみた。」
今回対話をともにしたのは、アート教育実践家の末永幸歩さん。
2020年のこと。僕は丸善で黄色い本を手に取ってみた。表紙をめくると大原美術館所蔵のクロード・モネ「睡蓮」が目に飛び込んでくる。最初から最後まであまりに素敵な内容だったので、ちょっとだけ勇気を出して著者にメールを送った。今や22万部のベストセラーとなった『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』の著者、末永さんとの出会い。以来、末永さんに仕事を依頼したり、末永さんのワークショップの現場を見学させてもらったり、なんだかんだで数年が経った。今回、末永さんの母校の武蔵野美術大学を二人で訪問。そこでの内容を記しつつ、もう少しはみ出して僕の目に映った末永さんのことを書き留めておきたいと思った。
協力:武蔵野美術大学 美術館・図書館
◆21世紀に生まれた1つのアート作品
『13歳からのアート思考』では、「自分だけのものの見方で世界を見つめ」「自分なりの答えを生み出し」「それによって新たな問いを生み出す」ことこそアーティストが作品の制作過程でしていること、と定義している。20世紀の巨匠アーティストたちが生み出した6つの作品を中心に、アート作品がどうやって生まれてきたのか、その核心は何なのか、ワクワクする文章で語られている。
書籍のジャンルで言えばまさに「アート・美術」なのだと思うが、ビジネスパーソンである僕にとってもおもいっきり関係のある内容だと思った。またこの本には、末永さんの知見もふんだんに盛り込まれており、「末永さんという人」の魅力にも自然と目がいく。そして巻末にはこんな一文がある。
おわりに、いつも無計画で手探りの教育で、しかしいつも私の好奇心を最優先してくれた家族に感謝の気持ちを伝えたいと思います。家族が私に与えてくれたのが最高の教育だったとよく思い返しています。
この「おわり」につながる「はじまり」のお話、いわばエピソード0を記したい。インタビューで末永さんが語ったほぼそのまま記載するので、是非まるまる味わっていただきたい。
子どもの頃、かなりユニークな家庭に育ったんじゃないかな、と思います。父親は、ベースとしてはイラストの仕事をずっとやっていたんですけれど、とにかく手当たり次第いろんな活動をしている人だったんです。パントマイムだ!と思ったら独学で練習を始めてしばらくすると観客を呼んでショーをやっちゃうとか、タップダンスだ!と思ったらそれ以前に専門的なダンス経験もないのにショーの中で披露しちゃうとか。油絵作品をいっぱいつくって個展を開いたり。家族でキャンプに行ったら、この石いいなって持って帰ってきて、そこに絵を描いて売ったり。65歳過ぎた最近では漫才を始めたそうです。何でも一回形にしてみる、という感じ。そんな姿を間近に見ていた子ども時代だったので、「人生、何でもできるんだな」っていうのは植え付けられたと思います(笑)。
自宅に来る父の友だちもユニークな人が多くて、手品がとても上手な人がいたり、ジャズ演奏が本当に上手なフリーのピアニストとか、占いが得意な人、父のプロデューサーを名乗る人がいたり。ゴミの埋立地建設に抗議して多摩の山奥に住み込んでいる人もいました。子どもの私はその人たちの本名も本職も知りませんでしたが、楽しかったです。雑多な環境でしたけど、良い原体験だと思っています。自宅に父が使っていた画材道具だったり芸の小道具があったりして、思い付いたら何かができる環境だったかな。
そんなこんなでお金はなかったのですが、母は市区町村の瓦版なんかで無料の体験とかをいろいろ探してきてくれました。田植え体験とか、田舎でのホームステイとか、キャンプ体験、劇団、人形劇鑑賞とか。探せば無料でいろいろあるんですよね。そういう体験をさせてくれたことは有り難かったなって思っています。その甲斐あって(笑)、私はすごく好奇心旺盛に育ちました。勉強好きでどの教科も「5」ばっかりという感じでした。図工や美術だけが大好きだったわけではなく、いろんな活動の中に、何かをつくることとか表現することも入っていた、そんな感じですね。
高校生になった時にすごく海外に行ってみたくなったんです。両親も海外に行けるような余裕は全然なくて、行ったことがなかったんですよ。なので海外は自分にとっては本当に未知の場所。日本と違う場所があるということ自体がすごい不思議な感じがして。それでスーパーでアルバイトして、1年間くらいで30万円貯まって、10日間のショートステイでイギリスに行ったんですが、それがまた良い経験になって。今自分が持っている考え方とか、ものの見方、常識とは、全然違うことがあるんだ!と気付き、それを発見するのがとても好きでワクワクしました。それが海外の文化なのか、アートなのか、という違いはあっても、ものの見方の多様性に惹かれる感じは、今にもつながっていると思います。
この海外経験が大きかったので、大学を考える時には美大は選択肢になく、語学や国際関連の勉強ができる大学に行きたいと思っていました。私は勉強が好きな子ではあったものの、受験のために情報収集するとか計画を立てるとか、そういうことはまったくしなかったんですよ。赤本を開いたこともなく、模試を受けたこともなく。両親も、「まあ、あなただったらいけるでしょ」という放任で。無謀に国立1本で受けたらダメだったんですね。それで浪人することになっちゃったんですよ。で、浪人したら予備校に行ってがっちり勉強するじゃないですか。そんな発想すらなくて、バイトをしたり図書館で勉強したりしながら1年間過ごしていたんです。そして案の定、また受験に失敗して。
2浪生活が始まった頃、母が見かねてとんでもない提案をしてきて。「子どもの頃からつくることが好きだったよね。藝大を受けてみたら」と急に言ってきたんですよ。「うまくいかなくても、この時期に制作に打ち込んだ経験は、きっとそれだけでも糧になるよ」と。東京藝大は最高峰で、当時は数十倍の倍率でした。でも自分もその気になっちゃって。2浪目にして進路変更したんですね。画塾に急に入ってきて、そこの先生もちょっと驚いていたと思います。でも、石膏デッサンなんかもぐんぐん上達し、藝大の一次試験は通ったんです。ただ、すでに2浪目ですから絶対今年決めなきゃっていう年だったのに、滑り止めのことを考えるの忘れちゃっていて。気付いた時には私立の美大の願書の締め切りがほとんど過ぎてたんですよ。
そんな中、まだ間に合ったのが、ここ武蔵野美術大学の芸術文化学科(芸文)だったんです(笑)!運良く合格しました。しかしこんな形で芸文に入ったので、ウキウキして上京してきた新入生たちの中で自分はみんなより2年も年上かぁ、と斜に構えた感じでした。芸文は、多方面で活躍している方の講演会やさまざまなアート・プロジェクトなど、いろんな面白い講座や課外授業もあったりしましたが、ほとんど参加していなくてあまり意欲的な学生ではなかったです。ただ、制作には打ち込んでいました。
決して褒められない大学生活だったんですけど、今考えてみると芸文にいられて本当に良かったなって思っていて。自分が『13歳からのアート思考』に書いた、「アートって花(=作品)だけじゃないよね、自分の興味のタネから探究の根を伸ばしていくことにアートの本質がある。その結果として咲く花の形って、いろんな表現であり得る。絵画だからアート、彫刻だからアートというわけじゃなくて、文章も音楽も、もっと言えば形のない思想とか活動だって、根元にその人の興味のタネや探究の根があるのであれば、アートの花だといえる」っていうのは、まさに芸文の考え方なんですよ。芸文は比較的新しくできた学科で、武蔵野美術大学で、絵画とかデザインとか分かれていた学科をつなぐような存在。それこそ、プロセスにフォーカスして、学生が生み出す表現はいろんな形でいいという学科だったので、私はもろに芸文の思想に影響を受けているわけです。芸文にいたことは、今、大きな糧になっているなって思います。
2年も浪人したという負い目があったからか、資格でもなんでも取っておいたほうがいいという浅はかな思いがあり、教職は取っていたんです。4年生になって教員採用試験も受けました。そうしたら奇跡的に受かって。採用試験もかなりの倍率があった時代でしたので、受かるとは思わなくて、パソコンで合格発表を見た時に「何かのミスで自分の受験番号が一瞬表示されたのかも」と思い、すぐに写真を撮ったほどです。証拠として(笑)。あと、就活もしていました。美大出身ということでデザイナーになりたい気持ちも強くあって、憧れの洋食器メーカーの内定をもらいました。ということで教員と会社員の二者択一になりました。
ゼミの先生に神妙に相談したところ、「どっちでもいいんじゃないですか」って言われたんですね。適当な答えだなぁ、と思ったんですけど、続きがあって、「でも一旦選んだら、選ばなかったほうはきっぱり忘れて、選んだ道に進むといいと思います」って言ってくれたんですね。その時はあまり響かなかったんですが、今考えると良いメッセージをいただけたなと思っていて。この先、選択する場面はいっぱい出てくるので、計画段階でどっちが良いのかとこねくり回すのではなく、自分の気持ちに素直になって、流れに従って出たとこ勝負で、というふうに受け取っています。最終的に教員を選びましたが、後から振り返ってみると、小学校の時も中学校の時も卒業アルバムに「学校の先生になりたい」って書いてありました。しかも物語形式で(笑)。やっぱりすべてはつながっているんだな、と思いました。
中学校の美術の先生になったんですけど、もう天職だと思うくらいすごく楽しくて。きっと学校の先生になった多くの人は、そういう実感を持つんじゃないかな。教員(大人)同士の時間もありますが、基本的には子どもたちとずっと関わって、もう今までの人生にないくらい泣いて笑って怒ってっていう熱いものが中学校にはあるので。出会いと別れを繰り返しながら、あっという間に数年間が経ちました。でも、もちろん楽しいことばかりじゃなくて、教育方針であったりとか、悩んだり葛藤することとかもありました。それでも全体を通して教員になって良かったと思っていました。
でも数年経った時に、絵画制作をもっとしたいなと思うようになり。自分自身の制作活動が大学卒業後にプツっと途切れちゃったな、と。今しかないという気持ちになって、教員の職を辞めて制作に打ち込もうと思い、大学院に行くことにしました。東京学芸大学の修士課程に絵画の研究室があって、そこに入りました。ですが、入ってみると自分の気持ちが絵画制作には向かなくなっていて。そもそもアートっていうものに対しての疑問が出ちゃったんです。何のために絵を描くのか?アートっていったい何なんだろう?って思ったりすると、全然絵が描けなくなっちゃったんですね。
でも良かったのはその当時の学芸大学の修士課程には、ワークショップの研究をされている先生方が多くて、自分も自然とそこに目が向くようになり、子ども向けの造形ワークショップをするようになったんですよ。大学院で知り合った仲間と一緒に地域の子どもたちを集めてワークショップを開き、そこでの気づきをディスカッションしたりして。まさに実践研究で、自分にとってすごく学びになりました。今まで、学校教育だけしか見えていなくて、考え方が凝り固まっちゃっていたんですが、学校外のワークショップについて考えることによって解きほぐされていくのを感じて。仲間たちも大学院まで進んでしまった人たちなので、言う事、考える視点、見る視点がユニークなんですよ。それまでとは異なる角度から教育を捉え直す良い経験になりました。
その当時、中学校教諭の職は辞めたものの、中学校や高校の非常勤(時間講師)として週に数日、美術の時間だけで教えるという形で教鞭を取っていました。そこで大学院のワークショップで得た柔軟な考え方を学校教育にも自然と生かしていくようになって、そこから授業づくりがとても楽しくなりました。その中で、『13歳からのアート思考』で書いた、「アートは花だけではない。自分の興味のタネと、探究の根こそが本質だ」という考え方も自分の中で認識しました。中学校の教諭時代は、やっぱり「花(=作品)づくり」ばかりになっていたことに改めて気付けた。花以上にタネや根にフォーカスするような授業の形があってもいいと思った。そういう問題意識から、『13歳からのアート思考』に著したような授業がつくられていき、美術が苦手・好きでないと言っていた子どもたちが「自分なりの答え」を自信を持って表現する姿が見られるようになって、良いサイクルができていました。
家でもパートナーと美術の授業や、現代アートについていろいろ話していたんですね。それこそブリロ・ボックスの話とか。そうしたらパートナーが、「アートのことは全然興味なかったけど、面白いね」って言ってくれて。「こういう授業だったら受けてみたかった。自分みたいなアートと無縁のビジネスパーソンも、こういう形だったら楽しめると思う」と。それでその気になって。中学校の生徒だけじゃなくて、社会のいろんな人に授業を届けたいなという気持ちが沸いたんです。
ちょっと矛盾するようですが、自分はやはり表現することが好きなので、アウトプットをしたいという気持ちもあるんです。そこで、本にしたんです。『13歳からのアート思考』の3分の1くらいのボリュームでしたが、ちゃんと表紙もつけて、本の形に仕上げました。いわばプロトタイプ。出版のお話とかがあったわけではないんですけど。自分なりの「作品」をつくったわけです。考えを形にしてみたら、そこからいろんなご縁が転じてきました。まず、教育系の出版社に原稿を送ったら、編集者さんから連絡をもらい会うことができました。会えただけでもすごいと思いつつ、「内容は面白いんですけど、イチ美術教師が書いた本だと読む人が限られちゃうので、ビジネスの有名な方とタッグを組んで共著にしたらどうですか」って言われたんです。自分の作品だと思ってつくったものを今から共著にするっていうのは自分にとっては許容できず、その日は家に帰って悩みながら、でもやっぱり違うなと思ってお断りした直後に、もう一つのご縁が舞い込んできました。
佐宗邦威さんという、後に『13歳からのアート思考』の巻末に解説文を寄稿してくださった方がいるのですが、仕事のつながりで私のパートナーが「家族が書いたんです」と、プロトタイプを渡してくれたんですよ。そうしたら佐宗さんが「その日に自宅のお風呂で一気読みして、めっちゃ面白かったです。自分の担当編集の方に送りました」って連絡をくださって。佐宗さんがダイヤモンド社で本を刊行された直後だったということで、編集者の藤田悠さんに渡り。私の計画していないところで、出版社に自分の書いたものが辿り着いたわけです。藤田さんも一気に読んでくださったそうで、すぐにご連絡をくださいました。すごく不思議なご縁で、佐宗さん、藤田さんのお二人に出会えた。そこから最終的な形にするのには、そのプロトタイプからさらに1年間くらい執筆を続けることになりましたが。
こうして21世紀に、『13歳からのアート思考』という作品が生まれたのである。

◆7つ目のクラス

末永さんの半生を知ることは意義深い。ベストセラーの著者だから「副読本」的にその半生も覗いてみよう、というのもなくはないが、僕はちょっと別の受け止め方をしている。
『13歳からのアート思考』では、
かつて、西洋美術が花開いたルネサンス期の画家たちには「目に映るとおりに世界を写しとる」という明確なゴールがありました。それ以来、彼らはおよそ500年あまりにわたって、3次元の世界を2次元のキャンバスに描き出す技術を発展させてきたのです。
しかし、19世紀に発明された「カメラ」が20世紀に普及していったことによって、彼らを取り巻く状況は一変しました。絵画による「目に見える世界の模倣」は、写真撮影という技術革新によって容易に代替されてしまったからです。
しかし、これによってアートが死に絶えることはありませんでした。
マティス、ピカソ、カンディンスキー、デュシャン、ポロック、ウォーホルそれぞれによる、「20世紀に生まれた6つのアート作品」を主な題材とし、6つのクラス(授業)を時系列で展開していく形で書籍は構成されている。
「目に映るとおりに描くこと」「遠近法的なものの見方」「具象物を描くこと」「アート=視覚芸術」「イメージを映し出すためのもの」……20世紀のアーティストたちは、過去のアートがとらわれてきたさまざまな常識を乗り越えようとしてきました。
そして、ついにウォーホルの《ブリロ・ボックス》に至っては、そうした格闘が行われてきた「アートという枠組みそれ自体」にもヒビが入ることになったのです。
これはアート、これはアートではない、と分断する壁。壁は、権威的なものとそうではないものとを振り分けるということでもあり、権威の側はやがて聖域ともなり得る。しかし!そんな因習的な壁あるいはわれわれの心の中にある壁は、実は幻想だったのでは?そう気付かせるに至った20世紀のアート作品、アーティストたちの功績を、末永さんは6つのクラスを通して分かりやすく表現している。6つの作品に代表されるそれぞれのイノベーションは、今振り返ってみるとあたかもつながっているようで、そのつながりはなんとも美しい。言わば歴史の「Connecting the dots.」。そこに立ち現れたのは、だだっ広いフラットな世界。
フラット。つまり誰しもが参加できる。不当な圧力のない自由な世界。と言えば聞こえは良いが、後ろ盾のない厳しい世界、とも言える。心細くもなる。
そして、アートの歴史とは違うところでの、大きなうねりもある。社会の複雑性が高まり、これまで正解とされてきたことが通用しにくくなった。僕らの不安はちょっとずつ募っていった。そこにきて、2022年あたりから急激にAIが身近になった。AIに任せていけば安心かも、と少しだけ気持ちが軽くなった。しかし、別の不安が顔を出し始めた。AIが幅を利かせた世界で、人は、僕は、何をしていけば良いのだろう?心細くもなる。
そこで僕らの背中を押してくれるのが、末永さんによる提案。「われわれには、アート思考がある」。ここ数年、傍から末永さんの活動を覗かせてもらっている中で、末永さん自身がアート思考を実践・体現しているのだと思い至った。末永さんの存在こそ最良のテーマだと思えた。つまり、僕にとって「7つ目のクラス」。末永さんの半生を知ることは、生きた歴史をリアルタイムで学ぶことでもあり、だからこそ意義深い。
そして末永さんの探究の根は、まだまだ伸びていく。

今書いているのは、「感性」についての本です。『13歳からのアート思考』では、アーティストが作品を生み出す過程でしていることは3つ、と書きました。「自分だけのものの見方で世界を見つめ」「自分なりの答えを生み出し」「それによって新たな問いを生み出す」。そこに共感してくださった学校、企業、さまざまなところから講演やワークショップのご依頼をいただいていろんな現場に関わっていく中で、思ったことがあります。企業で研修をさせていただくと、皆さん「自分だけの答え」を出すことに目が向いていて、とにかく新規価値を創造しなきゃ、これまでにはない答えをつくらなきゃ、というところに注目されていると感じました。かたや学校では今、探究学習が取り入れていることもあって、まず「新たな問い」を立てることが大事だと生徒たちに指導している場面も多く見かけ、問いの立て方を教えてほしいと言われたりもします。
これらの状況に対し、私は3つのうちの最初の「自分だけのものの見方」を徹底しなきゃいけないと思ったんですよ。逆に言うと、答えをつくる方法とか問いを立てる方法なんていうのはなくて、自分だけのものの見方さえできてれば、答えや問いは勝手に出てくる。そして、自分だけのものの見方で世界を見るっていうのは、観察眼を鍛えましょうとかそういう話じゃなくて、「感性」だと思うんですよね。感性を開いて、世界からのいろんな働きかけを受け入れることが、自分だけのものの見方で世界を見つめることにつながるというふうに考えています。感性とは、扉のようなイメージです。そこが閉じていたらこの世界にいろんなものがあったとしても受け取ることができない。逆に、扉を開くことができれば何かを探し出そうとしなくても、勝手に入ってくるんだと思う。入ってくるものを受け止める。そうすることによって初めて「自分だけの答え」が出てくるわけです。
感性の扉を開くためのヒントを、アーティストと子どもから見出す、という構成の本です。アーティストは、まさに自分だけのものの見方で自分の答えを創造している人たちなので、作品や生き様の中にヒントを見出すことができる。それに加えて、子ども。小さい子どもたちは自然に世界を自分なりのものの見方で捉えているので、子どもの視点を想像することによって大人も感性の扉を開くヒントを得られると思っています。
私は大学院時代にも造形ワークショップで子どもと関わる時間が多かったですし、子どもの工作番組の監修を3年間に渡ってさせていただいているんですが、全国のいろんな子どもたちの表現した作品に触れたり、制作プロセスを見ることができて、そこから得た視点もたくさんあります。ただ、一番大きいのは自分自身の子どもと直接触れ合い、一心同体で感じ取ったこと、親だからこそ分かることがあるなっていうのはしみじみ感じていて、そんなことをもとに書いています。
だだっ広いフラットな世界を前に、僕らあらゆる人びとの感性が開かれた時、結果として末永さんの作品は、自然な形で「20世紀に生まれた6つのアート作品」に連なるんじゃないだろうか。その時僕らは、「歴史のドットがまた一つ、つながったんだぁ」という言葉をもらす、そんな気がしている。
◆「悔しい。」
末永さんは寛容な人、ひらたく言うと気が長い人だと僕は思っている。詳細は書かないが、一般的な感覚からいってイラっとしたりクレームを入れてもおかしくない場面を何度かお見かけしたが、末永さんは声を荒げるでも顔をピクつかせるでもなく、それどころか場を和やかにしていた。盤面をひっくり返していた。その度に、肝が据わっているなぁ、と感じた。
今回のインタビューで末永さんの半生を知ることで、ああ、なるほど、こんなふうに価値観形成されてきたからか、と妙に腑に落ちた。まさに「Connecting the dots.」。そしてもう一つ知ったことがある。
2020年までは中学校の先生だったんですけれど、本を出版してから180度活動が転換したというか、本当に多方面で教育や美術に関わることができています。講演やワークショップとか、プロジェクトでの協業とか、新しい教育の取り組みとか、いっぱいアウトプットする機会があるんですけれど、そのアウトプットが自分にとって毎回インプットになっていて、アウトプットとインプットが同時にできているような感じ。この5年間で書いたノートが何冊もあって、本を読んで勉強したことや取り止めもないアイデアなど、びっちり書いてあるんですよ。この5年、すごい頑張っていたんだな、と自分で思いました。アウトプットするということは、同時にそれくらいインプットをしているんだなと思います。
他方、活動が広がって、難しさもいっぱい感じました。たとえば、フリーランスとして働いているのですが、公務員や会社員として働くことと比較した時、福利厚生のある組織に所属していた方が安泰だという価値観は根強い気がします。会社員こそ「しがみついてでも頑張れ」と言われますが、フリーランスについては「なにかあればすぐ崩れちゃうような働き方でしょ」という認識が存在していて、まして、家庭や子育てに犠牲を払ってまで力を注ぐようなものじゃないと捉えられてしまうことが、すごい悔しいなって思うんですよ。そんなことないじゃないですか。
また、自分は5歳の子どものお母さんなので、母親としてまた女性として活躍することの難しさもすごく感じています。活動が小さいうちは気になりませんでしたが、その規模が大きくなるにつれて顕在化していった気がします。もう21世紀になんだからフリーランスも全然ありでしょ、とか、昭和じゃないんだから女性が仕事するのも普通でしょ、という考え方がある一方で、現実的にはまだまだそこに対するネガティブなものの見方があるな、と。小さい子どもを持つ女性が働こうとする場合、子どもを保育園に預けて子どもを持たない人とほぼ同様にフルタイムで働くか、それか仕事を辞めて子育てに専念するか、二者択一になりがちです。事実、多くの会社のシステムも、保育園の制度もそうなっています。「週3だけ保育園に預ける」というのができません。
私の場合、子どもとの時間が自分にとっての大きなインプットにもなっているので、子どもと過ごす時間を大切にしたい。他方、どんどん広がっていく仕事や活動にも全力を注ぎたい。人一倍仕事に打ち込むことで、その先の景色を見てみたい。その両方を取ろうとすることに対する社会からの否定がある。どっちかを選ばなきゃいけない。でも、従来の二者択一に限らない在り方があってもいいじゃないかと思う。ものすごく大変ですが。でも、もし過去に遡って選択できるとしても、今の在り方を選択したい。
大学院で子どもの造形ワークショップを通した研究をしていたというのもあり、私にとって子どもと過ごす時間は勉強でもあるんですね。子どものありのままの姿を観察して何かを学び取るっていうことを研究でも実践していたので、今も自分の子どもに対してそういう向き合い方をしていて、お金を払ってでも得たい時間だと思っています。仕事の時間が思うように持てずに焦りを感じることも多々ありますが、そんな時には子どもとの時間が自分のための大事なインプットの時間だと捉え直すようにしています。
『13歳からのアート思考』という末永さんの本(作品)から、声が聞こえてきた。今回インタビューをするまでは、聞こえてこなかった声だった。切実な声。末永さん本人が社会の不公平や不寛容に物申す、改善を促す、そんなことを目的に書いたのではまったくないと思われるが、この作品には、そして末永さんの生き様には、不公平や不寛容を指摘できるようになるための社会の土壌づくり、そんな作用があると思った。22万部というポピュラリティとともに、「結果的に」軽やかに世間に流布している。副産物でありつつも、本質的だと思った。
二者択一だなんて、誰が決めた?
アートと非アートを分けていた壁。それが幻想だと気付いたフラットで自由な世界で、感性を開き本当の意味で自由を獲得できるか。アーティストになる可能性を秘めた僕ら一般人の手にそれが委ねられた時、改めてこの末永さんの「悔しい」という言葉や状況に目を向けたい。あらゆる人に目を向けてほしい。

◆いまを生きる

冒頭でも書いたが、『13歳からのアート思考』は大原美術館所蔵の「睡蓮」からスタートする。大原美術館のエピソードに対し、きっと末永さんは特にお気に入りというか、深い敬意を払っているのだろうと思った。美術史家で元大原美術館館長の高階秀爾さんと末永さんを引き合わせられるのは僕しかいないと勝手に思い、2022年に二人の対談の場をセットした。探究の根が伸び、つながるような、活気のある場になった。
その対談の締めくくりに、アートがわれわれにもたらすものとは?と二人に投げかけてみた。末永さんは、
美術の授業を終えて、学生たちにレポートを出してもらったり、話を聞いてみたりするんですね。そうしたら、自分がつくった作品についてのことじゃないなんてことも。かなり離れていて。自分の幼少期の体験を書いていたりだとか、最近自分が実は引っかかっていたこと、違和感を持っていたことを書いている学生がいたり。あと、日常の中でこの一連の授業のことを思い出しながら歩いていたら、今まで当たり前だと思っていたものの面白さとか、ばかばかしさに気付いたとか。今まで見過ごしていたものが異様に目に付いたとか。そんな感想がたくさんありました。こんなことから、こうやってアートに関わっていくことによってもたらされるものっていうのは、「あれ?」っていうふうに、物事に対して引っかかりを持つような「感性」というか、心なんじゃないかなとも思うんですね。自分なりの物の見方をして、自分の答えをつくっていくような、その「駆動力」になるのかなって。いつも「あれ?」って引っかかって疑っていくことなんじゃないかな、と。それを繰り返していくことによって、徐々に自分の問いが出てきたりとか、自分が考えていきたいなって思うような主題が生まれたりとか、そんなことにつながっていくんじゃないかな。それがアートというものなんじゃないかなと考えました。
高階さんは、「今の末永さんのお話に尽きるので、私はそれを繰り返して言えばいいと思うんですけど」と笑わせ、場を和ませた。「最後に付け加えるとすると、アートは生きる喜びを与えてくれる。アートっていうのは本当に全人間的なもの」という言葉で締め括った。
末永さんは、自分の中の違和感を見過ごさず、そして行動を起こしてきた。幼い頃から、ブレずに、極々自然に。まさに全人間的に。
そして今、末永さんは新しい環境へ飛び立とうとしている。

画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?
著者

末永 幸歩
アート教育実践家・アーティスト
武蔵野美術大学 造形学部 卒業。東京学芸大学 大学院 教育学研究科(美術教育)修了。 中学校の美術教諭としての経験をもち、「制作の技術指導」「美術史の知識伝達」に偏重した美術教育の実態への問題意識から、アートを通して「自分なりのものの見方」で「自分だけの答え」を探究する授業を行ってきた。 2020年にアート教育実践家として独立。全国の学校・企業・社会の様々な場での講演やワークショップの企画実施、書籍執筆など、多岐に渡る活動を通して生きることの基盤となるアートの考え方を伝えている。 Eテレ「ノージーのレッツ!ひらめき工房」監修、文化庁「文化芸術の充実・改善に向けた検討会議」委員、品川学藝高等学校リベラルアーツコース アドバイザー、九州大学大学院「アート思考」講座担当、東京学芸大学 非常勤講師など兼任。 著書『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)は4ヶ国語に翻訳され、22万部超のベストセラー。 プライベートでは一児の母。「こどもはみんなアーティスト」というピカソの言葉を座右の銘に、日々子どもから新しい世界の見方を教わっている。