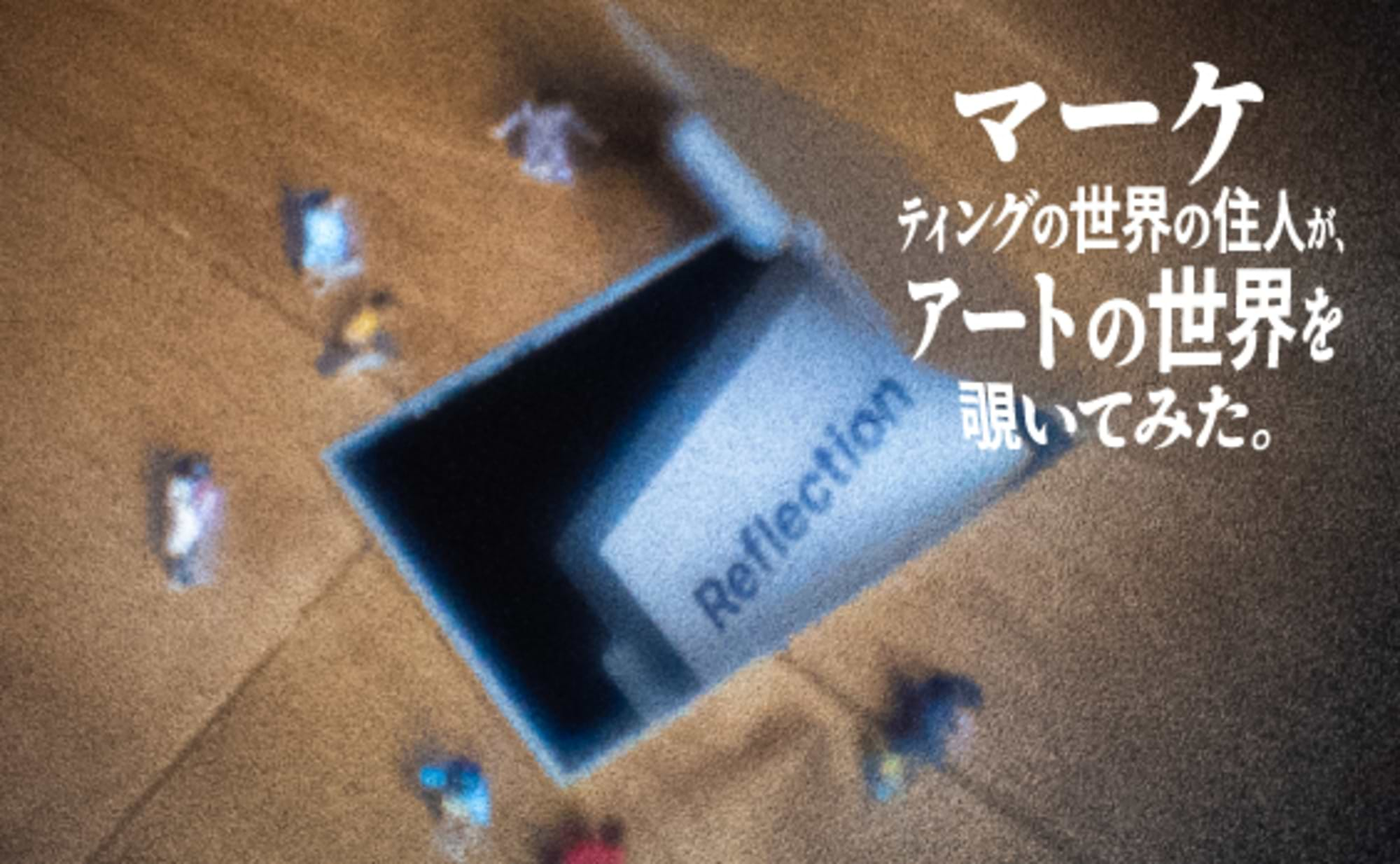ときめいた教科書。学生時代ではなく、割と近年の話。日本文教出版の「高校美術」はただならぬ一冊らしい、という噂を耳にし、初めて教科書供給所というものに足を運び購入した。なんと言ったらいいんだろう。教科書だというのに、めくってもめくっても宝石箱。今でも開けばときめいてしまう。
ゲルハルト・リヒターの「オーバーペインテッド・フォトグラフ」というシリーズの作品「27. April 2015」がこの教科書の表紙。ちなみに、美術手帖によるアンケート「読者が選ぶベスト展覧会」で2022年のトップは、東京国立近代美術館の「ゲルハルト・リヒター展」だった。リヒターは1932年生まれのドイツ人アーティストで、表現手法というかシリーズが複数あり、シリーズごとにものすごい数の作品を生み出している。教科書の表紙になることが一つのベンチマークになるのかは分からないが、今の時代を生きる巨匠リヒターは、未来へと続くアート、その長い歴史に名を刻む存在であることは間違いないらしい。
「写実的な絵画」ではなく、「写真のような絵画」の「フォト・ペインティング」というシリーズがあることを知り、僕は写実的であることと写真と見まがうことの違いに、混乱しつつ、お見逸れしつつ。こういう表現に至る現代アートの歴史は、なんだか恐ろしいなぁとも思う。なんて高みなんだろう。
◆
ところで、「トムとジェリー」に出てきそうなチーズ、と聞いただけで画が浮かぶ方はいるだろうか。三角柱のような塊で、大きめの気泡?みたいな穴がけっこうあるのが特徴。なんだったら、ジェリーがその穴をトンネルみたいに通っていた気さえする。幼いころの記憶をたどっているので自信はない。僕自身はチーズがそれほど好きではないせいかもしれないが、あんなチーズを現物では見たことがない。でも、トムとジェリーに出てきそうなチーズを、「いかにもチーズ」と認識している自分がいる。不思議。
ある日、ショッピングモールをふらふらしていて、ケーキコーナーを通り過ぎた。視界に入ってきた、いかにもチーズ!?先を進む下半身と、「ケーキコーナーなのに、いかにもチーズ」に目を釘付けにされた上半身。コケそうになった。近寄って見ると、これはチーズケーキか。いかにもチーズ、をチーズケーキでもって(つまりチーズを原材料に)模倣というか再現していた。うーん、ややこしい。奥が深い。目が離せない。
アートの世界では、トロンプルイユという手法が流通していることを知った。いわゆる「だまし絵」。だまし絵なら馴染みがある。床から水が流れ落ち、落ちた先は当然その床よりも下にある床、のはずが、床を目で追っていくと段差も勾配もない同じレベルの床だった。そんなマウリッツ・エッシャーの絵本を、子どものころ病院かどこかの待合室でよく見た気がする。割と最近の錯視体験は、カップヌードルミュージアムとかのフォトスポット。絵じゃないから、だまし空間?あれはトリックアートという言葉のほうがぴったりの、和気あいあいの大衆性。
◆
また、ある日は国立競技場に向かってふらふら歩いていた。ちょっと時間が早いな、そうだ、この辺にギャラリーがあった気が。以前ジュリアン・オピーの展示を見に行ったMAHO KUBOTA GALLERYに寄ってみよう。ガラス張りのギャラリーから、一輪ずつの花の絵が見えた。きれいだなぁ。たっぷりとした絵の具。その、ねちょっとした塊から、写実的とはまた違う形で、しかし花としか言いようのないものが再現されている。そんな絶妙な筆跡。映画「線は、僕を描く」で横浜流星さんが墨の筆でびゅーっと線を引いて、見事に竹とかを描いていたが、あんな感じで一発なのに迷いなく潔く花(花びら)の形状が描かれていた。なんて巧みなんだろう。
この花を生み出したのは、武田鉄平さんという現代アーティスト(話がまったく逸れてしまうが、存命かは問わず海外のアーティストは呼び捨てなのに、存命の日本人にはさん付けしてしまう自分がいる。すみません)。その花は、光でテカっている所と影になっている所があるので、平面の絵画だけどかなり凹凸というか絵具の盛り上がりがあるのだろう。本物の花ではないことは誰が見ても明らかなのに、そこには確かに花の端麗が立ち現れている。美しさをシンプルに感じずにはいられない。
花と言えば、個人的な思い出も多少はある。それだけじゃなく自分の外の物語、たとえば「カリオストロの城」で手品師のようにルパンが出した花、「幽遊白書」で軀が雷禅に手向けてほしいと幽助に渡した花、「はなかっぱ」でスランプで咲かなかった花。自分の内のものでも外のものでも、物語であればあるほど感傷を引き連れてくるようだ。
しかし、無地の背景に佇む、たっぷりとした絵の具から生まれた端麗な一輪は、不思議と僕の湿っぽい感情とは結び付かなかった。自分とか、思い出とか、物語とか、そういうのが投影されることなく、ただ美しさが際立つ。「世界に一つだけの花」も「赤いスイートピー」も頭の中で鳴ることはなかった。尾形光琳が突き詰めたカキツバタのデザイン性や、千利休が想像させた朝顔。そんなもののほうが近いように思えた。とにかく、毅然とした存在感。
20年くらい前に、一度だけプロダクトデザイナーの深澤直人さんとの対話の機会に恵まれた。作品集に書かれていた「デザインの輪郭」のこと。「ありそうでないもの」のこと。深澤さんの言葉自体が僕の内側の輪郭にすっとハマり、今でもちょうどよい圧力で僕の中にとどまっている(あまりに憧れの人だったので、作品集にちゃっかりサインをしてもらった)。
美しさに「輪郭」があるのだとすれば、武田さんの花みたいなんじゃないかな、と思う。
◆
事件はギャラリーに入った後に起こった。キャンバスに近付くと、異変に気付く。ねちょっとした絵の具で描かれているはずなのに、絵の具の盛り上がりが見えない?凹凸がない?たっぷりの絵の具で描いた後、それをしっかりとしたライティングのもとで撮影した写真作品、でもないことはさらに近付いて見てすぐに分かった。ケチャップ並みの光沢や、FIRST TAKEな筆運びなんかを、細かく細かく筆で描き込んでいるのであった。写真のような再現を、手仕事でやっている。
写実的な絵画というのはよくあるが、武田さんは写実する対象を「たっぷりの絵具で描かれた、抽象度を高めたモノ(花)」に設定していた。和気あいあいのトリックアート体験とは異質の、僕にとって本当に事件だった。なんて企みなんだろう。
「CM上の演出です」みたいに、「○○上の○○」という状況がある。もしくは「○○の中の○○」。武田さんの作品は、花を写実的に再現したものではなく、いかにも絵具の塊に見えるので、「絵画上の花」というよりも「絵画上の絵具」といったところか。しかし、あの美しさは花の本質のようにも思えるので、「絵画上の絵具上の花の美しさ」。そして、きれいだなぁ、で終わるところをトロンプルイユであると気付いたとき、この美しさは描くことで生まれたのだ、描くことでしか生まれなかったのだとあらためて思い知らされる。描くという人間の行為の至高に驚く。彫刻上でも、マンガ上でも、アニメ上でも成立しない、「描くことを描く」。
絵、絵具、花、美しさ。いろんなレイヤーの存在。めくっていくように、異なる質の層に意識を向けていく。順に丁寧に見ていくと、積層に自分自身がしみしみと浸透していくようだ。静的なはずの「見る」が、気付けば動的になっている。そして層から層へとダイナミックに行き来していると、目にしているこの作品に対する信頼みたいなものが強まっていった。ハマってきたのかな。
「視覚」は浸透していくプロセスとともに、洞察、先見、展望、そして理想の姿とも訳せるのだとすると、鑑賞者としての自分にとどまらず、ビジネスパーソンとしての自分とかも含め、もっと広く、もっと等身大な自分にとって、とても本質的なことだと気付かされる。視覚のその先。こんなに豊かな営みだったとは。

Photo by: Keizo Kioku
武田鉄平氏プロフィール
画像制作:岩下 智
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?