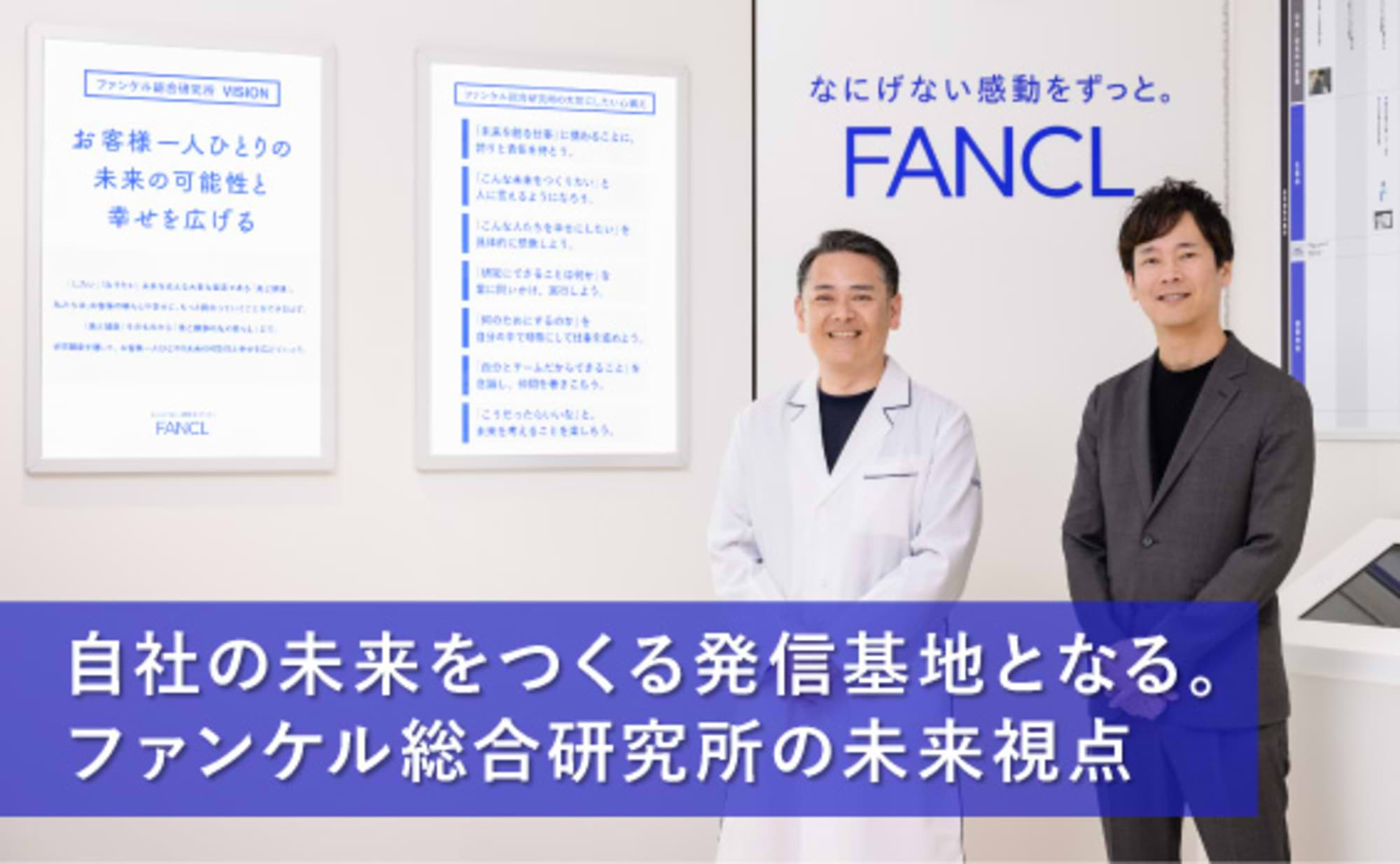キユーピー マヨネーズ100周年。ワクワクする「未来のマヨネーズ」の描き方
1925年に誕生し、長年日本の食文化を支えてきた「キユーピー マヨネーズ」は、2025年に100周年を迎えました。この節目にあたり、キユーピーでは未来志向の価値創造を目指し、電通未来事業創研が提供する「Future Craft Process」や「Expert Idea 500」を取り入れたワークショップを実施しました。
「Future Craft Process」とは、「未来の社会実態」「未来の生活者インサイト」の2つの視点から未来の企業価値をつくり出すアプローチ手法(詳細はこちら)。「Expert Idea 500」は専門家から500以上のアイデアを収集し、それを基に新しい事業の領域やコンセプトを導き出すサービスです(詳細はこちら)。
今回は、実際にワークショップに参加したキユーピー 経営推進本部 経営企画部 部長 髙田典明氏と、マーケティング本部 調味料戦略部家庭用チーム 中村友美氏、電通未来事業創研の伊神崇氏、吉田健太郎氏による座談会を実施。ワークショップを振り返りながら、未来を起点にした商品・サービス開発の可能性や、企業としての進化のあり方についてお話を伺いました。

誕生から100年。進化を止めず未来に向け新たな価値創造を目指す
伊神:まずは、2025年にキユーピー マヨネーズが100周年を迎えられたこと、誠におめでとうございます。100周年に向けてさまざまな取り組みを進めてこられたと思いますが、その背景や具体的な内容についてお聞かせいただけますか?
中村:ありがとうございます。キユーピー マヨネーズの100周年のテーマは「still in progress.」。これには「進化は止まらない」という意味が込められています。1925年のキユーピー マヨネーズ発売以来、100年もの間、多くのお客さまにご愛顧いただいておりますが、私たちはこの節目を、進化を止めることなく次の時代へと歩みを進める機会と捉えています。その想いのもと、未来に向けた多様な施策を展開しております。

伊神:まさに「進化」という点で、今回私たちとご一緒させていただいたワークショップにつながっているわけですね。今回「未来のマヨネーズ」をテーマに検討されたのは、どのような背景があったのでしょうか。
中村:100周年を機に未来に目を向けたときに、「どのような未来をお客さまと共に創っていくか」という考えがありました。生活者の皆さまが将来どのような暮らしを望んでいるのか。その姿を見据え、キユーピーとして何ができるのかを考えることが出発点でした。
実は90周年の際にも同様に取り組みを行いましたが、この10年で時代は大きく変化し、お客さまのニーズも変わってきています。これからも生活者の皆さまの食と健康に向き合い続けるためにも、90周年からさらに進化することが100周年においての課題と考えました。
髙田:90周年のときには、近い将来の課題解決に重点を置く「Issue Driven」の考え方が中心でした。しかし100周年に向けて、課題解決型ではなく価値創造型の「Vision Driven」で進めるべきだという考え方にシフトしています。次の100年を見据え、未来志向のアプローチに切り替えて取り組みを進めてまいりました。
未来のペルソナ像を描くことで生まれた544のアイデア
伊神:今回のワークショップには、マーケティング、広告宣伝、研究開発といった多様な部門の方にご参加いただきました。「Future Craft Process」で、まず3日間にわたってワークショップを実施し、「マヨ食によって健康でウェルビーイングな暮らしを送っている未来の人物像(=Future Persona)」を定義するところから始まりました。このアプローチについてはいかがでしたでしょうか?

髙田:未来のペルソナを設定したうえでアイデアを創出するというアプローチは、これまで経験がなかったので、当初は「本当にアイデアが出てくるのだろうか?」といった不安があったのが正直なところです。しかし、実際に進めていく中で、多くのアイデアが次々と生まれて驚きましたし、最終的には当初の想定を大きく上回る成果が得られたと思います。
私たちはこれまで、メインターゲットを子育て世帯を中心としたファミリーライフステージ層に設定することが多かったのですが、あえてさまざまなライフステージにある幅広いペルソナを描き出して考えることで、未来を見据えた新たな視点を得ることができました。

伊神:その後、ワークショップで制作した20のFuture Personaをもとに、「Expert Idea 500」を使い、外部有識者とともに未来のマヨネーズに関するアイデア創出に取り組みました。そこから評価の高いアイデアをさらにブラッシュアップし、最終的に11の新商品やサービスのコンセプトが生まれました。
髙田:外部の視点を積極的に取り入れながら未来を構想するプロセスは、新たな気づきも多くあり、非常に有意義でした。弊社でも50~60件ほどのアイデアを出していたのですが、外部有識者の皆さまからも多数のご提案をいただき、最終的には544ものアイデアが集まりました。自分たちでは考えつかなかったようなアイデアがたくさんあって、見ていてとてもワクワクしました。
吉田:ワークショップを通じて、本当に多くのアイデアが生まれました。多くのアイデアが集まっていく過程で、意見を出しやすい雰囲気が自然と生まれたように感じています。
中村:そうですね。出てきた意見を否定せず、前向きにブラッシュアップしていく姿勢があったからこそ、より自由に意見を出しやすい雰囲気が醸成されたのだと思います。電通の皆さんにはそうした雰囲気づくりをしていただいて、本当にありがたかったです。

伊神:今回出てきたアイデアは、キユーピー マヨネーズの過去から未来を語り合う100周年記念社内イベント「ミライマヨファーム」で展示してらっしゃいました。その中でも、特に印象的だったアイデアを教えてください。
中村:「パーソナライズ・マヨドレッシング」は、ボタン一つでその日の気分や体調に合った自分専用のマヨネーズやドレッシングを作れるフードプリンターというアイデアでした。10年後という少し手触り感のある未来に向けたアイデアだったこともあり、イベントで展示した際には、来場者の方々から「これ欲しい!」という声が最も多く寄せられました。

「食でコミュニケーション カラーおえかききマヨペン」や、養鶏場の一口オーナーになることから始まり、自分好みのマヨネーズをつくる「Myニワトリのタマゴで作るマヨ!Kewpie Craft Mayo Fan Club」なども印象的でした。どちらも、個食化の進行や人口動態といった社会の潮流を踏まえたアイデアで、今の時代ならではのニーズや価値観に対応した提案でした。
伊神:どちらのアイデアも、「楽しさ」を通じて食の可能性を広げるような視点が非常にユニークでした。これから私たちがマヨネーズとどのように向き合っていくのか、その可能性を象徴する取り組みだったと感じています。
吉田:「カラーおえかききマヨペン」のアイデアが生まれた背景には、子どもの個食というテーマがありました。現代では、一人っ子世帯やシングルファーザー・シングルマザーのご家庭も当たり前になってきて、子どもたちが一人で過ごす時間も今後さらに増えていく可能性があります。そうした中で、子どもたちが一人の時間でも楽しく過ごせるようにするにはどうしたらいいか。
そこでマヨネーズが「一人での食事も楽しくする存在になれたら」、という発想が今回のアイデアの出発点になりました。未来の幸せをどう作っていくのかという視点で考えていただいたのが、すごく良かったなと思いました。

「Kewpie Craft Mayo Fan Club」についても、バリューチェーンに対する意識の高さが感じられました。単なる商品アイデアにとどまらず、生産の最適化や安定供給のあり方まで踏み込んだ発想がありました。その視点は個人的にも非常に重要だと感じました。

中村:バリューチェーンは、弊社の中でも重要なキーワードになっています。不確実性の高い状況下においては、持続可能な商品開発にとどまらず、それぞれのサプライチェーンやバリューチェーンの中で競争していくことが求められます。いかにバリューチェーンの各段階において付加価値を創出していくか。「Kewpie Craft Mayo Fan Club」はその視点を象徴するアイデアだったと感じています。

「栄養、おいしさ。まとめてふりかけ。完全栄養マヨフレーク」も、非常にユニークなアイデアでした。イベントでは研究開発チームに協力してもらい、実際にフレーク状のマヨネーズを試作・展示したのですが、来場した社員にサンプルの香りを体験してもらうと、マヨネーズそのものの香りがすることに非常に驚かれました。世の中の食の価値観が変わっていく中で、こうしたアイデアもぜひ実現に向けて進めてほしいという熱を帯びたコメントがたくさん届きました。
固定観念をなくし、キユーピー マヨネーズの持つ可能性を広げることができた
伊神:今回のワークショップを通じて、「未来のマヨネーズ」というテーマのもと、さまざまなアイデア創出に取り組んでいただきましたが、実際にご参加いただいた皆さまからの反響はいかがでしたでしょうか?

中村:社内でも、キユーピー マヨネーズに改めて真剣に向き合ったことで、キユーピー マヨネーズの持つ可能性や魅力はまだまだ広がっていくと感じられたと話しています。また、ワークショップには多様な部門からメンバーが参加しましたが、こうした幅広い領域のメンバーが一堂に会し、マヨネーズについて語り合う機会はこれまであまり多くなかったように思います。そうした意味でも、部門を越えてじっくり対話できたことは、非常に有意義でした。
中村:キユーピー マヨネーズを「時代を超えて守るべき要素」、そして「時代の変化に応じて進化すべき要素」に要素分解したうえで、丁寧に議論したことで、しっかりと本質を捉えて議論できたと思います。参加メンバーからも「このまま終わらせたくない」「実現に向けてしっかり取り組みたい」といった前向きな声も多く聞かれました。実現に向けたステップの足がかりとして、大きな成果だったと思います。
未来志向のアイデアで、人々の食卓に幸せを届ける提案を
伊神:今まさに新たな進化の過程にあるキユーピー マヨネーズですが、これから先の10年、20年という中長期的な視点で、どのような進化をお考えでしょうか。

髙田:今回、100周年に向けたさまざまな取り組みを進める中で、改めて「未来」「グローバル」「挑戦」という3つのキーワードが重要であると感じました。まず「未来」について。今描いた未来像がすべてではなく、むしろ未来は常に変化し続けるものであるからこそ、これからも常に未来を考え続けていく姿勢が重要だと思いました。
「グローバル」については、現在、8カ国で自社生産し、79の国と地域のお客さまに商品をお届けしており、当社グループの海外売上高比率は年々伸長し約20%あります。今後は、今回のような取り組みを海外市場でも実施し、既存市場の深掘りや、新たな国・地域への展開にもつなげていけたらと考えています。日本で生まれたマヨネーズが、世界中の生活者により深く、広く受け入れられていく未来を描いていきたいです。
そして3つ目の「挑戦」ですが、現在進行中の4年間の中期経営計画においても、「Change & Challenge」というテーマを掲げています。この計画の中でも、まさに「挑戦」が重要な軸になっています。マヨネーズを通じて、未来に希望を持てるような新たな価値提案ができるよう、チャレンジし続けることが重要だと考えています。

※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者

髙田 典明
キユーピー株式会社
経営推進本部 経営企画部
部長
1999年入社。20年間家庭用営業に従事し、量販店、CVSを中心に家庭用商品のプロモーション提案、エリアマーケティングを担当。2019年より家庭用本部マヨネーズチームリーダーとしてマヨネーズの企画開発、100周年プロジェクト立案に携わり、本プロジェクトに参画。現在は経営推進本部経営企画部に所属。

中村 友美
キユーピー株式会社
マーケティング本部 調味料戦略部 家庭用チーム
2008年入社。15年間研究開発に従事し、ベビーフードやパスタソースの商品開発を担当。その後マーケティング本部でマヨネーズやタルタルソースの企画開発に携わり、キユーピー マヨネーズ発売100周年プロジェクトやマヨネーズの未来を描く本ワークショップにも参画。

伊神 崇
株式会社 電通
第2ビジネストランスフォーメーション局 グロース・ブランディング部
ビジネス・デザイナー
広告/マーケティング領域において、コミュニケーションデザイン、マーケティング戦略・施策立案、またその調査・分析などに携わる。エリアマーケティング、再開発エリアのコンセプト・戦略立案、大型商業施設のマーケティング業務、大型地域プロジェクトの構想立案なども手掛ける。位置情報を活用した人の流れ分析、観光分析なども実施。2018年よりビジネスデザインにも領域を拡張し、企業の新事業/新領域開発支援、経営/事業分析を通じた戦略立案、意思決定支援、ブランドコンサルティング業務など企業の成長に寄り添う業務を実施。

吉田 健太郎
株式会社電通
ソリューションクリエーションセンター/未来事業創研ファウンダー
第4マーケティング局 チーフ・ディレクター
モバイル事業、スマホアプリ領域を中心とした市場分析、戦略プランニング、コンサルティングなどに従事。電通モバイルプロジェクトリーダーとして、CES/MWCに2011年から毎年参加し、TECHトレンドを把握。2021年 電通グループ横断組織「未来事業創研」設立。未来の暮らしの可視化からのバックキャストでの事業開発を得意とする。消費者庁 新未来ビジョンフォーラム フェロー、経営管理学修士(MBA)。