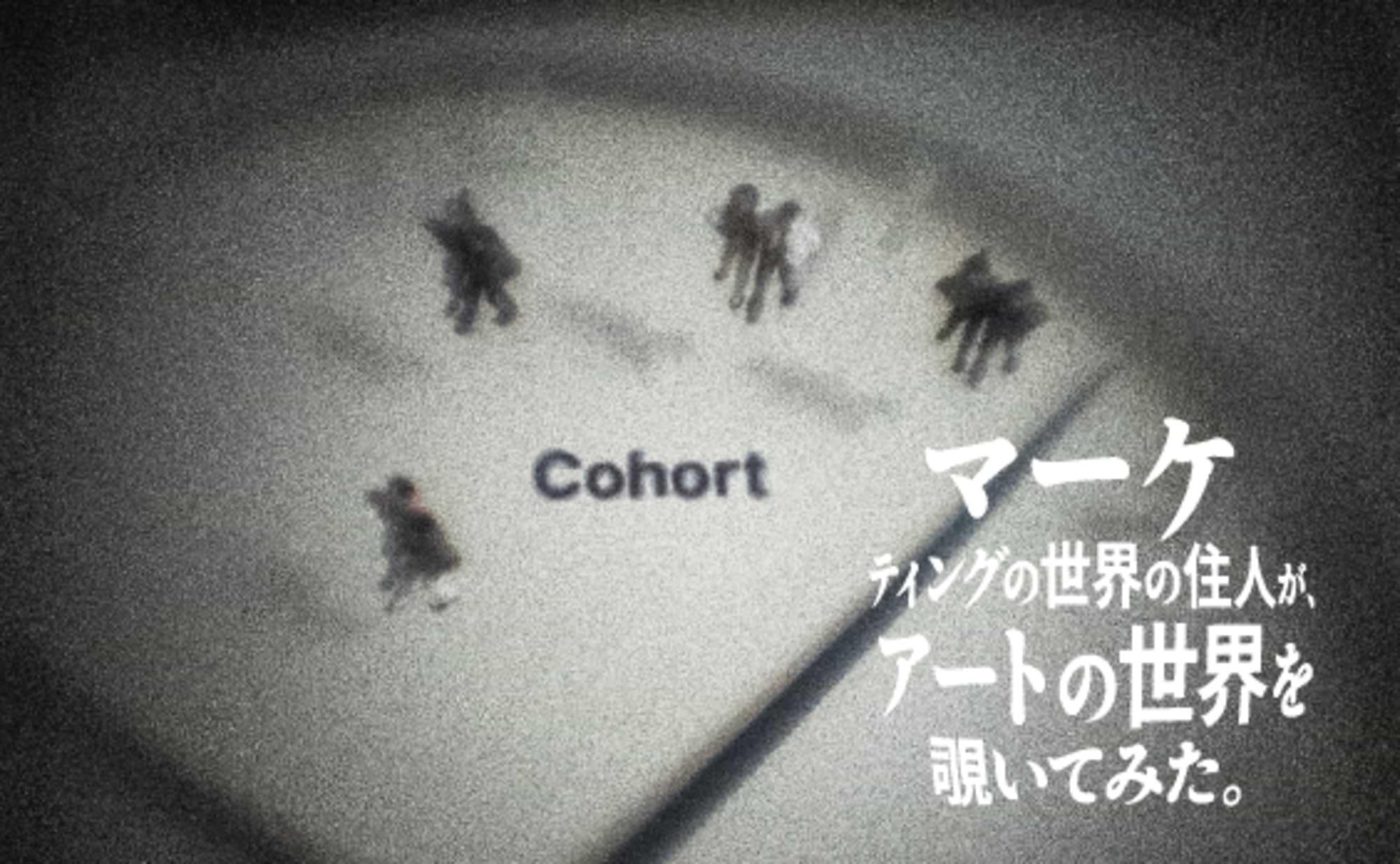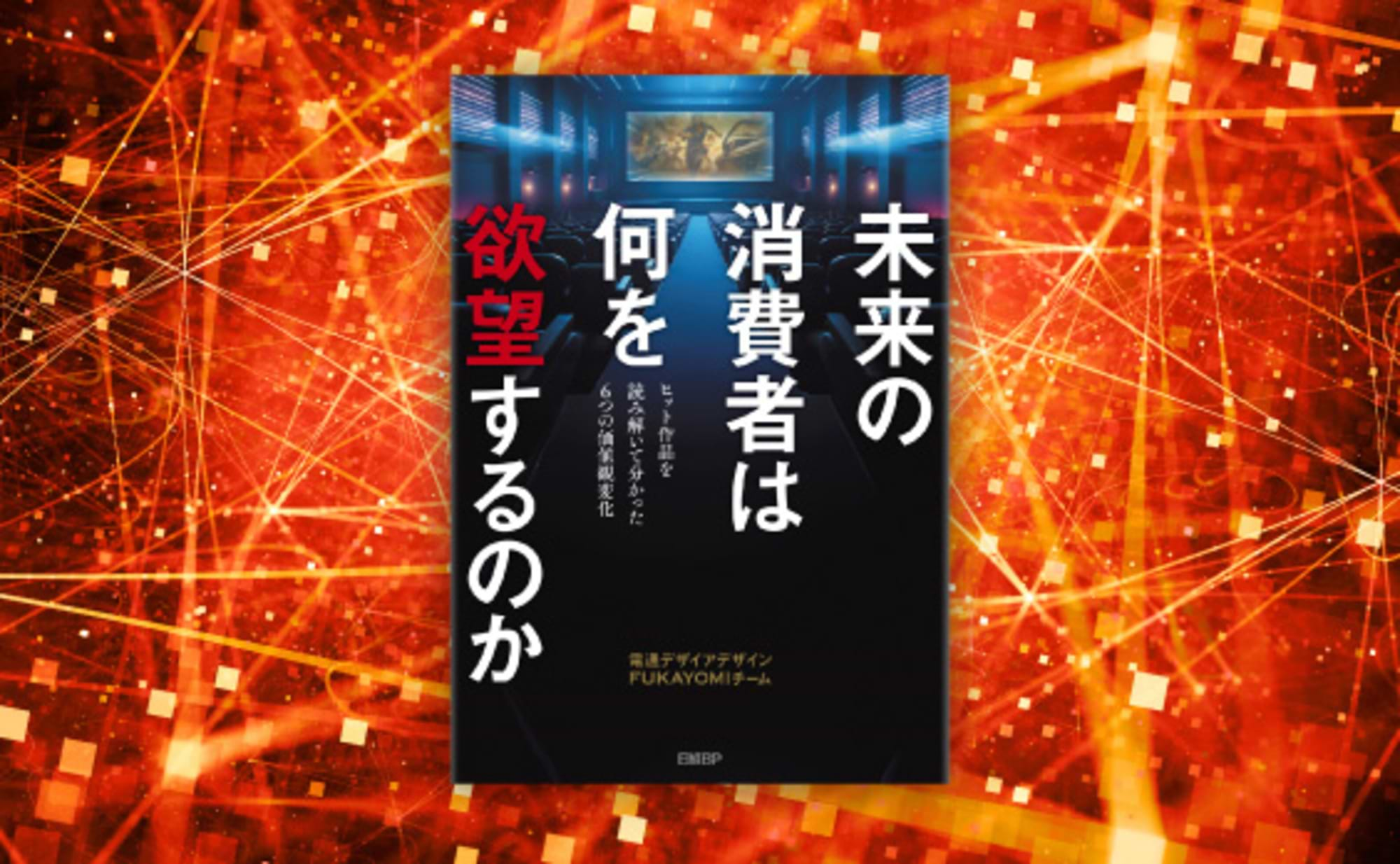アートの世界を覗いたら、マーケティングの世界の景色が変わった。

電通・宮川裕による連載「マーケティングの世界の住人が、アートの世界を覗いてみた。」
キュレーターの南條史生さんは、「ヨーゼフ・ボイスが社会を変える行為を社会彫刻と名付けたように、極めてクリエイティブな仕事を“現代アート”だと定義するなら、それはもはや絵画や彫刻に限らない。マーケティングの仕事も、日々の業務も、思考のプロセスも、創造的であれば現代アートたり得る」と言った。
東京国立博物館の松嶋雅人さんは、「マーケティングや広告の仕事だけではなく、博物館も含めて共通して言えることだが、本来、“枠や制限のないはずの場所”が、いつのまにかこうあるべきみたいな前提に縛られてしまっている。でも今、世界中の博物館や美術館が変わろうとしている」と言った。
2人が指摘するのは、美術業界にとどまらないところでの、価値観のアップデート、原動力となるクリエイティビティ、そして実行力の重要性。僕にとって、それはあたかも垣根を超えた予言のように感じた。
では、マーケティングの世界の住人は今どうしているのか。気心の知れたマーケティングプランナー、僕の同期の佐藤尚史と平嶋雅にマーケティングの現在地、そしてこれからを聞いてみた。
◆社会の変化とマーケティング
宮川:電通は、事業会社であるクライアントに対しマーケティングサービスを提供するマーケティング支援会社という側面を持っています。その中において、僕ら3人の所属部署は、ずばり“マーケティング”の名を冠しているわけだけど、その立場で今のマーケティングというものをどう捉えているのか、そんなところから聞いてみたいです。

佐藤:まず僕らが入社した2001年って、まだスマホもなければ、ロボット掃除機も普及していなかったよね。生活の不便を解消する余地が、まだ多く残されていた時代。生活のマイナスをゼロにするような機能のイノベーションが続々と出てきた。そのニュースをどうやって最適に届けるかが主流だった。でも今はそうじゃなくて……。モノが世の中にあふれていて、アジア圏からも似たような商品が安価に入ってくる。つまり、多くの人がもう満たされている状態。
そのような中、われわれはクライアントのプロダクトなりサービスのことを伝えなければならない。マーケティングプランナーとして、昔であれば「お困りごと、ありますよね」「それを解消するのがこのプロダクトですよ」と、ある種のペインポイントを起点にプランニングできた。ところが満たされた時代である今は、そうはいかない。マーケティングは“ゼロからプラスへ”。つまり、人生をより豊かにするとは何か?を考え、リードしなきゃいけない。そこが大きな転換点であり、面白い挑戦だと思っています。
宮川:マーケティングプランナーとしての振る舞い方も変わったと?
佐藤:昔はセオリーというものがあった。インサイトを掘って、商品の最適な見せ方を考えて、それをクリエイティブメンバーに伝え、表現としてジャンプさせるという型。それが、ゼロからプラスへという時代になると、そのやり方が通じないところがあって、まず自分でやり方をつくるところから始めなければならないという感覚がある。既存のフレームだけでは太刀打ちできなくなってきていて、異種格闘技のような状態というか。そして、どのツールを使ってどのデータを見るとどんな幸せを探り当てられるか、その方法論もたくさんある。この複雑性は僕らが若手だった頃とはまったく違う。

平嶋:ゼロからプラスの話を聞いて思い出したけど、今回の連載第1回で、文明と文化の対比について書いていたよね。文明は不便を克服するための技術や知恵の蓄積、文化は地域性や多様性の発露、という話。あれはすごく面白かった。マーケティングも、かつては文明的なもの、つまり課題解決や効率化を重視していたと思う。でも今は、より“文化的な方向にシフト”してきているんじゃないかな。多様な価値観の中で、どう意味や価値をつくっていくか。そういう仕事になってきたと肌で感じています。
少し話はそれるけど、あだち充先生の「クロスゲーム」という漫画があって。甲子園を目指している主人公の幼なじみの女の子が凄腕のピッチャーなんだけど、男子の硬式野球部では試合に出られないから、バッティングピッチャー(バッティング練習の時にボールを投げるピッチャー)としてチームを支えるんだよね。仲間の弱点や良さを見つけて、それを改善したり伸ばしたりするような球を投げることで、チームを強くしていく。
今のマーケティングプランナーって、そういうバッティングピッチャー的な立ち位置が求められていると思う。昔は電通のプランナーとして「打席に立つ」という言い方をよくしていて、バッターに例えることがよくあったよね。そして如何にホームランを打てるかという価値観での評価が多かったと思うのだけど、むしろ今は、クライアントの強みや課題に合わせてボールを投げることで、それが最終的にクライアントのホームランにつながるかどうかが勝負。そういう伴走型のバッティングピッチャー的な在り方こそ本質的に必要になってきたと感じています。対社会においても同様に文化の多様性をひもとき、ここに投げてみよう、ここに投げてみようと模索し、大きなうねりをつくっていくのもマーケティングの仕事だと思っています。文明的というより、まさに文化的。
佐藤:従来はインサイトといえば、おおむね消費行動にまつわるインサイトを指すことが多かった。商品が売れるための消費者としてのツボ。でも今はそれだけじゃ足りないと感じています。文明から文化へ、という話にもつながるけれど、社会に根付いている価値観や文化的な背景、「カルチャーインサイト」とか「ヒューマンインサイト」と言ってもよいものと、プロダクトをどうつなげていくか、そういうところを探索していく仕事に変わりつつあると言ってもいいのかもしれない。世の中のニーズに応えるというよりも、世の中への提案という在り方。
平嶋:まさに、僕も同じようなことを考えていた。今回の連載で「現代アートに向き合うとは、正解を求めることではなく自分はどう考えるのかという意見表明をすること」とか、「作品そのものより、それを見た人がどう感じたか、どう考えたかのほうがずっと大事」といったインタビューコメントがあったよね。そこにプロダクトと顧客の関係性に似たものを感じて共感した。われわれの仕事も、もっと現代アートのように既存の枠組みを超えていくことで、人の新しい意識や行動を生み出すものでありたい。宮川の書いた連載を読んでいて、そんなことを思った。
宮川:南條さんも、「クリエイティビティを発揮する仕事はすべて現代アートである」といった主旨のことをおっしゃっていた。マーケティングの世界の人がアートの世界を参照することで、新しい視座を得られることはいろいろとあると思っています。

◆マーケティングの時間軸
宮川:僕はアートというものと関わるようになって、長いスパンで考えることの意義をとても意識するようになりました。松嶋さんの受け売りなんだけど、僕たちはどうしても自分の人生が100年程度なので、せいぜいそのくらいのスパンで考えがち、自分の人生という長さの中に閉じがち。だけどアートの世界ではもっともっと長い時間軸で物事を捉えていて、「われわれは歴史の途中にいるにすぎない」と。
佐藤:その話に被せるとすると、僕らが入社した当時ってマスメディア全盛の時代だったよね。シェア・オブ・ボイスの確保が主要な勝ち筋だった。でもそれって、今振り返るとちょっと特殊な時代だったのかもしれないな、と。僕はむしろ今のやり方のほうが本来の姿に近いんじゃないかと思っている。
平嶋:本当は当時も今のようなアプローチをとるべきだった?
佐藤:そうかもしれない。メディアの質や量だけに頼るのではなく、プロダクトごとにゼロベースで考えて、生活者にどう伝えるのが最適なのか一つ一つのコミュニケーションをつくっていく。そういう手づくり感というか、細やかな個別対応こそが本来のマーケティングのあり方なんじゃないかと思うんです。
宮川:そう考えると、マスが台頭した時代、一億総○○時代というのは、ほんの一時期に過ぎないのかもしれず、佐藤が言っている考え方のほうが時代の状況として自然なのかもしれないね。アートの世界の人たちの、何千年という単位で文化財を受け継いでいく価値観から学べることって、僕たちマーケティングプランナーにとっても大きいのではないかと思う。一時的な時代の熱狂だけを見るのではなく、もう少し長い目で物事を捉えることの大切さというか。
佐藤:そうだね。ロングスパンで物事を見ると、マーケティングも目の前の成果を追いつつ、「今のやり方をどう磨き、突き詰めていくのか」という長期視点が当然生まれてくる。その上で、僕はマーケットという意味においてもカルチャーがより重要になってくる気がしていて。大衆が常に同じ番組を見る、同じ広告を見るという時代ではないけれど、でも「鬼滅の刃」が映画で400億円の興行収入を叩き出すようなマスレベルのヒットは、確かに生まれている。コンテンツや文化そのものがマスになり得る時代。だから僕は、マーケティングにおいてカルチャーというレイヤーにももっと目を向けるべきだと感じているんです。

宮川:長いスパンで物事を俯瞰する。その上で大事なこととして、“持続可能性”の観点が必然的に現れてくると思っています。われわれは、クライアントありきの立場ではあるけれど、この一つの地球における持続可能性を前提とするならば、伴走者として提案すべきこと、そして提案すべきではないことという、ある種の審美眼みたいなものも生まれてくるのではと思っていて。
平嶋:CX(Customer Experience Transformation:顧客体験の変革)領域でも、時間軸で価値を考えるのが基本。今この商品がどんな意味を持つのか、そして将来的にその人の人生にどんな影響を与えるのか。CXと社会の未来像は不可分なので「どんな社会を目指していくか?」の設計も必要になってくる。
佐藤:電通グループは「B2B2S」(Business to Business to Society)を掲げているけれど、最後のSを「ソサエティ」ではなく「サステナビリティ」と読み替えてもいいんじゃないかな。もちろん現実的に短期の成果にしっかりと向き合いつつ、長期の視点を織り込んで社会に対してどんな影響を与えるのか。その意義を可視化することで、クライアントのビジネス自体の持続可能性を高めていく。そんな提案がますます求められるようになるのかなって思います。
それに加えて、たとえば自分がSNSで「社会をよくしていこう!」と発信しても、なかなか届かない。でも、企業やプロダクトのメッセージに乗せれば、遥かに大きな形で発信することができる。そこに生活者の気持ちがピタッと重なって、社会に届いたときの手応え。それってマーケティングプランナーとして働くからこそ味わえる醍醐味の一つなんじゃないかな。
◆マーケティングプランナーの持続可能性
宮川:今までの話を踏まえて、マーケティングプランナーとしての存在価値、その発揮の仕方について。マーケティングプランナーの役割や立ち位置をどう捉えるか、それは人によってずいぶん違うのだろうなぁと思っていて。

佐藤:今のマーケティングのスタンダードって、客観的なデータを使って精緻に最適化していくアプローチだよね。たとえば行動ログを分析してインサイトを導き出すとか、A/Bテストを繰り返して成果を改善していくといったある種サイエンス主導のやり方。それ自体は必要不可欠だし、僕自身も学び続けているけれど、これを突き詰めていくと、個性が埋没していく側面もあると思っている。どの会社も同じようなスキルを持ったマーケティングプランナーがいて、同じようなフレームで戦略を立てていく。結果的にアウトプットも似通ってしまうかもしれない。
だから僕はあえて、そこにもう一つ別の軸を掛け合わせたいと思っていて、それが“人文知”なんだよね。歴史や哲学、心理学、行動経済学など、人間の思考や行動の本質を知るための知識。たとえば「ホモ・サピエンスはこういう場面でこう動く傾向がある」といった視点を、自分の中にナレッジとして持っておく。そういった教養が、データとは異なる文脈から発想を飛躍させるためのジャンプ力になると考えています。
マーケティングプランナーはクリエイターとは違ってニュートラルでいなければならない、という暗黙の了解みたいなものがなくはない気もする。個性が立ってはいけない、みたいな。だけど僕はめちゃくちゃ個性を立てて、「人文知にもとづいたジャンプは任せて!」というフラグの立て方はしている。

平嶋:電通の強みはそうした多様さの“マッチング力”だと思っていて。何かと何かをつなぐことで生まれるインパクト。それに気づいたのはクライアント先に出向していた頃。異なるミッションを持った部門同士が噛み合わずにいたとき、それぞれの目指す方向を一段上の概念でまとめてみたら、不思議と協力関係が生まれたことがあった。そういう経験から、一見相容れないものをどうつなぐかという視点を持つようになりました。
電通のある役員が「電通の強みは“矛盾吸収力”だ」と言っていてすごく共感した。合うもの同士をマッチングするというよりも、相反するように見えるもの同士をうまく包み込んで新しい概念として再構成していく。部門間のアサインの調整でも、社会とサービスの接続でも、そうしたマッチングを意識して設計している。僕自身、建築学科出身ということもあって、物事を立体的に積み上げて一つの価値構造にしていくのが好きで。
佐藤:電通も最近は本当に多様な人材が入ってきていて、背景もスキルもそのバラバラさたるや。運動部出身もいれば起業経験者もいるし、プログラミングに特化していた人や、カルチャー寄りで広くつながりを持っている人もいる。多様性って耳ざわりはいいけれど、実際にチームで何かを決めようとすると全然まとまらない(笑)。
矛盾吸収力というのを僕なりに引き寄せて考えると、「山の頂上、ゴールイメージは共通させる」こと。ただ、メンバーの山の登り方、各々アプローチの仕方は違っていてよくて、目的が明確に共有された上で登り方が違うからこそ化学反応が起こり得る。それがディレクションする、ということだと思っています。
平嶋:そのゴール設定が、全員にとって「目指したい」と思えるものであることが重要ですよね。その設計が、まさにマッチング力の見せどころ。
宮川:そこに大きな構えで俯瞰する価値観が備わっていれば、メンバー全員にとっての目指したいものと、「社会のため」ということが合致するのかもしれない。
平嶋:さらにマッチング力の応用、経営にも通じる視座として、必ずしも全員が「同じゴールを目指している」と自覚しておらず、メンバーそれぞれが「自分のゴール」に向かって走っているつもりでも、結果的にそれが組織や社会全体にとって望ましい方向に作用させるという設計もある。そこでも包括的な大きな視野が欠かせない。
佐藤:冒頭の、人生をより豊かにするために「ゼロからプラスへ」、文明的というよりも「文化的な方向にシフト」、先ほどの、ゴールを共有しアプローチは各々で「結果的に化学反応を起こす」こと、それから宮川の以前の記事にもあった「アーティストが探究の根を伸ばす」こと、これらはすべて通底していると感じていて、まだ見ぬ価値、「こういうことはどうですか」と提案するということ。僕らが若手だった頃とは明らかに異なる在り方は、“アート思考”と言っていいんじゃないかな。
宮川:僕らもきちんと年をとっていると(笑)。ではこの流れで、今の若手メンバーとの接し方や、伝えていることは?
平嶋:僕はもう完全にバッティングピッチャー。そして繰り返しになるけど、常にマッチングを考えている。
佐藤:僕は「自分なりの世界の見方、スタンス、それは如何なく発揮していいんだよ」と伝えている。「それが戦略のユニークさにつながっていくんだよ」と。それから、雑談の中から相手の強さを引き出していったりする、予定調和ではないファシリテーション力。
宮川:模範解答みたいなものが存在している前提で、そこに向かって最速で到達するスキルと、偶発性も肯定し探究していく在り方、いわばアート思考の実践みたいなことはだいぶ違うからね。多くの人に培っていってほしいですね。
◆アートの世界を覗いたら、マーケティングの世界の景色が変わった。
宮川:同期ということもあって、つい話しすぎてしまったけれど、そろそろクロージングということで。
平嶋:「どんな社会をつくりたいのか?」という視点って本当は大事なのに、日々の業務に向き合っているとつい見失いがち。そういう中で、自分の仕事が社会にポジティブな影響を与えるものになったらいいなと思って、局内の有志メンバーで立ち上げた「おじ活研究所」っていうプロジェクトに参加しています。「おじ活」=おじさんの活動を研究するプロジェクト。40代の男性が社会的にもっとも幸福度が低いという調査結果があって。その要因の一つとして、家庭や仕事、後輩の育成など、いろんなものを背負っていて、自分の時間や楽しみが後回しになりがちなところがある。だから、「もっと楽しんでいい」「趣味に励んでもいい」という空気を社会に広げられたら、社会全体として幸福度が上がるんじゃないかと考えています。これは一つの企業で実現できることではないので、それこそ異なる立場や思惑を持つ複数の企業と一緒に、それぞれのやり方で同じゴールに向かって歩んでいけば、やがて社会が変わっていくかもしれない。そうした長期的な視点で、前向きなムーブメントをつくっていきたいと思っています。
佐藤:僕は「DENTSU DESIRE DESIGN(通称:DDD)」というプロジェクトに関わっていて、生活者の「欲望」を深く掘り下げる研究をしています。その中でも、僕が担当している分科会「FUKAYOMI」では、映画や小説、漫画といった物語を題材に、「なぜ多くの人の心を打ったのか」を読み解いている。大ヒットコンテンツは単に話題性やキャスティングだけで成功しているわけじゃなくて、クリエイターの個人的な「こうあったらいいな」という欲望があり、そこに観客が共感したり、価値観の変容が生まれたりするからこそ広がるんだよね。僕らはそうした欲望の変化を見つけて、定性的・定量的に読み解いていくことで、「未来に生まれるであろう欲望」の兆しを捉えようとしています。この研究の成果は、7月に書籍として出版される予定なので、ぜひ気になる方は手に取ってみてください、という宣伝でした(笑)。で、宮川は?
宮川:特に宣伝はないけど(笑)。僕はマーケティングプランナーという仕事柄、常に「相手にとって最適な答えは何か」が基本スタンスにあった。でもアートの世界に触れていると、「あなた自身はどう思うの?」って問いが常に飛んでくる。そこに戸惑いながらも、まあ楽しくやってます。だからこそ、今日こうして対話してみたかったわけで。
平嶋:今回宮川の書いた連載を読んで、「もっと創造的に枠を飛び出していい」って背中を押された気がする。
佐藤:僕らは普段、アートを意識して仕事しているわけじゃないけど、休日に美術館へ行ったり映画を観たりすること自体が、自分の思考の外へと出かけていく行為なんだよね。そこで感じたものを意識的に取り込むことって、すごく大切だと思う。そしてそれを仕事に還元することも、もっとやっていきたいと思った。マーケティングプランナーって、表現をつくるという意味でのクリエイターではないかもしれないけれど、企業やプロダクトが社会にどんな価値を提供できるかを考える上では、クリエイティブであるべき職種だと考えています。だから、マーケティングプランナーこそアートの視点も取り入れて、もっと大きな未来に導くような提案をしていくべきだなって思いました。
宮川:僕はアートの世界を覗いてマーケティングを捉え直すことをやっているのだけれど、今回マーケティングの世界の住人である平嶋と佐藤の話を聞いていて、南條さんや松嶋さんがおっしゃっていたことともつながっているなとあらためて感じました。今後もアートの世界の方々とお会いする予定なので、そこで得たものをまた持ち帰ってきたいと思います。


画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?
著者
この人の記事

佐藤 尚史
株式会社電通
第2マーケティング局
プランニングディレクター
古今東西の人文知を武器に、ビジネスグロースのためのコンサルから企画開発、マーケティング戦略からワークショップまで「社会をよくすることの全て」をドメインとする「The Director」として活動。たまにシナリオライター。

平嶋 雅
株式会社電通
第3マーケティング局
シニア・ソリューション・ディレクター
CX領域のソリューションディレクターとして、企業と顧客の新たな関係づくりやブランド成長を支援。2017年から2020年まで大手通信会社に出向し、DX推進チームの一員として、顧客データの活用高度化やCX向上の取り組みに参画。