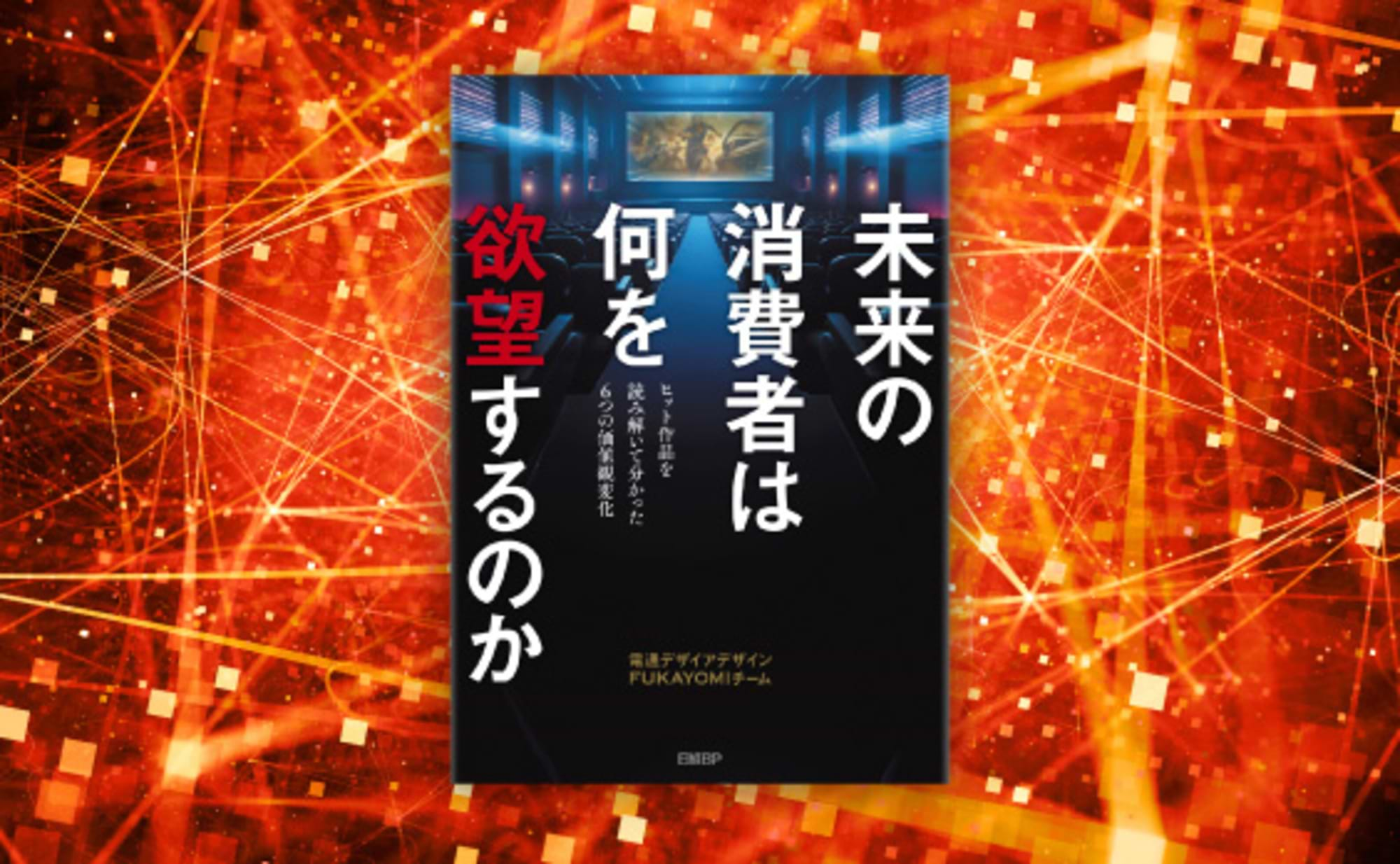記録的な興行収入をたたき出したアニメ映画や、放送するたびSNSのトレンドに上がる人気ドラマ。それらがなぜヒットしたのか、深く考えてみたことはありますか?FUKAYOMIは、映画・ドラマ・アニメなどのヒット作品を読み解き、私たちの価値観変化や未来の欲望を予測する電通の独自メソッド。単なる作品批評にとどまらない鋭い視点は、ビジネスの突破口をひらく大きなヒントになるかもしれません。
※この記事はDo! Solutionsに掲載された記事を編集・転載したものです。
<目次>
▼ヒット作から、価値観変化と未来の欲望をあぶりだす
▼国際的ヒット映画「怪物」に見る、多層的な視点への欲望
▼作品からのさまざまな発見を、ビジネスのヒントに
▼“FUKAYOMI”すれば、ビジョン策定やコンテンツ制作の幅が広がる
▼FUKAYOMIを入り口にすれば、難しそうな未来予想もハードルが低くなる
▼FUKAYOMIのメソッドと実績がこれ一冊に!『未来の消費者は何を欲望するのか~ヒット作品を読み解いて分かった6つの価値観変化』発売
ヒット作から、価値観変化と未来の欲望をあぶりだす
──まずはFUKAYOMIについて教えてください。お二人は電通報でも何度か取り上げているDENTSU DESIRE DESIGN(以降「DDD」)のメンバーですよね。FUKAYOMIは、DDDの分科会といったイメージでしょうか?
佐藤:そうですね。DDDは“欲望”を基点とした生活者調査やマーケティング支援を行う電通のプロジェクトで、いくつかの分科会が存在するのですが、その一つが未来の欲望の予測に挑戦するFUKAYOMIチームです。“未来の欲望”は今まだ可視化されていない潜在的なものなので、それを予測するにはかなり奥深くまでインサイトを掘らないといけません。どういう方法論があるだろうかと考えた時に、「映像作品コンテンツ」に着目をしたことがFUKAYOMIの始まりです。
──なぜ映像作品だったのでしょうか?
佐藤:一つは僕が大学時代に自主映画を制作していて映画が大好きだったこともありますが、実は社会人になってから趣味でシナリオ学校に通ったことが大きく影響しています。映画やドラマのシナリオはとても戦略的に作られていて、決められた時間枠の中に制作者の考えや見る側の心の動きが緻密に計算されて盛り込まれています。シナリオを学びながら、ヒットした作品をひもとくことで今の社会が共感する欲望や価値観を抽出できるのでは、と直感したんです。それで実際にいくつかの作品を分析しながら、半年かけてFUKAYOMIのメソッドを体系化していきました。

──そのFUKAYOMIメソッド、具体的に教えていただけますか?
佐藤:「価値観変化の流れ」を読み解く独自のフレームワークを用い、ヒット作品の中でどういった「欲望の生成」「欲望の解消」「価値観の更新」が行われているか、そしてそこからどんな「新しい欲望」が生まれ得るかを抽出・分析します。プランナー個人の視点から読み解くことに加え、ソーシャルリスニングなどの分析も踏まえてチームでディスカッションを重ね、共感性の高い結果を導き出していることがポイントです。
国際的ヒット映画「怪物」に見る、多層的な視点への欲望
──具体的な分析事例を、何か一つご紹介いただけますか?
石川:例えば、書籍でも分析しましたが第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞とクィア・パルム賞を受賞したヒット映画「怪物」。 これは、息子の異変に気づいたシングルマザーの母親が担任教師の体罰を疑うことからストーリーが始まるのですが、途中で視点が担任に変わり、そして息子とその友達へと移っていく中で、同じ出来事に対して多層的な真実が浮かび上がる、という展開になっています。
──劇中では断定されない「怪物とは何なのか」という結論を巡り、国内外でさまざまな考察が巻き起こりましたよね。
石川:はい。この映画は、情報があふれる現代社会において「真実に近づきたい」という私たちの欲望をかき立て、さらに「自分の見ているものはどこまで真実かわからない」「もし違う視点から見たら、まったく異なる意味を持つのではないか?」という価値観の変化をあらわにした象徴的な作品だったと思います。さらにそれを踏まえると、この先の未来では「一つの真実を求める」よりも「俯瞰(ふかん)的に複数の視点を持ちたい」というマルチソースへの欲望が強まることが予測できます。こうした欲望は「怪物」だけでなく、途中で視点が逆転する展開は最近の多くのヒット作品から読み取ることができるんです。

──たしかに最近、複数の視点から真実を立体的に描く作品が増えていますね。「マルチソースを求める」という新たな欲望も納得感があります。ちなみにFUKAYOMIでは、これまで何作品ほど分析してきたのですか?
佐藤:150作品ほどです。年代別に欲望の変化を捉えてみたり、複数の作品から読み取れる傾向を分類したりと、いろいろなアプローチを行っています。さらに、DDDが年に2回行っている「心が動く消費調査」の定量分析も重ね合わせ、一部の主観だけにとどまらない裏付けも取っているので、納得感の高い分析結果になっているのだと思います。
作品からのさまざまな発見を、ビジネスのヒントに
──FUKAYOMI流の読み解き方がわかったところで気になるのは、「それがビジネスにどう応用できるのか」という点です。
佐藤:分析結果の生かし方は幅広くあると思います。例えば「価値観の更新」に注目して、「そういう価値観の変化があるなら、当社のこんな技術が使えるな」と新商品やサービス開発に生かすことができますし、価値観変化に合わせて既存商品の訴求方法を刷新することもできます。先ほどもお話ししたように150作品ものヒット作を分析してきたので、クライアントのターゲットや課題感に合わせて適した価値観や欲望の情報をお伝えできると思います。
──なるほど。新しいマーケティングの切り口を探している人には、ダイレクトなヒントが得られそうですね。
石川:それで言うと、劇場版「名探偵コナン」シリーズの分析はマーケティング応用への気づきが多かったです。劇場版「名探偵コナン」は90年代から続く超ロングシリーズにもかかわらず、毎年興行収入を拡大している驚異のヒット作品です。そのシリーズを第1作からまとめて分析してみたんです。
詳細は割愛しますが、特に近年の大きな勝因は「推し活」文脈をうまく捉えた点にあることが分かりました。毎回フィーチャーする登場人物を変え、その人を中心とした登場人物の関係性を描く。あたかもその公式が二次創作をしているような感じで、毎年4月の映画公開時期にはまるでコミケが盛り上がるようにお祭り状態になるんです。
佐藤:するとそのフィーチャーされた登場人物を入り口に、毎年新しいファンが流入する。この巧みな戦略で、この数年は興行収入100億を超えている大成功コンテンツになっています。ポイントは、これまで大多数の人の推し活の対象にはなりづらいとされていた脇役キャラクターに光を当てたこと。プロダクト全体を見て終わるのではなく、一つ一つの要素に着目していくと必ずそれを偏愛している人たちがいる。その“偏愛”や“推し”という価値観を突破口にファンを広げていく手法は、そのまま他のマーケティングにも応用できますよね。
実はロングセラーお菓子の「たべっ子どうぶつ」も似たような手法を取っています。パッケージに描かれた動物たちをカプセルトイにして売り出したことから火がついて、体験型イベントやアパレル、ゲーム化、そして映画化にまで広がり、製品自体の売り上げも毎年2桁増を達成。今や大ヒットコンテンツに。英語を学ぶためのビスケットが推し活の対象になるなんて、最初は誰も考えなかったんじゃないでしょうか。
──FUKAYOMIからマーケティングへの接続、新たな視点が得られておもしろいですね!
佐藤:僕をはじめFUKAYOMIのメンバーは全員戦略プランナーなので、作品から得た知見をどうビジネスに応用させるかということは常々考えています。DDDはマーケティング支援の実績が豊富ですから、FUKAYOMIの活動も単なる作品批評とは大きく異なり、ビジネスへの有効なヒントとなるのがユニークなところであり強みですね。
“FUKAYOMI”すれば、ビジョン策定やコンテンツ制作の幅が広がる
──FUKAYOMIのビジネス応用という視点から、他にも可能性はありますか?
佐藤:より大きなところで言えば、ビジョンやパーパスの策定に役立てることもできると考えています。というのも、未来に向けて企業が生活者に何を提供できるかというビジョンを決めるときに、「未来の人たちがどういうことを欲望するのか」を前提に置かないと的を射ないものになりかねないからです。
それから、個人的に協業していきたいと思うのは、メディア関係の方々や販促企画を行っている方々です。これまではコンテンツやタレントなどの知名度や人気度を生かしたタイアップ企画が販促の主流でしたが、FUKAYOMIによって視聴者側の価値観や欲望の視点を深掘りしていくことで、より細やかで最適化されたコンテンツとのマッチングや企画立案につながっていくと思います。
──生活者のインサイトを細やかにつかむことで、企業・コンテンツ・顧客との新しい関係性が生まれるかもしれませんね。
石川:世の中にはいろんな消費者調査データがありますが、それらの多くは顕在化された声を数字にしているので、生活者も気づいていないような心の奥まで知ることは難しいとされています。潜在的なニーズを捉えるためにFUKAYOMIを使っていただき、それを刺激にいろんなビジネスや関係づくりに生かしていただけたらと思います。
FUKAYOMIを入り口にすれば、難しそうな未来予想もハードルが低くなる
──ここまでのお話をお聞きして、FUKAYOMIによる分析結果はもちろんのこと、FUKAYOMIというメソッドそのものを身につけることがビジネスパーソンの大きな力になるように感じました。
佐藤:ありがとうございます。僕もそれがとても重要だなと思っていて、映画をたくさん見て、その裏にある共感ポイントや心を動かされた要因は何だろうってことをひもといていくと、だんだん人間の欲望や気持ちというものが見えてくるようになるんです。そうすると、自分の中でいろんな発想や切り口を持つことができて、ビジネスのいろんなシーンで今までよりたくさんの意見が言えるようになる。そのためのトレーニングとして、FUKAYOMIメソッドは一つの有効なフレームワーク。われわれが深読みしたものをクライアントに提供するだけでなく、個人個人でぜひ実践していただけたら理想的です。
──例えばそうした研修プログラムをソリューションとして提供することも、可能なのでしょうか?
佐藤:FUKAYOMIのサービスは、クライアントからのご要望があれば、個別の課題に合わせて柔軟に対応する方式を採用しています。例えば物語のシナリオ構造と、それによる人間の心の動きを知ることは、企画書を書く時にそのまま役立ったりもします。また、ストーリーテリングのスキルアップにもつながるので、プロジェクトで価値観変化を検討し、未来の欲望を予想するステップに取り込んだり、研修などのメニューとしてプログラム化することも可能です。
人の欲望を探るとか、未来を予想するとか言われるとなんだか難しいことのように思われがちですが、FUKAYOMIの考え方は、消費者の価値観の変化の潮流から、未来の欲望を予測するというとてもシンプルなものです。ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
FUKAYOMIのメソッドと実績が一冊に!「未来の消費者は何を欲望するのか~ヒット作品を読み解いて分かった6つの価値観変化」発売
──FUKAYOMIメソッドが2025年7月26日に書籍化されましたね。
佐藤:はい。発足以来5年間にわたる活動の集大成として、代表的なヒット30作品の分析から導き出した「6つの価値観変化」と、そこから予想される「3つの未来欲望」を1冊にまとめた書籍です。自社のビジネスに今までの延長線とは違う風を吹かせたいという方にはきっとヒントがあると思うので、多くの方に読んでいただけたらうれしいです。そしてもっと詳しく知りたいという方は、ぜひ直接お話しする機会を設けさせていただければと思います。

──これを読んだ後は、もはや何も考えずにコンテンツを見ることはできなくなるかもしれませんね。
石川:確かにそう言われると、私もFUKAYOMIチームに加わってから、普段プライベートで映画を見るときも「これって観客の価値観にどんな変化をもたらすのかな」と考えるようになりました。でもそのおかげで、FUKAYOMI以外の業務でも、価値観変化や時代背景を踏まえた長期的な視点を持てるようになったと思います。
とはいえこの書籍に関しては、ビジネスに限らず映像コンテンツが好きな人なら誰でも楽しめる内容。ぜひ、ライトな気持ちで読んでみてほしいです。
■書籍の紹介ページはこちら
■“欲望”基点のマーケティング支援サービス DENTSU DESIRE DESIGN
無料の資料ダウンロードはこちら

この記事は参考になりましたか?
著者

佐藤 尚史
株式会社電通
第2マーケティング局
プランニングディレクター
古今東西の人文知を武器に、ビジネスグロースのためのコンサルから企画開発、マーケティング戦略からワークショップまで「社会をよくすることの全て」をドメインとする「The Director」として活動。たまにシナリオライター。

石川 柚里
株式会社電通
第1総合ソリューション局
ソリューション・プランナー
飲料メーカーや化粧品ブランドの戦略立案、体験設計から、企業マーケティング変革支援まで幅広く従事。国内外の映画・ドラマ視聴とミュージカル鑑賞が趣味で、FUKAYOMIチームには昨年よりジョイン。