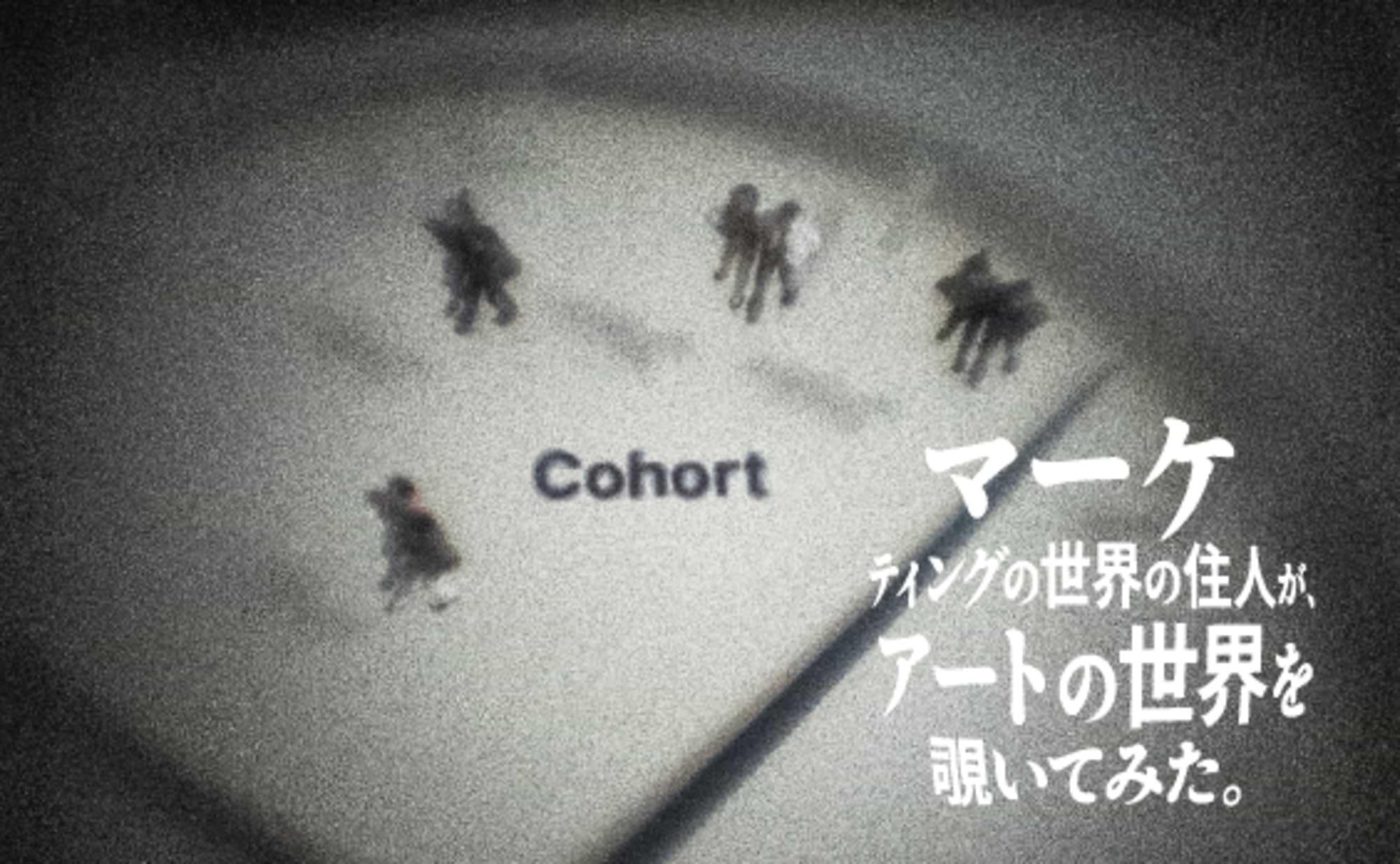20年くらい前だろうか、池田晶子さんの「14歳からの哲学」を読んだ。「正しい」ということはすべての人間に共通で(おそらく、どの事象が正しい・正しくないかではなく、正しいという言葉の概念が共通、という趣旨)、人間は正しいと思っていること“しか”できない、といったことが書かれていた気がする。14歳はだいぶ過ぎていたけど、なかなかな衝撃を受けたことだけははっきりと覚えている。
プレゼンや、複数の人に向けた発表、それから講義なんかを前にした時の話。頭、思考を動かして、なんとなく自分として腑に落ちるところまできてみる。そこにあるのは、自分としての「一応の正解」ということになる。それをよりどころに手と目を動かし、原稿やスライドをつくる。一応の正解に到着したはずなのに、それとピッタリ一致するものができたためしがない。頭、思考が甘かったのか。手と目の再現力の限界なのか。とにかく必ずズレたものが出来上がる。
「更新版・一応の正解」をもとに、今度は一人リハーサルをする。またもやしっくりこない。声や呼吸の限界なのか、机上(パソコン上)と現実(しゃべる身体)のズレなのか、はたまた声に出すことで頭、思考が活性化するのか、とにかく必ず更新版の再更新が必要になる。
これを前向きに捉えると、気づきの連続、納得感の更新ということなので、手間だけど事前準備の所作としてこの三段階目までを何周か必ず行うことにしている。そしてここまでは、言ってしまえば自分の問題、内部完結できることなので、更新というのはまあちょっとした気づき、といったところ。
そしていざ本番。相手がいて、しゃべる。大人数か少数かはさておき、提示する。(自分としての)「正解」にもかかわらず、経験上、やる前からわかってしまっているのだが、想定とピッタリと一致した着地、になったためしがない。だいたいにおいて想定外の反応。想定内だけれど、見過ごしてしまうような微弱な反応なんてことも。この(自分としての)正解の儚さたるや、「正解」でグルーピングするのもおこがましかった、と毎度思い知らされる。「正しい」に正直に生きているはずなんだけどなぁ。
が、悲観しているわけではない。自分の外側に出す価値、というのも毎度思い知ることができる。出かけて行った先でこそ気づきを獲得できる、という夢のある話。獲得のプロセスで、はずかしめを受けたり下手すると怒られたり。髭も剃らずに一人ぼーっとする週末の午前中みたいな弛緩はないけれど、得られるものが大きいからまあ仕方ない。

毎年、フェリス女学院大学で講義をする機会がある。テーマは「アートとビジネス」。僕に登壇を依頼している先生は美術館に勤務しているので、僕よりもよっぽどアートビジネスのど真ん中を担っているはずだが、先生の意図は、アート周辺も含めたビジネスの多様さや、アート思考といったことも含め一般のビジネスパーソンにおけるアートとの関わり方や意義などを学生に見せてほしい、というもの。
学生の、このテーマへの関心の高さなのか、電通も含めた業界への好奇心なのか、それとも僕という外部の人間に対するサービス精神なのか、とにかく毎年学生はきちんと反応を示してくれる。しかも、かなり味わい深い反応。普段は大学生と直接やり取りする機会がないので、自分とは違う視点の価値、裏を返すと同質化というのはリスクなんだと肌で感じる、そんな大きな気づきの場になる。
今年の講義は、アートを通じた「業務の拡張」「教養の拡張」「視野の拡張」という3部構成。今回のコラムは、その簡易レポートにしてみた。
◆

学生に伝えることを念頭に置いて「業務の拡張」と言った時、真っ先に製作委員会や実行委員会のことが思い浮かんだ。電通は広告制作にせよマーケティング支援にせよ、BtoB企業として事業会社たるクライアントの業務支援をするのが基本。ではあるものの、主にコンテンツ系において、電通が中核の1社というポジションになることもある。
そこで、まずは「ブルーピリオド展」でクリエイティブディレクターを担っていた宮下良介さんに相談の一報を入れた。キービジュアルの画像ファイルが添えられて、31分後に返信がきた。は、早い。ありがたい。次に、「Immersive Museum」のプロデューサーである野口貴大さんにも相談の一報を入れてみた。5分後に、大丈夫ですと返信がきた。は、早い。早過ぎる。なんとありがたいことだろう。しかも、大学生が相手ならこの実施風景がよいと思いますよと、こちらも画像ファイルが添えられていた。
余談だが、まあまあ長い社会人生活の中で、電通に限らず世の中には即レスの人がいつの時代にも一定数いることを知った。きっとこの人たちは、ものすごい高回転で仕事をしているのだろう。100%尊敬してしまうが、どうか体にだけはお気をつけて、と思ったりもする。

「ブルーピリオドはよく読んでいます。展覧会になることでアートがさらにビジネスにつながるんだなと思いました」「ブルーピリオドはアニメを見ていましたが、展示会や実写化を知らなかったので驚きました」といった気づきを伝える学生もいた。

「イマーシブミュージアムに以前訪れたことがあります。私はそれまで美術館しか訪れたことがありませんでしたが、映像や音楽を通してアート体験することができ、新鮮でした」「電通が関わっていることを初めて知り、華やかでとても興味がわきました」といった感想も。
そして業務の拡張の観点で、僕が直近で携わった仕事も紹介。製作委員会、実行委員会とは異なるスキームの説明をした。

アートとは直接関係のないとある大規模イベントで協賛企業の1社を担当しており、そこでのアクティベーションを提案、実施を担った。企業のアクティベーション、つまり企業としてのマーケティング・コミュニケーション活動の一環である。中核にあるのはアート活動ではなく企業活動。そこにアートを持ち込む。接続させる。そこでのアートは、いわゆるコミッションワーク(アーティストによる受注制作)ということになる。イベント参加者にとってみれば、眼前に現れた巨大な造形がコミッションワークかどうかなど当然意識することもなく、しかし純粋に楽しみ、イベントは盛況だった。

アーティストが作品を通じて放つパワーを、こういった形で企業活動に摩擦少なめで接続させるのはわるくないと思った。企業がアートと対面することに慣れていく、その一つの形になると感じた。
◆


次のセクションは「教養の拡張」。僕の友人で、アメリカの美術館で学芸員をしているフランク・フェルテンズさんのことを引用しつつ、海外の人と接する時、Nice to meet you.だけだと寂しいですよね、という問いかけからスタートした。
それを踏まえて、横浜美術館のリニューアルオープン記念展とそこで展示されている片岡球子さんの作品を紹介。講義に先立ち、横浜美術館の館長と担当学芸員によるギャラリートークに参加し予習しておいた。片岡球子さんは横浜で小学校の先生をやりながら絵を描き続けていたこと、30代の時にこの絵が院展で入選したのを皮切りに入選し続けて、80代で文化勲章も受章していること。ギャラリートークの受け売り状態で、そんな背景情報なんかもからめつつ、フェリスも横浜の学校ということで、トークの取っ掛かりとして片岡球子さんのことは扱いやすいのでは?と学生に提案してみた。そして、かかりつけのお医者さんや、お気に入りのカフェのように、

と畳みかけてみた。今回の講義で最も反響が大きかった。地元ネタは強い、ということか。いやぁ、予習しておいてよかった。
実際、外交でなくても、また企業のエグゼクティブ層でなくても、自国の文化を話すシーンはビジネスパーソンにおいても確実に増えており、アートの知識や実体験はいわばリアルな教養。日本には美術館や博物館が6000施設近くあるらしい。6000サンプルもあれば予習し放題だ。

そして本筋から離れ、僕が13歳の時に作った版画なんかも見てもらった。中学生の作品ということで、まあこんなもんだよね、という苦笑いはありつつ、僕は作家になれる人生ではなかったものの、ちょっとずつユニークに教養を身に付けることで、こうして大学生の前に立つかけがえのない機会に恵まれた。ささやかで、でもリアルな、1サンプルの提示が実現したと言えなくもない。
◆

最後は、マーケティングの世界の住人として一番大事だと思っている「視野の拡張」。アートを通じた僕にとっての大きな気づきの事例として、アーティゾン美術館での毛利悠子さんの展覧会のことを紹介。(こちらのコラム後半で触れた内容を参照のこと)



それ以外にも、ジェンダーのことについて、アートが促す気づきを提示しつつ、2025年度の電通の新入社員の男女比はどの程度でしょうかクイズ、なんかも出したりした。

正解は、148人のうち女性77人ということで、過半数。僕が入社した時の、女性の新入社員は1割くらいだった状況と比較すると、明らかに母集団そのものが変化している。数字というのは生々しい。さらに、僕の所属長は、今も一つ前の時も女性であること。ビジネスの現場で「Diversity, Equity & Inclusion(DEI)」の観点が標準装備されつつあること。DEIのキモとして、

そんなことを伝えてみた。「盲点が減るという言葉が非常に印象的だった。常日頃から頭に入れておきたいと思う言葉だった」「思っていたよりも時代とともに価値観がアップデートしていて驚きです」といった感想から推察するに、講義の内容が彼女たちにとってもある意味想定外だった、ということか。外に出かけて行って伝えるって、やっぱり大事だなぁとあらためて思い知る。
◆
最後に、学生からの感想をいくつか掲載するが、筆跡含めた彼女たちのリアルに対し、「全部正解」と伝えたい。






画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?