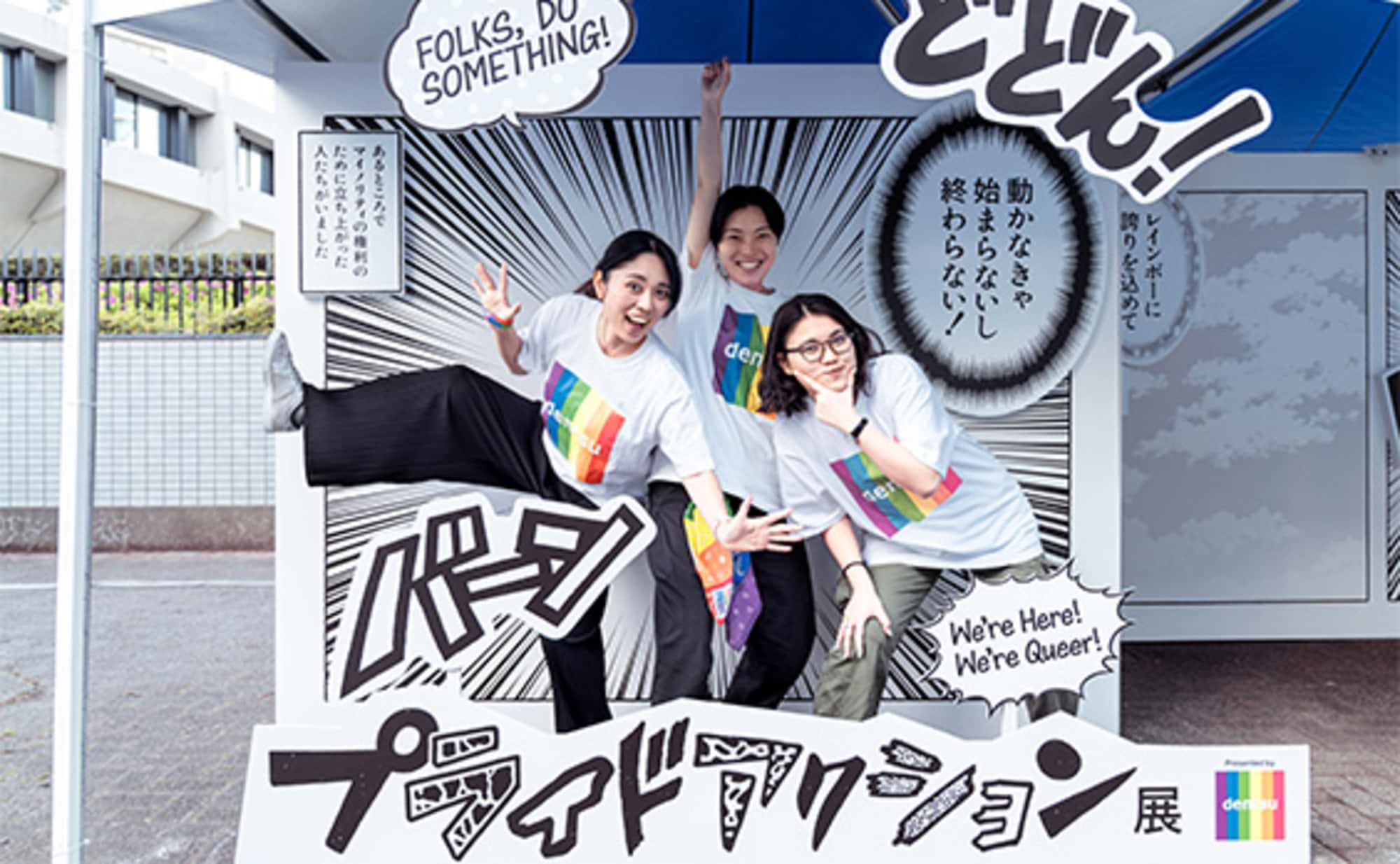社会で、会社で、学校で。誰もが「DEI」や「多様性」と言うけれど、いざ自分がLGBTQ+について何かを尋ねられたら、言葉に詰まってしまう。あるいは、暮らしの中で「正解」がわからず、戸惑って、なかなか一歩を踏み出せない。
そう感じたり、悩んだりしたことはありませんか?
「LGBTQ+について知る・考える・行動する アライアクションガイド」は、そんな悩みに寄り添うためのデジタルブックです。公開から5年目を迎えたいま、構成と文章を担当した筆者が、その誕生背景からこれまでの道のりを振り返ります。
アライアクションガイドとは

「アライアクションガイド」は、LGBTQ+支援のアクションをまとめたデジタルブック。2011年の発足以来LGBTQ+の理解促進や支援活動に取り組んできた dentsu DEI innovations(旧 電通ダイバーシティ・ラボ)が、具体的な支援アクションをまとめています。


2021年6月、「LGBTQ+調査2020」をもとに初版を公開して以来、毎年プライド月間の前後に更新を重ね、表現や解釈をよりインクルーシブなものへと磨いてきました。現在公開しているのは2025-2026年版で、第5版となります。
このガイドは当初から誰でも無償でダウンロードできる転用可能なデジタルブックとして公開してきました。いまでは企業が自社の知見をオープンにして社会と共有することは珍しくありませんが、当時としてはいち早い取り組みでした。
5年で広がった「使い方」
こうして公開されたガイドは、個人でご覧いただくことはもちろん、多くの企業や団体、教育機関で活用されてきました。実際の事例を許諾のもとでご紹介します。
【事例1】三井不動産 人事部 D&I推進室
全社員向けのLGBTQ+に関するe-learningのベース資料として、「アライアクションガイド」を活用しました。ガイドの内容を自社向けに再編集し、スライドとクイズで構成しています。
受講者からは「内容が簡潔でわかりやすい」「図が多くて頭に入りやすい」と非常に好評でした。このガイドは、印象に残る言葉が多く、記憶にも残りやすかったと感じています。中でも「『LGBTQ+は左利きと同じ割合』が特に印象に残った」という意見が多く寄せられ、「自分もアライとして行動を意識したい」といった前向きな声も上がりました。
現在は、三井不動産グループ全体での理解促進のため、グループ各社の研修等に活用できるよう本資料をグループ内に展開しています。

【事例2】ブックオフグループホールディングス ダイバーシティ推進担当
社内でファミリーシップ制度の導入準備を進める中で、まずは担当者の理解を深めるための資料を探していたところ、「アライアクションガイド」にたどりつきました。内容が非常にわかりやすく、すっと情報を受け取ることができ、「LGBTQ+の話ではあるけれど、自分の話でもある」と感じながら読み進めました。
制度の社内周知用資料を作成する際には、このガイドの内容を参考にしながら、社員に伝えるための表現や構成を検討しました。
当事者の社員からは、ファミリーシップ制度について「この会社でLGBTQ+へのサポートは期待できないのではと不安を感じていたけど、応援してもらっていると思い、本当にうれしかった」という声をもらいました。進めてよかったと心から思った瞬間でした。
この他にも、たくさんの活用事例をご報告いただいていますが、共通していたのは、「学びや対話の土台」として使っていただいていたことでした。
「自社の武器」ではなく「みんなの道具」にした理由
こうした使い方を可能にした理由のひとつは、最初から「オープンであること」にこだわった点にあると考えています。もし私たちがLGBTQ+に関する知見を自社内での利用だけに閉じていれば、競争力を高める「武器」にはなったかもしれません。しかしそれでは、DEI(Diversity, Equity & Inclusion=多様性・公平・包摂)の理念そのものに矛盾してしまいます。
DEIは、一部の組織が囲い込むものではなく、社会全体で共有し、育てていくべき価値です。だからこそノウハウを無償公開し、「誰でも使える道具」としました。その選択そのものが、「アクション:行動で示す」という名前に込めたメッセージでもあります。
ただ、ガイドが多くの現場で使われる中で、改めて直視せざるを得なかったのは、LGBTQ+を取り巻く現実は決してシンプルではないということでした。
「完璧な正解」より、「試行錯誤の余白」を
社会で語られやすいのは、整えられた「多様性」です。メディア映えする事例やわかりやすく一貫した“物語”が重宝される。けれど現実のLGBTQ+の姿は、もっと入り組んでいて、複雑で、ときに痛みを伴います。
カミングアウトして生きる人もいれば、しない人もいる。したくても、できない人もいる。したくなくても、せざるを得なかった人もいる。助けを求めたい人もいれば、放っておいてほしい人もいる。そして同じ人が、昨日と今日でまったく違う気持ちや状況を抱えることもある。
アライもまた、「声をかけてよかったのか」「踏み込みすぎなかったか」と迷う。失敗する。後悔する。立ち止まる。
こうした揺らぎを「きれいな正解」で覆ってしまうのは危ういことだと思います。そこから外れた人が排除されたり、「正しくふるまえなかった」と萎縮してしまったりするからです。現実は、わかりやすく整えられるほどに一様ではなく、常に変化し続けている。必要なのは、完璧な完成品ではなく「まずここから」と始められる手がかりなのではないでしょうか。
だからこそ、アライアクションガイドは、「完璧な正解を押し付ける書」ではなく、「迷ったときに背中を押す未完成な道具」でありたいと考えています。


広告人がDEIに向き合う強み
この「試行錯誤の価値」は、広告の現場にも通じていると思っています。
広告づくりの現場も、最初から思い通りに進むことはほとんどありません。多様な人が関わり、意見がぶつかり、衝突も起きます。何度もやり直しを繰り返し、ときには失敗もします。それでも、へこたれずに立ち上がり、次の方法や新しいアイデアを探す。その積み重ねの先にようやく一つのメッセージや表現が生まれる。しかし、そのあとも「本当にこれでよかったのか」とくよくよしながら、今度はもっとよくしようと思う。
広告人は、試行錯誤を続けるだけでなく、立ち上がり続ける訓練を受けてきた人たちだと言えるかもしれません。
この点で、広告づくりとDEIの実践は似ていると思います。どちらも衝突や葛藤が避けられず、迷いや失敗を経て進んでいく。だからこそ広告人が培ってきた「試行錯誤し続け、立ち上がり続ける力」は、DEIにおいても役立つと思うのです。自信とか、自慢とかじゃなく、私たち広告人への励ましとして。
ただし決定的な違いもあります。広告づくりでは、試行錯誤そのものは通過点にすぎず、形にならなければ徒労に終わる。しかしDEIは違います。試行錯誤や衝突そのものに価値がある。分断されがちな「私たち」と「あの人たち」をかきまぜ、新しい理解や関係を生むきっかけになるからです。
だからこそ、私たち広告人がDEIに向き合うときは、成果を出す力だけでなく、「試行錯誤の過程そのものを肯定する視点」を自然と持ち込むことができる。それが強みだと思っています。


未完成のまま、ともに進む
公開5年目を節目として、「アライアクションガイド」について、あらためて言葉にしてみました。制作当時からここまで明確に考えていたわけではなく、そして、もちろん一人でつくったものではないので、チームで迷いながら書き直し、試しては調整する中で、形になったものです。
「アライアクションガイド」の構成・文章を担当した私がいま言えるのは、LGBTQ+の現場はもっと複雑で、衝突や痛みも伴うものだということ。そして多様性やDEIとは、見栄えのよい取り組みを整えることではなく、その複雑な現実に向き合い続ける営みではないかということです。
このガイドは、完成品ではなく、現場で悩む誰かに「まずやってみよう」と思ってもらうための道具でありたい。これからも未完成のまま、10年、20年と更新を重ね、前に進む力をみんなで分かち合いたいと思います。
これからも「アライアクションガイド」をよろしくお願いします!
記事編集:増山晶(dentsu DEI innovations)
この記事は参考になりましたか?
著者

福居 亜耶
株式会社電通
第6CRプランニング局
コピーライター/CMプランナー
CMプランニングやコピーライティングを中心としたクリエイティブ業務に従事しながら、社内外のDEI推進やサステナビリティ関連の取り組みにも携わる。