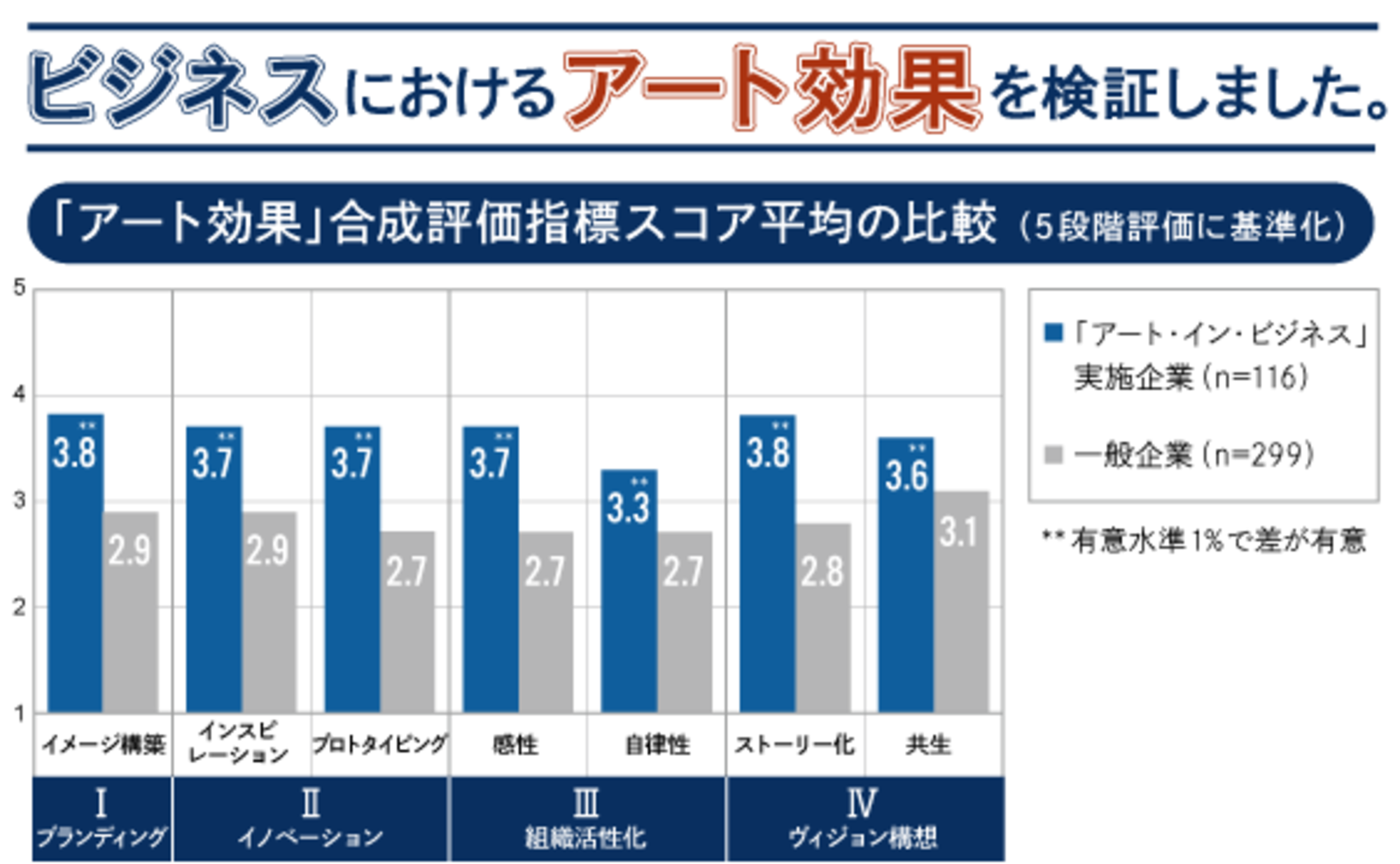「アート・イン・ビジネス最前線」の連載第5・6回では、医師であり美術回路(※)のメンバーの1人でもある和佐野有紀氏による、「アートと私たちの関係性」をテーマにした寄稿をお届けします。
(※) 美術回路:アートパワーを取り入れたビジネス創造を支援するアートユニットです。専用サイト。
**
はじめまして。美術回路メンバーの和佐野有紀と申します。
何が本業かは分かりませんが、私は医師をしながら、「PROJECT501」というアートプロジェクトのディレクションや、アート、ビジネス、社会界隈のリサーチをやっています。最近、代官山ロータリークラブというところに入れていただいたので、肩書にロータリアンというのも追加しようかと思っています。
のっけから盛りだくさんになってしまいました。
さて、医療とアートとビジネスというと、一般的にはあまり関係のないものに見えるでしょうし、全てに携わる立場からしても現時点で直接のつながりはないと思います。
でも本当は、医療もアートもビジネスも、根源的には同じコトなんじゃないかと思っています。
ビジネスの語源はbisignisseというアングロサクソン系の単語で、英語のcareとかanxietyという、「心配や不安、その対処」を意味する言葉です。昨今「ビジネス」というと、経済合理性が絶対条件かのように捉えられがちですが、本来は他者を「心配し、注意をはらう」ことが“結果的に”価値をもたらし、それが評価につながったという流れだと思うんです。
そう考えると医療はかなり語義に忠実な意味でのビジネスですし、アートなんてまさにその最たる例です。アーティストは他者や社会をよくよく観察して、そこから気づきや違和感みたいなものを抽出し、表現という手段を用いて周りを巻き込みながら、積極的に自分の外の世界に関わっていきます。その意味では、本来的なビジネスそのものにも感じられます。
「ビジネスの目的は経済合理性の追求ではない」
私はそう思っています。
他者、そして自分を含む社会・世界をつぶさに観察して、心配事がないかを注意深く点検する。先ほど書いたように、想像をめぐらせたうえで「他者のために何らかの価値をもたらす行為」こそがビジネスの目的なのかなと思います。
その結果として、経済的評価が後からついてくるというイメージです。経済合理性はそのまま自律性につながるので、よりよいビジネスを継続していけるというサイクルが生まれます。
ある意味エッセンシャルなこういった枠組みは、景気や社会的な気分のいい時にはけっこう見過ごされがちです。が、例えば地球が危ない、みたいな世界的危機が共有されつつある現在のような時期には、SDGsや社会的インパクト投資のような、やや時間軸の長い事業評価の目線は回復されがちなところもあります。だからこそ今みたいな時には利他の精神がかえって実感されやすいのかなぁとも思います。
ちなみに、これはアートにおいても同じで、「美は目的とされるものではなくて、結果的に宿るもの」だと言われています。「網膜的な美しさ(を目指すこと)に惑わされるな」というのは、20世紀以降のアーティストの多くが口にするところでもあるんです。

壁に設置された台の上には、一つのりんご(本物?)と、それを支える手(たぶん本物)。ということは壁の後ろには、向かい合う誰かがいる可能性があり、さらにその手を壁に塗りこめるという行為が存在した可能性もある。見ているうちに、我々の見ていると思っている世界のどこまでがリアルなのか? 誰が見ていて誰が見られているのか? そもそもこの世界の境界はどこまでなのか? など人間存在についてのかなり根源的な感覚が揺さぶられる新しい体験へといざなわれる。アートは、これまで見えていた世界がまったく別物に見えてくるという魔法の装置でもある。
そうなんです。アートというと、やはり美しさに価値があるのかなぁと思うのですが、それがそうでもない。
著者の1人として参加した「アート・イン・ビジネス—ビジネスに効くアートの力」のなかでも書いたのですが、アートの本質は「問いかけ」にあると思っています。これはよく言われることなんですが、本当にそう思います。そして、良質のアーティストは問いをたてるプロフェッショナルだと感じます。
アーティストは絵のプロフェッショナルではなく、問いを立てるプロフェッショナル
アーティストはものすごくよくモノを知っているんです。そしてものすごくよく世界を観察している。
飽きることなく、寝ても覚めても自分のなかで設定された主題を軸に、世の中の動き、人の表情や反応、そして世界の今、そして未来などを見続けているんです。アーティストってよく絵が上手とか思われがちですけど、それだけじゃなくて観察のプロ、そしてそこからの問いを設定するプロだなぁと私は感じます。ある意味とても執念深くて、それでいて柔軟。
「いかにして都市で遊ぶか」をテーマにグラフィティやスケートボードカルチャーの視点から街を読み込んでいく「SIDE CORE」というアートコレクティブがいます。メンバーもあえて固定せず、その時々で変態していくって意味でもとても新しくて現代的な組織なんですけど、そこに参加していた「EVERYDAY HOLIDAY SQUAD」は、渋谷をテーマに作品をつくる中で、実際に渋谷で生活しているホームレスにカメラを預けて写真を撮ってもらい、それを作品として展示したりしていました。
その写真には、私たちの歩いている渋谷の街が、見たこともないような切り取られ方で写っていて、ものすごく新鮮でした。彼らは、例えば、渋谷圏の都市開発について何か申し立てるわけでもなく、ホームレスをめぐる問題について声高に主張するわけでもなく、ただフラットに、「街をこんな風に見ることもできるんだよ」と投げかけるだけなんです。
けれど、それを観た私たちは、結果的に何かを考えさせられてしまうという仕組みになっているんです。なかなかそういうのって、いわゆるビジネスの形で目指してもむつかしいことなんじゃないかと感じます。


渋谷の路上で生活しているしゅうかんさんの撮った写真には、彼の荷物が映り込み、そして我々の知らない顔でレンズをのぞき込む人々の顔が映っている。よく知っているはずの渋谷の街を、全く新しい視点で捉える経験から、見る側はさまざまに感じ取ることができる。
なるほど。たしかに、何か明白なメッセージを伝えるとかでなく、でも何か考えせられます。
見ている人の育ってきた場所や環境、そして現在の生活や仕事などなど。沢山の要素によって全く違った見方ができる可能性を許容する、余白を残したものを提示するっていうのも、アートの特性の一つだと思っています。
私は、医師として働いていて、患者さんの病気を治すこと、患者さんを少しでも長く生きさせるといったことを目指さなくちゃならないってかたくなに思い込んでいた時期がありました。それでああしろこうしろと、患者さんを誘導しなくてはならないと使命感に駆られていたことがあるんです。でもなかなか、こっちの想うようには患者さんは動いてくれず、言う事を聞いてくれなかったりするんですね。その上、嫌われたり、不信感を与えたりもして。
それである時、ふと気づいたんです。うまくいかない患者さんのことをちょっと嫌いになり始めている自分に。そして「相手のことを好きにならないと伝わらないんだ」という、かなり大切な事実を見落としていたことに。
相手のことに興味を持って、好きになることで初めて、相手の見ている世界が見えてきて、その世界のモノの見方で情報を翻訳しながら伝えることが、コミュニケーションにおいては不可欠だったことを悟るんです。
それに気づくまで、医者になって5年くらいはかかりました。歳でいうと30前くらいだったと思います。ある程度自分の知識と経験がまとまってきたなぁという思いと、それでも伝えられないもどかしさに悩んでいました。
でもそこで気づいたのは、「あぁ、これってアートと同じなんだ」ってことだったんです。
医師の仕事がアートと同じ?
アートを見るとき、作品の中に含まれる情報は沢山あって、そこから何を読み解くかは、見る側の個人の文脈や気分に委ねられます。それは本当に千差万別なのですが、アーティストはそのすべてを許容しています。
「この作品はこのような意味があり、このようなメッセージが含まれるので、こう感じてください」などと指定する作品はありませんし、その行為の強要自体そもそもアートではありません。医師の仕事、そして多くのビジネスも同じだと思っています。
「こういう問題がある可能性があるよ」
「もっと知ることもできるかもしれないし、でも知らなくていいかもしれないよ」
「解決するにはこういう手段があるよ、そもそも解決ってなんだろうね?」
絶対にこうしてほしい、と相手(鑑賞者、患者、顧客)に何かを強要するのではなく、上のような問いを含む情報を、相手に合わせて理解してもらいやすい文脈で提示する。これらの問をうまく伝えて、自分ごととして考えてもらう機会をつくることが、医師の仕事の本質であり、ビジネスの本質でもある、「心配し、注意をはらう」ことなのだと今は考えています。
ちなみに、その伝え方に王道なんてものはなくて、それぞれにしかできない極めて属人的な伝え方であればあるほど、意味を持つのかなぁと思います。
そして、なるべく分かりやすく伝えるためには、相手の視点を知ることがとても大切で、その根底には好奇心や好きになる力も重要かなぁと思っています。このあたりは、次回紹介するアートのコレクターの目線につながったりもするからおもしろいです。
ビジネスとアート、意外なところで実は同じものなんだ、というお話でした。
(後編に続く)
参照
雨宮庸介:http://amemiyan.com/
1300年持ち歩かれた、なんでもない石:https://ishimochi.com/
SIDE CORE:https://www.facebook.com/SIDE-CORE-295528030850334/
この記事は参考になりましたか?
著者

和佐野 有紀
アートコミュニケーター/医師
東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2018年、慶應義塾大学アートマネジメント分野にて前期博士号取得。研究テーマはアートマーケティング。現代アートコレクターの購買行動についてリサーチ。アート/アーティストの価値をきちんと知覚できる社会の実現、アートを基軸に自己と世界のあり方に意味を紡ぐことのできる豊かさの実装を目指し、原宿でPROJECT501(http://project501.tokyo/)を主宰。コレクターがアート購買にいたる過程をナラティブに紹介。ビジネスにおけるさまざまな手法を介したアーティストの価値化のリサーチを行う。趣味は妄想。特技は読書。