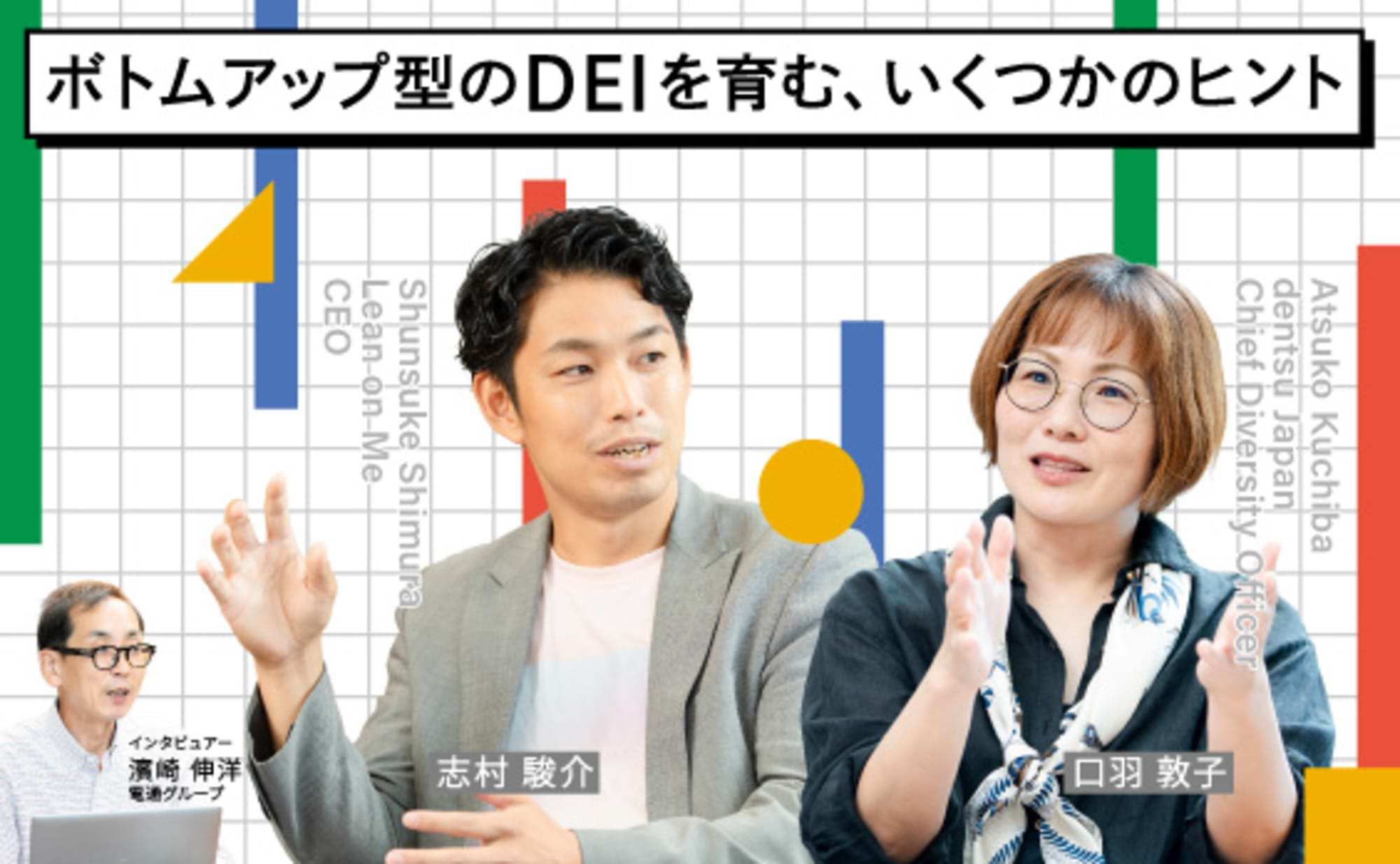経産省×電通対談。企業や組織にとって、なぜDEIが必要なのか?

相馬 知子
経済産業省

口羽 敦子
dentsu Japan
企業にとって、なぜDEI(Diversity:多様性、Equity:公平性、Inclusion:包摂性)が必要なのか?
DEIの重要性が叫ばれる中、その「目的」が曖昧なまま、形式的に取り組んでいる企業も多いのではないでしょうか。
経済産業省は、2025年4月、「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を公表しました。
同レポートでは、DEI実現による「日本企業の競争力強化」という観点を特に重視。企業の経営層をはじめ、幅広いビジネスパーソンにダイバーシティ経営の重要性を伝えるとともに、さまざまな知見を取りまとめて発信しています。
同レポートでは、ダイバーシティ経営とは以下として定義されています。
企業は、同質性が高い状態から脱却し、経営戦略実現に必要かつ多様な知・経験を持つ人材が活躍することができる環境の整備と、組織文化の醸成を行うことで、イノベーションを生み出し価値創造につなげていくことができる。
(ダイバーシティレポートP.4「経営陣へのメッセージ」より)
dentsu JapanのCDO(チーフ・ダイバーシティ・オフィサー)として、国内電通グループ全体のDEI実現に日々取り組む口羽敦子氏が、同レポートをまとめた経済産業省の経済社会政策室長・相馬知子氏に、日本企業のダイバーシティ経営推進に当たっての課題と解決策について伺いました。

<目次>
▼2025年のダイバーシティレポートは、より「競争力」にフォーカス
▼「知と経験の多様性」が企業の生き残りの鍵となる
▼トップダウンとボトムアップの両輪で企業のカルチャーを変えていく
2025年のダイバーシティレポートは、より「競争力」にフォーカス
口羽:まず、このレポートがどういうものなのか、簡単にご説明いただけますか?
相馬:昨年の秋に立ち上げた「多様性を競争力につなげる企業経営研究会」での議論を集約したものです。読み手としては、イノベーション創出をしていきたい企業、国際競争力を高めていきたい企業の経営陣を想定しています。
口羽:今も日本企業はDEIに取り組んでいますが、まだ形式的なものにとどまっている企業も多いと聞きます。そんな中で、このレポートでは「これからはもっとDEIを企業の競争力強化につなげていきましょう」という強いメッセージが一貫して出されていると感じました。2017年の「ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン」のときと比較して、「競争力」によりフォーカスした理由を教えてください。
相馬:経済産業省では、以前より「企業価値に繋がるダイバーシティ」という考え方のもと、さまざまな政策を行ってきています。2017年と比べると現在は、日本企業の間でも人的資本経営がかなり根付いてきていて、法律の改正もあり、DEIへの取り組みについての情報開示も進んでいます。一方で、「DEIを競争力につなげる」という目標が果たされているのか?という視点でデータを見ると日本企業の競争力は未だ高いとは言えない状況です。また、日本企業の経営者のアンケートを見ると、皆さん「人」という部分に課題を感じていらっしゃいます。
そんな背景もあり、「本来実現したいことである、競争力につなげるダイバーシティを実現するにはどうしたらいいのか?」を議論すべく、有識者を集めて研究会を立ち上げました。その研究会の成果が今回のレポートです。

口羽:レポートの中で、企業のいろんな悩みをまとめているページがありましたが、とても生々しくて共感しました(笑)。ああ、どこの企業も同じポイントで悩んでいるんだなと。経済産業省としては、DEIそのものが日本の国全体の競争力に直結すると考えていらっしゃるんですね。

相馬:そうです。ただ経済産業省だけでなく、政府全体に危機意識があります。厚生労働省をはじめさまざまな省庁が、それぞれの機能に応じて取り組んでいますが、その中で経済産業省の役割になるのが、「企業の競争力強化」というテーマです。ただ、企業は社会とつながっているものであって、企業の活動だけで課題が全て解決するということはありません。
経済産業省がこういうレポートを出すことで、グローバル企業、中小企業、あらゆる職場・職域でDEIが進み、結果として社会全体のDEIが進むとよいと考えています。
口羽:社会全体で一斉にやっていかないと進まないということは、私もDEIを推進する立場として、日々痛感しています。例えば、「仕事と子育てを両立している女性従業員」というクラスタがありますが、電通という一企業として働きかけるには限界があります。つまり、家に帰ってから先の、パートナーの働き方にまではアプローチすることは難しい。その背景には、日本人全体の意識や価値観、社会構造の影響があります。
相馬:日本だとまだ女性の家事労働の負担が大きく、政府も問題意識を持っています。解決を目指して男性の育休取得の推進なども進めていますし、経済産業省では東京証券取引所と共同で、女性の活躍を支援している上場企業を「なでしこ銘柄」として選定しています。また、「共働き・共育て」をテーマとした施策も推進しています。
口羽:女性活躍についていうと、毎年発表される「ジェンダーギャップ指数」がショッキングで。「教育」「健康」といった分野のジェンダーギャップは、日本はとても優秀で、世界でもトップレベルです。一方で「政治」「経済」ではずっと下位に沈んでいます。
相馬:まさに、その「教育」では上位というところ、ですよね。しっかりとした教育を受けた人たちが、社会で十分に活躍できていないとしたら、それは損失と言えます。
「知と経験の多様性」が企業の生き残りの鍵となる
口羽:もう一つ、2017年との大きな違いとして、「知と経験の多様性(知と経験のダイバーシティ)」という言葉を強く打ち出されていますね。
相馬:企業の競争力という観点では、性別・障害の有無といった外から見えやすい部分の多い属性のみならず、一人一人の知識や経験そのものに着目した方が、説得力があると考えました。2017年のガイドラインでもこの考え方は含まれていますが、「知と経験の多様性」というフレーズ自体は、人的資本経営の文脈で使われる言葉で、経済産業省から発信している「人材版伊藤レポート2.0」の中でも重要なキーワードになっています。そこと揃えた言葉を使うことで、よりメッセージが伝わりやすいと考えました。
ですがもちろん、「性別」「障害の有無」といった観点の多様性も大事です。それらが違えば経験していることも違うし、いろいろなものの見え方が違うので。
口羽:属性にフォーカスすると、「多様性といえば、女性や障害のある方のための取り組み」という受け取りをされることも、残念ながらまだあります。「企業の競争力を高めるための知と経験の多様性」という言い方をすることで、受け取ってもらいやすくなるのではと思いました。それが本質でもありますし。
私もグループ内で従業員に説明する際は、「私たちは、クリエイティビティやアイデアによって、今の世の中にない新しい価値を生み出すことで125年間やってきました。これからもその領域で成長し続けるには、自分と違う視点や経験を持つ人と、どれだけ掛け算できるか。それこそが競争力そのものです」という話をしています。
そして、そのための一歩として、ジェンダーを含むマイノリティ属性の多様性があるんだという話をするのですが、その2つには乖離(かいり)があると感じる方もいます。

相馬:そこは本当に難しいですね。一つあるとしたら、「インクルージョン」の観点だと思います。DEIのうち、ダイバーシティは「そもそも人は多様である」という前提ですが、インクルージョンは、「その多様な人たちみんなのもの」です。つまり、マイノリティだけのものではないんです。
属性にかかわらず、一人一人がしっかり意見を言えたり、能力を発揮していくのが、インクルージョンの本質です。この「一人一人違う」という視点は本当に重要です。例えば、「それでは、女性ならではの視点で発言してください」など、逆に属性に縛られるようなことを言われても困りますよね(笑)。
口羽:それはなんだ、となりますね(笑)。
相馬:とはいえ、属性は関係ないと言い切れるかといえば、女性と男性で社会の見え方には異なる傾向はあります。外国人従業員も日本人従業員と違う見え方があります。属性によって経験していることも違えば、不便を感じていることも違うので、日本の社会構造を考えたら、それぞれの属性に応じた対応は必要ですよね。
組織の中である程度属性がばらけていることは、知と経験の多様性を実現する上でも合理的だと思います。そもそも社会を生きる人間の半分は女性なので、その人たちがしっかり力を発揮して活躍できる環境を整えるのは、スタートラインかなと。
口羽:属性をばらけさせることが目的なのではなく、属性をばらけさせることで知と経験の多様性が必然的に生まれ、それがイノベーションにもつながるということですね。インクルージョンはみんなのもの、みんなが能力を発揮できるようにするためにはそれが大事、ということですね。
今、海外ではDEIに対する揺り戻しがありますが、そもそも多様性に富んだ国と比べたら、日本はまだ1周も回っていない状況だと思います。今回のレポートで「変わらず国としてDEIに取り組んでいく」と示していただいたのは、不安を感じながらDEI推進をしている企業にとっても、心強く、背中を押してくれるものだと感じました。
相馬:企業や国の競争力を高めようという本質は変わっていないので、そこはしっかり進めていただきたいと思っています。変化の激しい時代であり、なおかつ日本では人口減少が続いています。ビジネスのグローバル展開を進める企業も増える中で、あらゆる変化に強く、これまでにないイノベーションを生み出していくためには、組織として知と経験の多様性がないと、もはや立ち行かなくなっていくと考えています。
トップダウンとボトムアップの両輪で企業のカルチャーを変えていく
口羽:日本企業のDEIの取り組みにおける課題はどこにありますか?
相馬:どの企業もベースとなる情報開示や法律対応はしっかりやられていると思います。ですが、その情報開示も、ただ開示するに留まっている企業と、自社としてのプラスアルファを付けて開示している企業とでは、かなりの違いがあります。いろいろな属性に対する対応も、雇用数など数字の上で達成しているところは多いのですが、それが本当に競争力につながる「みんなのインクルージョン」になっているかというと、これもばらつきがあるのが現状です。
今回、レポートと同時に、企業の課題に応じた打ち手、具体的なアクションを公開しています。ですが、研究会の委員とは「このアクションを、順番にこなしていくチェックリストにはしたくないね」と話しています。1社ごとに事業環境も、事業戦略も、何もかも違うわけですから、自社の状況に応じてアクションを選択して組み合わせて進めてほしいというメッセージも書きました。

口羽:この「アクション」は、私にとって一番学びが多く、日々DEIを推進している立場として強く共感しました。いくつか掘り下げて伺いたいのですが、まずアクション2の「推進体制の構築」です。ここに「ボトムアップでの推進体制構築」ということが書かれています。

口羽:2024年の1月から今の立場でDEIを進めてきた中で、強く感じているのは「トップダウンで制度やルールを作るだけでなく、ボトムアップと両輪でないと回っていかない」ということです。
トップダウンで制度を作ったり、数値目標を積み上げていくこと自体は、実はやろうと思えばそこまで難しくありません。ですがボトムアップ、つまり一人一人の従業員にDEIをインストールして、会社の本当のカルチャーをつくっていくことが、最も大事なんです。これが実現できなければ、形式上のDEIに終わってしまうんですよね。

相馬:そうですね、多くの企業が同じ課題を抱えていると思います。
口羽:1年やってきて、私の中で一つの解は、「自社の従業員の強み」にフィットするように、DEI推進の施策をデザインすることだと思っています。私たちグループの従業員の強みは、一人一人の中にアイデアがあるし、「やってやるぜ」というパッションと実行力が内在している人がすごく多いところです。その強みを生かすために「DEIパーク」という施策をやっています。
国内電通グループの約140社から半期に1回、リーダーを選出してもらい、集まってもらいます。そこでDEIの基本知識を学びつつ、「自分の組織のDEI課題は何か」を考えてもらい、そのためのアイデア、企画、アクションを自分で練って、自分の組織で実行してもらうという取り組みです。そうすると、半期に1回、200以上の施策がボトムアップで生まれているんです!
相馬:いいですね!
口羽:それがとてもユニークな上、各組織の課題にしっかりとひもづいています。トップが「これをやりましょう」と言って一律な取り組みをやるよりも、現場で一緒に働いている人が「一緒にやろう」と言う方が、圧倒的に動かす力があるし、組織のカルチャーに与える影響も大きいと感じています。
相馬:まさにDEIは、「企業カルチャーの変革」なんですよね。組織の隅々までDEIの考え方が染み渡り、一人一人の行動が変わるということなんだと思います。お話を伺って、特にいいなと思ったのは、グループ一律ではなく、「組織ごと」に課題を見いだして、アクションを考えているところです。一つ一つの組織ごとに、現場の事情は全然違うわけですからね。
トップとボトムの話でいうと、社長や役員と従業員が意見交換する場を設けている企業もあります。そういうセッションは、経営戦略の浸透やカルチャーづくりのためにやっている場合も多いのですが、実はDEIの取り組みとかなり重なっているんです。
口羽:私たちも意見交換の場を設けていますが、DEIの冠を付けると、不満を感じている方や、疎外されていると感じている方が来てくださいます。そこで怒りや、本音をぶつけてくださるんです。私はそういうとき、「みんな見て!こういう方が私たちの組織にはいるんだよ!」と思っています。
相馬:みんなから見えていないという。
口羽:そうなんです。今まで見えていなかった方が可視化されて、そういう場で意見を出してくださることに大きな価値があると思います。特にシニア雇用に関しては、いろいろな意見がありますね。
相馬:シニア雇用もDEIの大きなテーマですね。これは「世代の多様性」が企業の競争力につながるということですが、日本の人口減が急速に進む中で、シニアの方にいかに活躍していただくかという観点は重要です。
<後編に続く>
・dentsu JapanのDEIサイトはこちら
https://www.japan.dentsu.com/jp/deandi/
この記事は参考になりましたか?
著者

相馬 知子
経済産業省
経済産業政策局経済社会政策室長
新卒で日立製作所に入社後、事業部門・工場・海外拠点等において、一貫して人材・組織関連の業務に従事。2020年5月からは、本社にてグループ全体のDEI推進に携わる。2023年8月より現職にて、日本企業におけるダイバーシティ経営の浸透に取り組む。

口羽 敦子
dentsu Japan
エグゼクティブ・マネジメント チーフ・ダイバーシティ・オフィサー 兼 ヘッド・オブ・サステナビリティ/電通そらり 取締役
タイの国立大学を卒業し、タイでキャリアをスタート。その後、電通へキャリア入社。以降、主にマーケティング部門で、国内外での事業開発やマーケティングなど、あらゆる業界のプロジェクトをリード。プライベートでは、八ヶ岳で週末2拠点生活を営みながら、地域の仲間と循環社会を目指す団体を立ち上げ活動中。