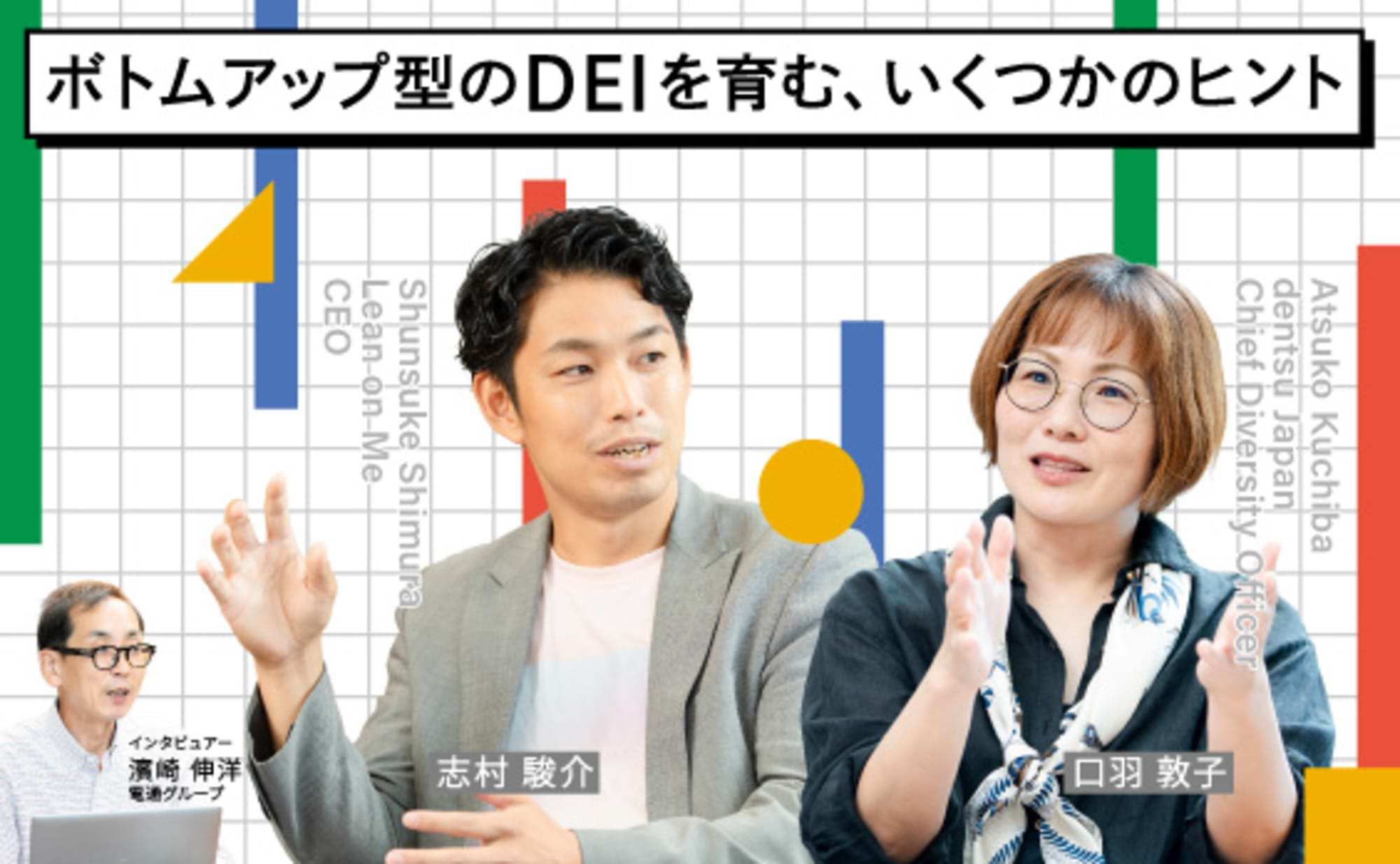経産省×電通対談。DEIがインストールされていくと会社は強くなる

相馬 知子
経済産業省

口羽 敦子
dentsu Japan
経済産業省は、2025年4月、「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を公表しました。
本連載では、dentsu JapanのCDO(チーフ・ダイバーシティ・オフィサー)として、国内電通グループ全体のDEI実現に日々取り組む口羽敦子氏が、同レポートをまとめた経済産業省の経済社会政策室長・相馬知子氏にインタビュー。
前編では、ダイバーシティレポートの真の目的やダイバーシティ経営を推進するポイントについて伺いました。後編では、実現のための具体的な方法や今後の展望についてお聞きします。
前編:経産省×電通対談。企業や組織にとって、なぜDEIが必要なのか?

<目次>
▼変化の激しい時代に求められる管理職の資質とは?
▼インクルージョンは「みんなのもの」
▼あと必要なのは、経営層の「決断」だけ
▼DEIがインストールされていくと会社は強くなる
変化の激しい時代に求められる管理職の資質とは?
口羽:前編でお話したアクション2に続き、印象に残ったのがダイバーシティレポートのアクション4「管理職の行動・意識改革」についてです。これからの企業に求められるリーダー像が明確に言語化されていると思いました。具体的に、「変化をプラスに捉え対応できるリーダー」「多様な部下の活躍を支援するマネジメント」と書かれていますね。

相馬:研究会で議論をする中で、「そもそもなんのための多様性なのか」と考えたときに、急速に変化する社会の中で確かな価値を生み出していくことが重要であろうと。そのため、「変化をプラスに捉え対応できる」という言葉をしっかり入れることになりました。
変化の激しい時代だからこそ、ダイバーシティが生きてくるんです。なので、管理職の役割は今まで以上に重要です。自分自身が変化に対応できることも必要ですし、部下一人一人の多様性を理解、支援し、成果を出せるマネジメントをする必要もあります。
口羽:dentsu Japanでは、2024年に管理職の定義を刷新しました。それにより、グループ内では管理職の多様性が一気に高まった会社もあります。この変化で女性管理職の数が増えたという数値上のことではなく、「女性管理職が増えるとは、こういうことなんだ」と、みんなが実感できたと思うんです。
例えば、今まで「もの静かでマネジメント向きじゃない」と思われていた女性従業員が、実はその人の周りですごく部下が育っていることが可視化されたり、みんなが相談しやすいことで組織の心理的安全性に貢献していたり。管理職に女性が増えた結果こうなった」という効果が大きく、私も含めて、意識が変わったと思います。
経済産業省の描くリーダーシップ像の先に、こういった定義の刷新など、具体的なアクションが追加されたら、多くの企業で意識変革が起こるのではないでしょうか。
相馬:まさに、具体的な企業の事例調査について検討し始めているところです。ある委員の方が、「カルチャー変革につなげていくには、管理職の行動を変えるのが重要だ」とおっしゃったんです。そして行動を変えるためには、評価基準をしっかり定めることが重要な要素の一つです。いくら「ダイバーシティやインクルージョンは大事だ」と思っていたとしても、現実にはどうしても評価基準に合わせて行動してしまいます。その観点から、今回、今求められるリーダーシップ像を詳細に書いた経緯があります。
インクルージョンは「みんなのもの」
口羽:もう一つ心を打たれたのが、アクション5の「従業員の行動・意識改革」です。特に「自分の中の経験の多様性」を高めるという部分です。例えば、育児休暇の取得のような「経験」も、企業の競争力につながるというメッセージだと受け取りました。

相馬:そうだと思います。「知と経験の多様性」には、1人の中に多様な知と経験があるだけでも、組織として多様になるという発想も含まれます。例えば、3人しかいないチームで新たな採用もできないといった場合にどうやって多様性を担保するかというと、外部とコラボするか、一人一人が多様な視点を持つか、の2つです。よく育休を取得した男性が「今までと全然世界が違って見えるようになった」というお話をされますよね。あるいは大学院に通ったことで新しい視点を手に入れたというのも、「経験の多様性」と言えます。

口羽:アクション5には「自己と異なる属性や価値観を持った多様な他者を受容し協働する」とも書かれています。ただ受容するだけじゃなく、違いを生かしあうというお話だと受け取りました。
例えば、マイノリティのインクルージョンを考えたときに、LGBTQ+の人や、障害のある人と一緒に働くことの意味は何かということです。ただ単に属性が違う人の能力を発揮してもらうというだけじゃないと思います。自分と属性が異なる相手には、「自分には見えていないもの」が必ず見えているはずで、そういう多様な人と物の見方をぶつけ合ったときに、これまでになかった視点が生まれて、イノベーションや競争力につながるんだと。
相馬:おっしゃる通りです。DEIは、マジョリティがマイノリティを受け入れてあげるという話ではありませんよね。だから「インクルージョンはみんなのもの」だと言っています。マジョリティ属性の人たちに、「わたしたちも多様性の一部で、インクルージョンされる人なんだ」という意識を持ってほしいですね。
口羽:「支援・配慮」ではなく、お互いがそれぞれ強いもの、違うものを持っているから、その違いを自分の強みにしてほしいというメッセージを感じました。日々DEIを推進している人が、自分の悩みを通してこのレポートを読むと、そういう深みを感じるんです。
相馬:そこまで読んでいただけると、うちのメンバーもうれしいと思います。
あと必要なのは、経営層の「決断」だけ
口羽:DEIが形式的な取り組みにとどまっている企業の方に、次の一歩を踏み出すためのアドバイスをいただけますか?
相馬:今日お話ししてきた通り、競争力強化やカルチャー変革という意識を持ってDEIに取り組むことだと思います。どんな経営者の方も、もっと会社の競争力を上げたい、良い企業カルチャーにしたいと思っていますよね。経営戦略を考えるときに、「自社にとって多様性ってなんだろう」という視点を取り入れていただくと良いと思います。
今回のレポートに、企業の取り組み事例をいくつか載せているので、自社の状況と照らし合わせて参考にしていただきたいです。ウェブを探せばたくさんの取り組み事例がありますから、その中から自社に合いそうな事例を参考にしていただくといいのではないでしょうか。
口羽:「DEIと競争力」という観点で悩みがあるんですが……DEIを導入して競争力が強まるのだと証明しようにも、変数が多く、因果関係を説明するのが難しいですよね。

相馬:委員会の中でもそのような議論を行ったのですが、そこは結局、経営者の決断だと思います。DEIに限らず、企業活動のすべてにおいて同じことですが、最終的には経営者の決断に尽きるなと。例えばマーケティングでもなんでも、「これをすれば必ず成功する」というものはないけど、「こういう材料があるから、きっと成績が上がるはずだ」と思ってやるわけじゃないですか。このレポートに載っているようなデータを見て、経営者が「やる」と思えるかどうかなんですよ。「思える」ようになってほしくて、このレポートをつくっています。
レポートにはいろいろなデータを載せています。例えばダイバーシティやインクルージョンの認知度が高い従業員ほど、心理的安全性や会社へのエンゲージメントのスコアが高いといった調査も載っています。心理的安全性やエンゲージメントが高い方が、企業経営として良いという、決断のためのデータとして使ってほしいです。
DEIがインストールされていくと会社は強くなる
口羽:最後の質問です。ダイバーシティ経営を推進することで、どんな日本社会をつくっていきたいですか。
相馬:今や日本の人材不足は深刻な問題です。これまで会社が定めてきた人材像を必ずしも100%満たさない人であっても、企業に加わって能力を発揮して活躍してもらわないと、企業経営自体が立ち行かない時代になります。そもそも、社会は多様な人で構成されています。多様な一人一人が自分の力を発揮できないことは社会にとっての損失です。誰もが生き生きと活躍して、生活できる、そんな社会への一つの道筋が、企業におけるダイバーシティ推進だと考えています。
女性活躍一つを例にとっても、ジェンダーギャップ指数を見る限り、まだまだ力を発揮する余地があるのは、データに出ているわけですよね。日本は社会的に豊かで、良い教育を受けた人がたくさんいます。その人たちが自分らしく力を発揮することで、得られる経済的なプラスは大きいはずです。
口羽:そうですよね。新しいビジネスを生みだすには優秀な人材が必要ですが、多様な人が活躍できない職場には優秀な人も来ません。そんな中でどうやって会社を引っ張っていくのかが、経営者に問われていると思いました。
相馬:例えば昨今、重視されているデジタル人材をダイバーシティの視点で見ると、今まではものづくりが中心であった企業にとって、デジタル人材は、まったく異質な人になりますよね。スキルも違うし、おそらく働くことへの考え方も、給与体系も違うかもしれない。
経験者採用をして、これまでと同じ制度で同じカルチャーでやろうとしても、同質性の高い企業の場合、うまくいかないと思うんです。デジタル人材に限らず、多様な人材の知と経験を会社に入れようと思ったら、インクルージョンが必須ですよね。
そのように企業活動のすべてのことにDEIの観点をインストールしていくことで、会社が強くなっていくと思います。会社のいろいろな取り組みをDEIのレンズを通してみると、やらなくてはいけないことがたくさん見えてきます。
口羽:DEIの取り組みは人事の話として事業とは切り離されてしまいがちですが、「人材不足」のようにみんなが納得する文脈にDEIを入れていくのが、まずは必要なのだと思います。私たちのグループでは、日々新しいアイデアを顧客企業に提案するのが仕事なので、「自分たちと全く異なる視点をチームに加えることで、新しいアイデアを生み出せる」というのが、一番理解してもらいやすいんです。前編で企業カルチャーをつくるためにボトムアップが重要だというお話をしましたが、事業にDEIをインストールする上でもボトムアップは重要です。
一つ、ボトムアップの取り組みを紹介すると、国内電通グループ9社がそれぞれの専門性を持ち寄って作成した「みんなのコミュニケーションデザインガイド」という施策があります。
関連記事:
電通、国内電通グループ8社と「みんなのコミュニケーションデザインガイド」を公開
私たちには、コミュニケーションの会社としての責任があります。情報をいろいろな接点で発信する際に「誰かを取り残すようなコミュニケーションをしてはならない」という観点から、どういうことに気をつけて情報を届けていくべきかを網羅的にまとめたものです。
グループ内はもちろん、同業他社やメディアにも、新しい常識として届いたらいいなと思っています。
相馬:どんな会社であれ、自社のビジネスにあったDEIを入れていくことが重要だと思います。電通はコミュニケーションを生業とした会社ですよね。これはイノベーションにもつながる、象徴的な取り組みだと思います。
ちなみにボトムアップをやっているメンバーは、マイノリティ側の人が多いのでしょうか?
口羽:いえ、いろいろです。前回お話しした「DEIパーク」に関していうと、半年に1回、各組織のDEIリーダーを変えているので、それはもういろいろな人が参加します。DEIの意識が高い人もいますが、まだ自分事化していない人もいます。そんな人たちも対話に参加してもらうと、みんなすごく衝撃を受けるんです。
「DEIパーク」では毎期最初に、マイノリティ当事者である社員から、悩みや力を発揮できない辛い経験を、自分の言葉で語ってもらうんです。そこでみんな「ああ、自分はなんて何も見えていなかったんだ」と気づきます。その上で自分の組織を見てもらうと、今まで見えていなかった課題が見えてくる。従業員にだけでなく、昨年は、これをグループ各社の幹部、役員の約250人を対象に実施しました。95%以上が「自分が変わった」とアンケートで回答し、各組織で具体的な取り組みを推進されています。幹部、役員が変わると、すごく組織が変わります。前編でもお話しましたが、トップダウンとボトムアップの両輪が必要なんです。
相馬:面白いと思います!DEIってどうしても、関心が高い人が取り組んでいると見られてしまいがちですからね。みんながDEIを自分ゴト化していくという取り組みは、参考になります。
口羽:カルチャーを組織の隅々にまで、深く根付かせるには、もちろん時間はかかるんですが、経済産業省のレポートも活用しながら、粘り強く取り組んでいきたいと思います。このレポートは本当に勇気を与えてくれますし、日本の未来を変えていく仕事なんだと、改めて希望が持てました。本日はありがとうございました!
・dentsu JapanのDEIサイトはこちら
https://www.japan.dentsu.com/jp/deandi/
この記事は参考になりましたか?
著者

相馬 知子
経済産業省
経済産業政策局経済社会政策室長
新卒で日立製作所に入社後、事業部門・工場・海外拠点等において、一貫して人材・組織関連の業務に従事。2020年5月からは、本社にてグループ全体のDEI推進に携わる。2023年8月より現職にて、日本企業におけるダイバーシティ経営の浸透に取り組む。

口羽 敦子
dentsu Japan
エグゼクティブ・マネジメント チーフ・ダイバーシティ・オフィサー 兼 ヘッド・オブ・サステナビリティ/電通そらり 取締役
タイの国立大学を卒業し、タイでキャリアをスタート。その後、電通へキャリア入社。以降、主にマーケティング部門で、国内外での事業開発やマーケティングなど、あらゆる業界のプロジェクトをリード。プライベートでは、八ヶ岳で週末2拠点生活を営みながら、地域の仲間と循環社会を目指す団体を立ち上げ活動中。