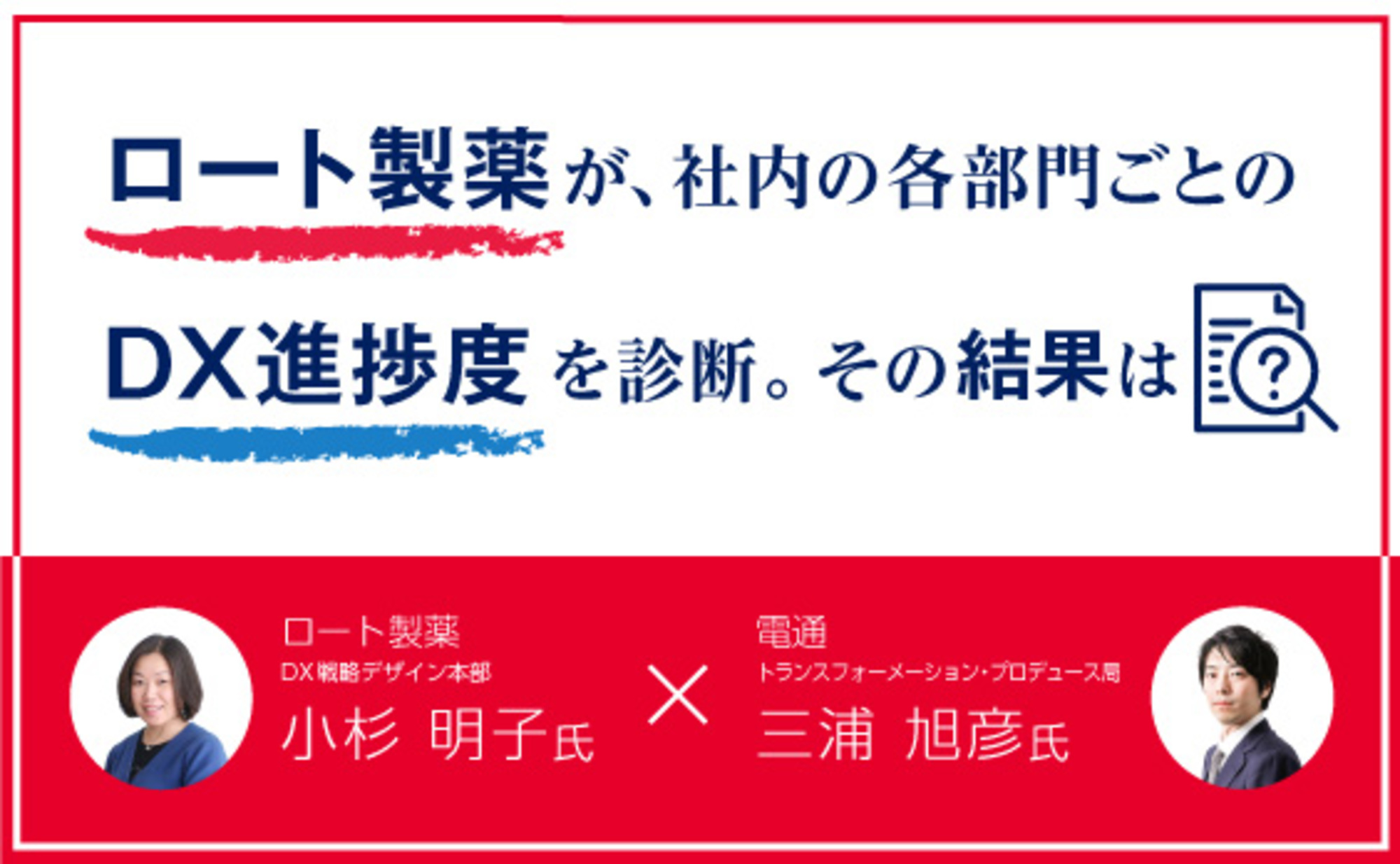企業として変えてはいけないものを守りながら、変化していくために大切なこととは?
駅を基点に、地域とつながる新しいビジネスが続々と生まれています。2025年4月に誕生した「エキュート秋葉原」は、ロボットの活用、オールキャッシュレスの集中レジ、駅の忘れ物の傘をアップサイクルした買い物かご、遊ぶと地域貢献ができるゲーム機などを導入した次世代型の新しいエキナカ商業施設。また、翌5月に高輪ゲートウェイ駅のイベントスペース「マチアイ」に期間限定でオープンした「earth song」は、「地域と花が循環する仕組み」をテーマに、地域と資源の新しい循環をつくるアップサイクル事業に取り組んでいます。
本記事では、前述の2つのプロジェクトを推進したJR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(以下、JR-Cross)常務執行役員 営業部長 新事業戦略部担当の江越弘一氏、新事業戦略部長の播田行博氏と、プロジェクトに伴走した電通第1ビジネス・トランスフォーメーション局の加藤剛輔氏、三浦旭彦氏が、持続的な事業成長をテーマに語り合います。
こちらからインタビューのダイジェスト版をご覧いただけます。

(左から)電通 加藤氏、JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー 播田氏、江越氏、電通 三浦氏
常に地域に熱い想いを注いできた。これまでの20年間の延長上にある未来の姿
三浦:本連載ではJR-Crossさんが推進し、電通グループが伴走して開業した新しいコンセプトのエキナカ商業施設「エキュート秋葉原」と、高輪ゲートウェイ駅に誕生した地域と資源の循環を生み出すお店「earth song」を軸に、各プロジェクトの成功のカギをひもといてきました。今回は双方を横断して、プロジェクトの背景や事業戦略、想いにフォーカスして議論できればと思っています。
最初に、JR-Crossさんが思い描いている成功のイメージをお伺いします。例えば、今から10年後、新事業が次々に話題となり、テレビをはじめとするメディアからたくさんの取材を受けるようになっていたとしたら――。どのような内容の取材になっていると思いますか?
江越:率直に言うと、10年後くらいにはあえてメディアに取り上げられなくなっているくらいのほうが良いなと思っているんですよね。毎年新しい施策を打ち出し続けて、「またJR-Cross?」「JR-Crossならそれくらい当たり前でしょ」という社会的認識をされているのが理想です。
ただ、10年後となると、時代は相当変化していますよね。当然、現在実施している施策をそのまま続けていても、お客さまにはまったく響かないと思います。だから10年後も、今と同様10年後の若手を中心とした新しい世代が自由な発想で各施策にチャレンジしている未来を想像しています。

三浦:組織内で世代交代しながら、企業としての視座を永続的につないでいくことを目指されているわけですね。今回、電通は「エキュート秋葉原」と「earth song」のプロジェクトをご一緒させていただきましたが、JR-Crossさんは若手や中堅社員を含めて、全員が地域に対して非常に熱い想いを持っていることに驚きました。
江越:地域への熱い想いは、JR-Crossの原動力ですね。今年度、エキュートは20周年を迎えましたが、実は20年前、「新しいエキナカ商業施設をつくろう!」と新事業を立ち上げて初代店長となったのが私です。それ以来、「地域と一緒に成長していきたい」という揺るぎない想いをずっと持ち続けていました。
地域のにぎわいに貢献したい。この一心で、さまざまなアイデアを出し、施策を打ってきました。この経験を積み重ねてきたことが、JR-Crossの財産なのだと感じています。
加藤:20年の間に、各地域はかなり変化しましたよね。ですから、単に現在の課題にフォーカスするだけでなく、「その次にどう変わるか」を見据えた施策が求められます。地域全体を見つつ、多様なステークホルダーにも目を向け、一歩先を行く新しいアジェンダをどのように作れば、地域全体がハッピーになれるのか。電通としても、常に意識しているポイントです。
播田:また、10年後といえば、エキュートが30周年を迎えるタイミングです。一般的な経営サイクルを考えると、場合によっては一度何らかの危機を迎えることもあり得ると思います。そのときに重要になってくるのが、「なぜ、この地域にエキュートがあるのか?」「その価値は、地域にしっかり受け入れられているのか?」という視点です。常に地域に溶け込み続け、地域の中に存在する必然性を確立していかないと、10年後の成功は成し得ないと考えています。
江越:地域によって、必然性の要因はまったく違いますからね。だから今回も、「秋葉原らしさ、高輪ゲートウェイらしさとは何だろう?」という根っこの部分から、徹底して探究しました。
播田:特に現場メンバーは、「街を歩いて、地域の方々が何を求めているのかに耳を傾ける」ことを実践しています。その上で、何度もディスカッションを重ねて、アイデアを広げていくんです。
三浦:歩いてみないと、分からないことがたくさんありますからね。この視点にはとても共感しますし、大事なことだと思います。私もメモを取りながら秋葉原を歩きまくって、アイデアを考えました。
「安全・安心を守る」という使命感を土壌に、パーパスの大幹を育てる
三浦:地域の生活者と一緒に新しいビジネスを創造してきたJR-Crossさんと、人の心が動く生活者発想で新しい視座のビジネス発想を創発する電通が、ワンチームで取り組めたことはとても良かったと思います。
JR-Crossさんのメンバーも、播田さんが所属する新事業戦略部だけでなく、開発や営業など、さまざまな領域からプロフェッショナルが集まりました。立場が違うがゆえに、「これは違うんだ!」と白熱した論議を繰り広げたこともありましたよね。
その様子に触発されて、「電通も負けていられない!」と私たちからも新しいアイデアをたくさん出させていただいて、2社のアイデアを共鳴させながら、一つの答えを導き出すプロセスはとても刺激的でした。
播田:そうですね。現場サイドの視点で議論するだけでなく、電通さんならではのイノベーティブな生活者発想の視点や地域に新事業を生み出すノウハウを融合させることができました。だからこそ、地域に本当に必要とされる施策が打てたのだと思っています。
三浦:電通としては、JR-Crossの皆さんが「安全・安心を守る」という使命感を強く持たれていたことにも心を打たれました。「駅という、国民の移動の要となるプラットフォームで、安全・安心が損なわれたらまったく価値はない」「この施策で、安全・安心を本当に守れるのか?」といった議論も多かったのが印象的でした。
江越:「安全・安心を守る」という意識は、JR-Crossに浸透する全施策の核となる考え方です。特に、デベロップメントカンパニーのパーパス「エキのひととき ちょっと、もっと、ずっと、」を実現させるためには、絶対に必要だと感じています。
例えば、事業の中心にパーパスという大きな幹があるとすると、その幹から伸びている枝葉が各施設によるさまざまな施策。まっすぐ伸びる枝もあれば、ユニークな形に曲がっている枝もあるんです。
また、幹を太く成長させるために欠かせないのが、「安全・安心を守る」という土壌です。何か迷ったときには幹の存在意義に立ち返り、安全・安心を実現する枝葉を広げていくといったサイクルで事業を成長させているんです。
播田:パーパスが真ん中にあるから、最初に聞いた段階では採用に至らないと思う意見が出ても、一度はすべてを受け入れざるを得ないんですよね。「自分が気づいていないだけで、パーパスを守るためにこの意見も重要かもしれない」「重要なら実現させないといけないし、難易度はかなり高くても実現できる方法があるかもしれない」といった議論が巻き起こり、あらゆる可能性を模索する。だから、変革するための新たな視点が生まれやすいのだと思います。
江越:このように電通さんと異なる視点を掛け合わせた刺激的なディスカッションを重ねることで、われわれのアイデアの引き出しは確実に増えましたね。地域が違うと、施策の向き合い方やアウトプットの仕方はまったく異なります。秋葉原の施策としてはお蔵入りしたけれども、アレンジ次第では別の地域のプロジェクトに応用できる可能性は十分ありますから。
三浦:それは良かったです。今回、面白いアイデアがたくさん生まれたので、皆さんから出た70個以上の施策案を、「アイデアブック」として1冊にまとめさせていただきました。業務中にパラパラめくるだけでも刺激になるし、視点を集中させたり、逆に拡散させるための材料になったらいいなと思って作りました。
播田:アイデアブック、本当にありがたかったです。JR-Crossでもこれまでのノウハウを蓄積しているとはいえ、内部で積み上げたものだけに固執していたら変化はありません。「外部の意見を取り入れると、どう変化するのか?」という視点の重要性を、改めて感じることができました。
変化を恐れない、パートナーとのイノベーティブな新しい化学結合で当たり前を超える
三浦:では、未来の事業に目を向けてみたいと思います。これまでの“当たり前”を超えていくための課題は、何だと思いますか?
江越:時代とともに、われわれのスキームも変化させなければいけませんよね。これまでの20年間に積み上げてきたものは当然、「是」だと思っていますが、だからといって、企業の成長が未来永劫(えいごう)に約束されているわけではありません。
大切なのは、変化を恐れないこと。そして、良質なアイデアを数多く出していくことこそが、今、われわれが問われている進化のかたちだと思っています。そのために、電通さんをはじめとする外部パートナーの方々とのコミュニケーションを通して、お互いのアイデアを掛け合わせていく。この引き出しの多さが、新規事業を開拓していく上での生命線だと感じています。
播田:その取り組みの一つとして今回、アイデア出しのフレームワークを電通さんと一緒に開発できたのは、非常に有効だったと思います。「ひらけ、エキナカ」というキーワードも、ワークを通じた議論の中で生まれましたから。
江越:そして、一つの成功事例が生まれると、その手法をJR-Cross内で共有して他のプロジェクトに横展開させていくことも可能になります。例えば、エキュートの店長ミーティングで施策事例の報告があると、「なぜ、この施策がうまくいったのか?」「自分たちも挑戦してみよう!」といった議論が始まるんです。
その数カ月後、似た手法の施策が別の店舗で立案されることも多くありますが、単なる模倣ではないんですよね。絶対に、その地域らしくアレンジされている。だから、お客さまからは違う施策に見えると思います。
加藤:それは、JR-Crossの皆さんがそれぞれの地域を深く理解しているからですよね。何が課題で、どういった施策が受け入れられるのか。店長だけでなく現場の若手メンバーも含めて、全員で同じ目線で取り組んでいるのもポイントだと思います。

若手の自由な発想を生かし、アイデアを広げる方法
江越:理想は、アイデアフラッシュも含めて全て若手に任せること。グループ外ともコミュニケーションを取って情報収集をして、もっと自発的に発信してもらいたいですね。そのために、「まだまだいける!」「ほかにアイデアはないの?」と彼らをたきつけるのが、われわれの仕事だと思っています。
播田:例えば、「この人と話をしてみたい」というキーパーソンがいたら、迷わずに行動してみる。実際に飛び込みで扉をたたき、話を聞きに行ったことをきっかけにディスカッションが始まり、立案・実施に至った施策もあります。
江越:東京・神奈川の複数店舗で実施したフェア「MATCH-UP MATCHA -抹茶に出会うひととき-」も、その一つです。新橋エリア担当が、地域に新しくできた伊藤園さんのミュージアムに、「何か面白いことができるかもしれない。行ってみよう」と訪ねたのが最初の一歩でした。
当の本人はそこまでの広がりを想像していなかったようですが、その裏では、上長が「もっと面白いことができるんじゃないの?」とたきつけていたんですよね。その流れで、「新橋だけでなく、有楽町、渋谷、横浜、藤沢などのチームにも話して、合同でやってみよう!」と、どんどん広がっていったという経緯があります。
加藤:自ら仕掛けていく姿勢が素晴らしいですね。自分から率先して仕事をつくっていく。従来、飛び込み営業というとネガティブなイメージがあったと思うんですが、JR-Crossの皆さんは完全に楽しんで実践していますよね。
三浦:同感です。既存の方法にとらわれずに常に変化し、挑戦し続けることは本当に大事だと思います。今後、例えば地域の皆さんにJR-Crossさんのアイデアを公示して、「一緒にやりませんか?」と声をかけてみるとか……。オープンイノベーション型で地域とのつながりをつくっていくのも良いかもしれませんね。
江越:それは、とても面白そうですね!今後も電通さんとJR-Crossのアイデアを掛け合わせて、次々と“当たり前”を超える取り組みを仕掛け、「エキのひととき ちょっと、もっと、ずっと、」というパーパスを実現していきたいと考えています。
播田:地域の方々にお話を伺うたびに感じるのは、駅への期待の大きさです。だからこそ、その期待以上のものをご提供しなければなりません。われわれのアイデアと、地域の方のご要望を融合させて、本当に喜ばれる施策を考えたいと強く感じました。
三浦:今後、ますます、AI含めたDXが加速する世界で、リアルの価値がより重要になっていくと予想しています。デジタルではできないもの――人と人との温かいコミュニケーション、地域に根差す交流のプラットフォームを駅という日本国民のプラットフォームを基盤に、JR-Crossさんだからこそできる唯一無二な提供価値を創っていけば、日本全体がもっと元気になるはずです。そういう新しい日本の未来づくりに電通もご一緒できたらと思っています。