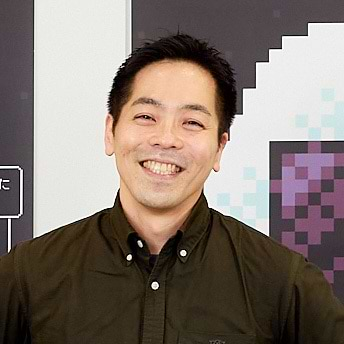成功しているビジネスだからこそ変えられないジレンマをどう乗り越えるか?
今までにないエキナカ商業施設を目指した「エキュート秋葉原」が2025年4月7日にオープンしました。新たなエキュートにすべく、何度も共創ワークショップを重ねる中で出てきたアイデアは、なんと70個以上。その中から、さまざまな挑戦が行われました。
本記事では、同プロジェクトを推進したJR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(以下、JR-Cross)新事業戦略部長の播田行博氏、「エキュート秋葉原」店長の西田宏氏と、プロジェクトに伴走した電通の高辺圭介氏、プランナーの菊池創造氏にインタビュー。これまでの当たり前を超えるために、どんな壁があり、それをどう乗り越えたのか、話を聞きました。
エキュート(ecute)とは
JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが運営するエキナカ商業施設。デリ、スイーツ、イートイン(レストラン)、ベーカリーなどをメインに販売している。「エキュート秋葉原」には、24ショップがオープンした。

(左から)電通 菊池氏、JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー 播田氏、西田氏、電通 高辺氏
ミッションは、これまでにない「エキュート」をつくること

エキュート秋葉原
──初めに「エキュート秋葉原」の新しさのポイントについて教えてください。
西田:ポイントとしてまず挙げられるのが、ロボットやメタバース、集中レジを導入し、施設内をオールキャッシュレスにしたことです。加えて、社会貢献型ドネーションゲームを設置したり、廃材を活用したアーティスト集団であるmagmaが秋葉原らしい地域の廃材を使って生み出したアートを飾ったり、電力のリサイクルに取り組んだりもしました。
さらに、一緒に働くキャストのモチベーションを上げるために、売り場への出入り口に気持ちのスイッチを切り替えるゲートも作りました。
──「エキュート秋葉原」の施設全体のコンセプトをご紹介いただけますか。
西田:「my gradation AKIHABARA(マイグラデーション秋葉原)」がコンセプトです。秋葉原は多様性に富む街で、ビジネスパーソンも多いですが、趣味の街でもあり、世界中から観光客が訪れる街でもあります。さまざまなお客さまの「色」が混じり合うことからグラデーションと名付けました。
──開発に当たって、どんな課題があったのでしょうか?
播田:コンセプトを「my gradation AKIHABARA(マイグラデーション秋葉原)」と打ち出している中で、「今までの『エキュート』は、いろんな人に対応していたのだろうか?」という点が議論になり、今回の施策につながりました。
私たちが会社から与えられた大きなミッションは「新しい『エキュート』、そして新しい商業施設の姿をぜひ打ち出してほしい」というものでした。JR東日本グループが推進する「Beyond Stations構想」に、今までとは異なる駅や街との関わり方を進めていこうという考え方があります。その中核駅に秋葉原が選ばれていたことから、ここで新しい姿を発信したいという考えがあったようです。
先述のように秋葉原は多様な人が集まる街です。そこに「われわれが普通の『エキュート』を出してどうする?」という思いがありました。そのため、今までできなかった新しい要素を盛り込むことがミッションとして与えられたと考えています。
開業に当たって実現したいことは大きく三つあります。一つ目は、オールキャッシュレスのような次世代型商業施設の体現。二つ目は、社会課題への対応です。今後は人口減少に直面するため、継続して発展するためには人手不足の解決、出店頂くショップ側が少人数でも運営できる体制を当社側が構築していくことが不可欠になります。また、街の廃材を利用するなどサステナブルな取り組みも社会課題解決として打ち出したいと考えました。三つ目は、地域との関わりです。秋葉原駅の玄関口にふさわしい期待感を持てる施設にすることで、秋葉原の街も期待感を抱いて楽しんでもらえるように意識して取り組んでいました。
目指したのは「エキュート秋葉原」に着いた瞬間に秋葉原に来たことが実感できること
──プロジェクトはどのように進められたのでしょうか?
菊池:プロジェクトは、いろんな部署から集まったメンバーと電通で共創ワークショップを何度も行いながら進められました。最初に、いろいろなデータや未来の予想、事例などを紹介し、その上でどう変わっていきたいかを言葉にしてみんなで持ち寄るワークを行いました。
こういうワークをすると大体いつも静かになるんですよ。「ホームラン打たなきゃ」という意識が働いてしまうからかもしれませんが(笑)。でもJR-Crossの皆さんは、本当に熱い思いを持たれていて、しかもちゃんと自分の視点からの言葉がたくさん出てきたので、日々真剣に考えている様子が伝わってきて、本当に感動しました。プロジェクトのサポートをするというよりも、学ばせていただいているという感じでした。
高辺:想像以上にアイデアが集まり、会議室の壁一面が染まるほどになったのはすごいことだと感じました。全部で70以上のアイデアが出ましたよね。そこからアイデアをさらにジャンプさせながら、さまざまなハードルを乗り越えて実現できたのは、JR-Crossさんだからこそだと思います。
菊池:ワークを通じて多くのお話を伺い、そこから「ひらけ、エキナカ」という言葉が生まれました。エキナカから地域や社会とつながっていったり、人の可能性を開いていったりと、ひらかれた駅になっていこうという思いが言葉になりました。
特に印象的だったのは、皆さんから「どこのエキュートに行っても、その駅ならではのエキュート感があんまり伝わってこないのは寂しいよね」という話があったことです。せっかく秋葉原という特徴がある街に誕生するのであれば、エキュートに着いた瞬間に「秋葉原に来た!」と実感してもらえる場所にしたいよね、という思いがありました。
播田:4月2日に内覧会を開催して、私は俯瞰(ふかん)したところでずっと見ていたのですが、すごく秋葉原感が出たと感じています。SNSなどで訪れた方の反応を見ていると「急に秋葉原駅が変わった!」という感想もあり、狙い通りです。
これまでの当たり前を超えるために必要なこととは?
──プロジェクトを進める中で、どんなハードルがありましたか?
高辺:構想はいくらでも自由ですが、当然、物理的、時間的な制約があります。特に駅は公共の施設なので、その制約条件の中で、新しさかつ面白さがあるものを残していくことは、想像以上に難しかったです。
播田:本当にハードルは山ほどありました。われわれは新しいことをやっていこう、これが街の役に立つ、貢献できるという思いでやっていましたが、関係者全員を同じ思いにすることはできません。「急に何かやりだしたけど、大丈夫?」みたいな雰囲気もある中、どう納得してもらうか、というところは苦労しましたね。
菊池:私たちが一緒に実施していたワークでは、すごくポジティブな議論をしていたことが記憶に残っています。それこそ営業の方はお客さまと接しているので、「絶対に失礼があってはいけない、安全」ということがベースにありました。そして、誇りは持ちながらも変わっていくことを促す播田さんの部署の方と両方の意見があったと思います。でも、一緒にワークを実施する中で、お互いに意見はありながらも「どうやったらお客さまに喜んでもらえる良い形で変わっていけるか」という方向に議論が向いていたので、本当にポジティブでした。
播田:JR-Crossのデベロップメントカンパニーは「エキのひととき ちょっと、もっと、ずっと、」というパーパス浸透に力を入れていて、みんな向いてる方向は一緒だと思うんですね。相対せず、大まかに同じ方向を向きながら、どっちの方向に行こうかという議論ができたと思っています。
オールキャッシュレスにレトロゲームも。「エキュート秋葉原」らしい施策が実現
──そういった困難を乗り越えて実現した「エキュート秋葉原」について、新しい取り組みを、具体的にいくつかお話しいただけますでしょうか。
西田:まずは、オールキャッシュレスですね。お客さまはセルフで会計ができます。また、集中レジでは、キャストはいなくても会計ができます。人手不足から時間帯によりワンオペになるショップもある中で、会計業務がなくなることでキャストが違う業務に専念できたり、少しだけ売場を離れることができるようになったことも一つ大きな特徴かと。
それに付随して、生成AIを活用した案内ロボットを1台用意しました。現状は質問に回答する機能があるのですが、ゆくゆくは弁当の売り子みたいな形で活用したり、駅の案内や秋葉原の街の案内などできることを増やしたいと思っています。ちなみに「記念撮影して」と言うと、ちゃんと手でハートを作ってくれます(笑)。しかも片方だけ。
播田:まだ回答に不完全な部分があるので、見習い中と貼っているんです。また今回はメタバースも用意しました。ウェブ上に空間を構築しており、実際のショップの配置と一緒なので、フロアマップのように見ながらお店を回れます。そこで質問をすると、生成AIが一通り答えるようにもなっています。
実際に「エキュート秋葉原」の雰囲気を感じてもらえるものになっており、将来的にはその空間でイベントを実施したり、販促をうまく絡めていくような場にできたらと考えています。かわいらしいキャラクターも用意しているので、いずれそのキャラクターでビジネス展開もできたらうれしいです。
これらの取り組みによって、人手不足の解決という社会課題へのアプローチと、お客さまに楽しみを提供することの両方を実現させることができました。
高辺:それからゲームの街でもある秋葉原らしい施策だと感じるのは、レトロゲーム機「PLAY FOR THE FUTURE -AKIBA DONATION-」ですね。遊んだ金額が、秋葉原を良くするための寄付になります。

「PLAY FOR THE FUTURE -AKIBA DONATION-」
播田:単にゲームを置くのではなく、街の活性化に結びつく寄付につながるという一連のサイクルが構築されています。楽しんでもらいながら、結果的にそれが街の発展につながるものが作れました。
あとは、駅でも特に多い忘れ物の廃棄されるビニール傘を活用した買い物カゴを作ったり、アーティスト集団magmaに秋葉原ならではの地域の廃材を活用したアートを作ってもらったりしました。アップサイクルで社会課題の解決に取り組みながら、それらを施設の中にうまくマッチさせ、個性を放つ空間にすることができたら、エキュートを訪れることがもっと楽しくなると思うんですよね。ちょっと寄ってみて「今日もあのアート見て行こう」と思ってもらえるものを用意できたと思っています。

忘れ物のビニール傘を活用した買い物カゴ

アーティスト集団magma制作の地域の廃材を活用したアート
──服飾規定も新しくされたそうですね。
播田:エキュートって、元々服装の縛りがきつい施設じゃないんです。ただ、これは悪いところなんですが、ルールを書面にまとめているために縛られている感じがあったんですよね。それを電通さんに読み解いていただいて、「個人の判断に任せながらお店の判断の中でやっていただければいいんですよ」っていうものを大きなくくりとして、ルールの1ページ目に作ってもらったんです。それだけでイメージは変わると思うんですよね。
菊池:元々の原案は、コスプレキャストという店員さんにコスプレしてもらおう、というアイデアでした。基本的に今お話ししているレトロゲーム、買い物カゴ、服飾規定の話も、前述の70個のアイデアの中から出てきています。
服飾についても、コスプレから議論を発展させて、「働く人にとって価値のある形にしていったらどうなんだろう?」という視点で話し合ってみました。そこから服飾の規定を今の時代に合ったものにアップデートしたいという意見が出たんです。原案とアウトプットの間にすごくジャンプがあったアイデアでした。
播田:働くキャストのためにランウェイゲートも作りました。毎日通るところに楽しさをプラスすることで、明るい気持ちで働いてほしいという気持ちを込めています。
高辺:これはショップの従業員の方が「キャスト」と呼ばれていたことが出発点になっています。「キャストが輝く場はステージだ」という発想で、キャストランウェイゲートという施策にたどり着きました。
播田:われわれ、商業施設を運営している側の役割は、お客さまを呼んでくることなのですが結果的に買ってくれるかは、現場のキャストさん次第なんですよね。できる限り気持ちよく前向きに働いてもらうことには、すごく気を使っています。
ポイントは「変えなきゃいけない!」という社員の強い思い
──今回のプロジェクトで一番のポイントになった点を教えてください。
播田:最初に伝えるには意外な回答かもしれませんが、実は、電力が足りないんじゃないかという話もありました。新しい施設だったら回線を引いてくればいいのですが、エキナカ商業施設はあるものからのやりくりが必要なんです。大まかなハード計画が既に確定している中で関係部署が協力してくれたことが、このプロジェクトの実現につながりました。
それから、電通さんにお声がけしたのは一番のポイントだったかもしれません。電通の高辺さんからは、最初別のご提案をいただいていたのですが、何となくその提案から、今回の秋葉原のプロジェクトの強力なパートナーになってもらえるのではと感じ、思い切って「こういうことってできませんか?」と聞いたことは、自分としてはよくやったなと思っています(笑)。
西田:今回は特に、社員の問題意識が高かったこともありましたね。みんなの「変えなきゃいけないから、変えよう」という気持ちが強かったことが前提にあり、そして幹部も問題意識を持っていて。変えるための提案をして、ほぼダメだと言われた記憶がないんですよね。そこがポイントだった気はします。
播田:社員に関してはやっぱり同じ会社のメンバーなんだな、という一体感を感じましたね。みんなも変えないといけないという意識を持っていたんだな、と。知っているようで知らなかったんで。こういう機会が今まであまりなかったから、共創ワークショップの場ができて良かったと思います。
菊池:私たちから見ると、変えたいという気持ちが皆さんからほとばしってましたけどね。みんなで話し合って決めていったので、誰のアイデアだったか分からなくなっていましたよね。議論を重ねていい方向に変えていけたのが印象的でした。
播田:さっきの電力の話もそうですが、困難なことでも最終的には社員たちは「でも、どうやったら実現できるだろう」という方向に考えていることを今回すごく実感しました。
西田:開業告知動画は「秋葉原らしい、新しいエキュートを感じてほしい」という想いで作りました。
西田:いくつかパターンがありましたが、「みんながこれだ!」と全会一致でした。「秋葉原」の文字を隠したときにも、秋葉原だと分かります。多分そこで全員がビビッと来たんじゃないかと。
播田:Xでの評判を見ていると、秋葉原にぴったりだとか、すごくかわいらしいという感想はやっぱりありますね。
──最後に今後の展望をお聞かせください。
西田:実は、今回のサステナブルな取り組みを一つのプロジェクトとして捉えて、電通さんに「ちょっといい選択、ずっといい未来」という言葉と、それを推進していくためのロゴも作っていただきました。この言葉を常に意識して、風化させずに取り組んでいきたいです。
あとはワークショップを通して創った、運営コンセプトの「ひらけ、エキナカ」です。地域、社会、人との関係性をひらいていく上では、この言葉をいかに使い倒していくかが大事だと思っています。
播田:今回「エキュート秋葉原」で挑戦したマインドは、他のエキュートにも持っていきたいです。今後もエキュート自体がお客さまに新しいものを提供できるよう、燃え尽きたりせず、続けていきたいと考えています。
──今回は、貴重なお話をありがとうございました。