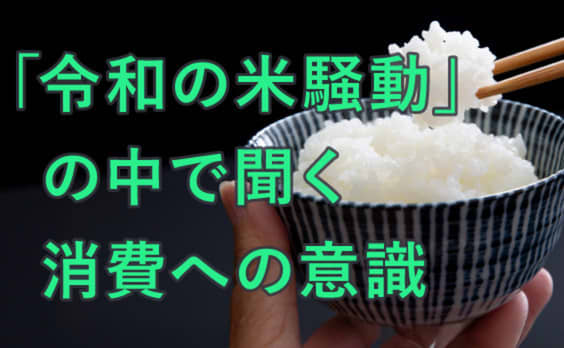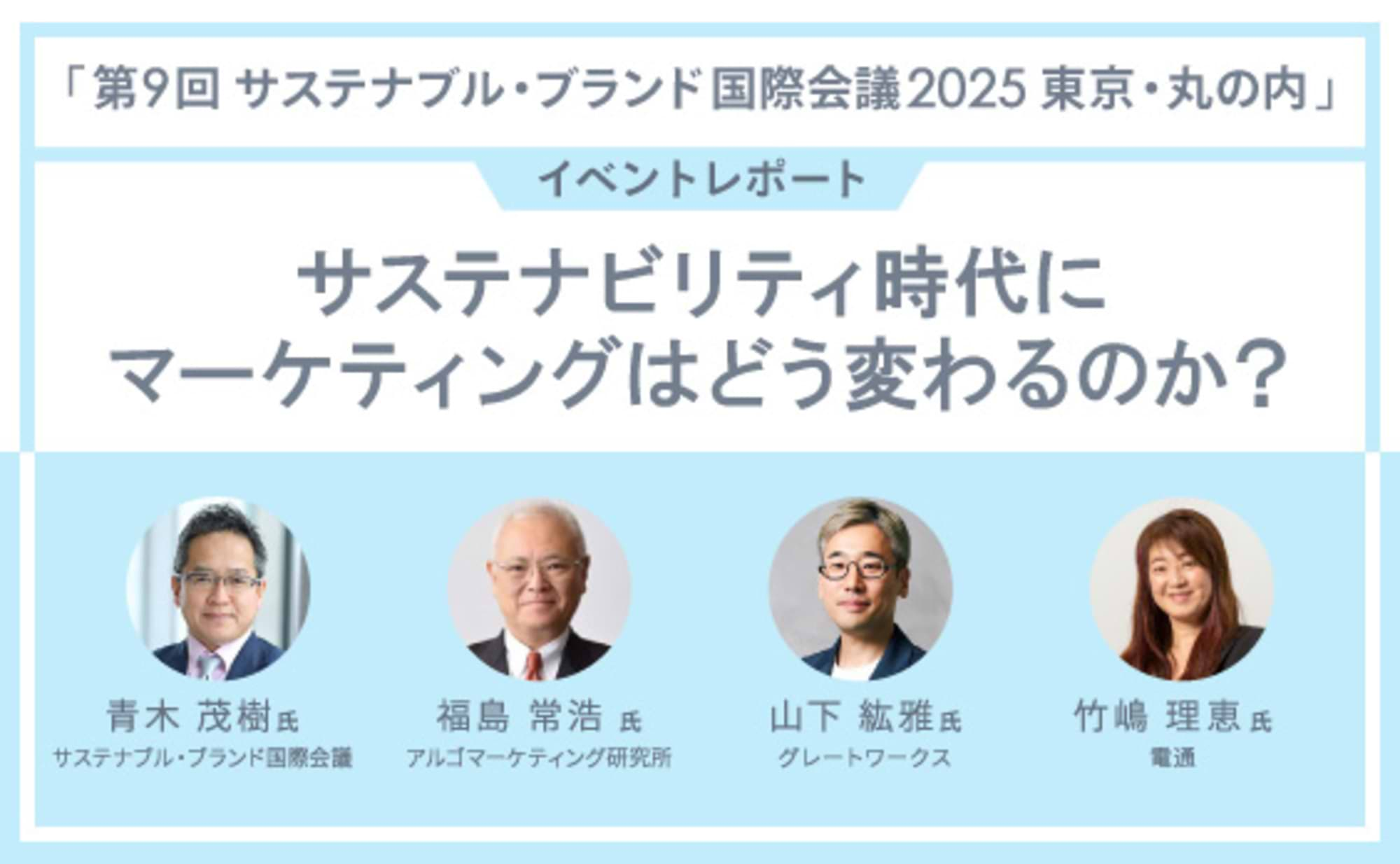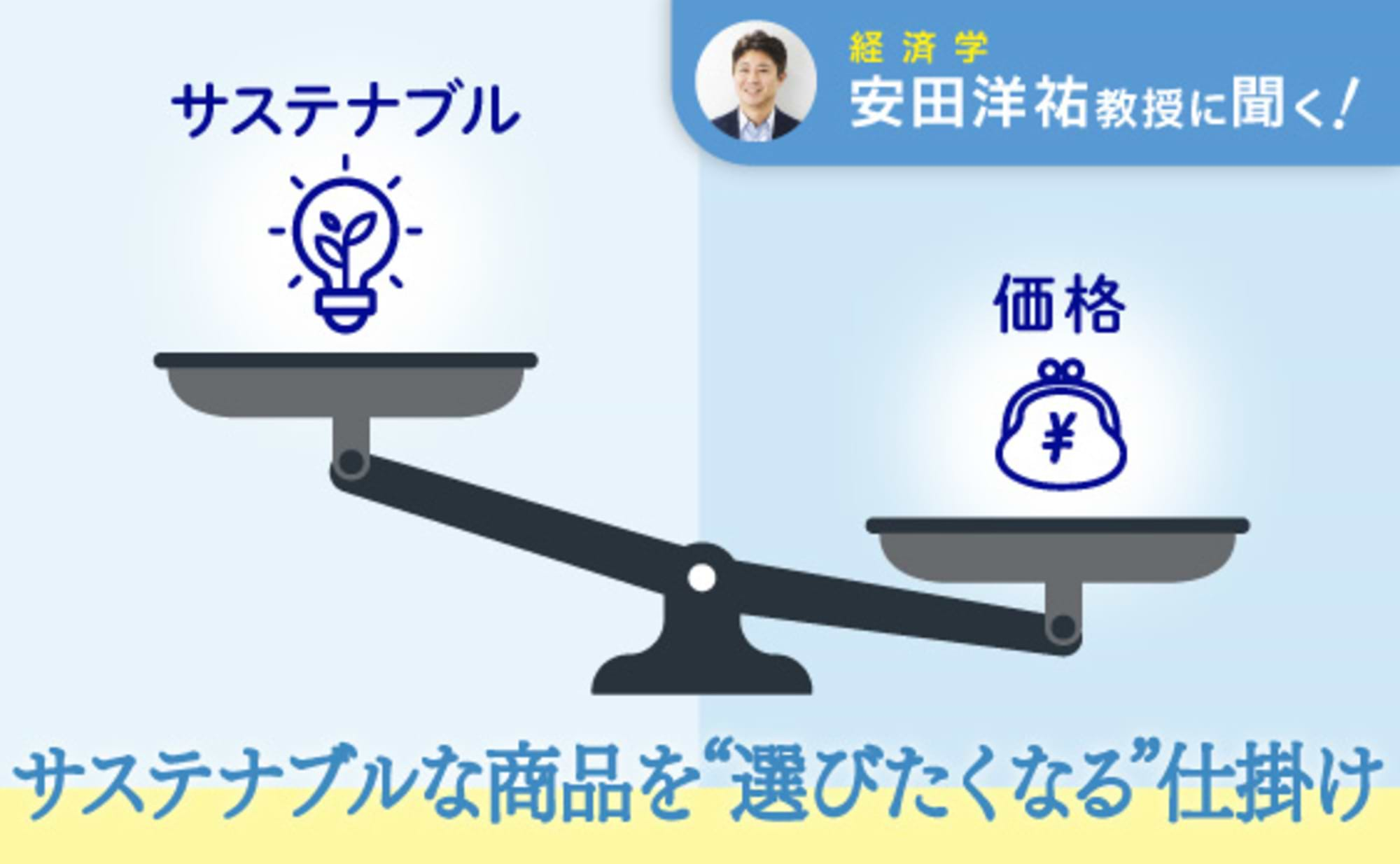電通が2025年6月に行った消費者アンケートでは、「物価高で環境に配慮する余裕がない」という消費者意識が根強く見られました。
「サステナビリティに配慮された商品は高価格でも買いたいという意識はあるが、実際の行動には移されない」「同じ商品・同じ価格の場合、サステナビリティ配慮よりも、自分にベネフィットがあることが記載されている方が選ばれやすい」ということを複数の学術論文が示しています。
そこで今回は、経済学の見地から「高価格帯のサステナビリティ配慮商品を“選びたくなる”よう仕掛ける方法」というテーマで、大阪大学経済学部の安田洋祐教授にインタビュー。電通サステナビリティコンサルティング室の遠山若菜がお話をお伺いしました。

(左から)大阪大学経済学部 安田洋祐教授、電通 遠山若菜
サステナビリティ配慮商品は、“サステナブルではない”?
遠山:最近、米や野菜などの値上げに直面し、「フェアな価格とは何か?」への意識が高まっているように感じます。サステナブルな商品は一般的に価格が高く、そこに環境や社会への配慮といった背景があると理解しつつも、実際には手に取りにくくなっています。サステナブルな商品がより選ばれるために、プライシング(価格設定)の面でどのような工夫が可能なのでしょうか。
安田:まず「フェアな価格」についてですが、経済学の観点では、価格はそもそも需要と供給によって決まるものと捉えます。市場に対して外部から価格を調整しようとする介入は、短期的には効果があるように見えても、中長期的にサステナブルではありません。少し意地悪な言い方をすると、「売れないサステナビリティ配慮商品はそもそもサステナブルではない」のです。
遠山:地球環境や社会にとって良いものでも、事業の持続性がないから、ですね。
安田:経済的なインセンティブの仕組みをきちんと設計し、それに乗せる形で事業を展開していくことが重要です。そうすることで、生活者にとっても自然な選択肢として受け入れられる可能性が高まるのではないでしょうか。また、同じ商品やサービスでも、どう伝えるかによって消費者の「支払い意欲(Willingness to Pay)」は大きく変わります。
遠山:なるほど……今日は「自然な選択肢」として受け入れられる可能性を高める、経済学の知見をいただけるとうれしいです!
値上げをチャンスに変える心理戦──おとり効果で選ばれる価格設計
遠山:事業の観点では、既存商品やサービスをサステナビリティ配慮商品に置き換えていくには、まだ慎重にならざるを得ない部分があるのが現実です。特に、すでに市場に出ている商品がある中での切り替えや、昨今の原材料高騰による価格改定など、複数の要因が重なる中で、どのような打ち手があるのか——。これは多くの企業が直面している課題ではないでしょうか。
安田:値上げが避けられない現状を踏まえると、むしろ今こそ「サステナビリティ」を付加価値として価格に組み込むチャンスではないでしょうか。経済行動の心理学で知られる「おとり効果(decoy effect)」を活用することで、消費者の選択を後押しすることも可能です。
遠山:おとり効果……。具体例を教えてください。
安田:例えば、新聞や雑誌などで紙媒体とオンライン版の両方を提供しているケースを考えてみましょう。紙だけの価格、オンラインだけの価格、そして紙+オンラインのセット価格があるとします。たとえば、オンラインだけの価格が3000円で、紙+オンラインのセット価格が5000円だとしましょう。このとき、多くの消費者はどちらを選ぶか迷うかもしれません。価格と価値にトレードオフがあり、どちらの方がより魅力的かをすぐには判断できないからです。
ここで仮に、紙だけの価格を、セット価格と同じ5000円に設定したらどうなるでしょうか。この場合には、紙+オンラインの方が紙だけよりも明らかにお得なので、消費者は二つの選択肢から迷わずにセットを選びます。すると、面白いことに、オンラインだけと比較しても、紙+オンラインが相対的に魅力的に見え、結果的により選ばれやすくなるのです。あくまでわかりやすくお伝えするための仮想の話ですが、価格の提示方法によって消費者の選択が変わることは想像いただけると思います。
この考え方は、サステナブルな商品にも応用できます。たとえば、サステナビリティの要素が入った新商品がサステナビリティ要素のない既存商品よりも20%高い価格で売られていても、多くの人はなかなか手を伸ばしてくれないでしょう。どんなに価値が高くても、価格の違いが目立ってしまうからです。ところが、既存商品の価格も20%値上げしたらどうなるでしょうか。消費者は「どうせ同じ値段なら、より価値のあるサステナビリティに配慮した商品を選ぼう」と判断する可能性が高いです。つまり、価格の相対性と付加価値の見せ方次第で、サステナブルな選択を促すことができるのです。

遠山:たしかに、通常の商品とサステナブル要素が加わった高価格の商品が並んでいれば、多くの人は価格の安い方を選びたくなりますが、価格が同じであれば「せっかくならサステナブルな方を選ぼう」という気持ちが自然と働きますよね。
安田:同じ商品がただ値上がりしていくよりは、自ら「サステナビリティ商品を選んだ」と感じる方が納得できるのではないでしょうか。
遠山:「サステナビリティ」と聞くと特殊で構えてしまう印象を持たれがちですが、サステナビリティをいったん「数ある商品オプションの一つ」と、ライトに捉え直すことでバイアスを外した捉え方ができますね。自社の商品・サービス群の中で「おとり効果」を活用する方法もありますし、値上げの際も、「ただ値上げしているだけの他社」と差別化できるよう、サステナブルな要素を加味した商品やサービスにすることは、自社ブランドを選んでもらう理由として強い説得力を持ちそうです。
「意味がない」から、意味がある?──シグナリング効果で企業価値を高める
遠山:買う側の心理では「商品が特別にサステナブルだから買いたい」というより、「サステナビリティに注力する企業だから安心・信頼できる」という感覚だと思います。サステナビリティはコーポレートブランディングの発信あってこそ、事業部が安心して取り組めるのではないかなと。
安田:そうですね。もし仮にサステナビリティへの取り組みが、企業の利益に直接的な効果を全くもたらさなかったとしても、それでも情報発信に投資する意義はあるかもしれません。理由は、「企業がサステナビリティに投資している」という事実は、投資家や就職希望者に対してポジティブなシグナルとして受け取られる可能性があるからです。これは経済学でいう「シグナリング理論」に基づく考え方です。
遠山:シグナリング理論とは、どんなシグナルが出るのでしょうか?
安田:例えばテレビCMを出している企業は就職活動で人気が出ることが多いです。CMにお金がかかることは一般的に知られているので、「CMを出すくらいだから、きっとあの企業は余裕があってもうかっているのだろう」という隠れたシグナルが人々に送られているわけです。そういう余裕があるところで働きたいなとか、消費者の場合には、広告にお金を出すほど商品に自信があるメーカーの方が安心できそう、といった理由で選びやすくなります。
遠山:「サステナビリティに力を入れている企業」も、直接の商品ベネフィットとは別のシグナルが出ているのでしょうか。
安田:逆説的ですが、「サステナビリティは短期的な利益を生まないからこそ価値がある」と捉えることもできるかもしれません。もし、サステナビリティを訴求しても「その商品が売れるわけではない」なら、そこにあるシグナルは「役に立たないことにあえて取り組める余裕のある企業」あるいは、「他社が慎重な中でスピード感を持ってサステナビリティに投資できるアジリティの高い企業」となり、いずれも将来性のある企業として評価される可能性があります。先行して訴求する場合は大きな価値があるように思います。
遠山:先行して取り組む企業が見ている景色と、二番手・三番手として後から追随する企業が見る景色は、時間とともに差が開いていきますよね。どのタイミングでサステナビリティ訴求にかじを切るかは、企業にとって非常に悩ましいです。しかし、「サステナビリティは売り上げに役立たないからこそ、価値がある」というのは、とても面白い観点です。サステナビリティのコスト増分を回収しなきゃ!ではなく、先行してサステナビリティへの注力を見せて「将来性がある企業」というシグナルを出し、株価や就職意向の期待を高めることにつなげる。そういう形での投資回収は確かにあり得ますね。
正直な「支払い意欲」を引き出す――BDMメカニズムで需要を推計する
遠山:最後に、冒頭でお話しされていた「支払い意欲」を引き出す価格設定プロセスについて、お伺いできますか?
安田:経済学にBDMメカニズム(Becker-DeGroot-Marschak mechanism)という、商品に対する個人の支払い意欲を測定する手法があります。ある人が商品に対してどれくらいの価値を置くかを、正直に申告するように動機づけるメカニズムです。このBDMメカニズムを活かして、「支払い意欲」を客観的に測って、「需要の推計」を事前に行うことで、価格戦略や販売戦略の精度を高めるサービスを、昨年エコノミクスデザイン社でローンチしました。
遠山:具体的にはどのような手法・プロセスで価格を設定していくのでしょうか?
安田:BDMメカニズムとは、1996年にノーベル経済学賞を受賞したヴィックリー(Vickrey)のオークション理論に基づき、消費者の「本音の支払い意欲」を引き出す価格調査の手法です。調査は疑似的なオークション形式で行われるため、「BDMオークション」とも呼ばれます。参加者が提示した金額(入札価格)が、メカニズム側が選んだ擬似的な価格(擬似価格)を上回っていたときに、後者(疑似価格)の金額で商品を買えるというものです。入札価格が疑似価格を下回っていた場合には、商品は得られません。メカニズムが定めるこの金額は参加者には伏せられており、ランダムに選ばれる場合が多いです。
この仕組みの肝は、参加者が疑似的なオークションに勝って商品を購入する際に、「自分が提示した価格」をそのまま払うのではなく、自分が直接コントロールできない疑似価格を支払う、という点です。この特徴によって、参加者は自分の商品に対する価値を正直に申告するのが最適になる、という性質が保証されます。つまり、オークションで「高い価格を最初から言うと損をしそうだから安めに言っておこう」、あるいは「どうしても欲しい商品だから高めに言ってみよう」といった心理的なバイアスを排除し、参加者から“本当に支払ってもいいと思える正直な価格”をうまく引き出せるのです。
遠山:BDMは調査参加者が正直に支払える価格をつけた方が損をしない仕組みですね。この調査は、商品発売前に行うのでしょうか。
安田:基本的にはそうですね。すでに発売され定価や価格相場がわかっている商品だと、それらが価格の基準になってしまうので、本音の価値を聞き出すのが難しいのです。
遠山:実際の調査でも、調査参加者は「買う」のですか?また、調査の方法も、同じ商品でも売られている場所にも影響を受けることも踏まえて設計されているのでしょうか。
安田:実際の調査でも買っていただきます。身銭を切って商品を獲得できる可能性があるからこそ、消費者から本音を聞き出せるので。調査では、値付け前にどういう説明やプレテストを行うか、商品をどういった場所や環境に置くか、補完的なアンケート調査で何を尋ねるかといった、BDMメカニズム以外のさまざまな点についても詳細にデザインします。
遠山:商品を手に取りたくなる工夫には表現も重要ですが、複数の表現パターンに対して、事前に支払い意思額も比較・分析することで、より適切な価格設定が可能になりそうですね。「サステナビリティはもうからないからやれない」と踏み出せないでいる企業の方々も、この金額でこの売り方なら買ってもらえるという納得感のあるデータを提示できれば、上層部の承認を得やすくなるのではないかと思います。
安田:まさに「需要の推計」が目的なので、そういった目的でBDMメカニズムを使っていただけるとうれしいです。
遠山:本日はお忙しい中、経済学の見地からさまざまな刺激になるお話をありがとうございました。
今回のインタビューでは、売り上げにつながらない“サステナビリティ商品”をどう魅力的に価格設定できるか、サステナビリティのプライシングをテーマに幅広くお話を伺いました。
おとり効果、シグナリング理論、BDMメカニズムなど、経済学の学知が、今の生活者との向き合い方を変える可能性を感じました。また、「サステナブルかどうか」という枠を超えて、意思決定のメカニズムに働きかける、心理学的アプローチを取り入れた購買行動の設計が、サステナブルな選択を自然と促す仕組みづくりに重要だと感じました。(遠山)