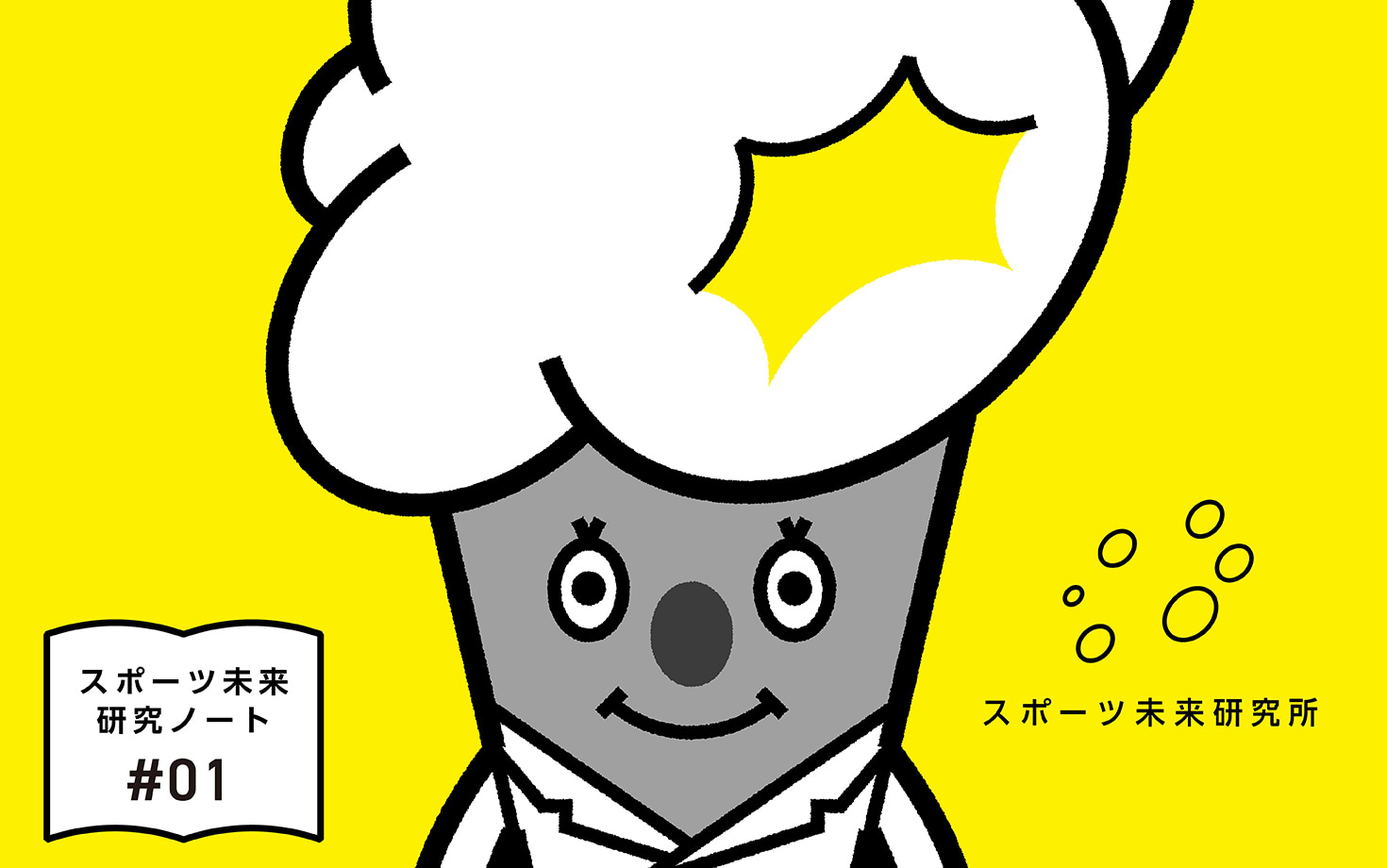「スポーツの価値」を定性的・定量的に明らかにしていく「スポーツ未来研究ノート」。今回は、水泳を通じて世界とつながり、現在はスポーツ庁長官として政策の最前線に立つ河合純一さんを、「スポーツ未来研究所」所長の大日方邦子と勝見文一研究員が訪問。幼少期から積み重ねてきたスポーツ経験が何をもたらしたのか、大会が人を変える理由、日本社会がこれからスポーツとどう向き合うべきかを伺いました。
![]()
水中ではみな平等。水泳に救われ、世界が広がった
勝見:どのようなきっかけで、スポーツと出合ったのですか?
河合:5歳でスイミングスクールに通い始めたのが最初でした。弱視でしたが受け入れてもらえ、水泳と出合いました。体を動かすことが好きで、体操やソフトボール、空手などもしましたが、飽きっぽい自分が唯一続けられたのが水泳でした。単調さに疑問を持つ時期もありましたが、記録が伸びたり、勝敗に心を揺さぶられたりする経験が続ける力になりました。50メートルのタイムが0コンマ数秒足りず、県大会への出場を逃した悔しさ、勝てたときに仲間と喜び合えたこと。小学生時代のそうした体験は今も鮮明に覚えています。
勝見:その体験が、進学やパラリンピックへの道にもつながっていったのですね。
河合:中学3年で視力を失い、教師になりたいとの思いから高校入学時に上京しました。小4の時の担任が水泳部の先生で、授業も水泳も本当に楽しそうに教えていたんです。その姿にあこがれていました。当時、視覚障害者が大学に進むのは容易でなかったので、進学を見据えて筑波大学附属盲学校(現・筑波大学附属視覚特別支援学校)高等部に入り、寮生活が始まりました。
大日方:そして、高校でも水泳部に。
河合:はい。視力を失ったばかりの頃は、自分が障害者であることを受け止めきれませんでした。でもプールに入れば以前と変わらない。水中ではだれもが体ひとつで勝負するだけで、世界のどこでも条件は同じです。その感覚に救われたんですね。盲学校の仲間に加え、都のスポーツセンターでは義足や車いすの選手たちと一緒に練習する機会もありました。義足の重さに驚いたり、車いすを押す経験をしたり。身体の違いを超えて泳ぐという行為そのものが刺激となり、自分の世界を大きく広げてくれました。
勝見:17歳でバルセロナパラリンピックに出場し、銀と銅のメダルを獲得されましたね。
河合:最年少の一人として結果を残せた喜びがある一方、金メダルを取れなかった悔しさが強く残り、次こそはとアトランタパラリンピックを目指しました。同時に、教員になる夢も強く、大学受験の勉強も続けていました。
大日方:当時、水泳への思いはどのようなものでしたか?
河合:水泳は自分の軸であり、社会と自分をつなぐハブにもなっていきました。国内外の大会に出場しつつ、進学した早稲田大学の水泳部ではオリンピック選手と同じ環境で練習する機会にも恵まれました。つらい日もプールに向かえたのは、強くなりたい、勝ちたいという気持ちがいつも勝っていたからだと思います。卒業後は公立中学校の教師となり、競技と両立しながら、学校のプールで好きな水泳と日常的に向き合えることをありがたく感じていました。
競技の魅力や価値、課題を、選手の言葉で伝える大切さ
勝見:2000年頃から、日本パラリンピアンズ協会の立ち上げにも関わられましたね。
大日方:選手数人が集まって、熱のこもった議論を重ねましたね。河合さんが「アスリートとして何を伝えるべきか」を強い思いで語っていたことを覚えています。
河合:25歳でのシドニーパラリンピックで日本選手団の主将を務めたことが大きな転機でした。取材を受ける機会が増える中で、水泳のこと、視覚障害のことだけでなく、もっと広い視野で語る必要性を感じたんです。一方で、教師として働きながら視覚障害のある子どもたちに自分の経験を十分に伝えられていないという歯がゆさもありました。そこで、視覚障害のある子どもたち向けに、恩師と年1回の水泳教室を始めました。その活動を10年ほど継続する中で、海外での活動にも興味を持つようになり、「自分の経験やノウハウが生きるのなら行ってみたい」と、2006年にJICA海外協力隊(短期派遣)に参加しました。
勝見:海外でも教える経験をされたのですね。
河合:もともと大学時代のゼミ仲間に協力隊経験者がいたことも、後押しとなったのです。赴任先のマレーシアでは、上級レベルの選手のほか、盲学校の子どもたちにも泳ぎを教えました。能力に合わせて少し難しい目標を立てると、必死に挑戦する。その姿に、何かを達成する喜びは、世界共通なのだと感じました。
勝見:協会では、どのような活動を?
河合:当時は選手選考の透明性など、曖昧な部分が多くありました。そのため、環境改善や社会への発信を、選手自身の言葉で行うことを大切にしました。障害の種類や競技が違っても、共通する課題は多く、個人の声では届かないことも「同じ境遇にある人々の声」として社会に届けられるようになったのは大きかったと思います。自分たちだからこそ伝えられる競技の魅力や価値、そして社会貢献の形を模索し続けました。
大日方:競技環境、選手選考、指導者の資質、練習環境などの課題を、データに基づいて示す必要性を議論していましたよね。自発的で、志の強い活動でした。
![]()
人が生き続ける限りレガシーは残り、行動を変えていく
勝見:大会をめぐる価値やレガシーについて、どのように捉えていますか。
河合:レガシーは、人そのものだと感じています。国内で大きな大会が続き、選手だけでなく、準備や運営に関わった人、観戦した人、見に行きたいと思った人も含めて、その経験が心に残る。競技場といったハードも残りますが、それ以上に、人の内側に積み重なるものこそレガシーだと思います。
大日方:2025年の、東京2025世界陸上や東京2025デフリンピックは非常に盛り上がりましたね。
河合:共通していたのは「生で見たい」という気持ちだと思います。デフリンピックでは聴覚障害者自身の準備と発信が大きな力になりましたし、2021年のパラリンピック以降、障害者スポーツを見る心理的ハードルが下がったことも後押しになりました。全体として良い流れができていたと思います。
大日方:当事者が多い会場、健常者が多い会場など、会場ごとに観客層が違っていたのも印象的でした。
河合:デフリンピックだからではなく、世界レベルのアスリートが来ていたという理由で訪れた人もいたでしょうし、駒沢公園を訪れたついでに立ち寄った人もいたでしょう。競技の迫力、応援の楽しさ、飲食、季節の心地よさなどが重なり、会場全体がエンターテインメントとして成立していたことが成功要因だと思います。
勝見:大会やイベントは、人の心にどのように残るのでしょうか。
河合:開催に関わった人が変わっていく姿を、多く見てきました。2025年の滋賀県での国スポ・障スポでは、職員の方々が「関わったことで、大会の価値がわかった」と口々に話していました。県民とつくり上げた経験そのものが喜びになる。閉会式でアーティストと歌った大勢の高校生たちは一生、この感動を忘れないでしょう。非日常の体験こそが記憶に残り、人を動かすのだと思います。大会が一過性で終わるかどうかは、準備から終了後までをどう設計するかで変わります。見た人が「また関わりたい」と思う循環が生まれれば、スポーツの価値はさらに広がっていきます。
勝見:レガシーを実感する出会いはありましたか。
河合:大分県の指導者会議で出会った方は、子どもの頃に地元で開催された障スポでボランティアをした経験から、理学療法士を志したそうです。2024年の神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会でも、1989年のフェスピック(極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会)神戸大会を学校行事で観戦した人が、スポンサー企業の担当者となって大会に関わるとともに、自分の子どもが観戦プログラムで来場することを楽しみにしていました。どちらも、まさにレガシーだと感じる出来事でした。記憶や感動が次の行動を生み、人が生き続ける限りレガシーは残る。その連鎖を広げていけばいい。その思いが、いまは確信に変わっています。
日本社会とスポーツの未来――10年先へ責任を持つ
勝見:日本社会でスポーツが果たすべき役割について、どのように考えていますか。
河合:日本の特徴である学校体育や部活動は、大切に守るべき文化です。同時に、地域スポーツクラブのような欧米の仕組みから学ぶ点もあります。それぞれの良さを生かし、日本の社会課題に応じて組み合わせていくことが重要です。スポーツ庁長官に着任して強く感じるのは、目の前の課題に対処しながら「10年先の責任を負う覚悟」を持つ必要性です。有識者の方々と議論しながら、社会にわかりやすく示すことが自分の役割だと思っています。
大日方:10年後のスポーツの姿として、どのようなものを描いていますか。
河合:少子化の中でも、「スポーツを通じて人生が豊かだと実感できる社会」です。競技に限らずジョギングや筋トレなどどのようなかたちでも、「する・みる・ささえる・あつまる・つながる」というさまざまな関わり方を通して、心身の健康と社会との接点をつくることができる。そのためのツールとして、スポーツほど優れたものはありません。その価値を全世代に届けていきたいと思っています。スポーツに無関心な人も、健康でありたい、幸せでありたいという思いは共通です。スポーツは必ずそこに貢献できる。私の揺るぎない信念です。
勝見:最後に、河合さんにとっての「最も大切なスポーツの価値」は何でしょうか。
河合:悔しさや喜びなど、自分の感情と真正面から向き合えることです。湧き上がる感情は、無我夢中で全力を尽くした先にしかありません。続けることで、楽しさや喜びを見つけ出していける。そこに、スポーツの大きな価値があると思います。
![]()
今後の予定
次回は、早稲田大学 佐藤晋太郎教授と、東海大学 押見大地准教授の共同研究「スポーツ観戦の共体験」について紹介します。
「スポーツ未来研究所」のトピックスやお問い合わせはこちら
https://www.dentsu.co.jp/labo/sports_future/index.html
![]()