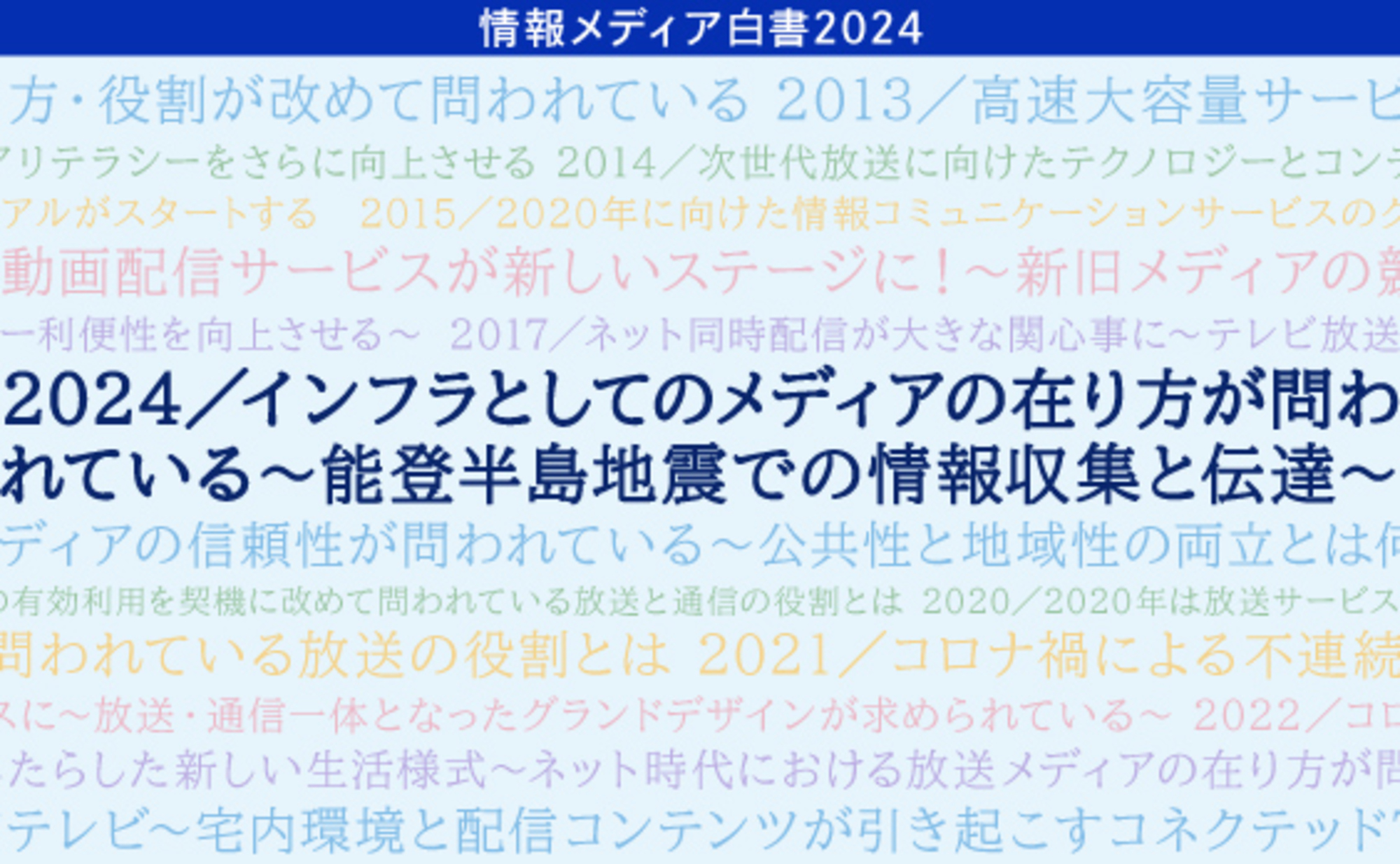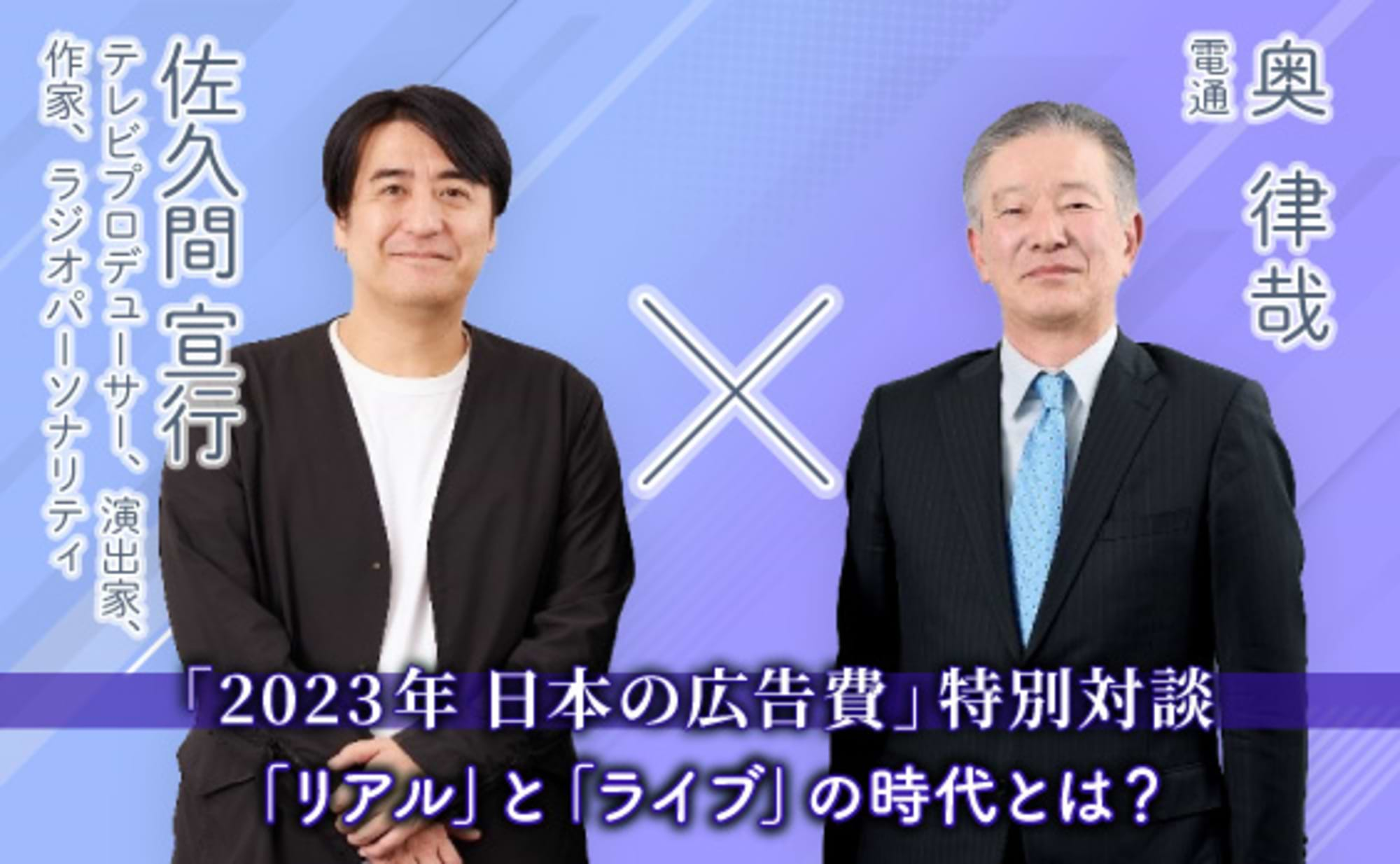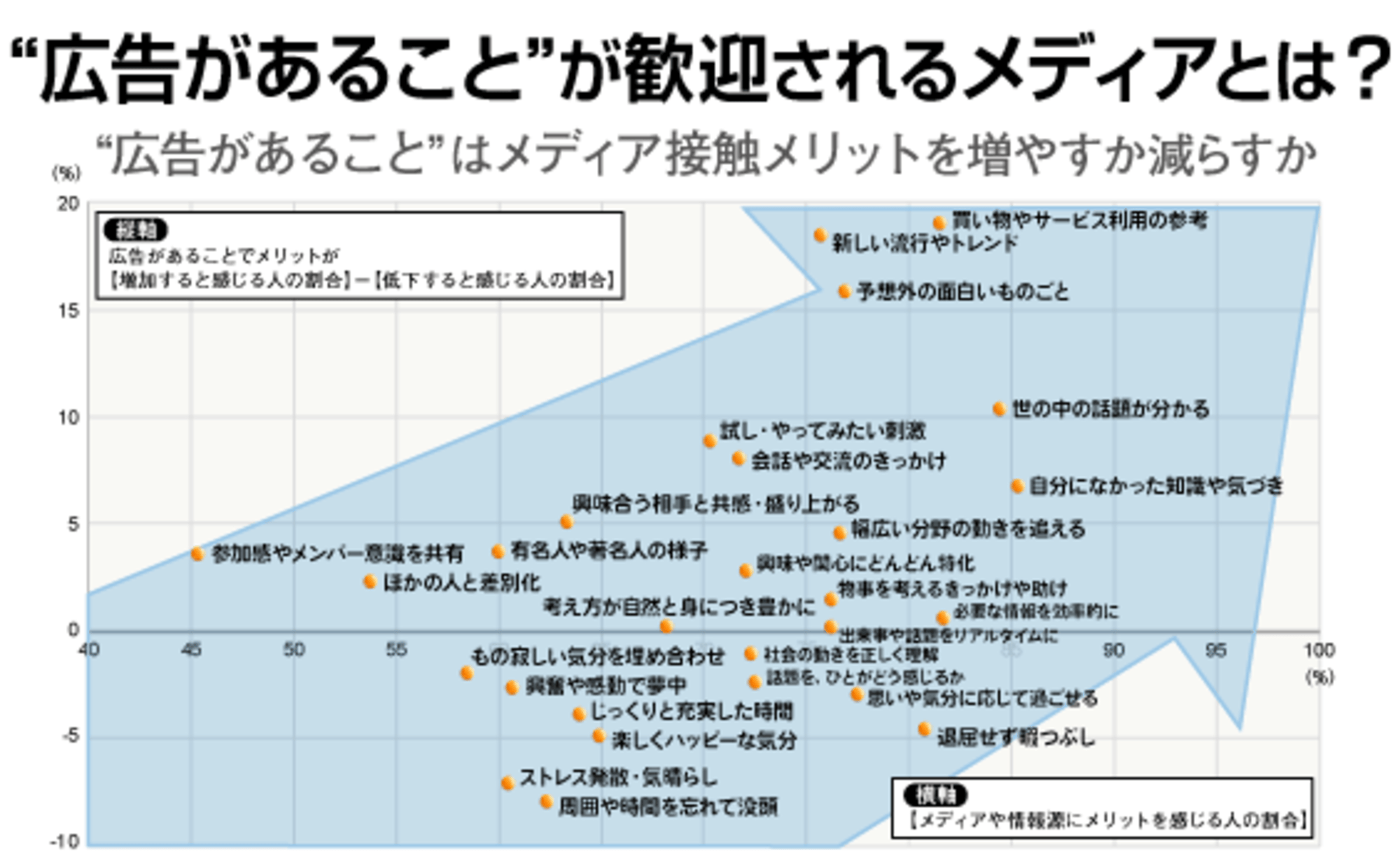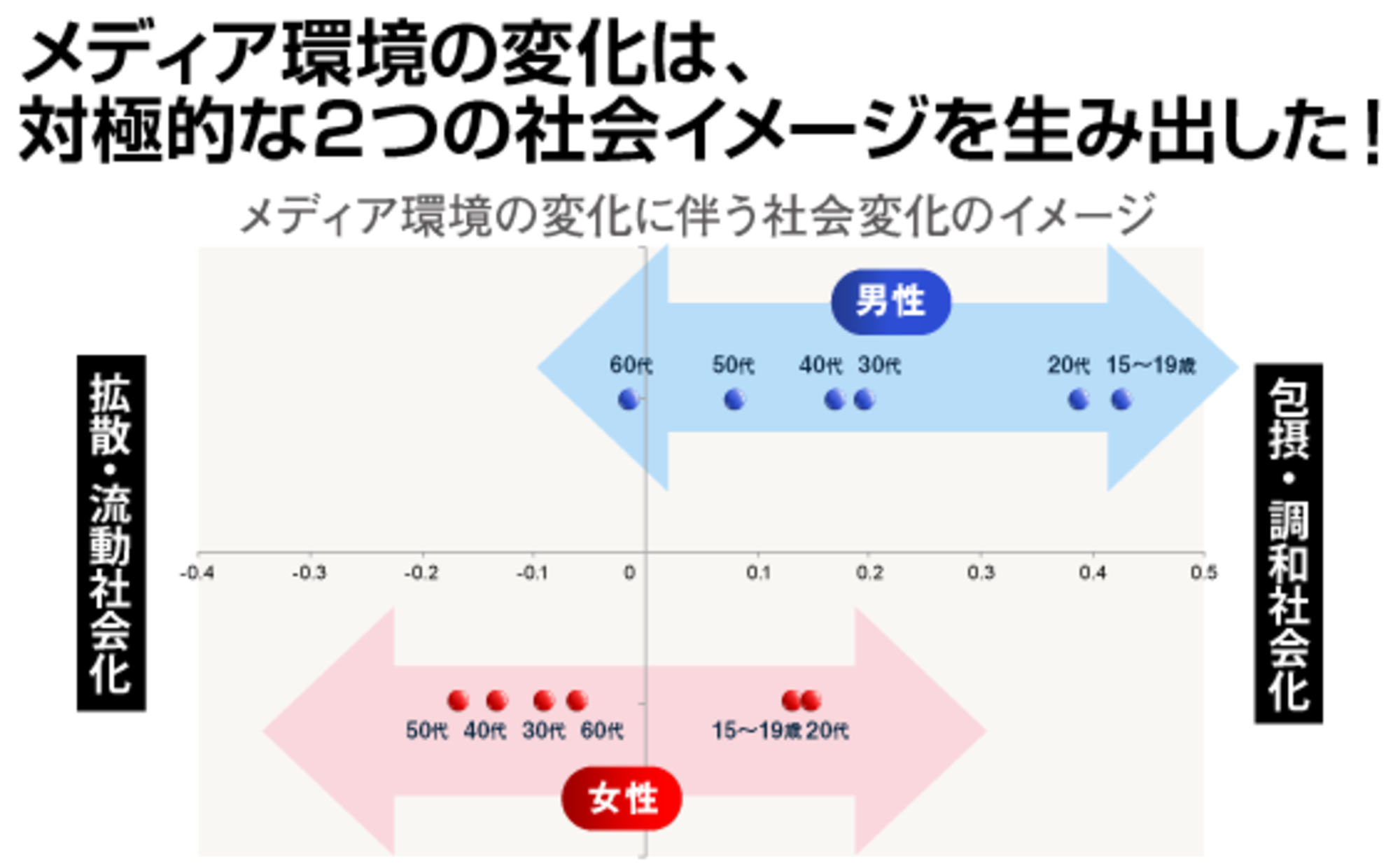ビデオリサーチ+電通総研共同リポート「スマホと日本人」(前編)
この記事は参考になりましたか?
著者

奥 律哉
メディアビジョンラボ代表
電通総研 名誉フェロー/ビデオリサーチ メディアデザイン研究所 所長
1982年、電通入社。ラジオ・テレビ局、メディアマーケティング局、MC プランニング局などを経て、電通総研フェロー、電通メディアイノベーションラボ統括責任者を歴任。2024年6月末、電通を退社。個人事務所 メディアビジョンラボを開設。主に情報通信関連分野について、ビジネス、オーディエンス、テクノロジーの3つの視点から、メディアに関わる企業のコンサルティングに従事。 著書等に「ネオ・デジタルネイティブの誕生~日本独自の進化を遂げるネット世代~」(共著、ダイヤモンド社)、「『一周まわってテレビ論』と放送サービス展望の解説書」(共著、ニューメディア)、「放送のネット同時配信の受容性を確認する」(「Nextcom」2017巻32号、KDDI総合研究所)、「新・メディアの教科書2020」(共著、宣伝会議)、「民間放送70年史」(共著、一般社団法人日本民間放送連盟)、「広くあまねくネット配信を/NHKと民放、競争から協調へ」(「Journalism」2022年12月号、朝日新聞社)、「情報メディア白書2024」(共著、ダイヤモンド社)など。 総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員。NPO法人/放送批評懇談会 出版編集委員会委員。

美和 晃
株式会社電通
電通メディアイノベーションラボ
メディアイノベーション研究部長
入社以来、電通総研で主に情報通信やデジタル機器・コンテンツ領域の調査研究や官・民のクライアント向け事業ビジョン構築作業とコンサルティングを実施。カメラ、ロボットから電子書籍まで幅広い分野を担当。2012年7月からメディアイノベーション研究部で情報メディア全般に関するプロジェクトに従事。2015年11月から現職。