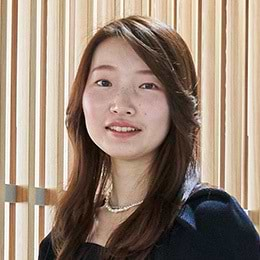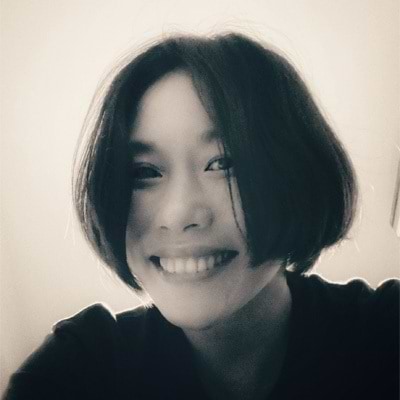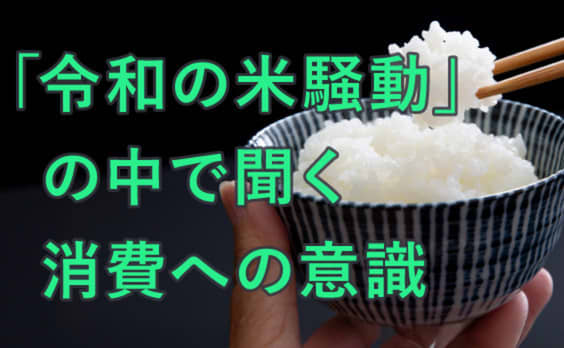電通ジャパンによる「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY 」はZ世代の知見やアイデアを生かし、企業のサステナビリティを推進するためのコンサルティングを提供するサービス。このプロジェクトメンバーの一部が所属する「若者消費ラボ」は、株式会社電通プロモーションプラス 内のミレニアル世代・Z世代ユニットです。今回は、同ユニットの五十嵐響介氏、大木佳奈氏、馬場理彩子氏を迎え、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」をリードする田中理絵氏とともに、Z世代視点のSDGs事例や、理想の組織の在り方について語ってもらいました。
Z世代のSDGsは「いいとこ取り」 田中: 前編でご紹介したように、馬場さんはZ世代当事者であり、「若者消費ラボ」の中でSDGsユニットに所属されています。Z世代の価値観にマッチしていると感じるもので、最近サステナビリティ関連で気になる事例はありますか?
馬場: 最近、じわじわ広がってきているなと思うのは「ビーガンなのにジャンキー」な食べ物です。身体にも環境にもやさしいビーガン食を取り入れたいけど、ジャンクなものも食べたい。そういう相反する気持ちを満たすことができるので、「いいとこ取りをしたい」というZ世代の価値観にぴったりなのではないでしょうか。実際に、ビーガン料理を提供する居酒屋や、大豆ミートを使ったハンバーガーが食べられるファーストフード店も注目されていますね。
株式会社電通プロモーションプラス 馬場 理彩子氏 田中: 「Z世代は、食べたことのないもの、飲んだことのないものを試すのが好き」という傾向はグローバルでも特徴として見られますね。今まで食べたことがないテクスチャとか、味の組み合わせとか。「おいしい」っていう感覚には個人差がありますが、「珍しい」はみんなと共有できるし、仮に好みに合わなくてもそれはそれで楽しめるので、「〇〇なのに△△」は、SNSとの親和性も高いですよね。大木さんたちとは以前、Z世代向けの商品やプロモーションのカラーが水色とピンクのコンビネーションが多いという話をしたことがありますが、組み合わせるというのも特徴かもしれないですね。
大木: SNSを見ていると、海外では「#MeatFreeMonday」(週に1回、月曜日は肉を食べるのを控えるというキャンペーン)のハッシュタグをつけてレシピなどをシェアし合っていますね。日本ではまだあまり浸透していない印象ですが、そうやって、楽しく「週1度だけならできそう」という気軽な形で人とシェアしながら、自然と生活の一部に取り入れていくのは、Z世代の価値観にもフィットするかもしれないと思っています。
五十嵐: 日本は特に、自分の周りに影響が広がってから「自分もやってみたい」という感覚を強く持つ人が多い気がします。火が付くまでは割と時間がかかるけれど、みんながやっているのを見て、「いいじゃん」って思えば一気に広がる。
田中: なるほど。ほかにも気になる事例はありますか?
大木: 再生プラスチックや再生紙から作られている文房具で、見た目にもこだわっているものが気になっていますね。学校生活におけるエモーショナルな瞬間を切り取ったイラストがプリントされたシリーズは、“エモい”と“エコロジー”を組み合わせた“エモロジー”なブランドとして人気です。リフィルもあるのですが、長く使えるように工夫されているだけではなく、自分たち向けにデザインされていると感じられるので、強く共感することができます。
田中: ビーガンなのにジャンキーな飲食店やエモロジーな文房具は、価格的には安いんでしょうか?それとも、少し高いけど「ワクワク」や「エモい」があるから選ばれているのでしょうか。
馬場: 一般的なものより、少し高いくらいの値段設定ですね。ちょっとだけ高くても、新しいことを試せるんだったらトライしてみよう、くらいの感覚だと思います。でも、選ばれるために一番大事なのは、まず「おいしい」とか「かわいい」という部分。プラスアルファでサステナブルな要素があると、さらに「いいね」と感じる、という順番なのではないでしょうか。
田中: サステナビリティの要素があると、口コミもしやすいのでしょうか?
大木: 切り口の1つにはなり得ると思います。例えば、おいしいだけではなく大豆ミートのサステナブルな唐揚げだから、Instagramのストーリーでみんなに伝えるとか。
株式会社電通プロモーションプラス 大木 佳奈氏 田中: そもそも「エモさ」や「情緒」がなぜ、Z世代に刺さるのでしょうか。
五十嵐: Z世代は多様な価値観を受け入れる世代といわれていますが、その反面、物事に対する好き・嫌いがどんどん減っているのではないかと感じます。SNSが普及して、世界中の多くの人とつながれる、自分からも発信できる時代になったことで、さまざまな価値観に触れることができて、「そういう考え方もあるのね」と受け入れられるようになったけれど、心は動きにくい。
多様なZ世代が参加しやすい、組織体制へ 田中: リバースコンサルティングは、若手社員がメンターとなって上司や先輩にアドバイスする「リバースメンタリング」がベースになっているのですが、ミレニアル世代である五十嵐さんは、Z世代から学びたいと感じることはありますか?
株式会社 電通 田中 理絵氏 五十嵐: まず、テクノロジーの扱い方について教えてほしいなと思うことがあります。あとは、これまで見過ごしてきたような問題をうまくエンターテインメント化して解決していくアイデア・発想力とかですね。例えば、環境に配慮するために、社内でごみ分別や空調の温度設定のルールを決めているのですが、ここにZ世代の発想を取り入れると、ただ呼び掛けるだけではなく、ルールを守るとポイントが貯まって、飲み物などの支払いに充てられるといった、楽しみながら取り組める仕組みができるかもしれません。そういう「言われてみれば、どうしてこれまでやらなかったんだろう」と感じるような視点、Z世代らしい気付きを取り入れることで、企業のサステナビリティを前に進めていけるのではないでしょうか。
株式会社電通プロモーションプラス 五十嵐 響介氏 田中: 組織のカルチャーや仕組みづくりに関しては、デジタルを使いこなし、多様性の感覚を養ってきたZ世代に合わせたほうがグローバルスタンダードに近いように感じます。ルッキズムとか、ジェンダー関連もそうですし、マウントをとる言動にもとても敏感です。実際、企業がサステナビリティに取り組む中で、インナー啓発に向けて若い社員をサステナビリティ活動のアンバサダーにするとか、国や部門を超えて現場の若手同士のつながりをワークショップでつくろうとする動きも増えてきています。もし皆さんがサステナビリティ関連のプロジェクトリーダーに任命されることがあったら、どう感じますか。
馬場: アンバサダーならいいのですが、プロジェクトリーダーは私だったら荷が重いと感じるかもしれません。事業として動かすスキルも経験も積んでからがいいと思います。自分の感じたまま意見を言えるということと、責任を持てるということは違うので。
大木: これは個人的な印象ですが、リーダーとして活動したいZ世代は、むしろ少数派だと思います。アイデア出しや実行に向けたプランはZ世代の感覚を取り入れつつ、責任者は上の立場の方が担うとか。そういう形の方が誰でも参加しやすいのではないでしょうか。
田中: 権限移譲の在り方も課題の1つですよね。第1回 でもモダンエルダーの話が出ましたし、第2回 でも組織でのZ世代視点の生かし方の話になったのですが、社会課題に向き合うチェンジメイカーだけでなく、「リーダーになるのは尻込みするけど、楽しくて役立つことには参加したい」という考えを持つ人も含め、多くのZ世代に参加してもらい、さまざまな感性をつないでいくことが大切だと思っています。最後にZ世代の馬場さん、今後やりたいこと、チャレンジしてみたいことはありますか?
馬場: 普段は、大きなプロジェクトの中の一部分とか、単発のキャンペーンに携わることが多いので、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」では、「若者消費ラボ」での知見を生かしつつ、事業の立ち上げから関わるなど、全体像を見渡すことにチャレンジしていきたいです。
「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」は、若者消費ラボなど電通グループ内外のZ世代当事者と共創し、義務感ではなく、楽しみながら周りに広がっていくサステナビリティを推進していくサービスです。Z世代の感覚を起点にした新しいサステナビリティの捉え方を取り入れることで、革新的なサービス開発や、次世代に受け継がれていく組織文化醸成の支援をしていきます。