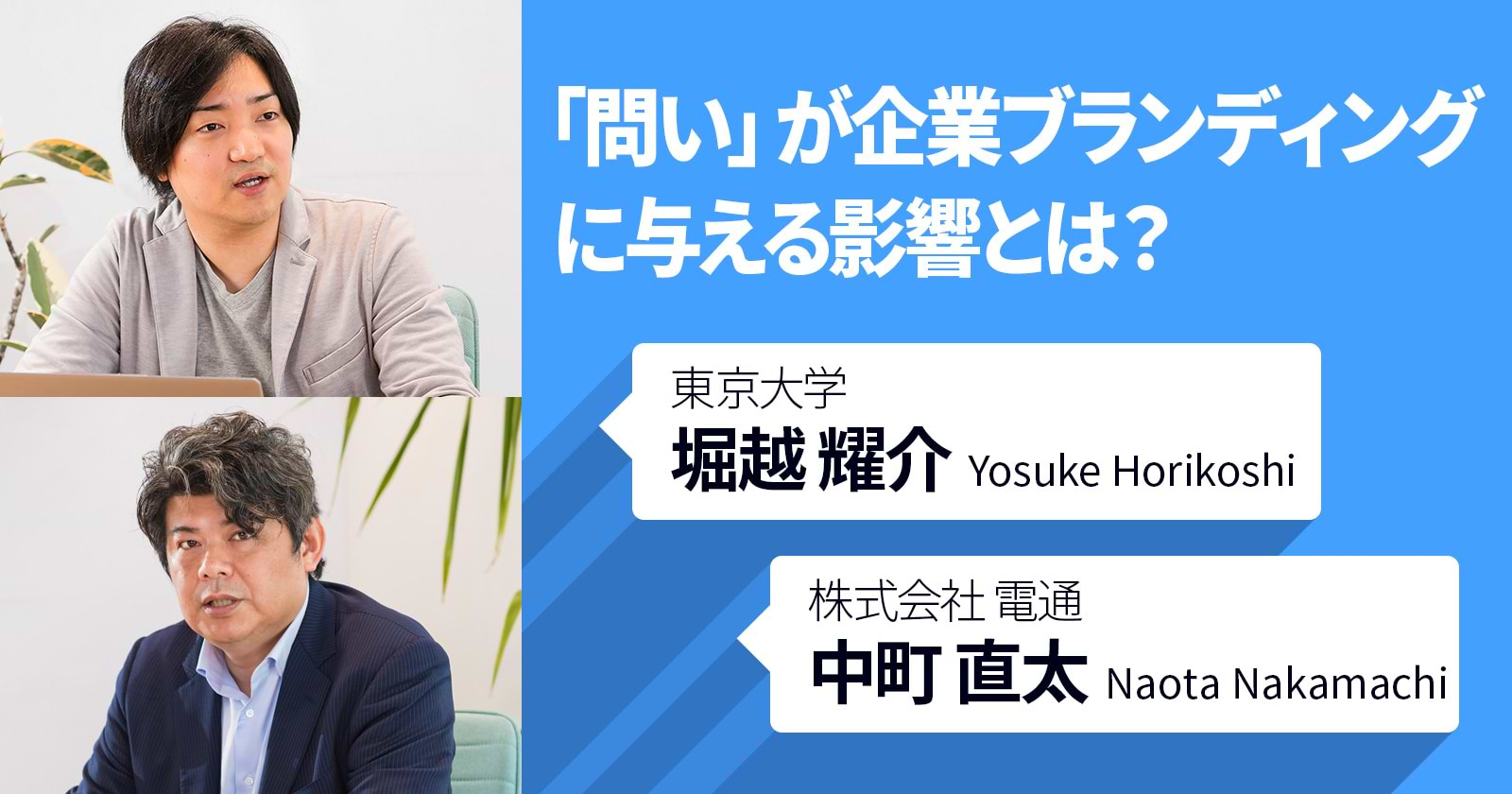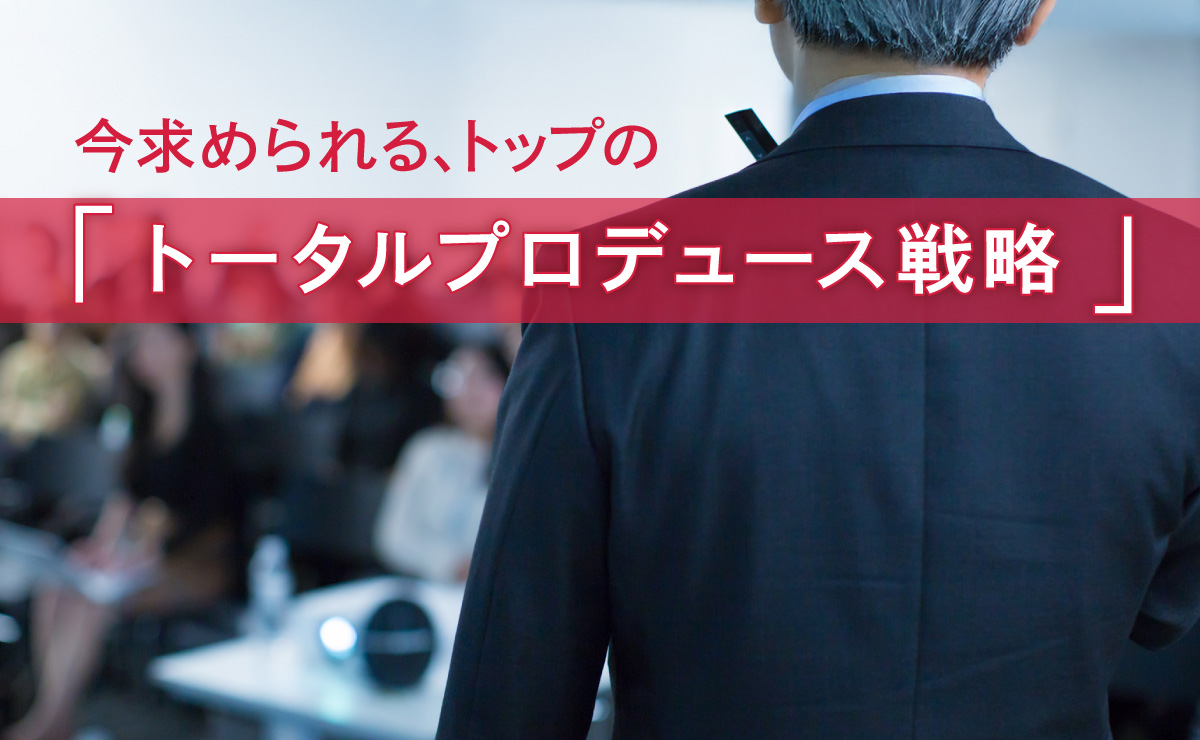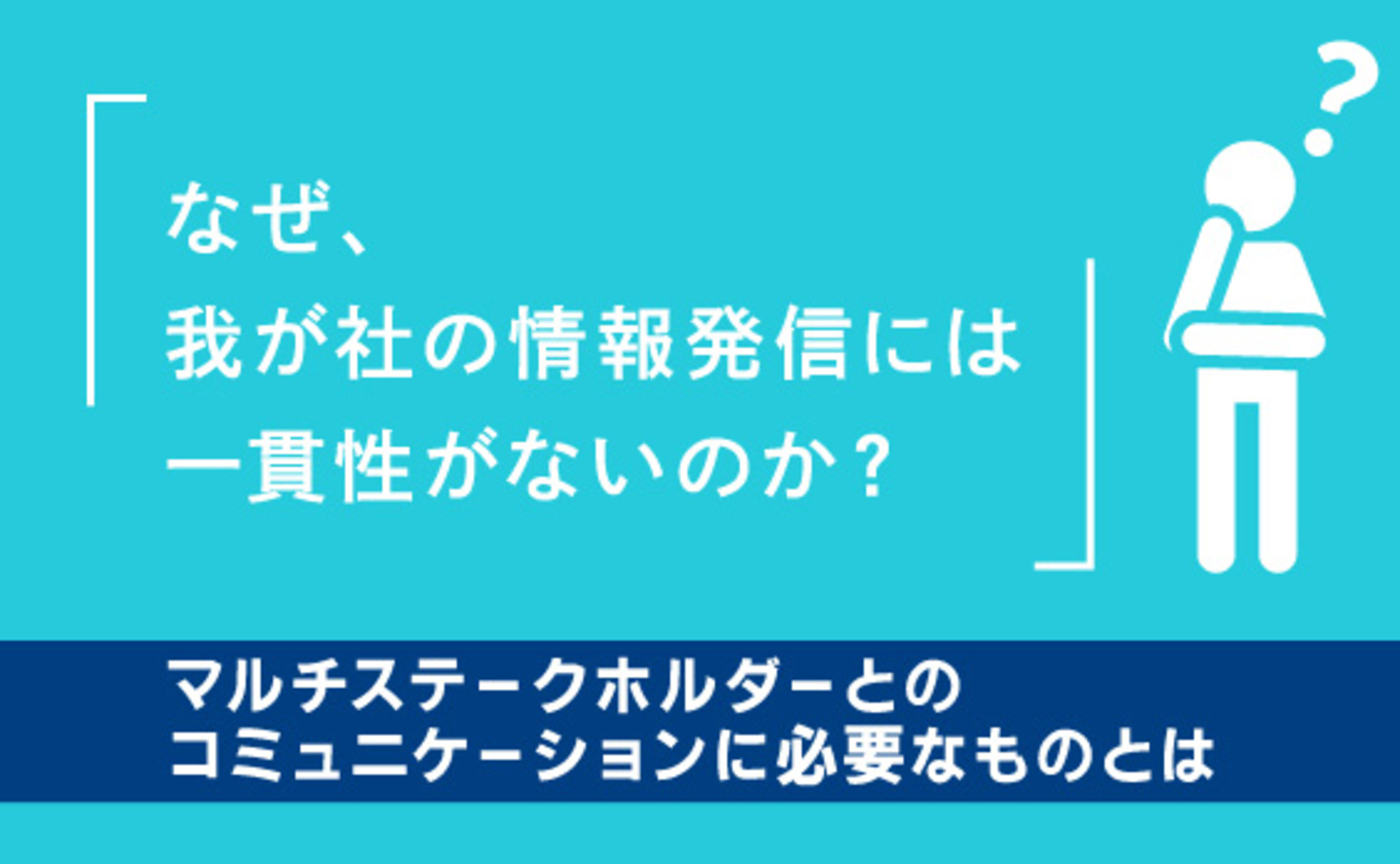Note: This website was automatically translated, so some terms or nuances may not be completely accurate.
To instill a company's "purpose" in employees. What role does the philosophical dialogue approach play? (Part 1)
In recent years, an increasing number of companies have been formulating their "purpose" as their raison d'être. Purpose lies at the foundation of elements like "vision," which represents an ideal future state, and "mission," which defines a social responsibility. Establishing this purpose contributes to enhancing corporate value and motivating employees.
Against this backdrop, in March 2023, Yosuke Horikoshi,a Specially Appointed Researcher at the Kamihiro Chair for Symbiosis at the University of Tokyo's Center for International Philosophy of Symbiosis (UTCP) , and Dentsu Inc. jointly launched the "My Purpose Development Program," which utilizes "philosophical dialogue."
This time, we interviewed Yosuke Horikoshi from the University of Tokyo, a practitioner of philosophical dialogue, and Naota Nakamachi from Dentsu Inc., who developed the program. In Part 1, we introduce the background behind the program's launch and an overview of the service.
The Meeting of a Researcher Practicing Philosophical Dialogue and a Corporate Branding Expert
Q. Increasingly, companies are not only setting corporate-level purposes but also beginning to focus on establishing employees' "My Purpose." How this My Purpose development connects with philosophy is a very intriguing point. First, could you tell us about the activities you've been involved in, Mr. Horikoshi, and why you, Mr. Nakamachi from Dentsu Inc., encountered philosophy?


Q. Many readers might imagine that philosophy researchers are primarily interested in philosophy itself, such as the pursuit of truth. Were you, Mr. Horikoshi, originally interested in the practical application of philosophy to society?
A customizable program centered on philosophical dialogue, tailored to specific objectives
Q. Professor Horikoshi, you already have extensive experience consulting for educational institutions and companies. What specific programs can you offer client companies through this "My Purpose Formulation Program"?

Q. Could you elaborate a bit more on why philosophical dialogue is effective for embedding corporate purpose and developing personal purpose?
We've seen that a company's purpose isn't just about defining it; its value truly shines through when it permeates the workforce and is put into action. For this, the method of philosophical dialogue plays a significant role. In the second part, we'll explore how this program transforms branding and discuss future prospects for utilizing philosophical dialogue.
The information published at this time is as follows.
Was this article helpful?
Newsletter registration is here
We select and publish important news every day
For inquiries about this article
Author

Yosuke Horikoshi
Philosophy/Education Researcher, Ph.D. (Education)
Specially Appointed Researcher, Uchihiro Synergy Philosophy Chair, University of Tokyo UCTP / Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Postdoctoral Research Fellow (PD). Completed Doctoral Program, Graduate School of Education, University of Tokyo. Doctor of Education. Specializes in philosophy of education and philosophy practice. As a practitioner, conducts philosophical dialogue and philosophy consulting in school education, local government/public facilities, and corporate/employee training. Publications include How to Use Philosophy: An Introduction to Philosophical Thinking (Jitsugyo no Nihon Sha) and "Starting a Business with Philosophy: The Threshold Between Philosophy and Work Opened by Philosophy Practice" (Gendai Shiso, Seidosha, August 2022 issue).

Naota Nakamachi
Dentsu Inc.
Marketing Division 4, Brand Consulting Department Manager
Senior Consulting Director
Senior Consulting Director After joining the company, he worked in the Marketing Promotion Division and Sales Division. He is currently in the Marketing Division 4, specializing in corporate brand consulting and PR consulting.In the corporate brand consulting domain, provides broad support to large enterprises with tens of thousands of employees across various industries, as well as startups. Particularly skilled in supporting corporate culture transformation through internal communication. In the PR domain, has experience producing television programs as a director at a broadcasting station and establishing PR systems during the founding of group companies. In client work, has extensive experience with large-scale projects, including supporting the enactment of new ordinances for local governments and devising PR strategies for major international events.